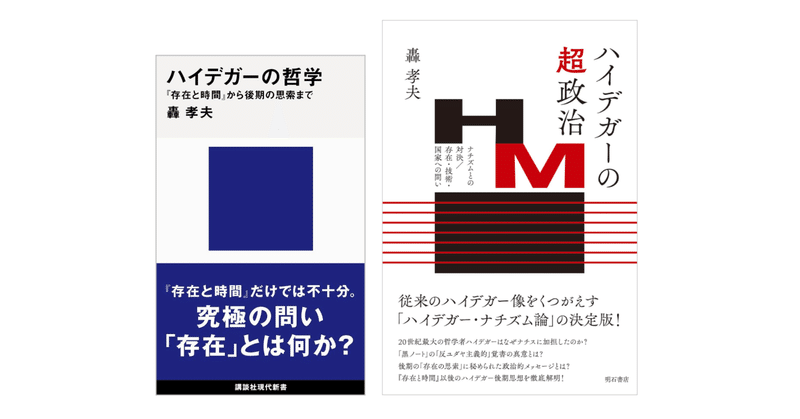
轟孝夫『ハイデガーの超-政治――ナチズムとの対決/存在・技術・国家への問い』/『ハイデガーの哲学 『存在と時間』から後期の思索まで』
☆mediopos3202 2023.8.24
ハイデガーは
とくに「黒ノート」の公開以降
欧米ではハイデガーの哲学から距離を取ることが
「政治的に正しい」とされる態度となっているそうだ
その「政治的な正しさ」というのは
いうまでもなくアカデミックな世界で
みずからの立場を保身することでもあるだろう
「ハイデガーのナチス加担の思想的動機を
明らかにしようとしているはずの論者が、
その点についての彼自身の明快な説明を
ことごとく無視する」のである
日本でなぜか人気のある
ドイツの哲学者マルクス・ガブリエルも
わざわざ日本に来てまで
ハイデガーを
「完璧なまでのナチのイデオローグ」
「本物のナチ」とこき下ろし
『ハイデガーを読むのはやめなさい!』とまでいう
おそらくハイデガーの
ナチス加担に関する実際のところについては
まったく知らずにいるはずだ
あるいは知りたくもない
知ってハイデガーを正しく論じでもしたなら
アカデミズムでは生きていけないと
それは「読むのをやめなさい」
という言葉にもそのまま表れている
しかし読まずにいて
どうやって理解できるというのだろう
これが哲学者を自称する者の態度であることに
利に敏い「迎合」的な知識人の姿を見てしまう
その意味でも今回とりあげた
轟孝夫によるハイデガーに関する著作は
ハイデガーの真意について理解するための
格好の手引きともなっている
ハイデガーが誤解されやすいのは
ナチスとかかわり学長になったときも
学長をやめナチスと関わらなくなってからも
もちろん戦後も同様に
基本的な態度を変えなかったからだろう
ハイデガーはその真意について
反省も含め明確に説明しているのだが
態度を変えないということは
ナチはナチで変わらないからだと
短絡的に受け取られてしまっているということでもある
しかし変わらないでいるということは
むしろハイデガーが意図していたことが
ナチスのイデオロギーとは異なっている
ということでもある
ハイデガーは「存在の問い」そのものを
政治的実践として行っていたのである
それは独自の共同体構想と
それに基づいた現実政治に対する
批判を内包したもので
戦争中も
その後ナチスを批判するようになってからも
そしてナチスが崩壊してからも同様に
批判は自由主義や民主主義へも向けられていた
戦争前と戦争後で態度を変えてはいない
問題があるとすれば
ハイデガー自身が説明し得たと思っていたことが
それを理解しようとも思っていない一般には
それそのものが傲慢な態度にしかみえず
誤解の種ともなったことについて
わかりやすい謝罪をしなかったことだ
そのためもあり
重要な意味をもつ
「存在・技術・国家への問い」への理解が
閉ざされてしまうことになる
ハイデガーのような関わりこそが
むしろその反省も含め新たな視点を得るための
重要な契機ともなり得るはずなのだが・・・
ハイデガーのナチス加担については
詩人のパウル・ツェラーンとの逸話がよく知られ
ハイデガーがツェラーンに
ナチス加担について語ることを拒んだとされてきているが
じっさいのところ
むしろハイデガーはツェラーンと対話を深めており
ツェラーンの病状をも気づかってさえいたようだ
先日刊行された新書の『ハイデガーの哲学』には
そうしたツェラーンとの関係も紹介されていて興味深い
■轟孝夫『ハイデガーの超-政治
――ナチズムとの対決/存在・技術・国家への問い』
(明石書店 2020/2)
■轟孝夫『ハイデガーの哲学 『存在と時間』から後期の思索まで』
(講談社現代新書 講談社 2023/6)
(轟孝夫『ハイデガーの超-政治』〜「序論」より)
「本書の目標は、二〇世紀ドイツの哲学者、マルティン・ハイデガー(一八八九−一九七六)の「存在の問い」の政治的含意を明らかにすることである。(・・・)存在の問いはそれ自身が共同体の基礎づけを目指していること、したがって存在の問いのこのような政治性の理解なしには、その問いの意義も理解できないことを示すのが本書の課題である。」
「ハイデガーはまさに存在の問いに内在する政治性に立脚してナチスに加担した。そしてナチスから離反したのちは、この存在の問いの政治性に基づいてナチズムを厳しく批判するようになる。それゆえハイデガーとナチズムの関係を的確に理解するためには、まずは存在の問いの政治的含意を捉えることが不可欠である。逆に言うと、存在の問いの政治的意義が理解できない限り、彼がナチスに加担した理由を捉えることは不可能である。」
「ハイデガーのナチス加担を批判する論者たちに共通するのが、彼がナチス加担の事実を隠蔽、ないしは矮小化しようとしているのではないかと疑う姿勢である。ハイデガーによる隠蔽の努力に抗して、ハイデガーとナチズムの密接な関係を示す動かぬ証拠を見つけ出すのが自分たちの仕事だというわけだ。そして彼らはハイデガーの思想からナチズム的な要素を見つけ出すことに精を出し極端な場合は彼の思想がナチ・イデオロギーの哲学への導入そのものだと言い募るのである、こうして当代一流の哲学者が、リベラルで良識的な世界観に反する危険な思想の持ち主として断罪されることになる。
しかしハイデガーはナチス加担と自分の思想との関係については、それを隠すどころか、むしろ積極的に提示している。彼はすでに学長時代に、自分がいかなる思想的動機に基づいてナチスに関わろうとするのか明確に語っている。また戦後の釈明でも、自分がいかなる思想的根拠に基づいてナチスに加担したのかについて饒舌に説明している。このように彼は自身の哲学と政治的選択の関係を隠すどころか、両者の連関につねに注意を促しているのである。」
「これまでのハイデガー・ナチズム論に欠けているのが、彼の存在の問いに固有の政治性を解明するという基本的作業である。この作業を欠いたとき、表面上は学問的な議論を展開しているように見えても、その説得力はハイデガーがどう取り繕うとナチはナチだという決めつけに依拠したものでしかない。」
「ハイデガーの存在の問いは徹頭徹尾、政治的な性格をもっている。つまり存在の問いの遂行それ自身が、現代において支配的な政治体性や政治的イデオロギーに対する批判と、それとは異なる可能性の展望という意義をもつのである。彼のナチス加担もそうした存在の問いの政治性に基づいている。この彼のナチス加担を動機づけた存在の問いの政治性が、学長辞任後はナチスに対する批判として現れてくる。」
(轟孝夫『ハイデガーの超-政治』〜「第2章 ナチズムとの対決」より)
「ハイデガーの「黒ノート」におけるユダヤ的なものをめぐる覚書は単に同時代のユダヤ人に対する差別的ステレオタイプを踏襲したものではなく、ユダヤ的なものについての彼なりの存在史的な解釈に基づいていることが明らかになった。ハイデガーによると、ユダヤ教はキリスト教を介して、その創造説と命令する神という観念により、古代ギリシアのアレーテイア、ピュシスの隠蔽を促進し、古代ギリシアの末期に現れたプラトン、アリストテレスの哲学と結びつきながら西洋形而上学に固有の思惟の様式を形作ったのである。こうしてハイデガーが「黒ノート」においてユダヤ的なものに言及するときは、ユダヤ的なものは決して人種的なものではなく、むしろ形而上学という形でわれわれ自身の思惟を規定するものとして理解されている。
(・・・)ハイデガーはナチス支持者として学長に衆院した時期かた、ナチスの人種主義には明確に反対していた。そこからの当然の帰結として、彼は人種主義に基づいた反ユダヤ主義やユダヤ人迫害も無意味なものとみなすのである。「黒ノート」の反ユダヤ主義だと非難されている覚書も、ユダヤ人に対する攻撃ではなく、ナチスがユダヤ人を排撃しながら、それ自身、形而上学という意味でのユダヤ的なものによって規定されていることを揶揄するものである。」
(轟孝夫『ハイデガーの超-政治』〜「結論」より)
「存在の問いに基づいたハイデガーの民族観は、ナチズムの公式イデオロギーとは似て非なるものであり、その人種主義とは根本的に相容れないものである。それにもかかわらず、彼はナチスのうちに近代のニヒリズムに対する対抗運動という性格を見て取り、その政権獲得を大学における学問の刷新とそれに基づいたドイツ民族の結集のチャンスと捉えていた。(・・・)
ハイデガーはこのナチス加担の失敗に対する反省に基づいて、意志と決断によって革命的変化をもたらそうとする自らの意志中心的な立場を放棄し、そのことによって後期の静観的で非政治的な存在の思索への「転回」が起こったという情緒的で俗受けしやすい解釈がしばしば唱えられる。しかしこのような解釈にはまったく根拠がない。(・・・)ハイデガーは学長辞任後も、まさに彼をナチス加担に導いたのと同じ思想的立場に基づいて、ナチズムに対する超政治的な批判を遂行していくのである。」
「ハイデガーのナチス加担の思想的動機を明らかにしようとしているはずの論者が、その点についての彼自身の明快な説明をことごとく無視するのはなぜだろうか。」
「(ハイデガーの、戦時中に書かれた「黒ノート」の覚書)では、民主主義を否定しファシズムを讃美するにしても、逆にファシズムを批判し民主主義を擁護するにしても、どちらも通常の政治理解の枠内にとどまるものでしかなかく、形而上学との対決とい真の問題次元には到達できないことが指摘されている。
(・・・)
こうした形而上学との対決というハイデガー固有の問題次元を捉えられない論者は、あくまで彼の立場を自由主義、民主主義/全体主義の二項対立の枠組みで理解しようとし、それを全体主義の側に位置づけるのである。そのことによって、彼がナチズムを批判している言明は過小評価され、ひどいときにはナチズム讃美と曲解されることになる。
(・・・)
一般的にはハイデガーの後期の思索はまったく非政治的なものだと見做されている。ただしハイデガーはナチスから離反した後も、さらにナチスが崩壊してからも、自由主義や民主主義には公然と批判的であるから、右の二項対立に従えば、やはり潜在的には全体主義に神話的だという疑いをもって見られることになる。こうして戦後になっても、自由主義や民主主義に対して帰依を表明しないハイデガーの姿勢がナチス加担に対する反省の欠如として受け止められ、彼に対する批判が今日に至るまで、繰り返し延々と続けられることになるのである。」
「われわれは主体的エゴイズムを問題視するとき、「私」に対して「われわれ」、すなわち民族全体を優先するという仕方でそれを克服しようとする。これによりたしかに個人的主体の我意、恣意性は抑制されうるが、このとき主体性の担い手が集団に移行しているにすぎないのである。つまりこのように民族全体のために個人の自由を制限するといったような考え方は、ハイデガーが『哲学への寄与論稿』で述べていることによると、「『自由主義的な』『私』——思想と『生』の維持という経済的な表象を『民族主義的に(völkisch)』拡張したものでしかない(・・・)。
しかもこのとき、人々は自由主義的な私という「悪」を克服したと信じており、すなわちおのれの道徳的正当性を確信しているので、今や民族全体が担うものとなっや主体性————実はこの主体性こそ「悪質なもの」として真に悪なのだが————は一切の道徳的制約を免れ、絶対化されてしまう。こうして人々はそこにおいて均質化され、「技術的に組織された人間による惑星規模での帝国主義」が完成されるのである。以上の議論には、人々がなぜ自由主義に対する対抗運動に引きつけられ、しかもそれが容易に暴力に転化していくのかが示されている。自由主義非難は民族や国家といった「公的なもの」のための自己犠牲を唱えることにより、最高度の道徳性の装いを備えている。他方でそては民族的主体を全面肯定し、絶対化するものであるため、そこでは主体性の「悪質なもの」という本質が一切の制約を受けることなく解き放たれてしまうのである。
(・・・)
主体性の形而上学をめぐる省察として展開されている彼の近代国家批判は、全体主義との哲学的対決と見なしうるし、それは実際ナチズムとの対決でもあった。」
(轟孝夫『ハイデガーの哲学』〜「はじめに」より)
「ハイデガーの哲学的声望を自身の箔付けに利用しながら、その一方では彼のナチス加担を批判することで自身の政治的、道徳的健全性も確保するという虫のよい姿勢は「黒いノート」の刊行移行、完全に不可能になってしまった。というのも、例の覚書によって、彼の哲学そのものが反ユダヤ主義、すなわちナチズム(国民社会主義)に汚染されてるいることはもはや疑問の余地がないと見做されるようになったからである。以降とりわけ欧米では、ハイデガーの哲学から明確に距離を取ることが「政治的に正しい」態度になっている。」
「近年、日本でもなぜかもてはやされている現代ドイツの哲学者マルクス・ガブリエル(一九八〇——)は、中国哲学研究者の中島隆博との対談を収録した『全体主義の克服』で、ハイデガーを「筋金入りの反ユダヤ主義者」、「完璧なまでのナチのイデオローグ」、「本物のナチ」などとさんざんこき下ろしたうえで、次のように述べている。「だから二〇一八年に京都大学で講演をしたとき、『ハイデガーを読むのはやめなさい!』と言ったのです。わたしは人々の眼を覚ましたかっら。ハイデガーが日本でとても力をもっていることは知っています」
(轟孝夫『ハイデガーの哲学』〜「第四章 ハイデガーのナチス加担」より)
「ハイデガーの思想はナチスに加担していた時期に「ナチ的」だったという主張は、彼がナチスを支持していた以上、それを裏付けていた思想もナチズムと同じ要素を含むはずだとの推論に基づいている。たしかに糧は「フォルク」の再生および統一という大きな目標をナチズムと共有していた。しかし問題は「フォルク」の意味をどのように理解するかにある。この点について、「フォルク」を生物的な人種として捉えるナチズムと「フォルク」を「風土的なもの」と捉えるハイデガーのあいだには大きな隔たりがあった。それゆえハイデガーは大学を起点として、ナチズムを人種主義的な「ふぉりく」理解かた、自身の「フォルク」理解へと導こうと試みたのである。
すなわち、ハイデガーのナチスへの積極的な関与を動機づけていたのは、彼の思想とナチズムの同一性ではなく、むしろ両者の差異であったということだ。」
(轟孝夫『ハイデガーの哲学』〜「第六章 ナチズムとの対決」より)
「ハイデガーは個人ではなく、共同体、すなわち基本的には国家のうちに「主体性」の本来的な形態を見て取っていた。つまり彼の「主体性」に対する批判的考察は、実質的には近代国家を俎上に載せているのである。」
「ハイデガーは近代国家の本質を「力」と捉え、近代国家の示すさmざまな動向を、この「力」という本質の帰結と解釈する。「力」はただひたすらおのれの持続と拡大だけを目指し、そのためにあらゆる存在者を操作可能なものとして自己の支配下に置くことを試みる。」
「ハイデガーの「ユダヤ的なもの」についての覚書は、ナチスの反ユダヤ主義やユダヤ人迫害を肯定するどころか、「存在の思索」の観点から、それがいかに無意味であるかを強調する意図で書かれたものであった。」
「「ユダヤ的なもの」とは決して「人種」的な意味における「ユダヤ人」のことではなく、「主体性の形而上学」に支配された人間性一般を指す、あくまでも純粋な哲学上の概念であることを忘れてはならない。したがって、このユダヤ的なもの」の克服のためには、他者の迫害ではなく、まずもって徹底した自己省察から始めなければならない、これがハイデガーの真意である。」
「しかしハイデガーの期待もむなしく、大半の論者は「黒いノート」に露骨に示された「存在の思索」の政治性を的確に捉えることができなかった。そしてそのことによって、彼らは「存在の思索」それ自身の意義もまったく理解できていなかったことを図らずも自ら露呈しているのである。」
(轟孝夫『ハイデガーの哲学』〜「第七章 戦後の思索」より)
「ハイデハーは戦後、自身のナチス加担について「沈黙」していたと非難されることが多い。しかし(・・・)彼はその問題について沈黙していたのではなく、むしろ饒舌すぎるほど語っている。ただ世間一般が望むような仕方で語らなかったというだけである。彼からすれば、ナチスの本質は「主体性の形而上学」のうちに見て取られる以上、自身のナチス加担を真摯に反省すればするほど、戦後社会においても「主体性の形而上学」がそのまま支配し続けているという事態を見過ごすわけにはいかなかったのである。
しかしハイデガーのこうした姿勢は、ナチス崩壊とともに道徳的に健全な秩序が取り戻されたとする戦後社会の根本前提とたまったく相いれないものだった。そのためハイデガーの反省は反省としては受け止められず、むしろ傲慢な開き直りとして人びと苛立たせた。」
「ナチス加担をめぐって人びとがハイデガーに求める反省と彼自身の反省のすれ違いは、ユダヤ人の詩人パウル・ツェラーン(一九二〇−一九七〇)とハイデガーの出会いと交流において先鋭化された形で示されることになった。
両者の関係は、通常はおおよそ次のように紹介される。ツェラーンは一九六七年七月、ハイデガーのトートナウベルクの山荘を訪れた。その際、両親を強制収容所で殺されたツェラーンはハイデガーにナチス加担についての明確な謝罪を要求したが、期待した言葉が得られなかった。この「沈黙」に大きな失望を抱いてツェラーンは山荘を立ち去った————。人びとはこの逸話から、ナチスによる被害者の心からの求めに対してさえ謝罪を拒むハイデガーの頑なさ、劣悪な人間性をあらためて確認するのだった。
私自身、ハイデガーの人格についての評価はともかく。両者の関係については右の通説以上の認識をもっていなかった。しかし実際にハイデガーとツェラーンの交流について調べてみると、事実はそうした通説とはまったく異なるものであった。
(・・・)
一九七六年一月末の自殺未遂後、なお入院中ではあったものの、許可を受ければ外出できたツェラーンは、以前から打診されていたフライブルクでの朗読会を行ってもよいとバウマンに伝えた。ツェラーンは一九五〇年代からハイデガーの哲学に本格的に取り組み、一般のハイデガー評価には逆行する形でハイデガーの後期の思索の「明晰さ」に賛意を示していた。またハイデガーもツェラーンの詩作品を高く評価しており、一九五七年にはツェラーンを南ドイツの都市ウルムの造形学校に招聘することを試みたりもしていた。
このように両者が互いに関心を抱いていたことを知っていたバウマンは朗読会を企画するにあたって、ハイデガーに参加可能な日程を尋ねた。ハイデガーはそれに対する返事で、自分は長らくツェラーンと知り合いになりたいと望んでいたこと、ツェラーンの深刻な危機についてもよく知っていること、朗読会の日程は七月二四日が望ましいことを告げている。(・・・)
この手紙にも示されているように、ハイデガーはツェラーンとの関係において、つねにツェラーンの病状を気遣い、彼を精神的危機から救うために手助けができればと考えていた。」
「ハイデガーは自分からナチス加担が話題になるようツェラーンに水を向けた(・・・)、彼はこの点について一度、ツェラーンと語り合う必要性を感じていたのだろう。そしてツェラーン自身も、もともとこの話をハイデガーにぶつける覚悟でフラウブルクに乗り込んでいた。ハイデガーの誘いに乗る形で、ツェラーンは滔々としゃべりだした。両者の対話の立ち入った内容は残念ながら報告されていない。ただノイマンは先ほどの手紙において、ハイデガーは越えることのできない限界内においてツェラーンを納得させ、またツェラーンもハイデガーにその人柄と誠実さを納得させたと書いて居る。この報告が正しいとすれば、ハイデガーがツェラーンの問いかけに対して「沈黙」によって王子、ツェラーンはそのことに失望したという通説とは異なり、両者のあいだにむしろそれなりに意味のある対話が成り立っていたことになる。」
◎轟孝夫『ハイデガーの超-政治』
【目次】
序論
第1章 学長期の立場
第1節 「黒ノート」における超政治
第2節 学長就任演説「ドイツ大学の自己主張」
第3節 学長期の労働論
第4節 学長としての実践とその挫折
第2章 ナチズムとの対決
第1節 ナチ・イデオロギー批判
第2節 「黒ノート」における「反ユダヤ主義的」覚書
第3章 技術と国家
第1節 技術と総動員
第2節 近代国家に対する批判
第4章 「戦後」の思索
第1節 ハイデガーの非ナチ化
第2節 悪についての省察
第3節 戦後の技術論
第4節 放下の思索
結論
あとがき
参考文献
年譜
●著者紹介
轟 孝夫(とどろき たかお)1968年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。
現在、防衛大学校人間文化学科教授。博士(文学)。
専門はハイデガー哲学、現象学、近代日本思想。
著書に『存在と共同―ハイデガー哲学の構造と展開』(法政大学出版会)『ハイデガー「存在と時間」入門』(講談社現代新書)『ハイデガーの超ー政治』(明石書店)がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
