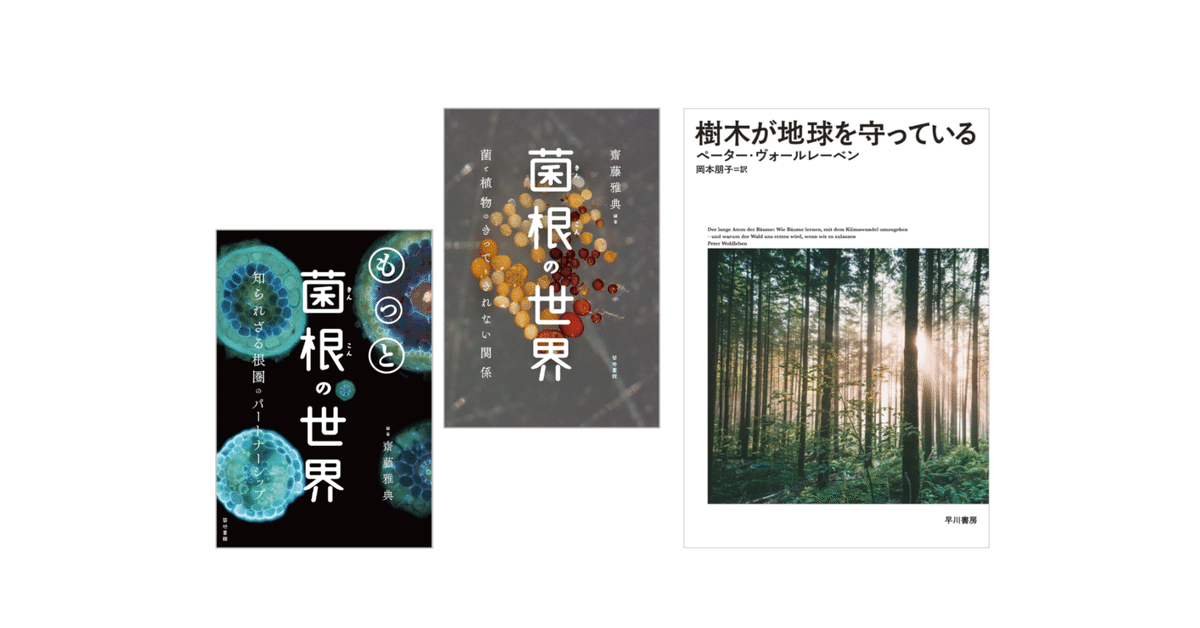
ペーター・ヴォールレーベン『樹木が地球を守っている』/齋藤雅典 (編著)『もっと菌根の世界』
☆mediopos3287 2023.11.17
「森の運命と人類の運命は
分かちがたく結びついている。」
これはたしかだ
環境問題が深刻な昨今人類は自らを
「自然の循環プロセスの中にふたたび組み入れ、
他の生物により多くの自由をあたえ、すべての生物が
安心して暮らせる地球の構築を目指す」必要がある
「気候変動を柔軟に乗り越えられるだけの
効率のよい社会的共同体を形成している」樹木を
広い範囲で再生させることで
人類も新たな道を歩んでいく希望がひらかれる
ペーター・ヴォールレーベンは
前著『樹木たちの知られざる生活』に続き
「人新世」と名づけられている時代に代わる
新たな地質時代としての
「樹木世」が提唱されることを願い
『樹木が地球を守っている』を著している
テーマは森を再生させるために
「森への介入をやめ、
自然に再生が行われるのを待つ」こと
「人間は自力で農園はつくれても、
森はつくれないと知る必要がある」
樹木や森林に関する生態の研究は
急速に進んでいるが
いまだ「木の謎は、カーテンをほんの少し開いた程度
開明されたにすぎない」という
そのなかでも細菌や菌類といった微生物の役割については
やっと知られ始めたといったところだ
植物と微生物の関係や森の知性については
齋藤雅典『菌根の世界』と
スザンヌ・シマード『マザーツリー』を
mediopos2146(2020.10.1)と
mediopos3000(2023.2.3)でとりあげたことがあるが
『樹木が地球を守っている』では
「菌根菌」ではなく「根粒菌」についてふれられている
菌根菌はリン酸を
アブラナ科・アカザ科・タデ科植物以外に供給するのに対し
根粒菌は窒素をマメ科植物に供給する
(その違いと共通点そして役割については
セイコウエコロジアbySEIKOSTELLAのサイトから
「菌根菌と根粒菌の違い」にわかりやすくまとめられている)
さてペーター・ヴォールレーベンは本書で
「ホロビオント(ホロ=全体、ビオス=生命)」という
微生物と共生する生命体についての考え方を示唆している
ひとりの人間にしても
「何千種もの細菌からなる小さな生態系」である
手のひらにさえ
一人当たり平均一五〇種類の細菌が存在し
左右それぞれの手においても
その組み合わせは大きく異なり
類似率は約一七パーセントにすぎず
しかも手洗いをしてもしばらくすると元にもどるという
いうまでもなく樹木も
そうしたホロビオントとして存在し
「同じホロビオントは一つとして存在しない」
そうしたホロビオントとしての生態系が
無数に集まってこの地球上の環境をつくりあげている
いまだそれらの「謎」はほとんど未知のままで
現状は環境破壊どころか
意図的な戦争や医療による人間そのものの破壊さえ
激しく進行しているところだが
そうしたさまざまなかたちでの破壊を抑止しながら
環境に対して「適度な謙虚さ」をもち
自然の自己治癒力を活かす方向へと
シフトしていくのは喫緊の課題だといえる
■ペーター・ヴォールレーベン(岡本朋子訳)
『樹木が地球を守っている』(早川書房 2023/9)
■齋藤雅典 (編著)『菌根の世界』(築地書館 2020/9)
■齋藤雅典 (編著)『もっと菌根の世界』(築地書館 2023/9)
■セイコウエコロジアbySEIKOSTELLA
「菌根菌と根粒菌の違い|共通点と役割を徹底解説!!」
(ペーター・ヴォールレーベン『樹木が地球を守っている』〜「まえがき」より)
「森の運命と人類の運命は分かちがたく結びついている。(・・・)樹木は現在進行中の気候変動を柔軟に乗り越えられるだけの効率のよい社会的共同体を形成している。それだけでなく、二酸化炭素を吸収し、その能力はどんな科学技術よりも優れている。したがって、森を活かすことは人類にとって最善の選択肢である。また、樹木には、周囲の気温を下げるだけでなく、雨量を適切な量に増やす働きもある。
以上のことを、樹木は人間のためにではなく、自分たちのためにやっている。」
「森林研究は、樹木の知られざる生態を解き明かすことで急速に進んだ。とはいえ、木の謎は、カーテンをほんの少し開いた程度開明されたにすぎない。とりわけ、細菌や菌類といった微生物の役割については、未発見の菌種が多いため、ほとんど解明されていないのが実情である。人間にとって腸内細菌叢が大切なように、樹木にとっても細菌や菌類は大事な存在だ。微生物なくして生命は存在しないと言っても過言ではない。この謎めいた菌の世界については、新たな研究報告がある。それによると、個々の木は独自の生態系を形成し、それは無数の不思議な生物が棲む惑星に匹敵するほど複雑だという。
さらに、森全体に目を向けると、驚くべき事実が判明する。森は大規模な気流を形成し、その気流は雨雲を数千キロメートルも離れた他の大陸まで運び、本来なら砂漠であるような場所に雨を降らせている。
樹木は、人間が引き起こした気候変動にただ受け身で耐えつづける生物ではない。環境を自らつくり出し、コントロール不能に陥りそうなものがあれば、それに対処するクリエーターである。
樹木は、環境の変化にうまく対応するために、二つのことを必要とする。それは、時間と静寂である。人間が森に介入するこちょは、どんな形であれ、生態系を乱し、森が新たな均衡を取り戻す機会を奪ってしまう。森を散策している際に、何十年も続けられた皆伐の現場を目の当たりにし、林業が森林破壊を助長していることを知った読者も大いに違いない。それでも、希望はまだある! 森は人間が放置すれば、どんな場所であれ素早く再生する力をもっている。私たち人間は自力で農園はつくれても、森はつくれないと知る必要があるだろう。森を助けたいなら、森への介入をやめ、自然に再生が行われるのを待つのがいい。適度な謙虚さと自然の自己治癒力に対する楽観的な見方さえもてれば、未来はとりわけ「緑豊かな」ものとなるだろう!」
(ペーター・ヴォールレーベン『樹木が地球を守っている』〜「数千年の学び」より)
「生涯学習は現代の教育政策が生み出したものだと考えるのは間違いだ。樹木は何百万年も前からこれをやってきたのだから。特に何前年も生きつづける樹木にとって、学習は生き延びるために不可欠である。端渓の生物は繁殖かつ大量に繁殖し、その際に遺伝子の突然変異を起こすことで必要な適応力を子孫に身につけさせることができる。たとえば、腸内細菌の代表格である大腸菌は、最適な条件下では二〇分ごとに繁殖する能力をもっている。こんなことは、樹木にとっては夢物語でしかない。極端な場合、成熟するまで数世紀かかることもある。」
「新しい経験をもとに行動を変えることを学習という。学習は長寿の生物にとって、生き延びるための最も重要な戦略である。
じつは植物は、私たちが考えているよりも複雑な方法で学ぶことができる。」
「生涯を通じて学びつづければ、知識は大量に増える。人間はそれらの知識を、近代以前には口承で次世代に伝え、近代以降は書物やコンピュータに保存してきた。しかし、木はどうだろう? 一本の木が死ぬと、その木が身につけた知恵も一緒に消えてしまうのだろうか? 「そうにちがいない」と、科学者は長年考えてきたが、最新の研究結果がこれをくつがえした。じつは、樹木も知恵を次世代に伝えている。」
「木は生涯をとおして学習し、その種には最新戦略が書き込まれている。よって、生まれた子どもは親と同じ失敗を繰り返して一から学び直す必要はない。(・・・)親木が長生きすることはデメリットではなく、逆に大きなメリットになる。なぜなら、木は年を取れば取るほど賢くなり、環境への適応力が高まるからだ、子どもの木は親の木が何世紀にもわたり学習したものを受け取ることになる。」
(ペーター・ヴォールレーベン『樹木が地球を守っている』〜「細菌————過小評価されている万能選手」より)
「土壌の中に生息する生物種の数についてだけは、フォートコリンズにあるコロラド州立大学のケリー・ラミレス博士率いる研究チームのおかがで、暫定的な数値が出ている。研究チームは、ニューヨークのセントラルパークで約六〇〇カ所の土壌サンプルを採取し、その中に含まれる遺伝子を分析した。その結果、一六万七一六九種の生物が発見された、それらはすべて細菌種に分類される微生物であり、なんと、そのうちの約一五万種は新種だった!」
「微生物は貴重な存在なのだ! その重要性は私たち自身の身体が教えてくれる。人間の身体の中には、少なくとも細胞と同じぐらい多くの細菌が存在している。したがって、細菌は、血液細胞や感覚細胞と同じように人間の身体の一部である。細菌の研究では、細菌がどれほど人間に影響をあたえるかが明らかにされている。たとえば、腸内細菌は、脳内の神経伝達物質をつくり出している。
(・・・)
一人の人間は、何千種もの細菌からなる小さな生態系といっていい。細菌の組み合わせが指紋のように一人ひとり違っている。ある研究によると、人間の手のひらには、一人当たり平均一五〇種類の細菌が存在しているという。しかも、細菌の組み合わせは、左右の手で大きく異なり、左右両方の類似率は約一七パーセント。これが、他人の手との比較になると、一三パーセントにまで下がる。この研究の対象になった被験者の手のひらの上では、計四七四二種類もの細菌が見つかった。これを、脊椎動物の種の多様性と比較してみるとその違いは明らかだ。(・・・)人間の手のひらのほうが生物多様性という点では優れていることになる。ちなみに、手のひらの上の小さな生態系は、手を洗っても壊されることはない。手洗いのあとしばらくすると、細菌が急速に繁殖して元どおりになるという。
人間は微生物なしでは生きられないし、微生物も人間なしでは生きられない。科学者はそうした共生関係にある生物を一つの生命体ととらえ、ホロビオント(ホロ=全体、ビオス=生命)と名づけた。地球上には多数のホロビオントが生息している。こういうと、まるでSF映画のように聞こえるかもしれない。しかし、人間のような一〇〇兆億個もの細胞からなる多細胞生物は、これまでのような個体として認識されるだけでは、多くの場合、科学的意味をなさなくなってしまった。ホロビオントという概念を受け入れると、種の多様性という見方すら非常に不十分に思われる。というのも、同じ生物種の中でも、ホロビオントは非常に他種多彩であるからだ。同じホロビオントは一つとして存在しない。」
「植物、特に樹木は、細菌との協力や融合を昔から行ってきた。」
「かつては、菌類と藻類が融合して子実体を形成することも「共生」と呼ばれていた。しかし、菌類と藻類は子実体を形成することで独自の「種」を形成し、その後は別々には生きられない。したがって「共生」という言葉は適切ではない。菌類と藻類が融合して形成する「種」は地衣類と呼ばれ、地衣類は「ホロビオント」とみなされる。そう解釈しないと、私たちの血液の中で病原体を攻撃する食細胞も、人間の体の一部ではないことになるだろう。
根粒菌は少なくとも木と融合する前は独立した存在である。そのため、木は根から栄養分を周囲の土に放出して、根粒菌をおびき寄せる。それに気づいた根粒菌は、木の最も細い根の部分である根毛に向かって移動する。根毛が根粒菌を認識すると。木は根粒菌の侵入を許可する。私にいわせると、この時点で、「共生」は終わり、木rと根粒菌は融合し、新しい存在(ホロビオント)に生まれ変わる。そこで、木が最初に行うのは、新しい住人の家として根に小さな粒を形成すること。もちろん、家をつくるためにはエネルギーが必要だが、消費したエネルギーは窒素肥料という形で返してもらえる。そのおかげで、根粒菌と融合した木は、窒素が少ない土地でも生長することができる。通常、木は周囲の植物よりも背丈を伸ばそうとするため、根粒菌との融合が大きなメリットになる。根粒菌の恩恵を受けているのは、ハンノキのいくつかの種類はニセアカシアといった木である。多くの樹種は生まれながら細菌と融合するための機能が備わっていない。いっぽう、そうした機能があっても、それを使わない気も存在する。その代表的なものがセイヨウシデである。」
「新しい知識を受け入れようとしない科学者は、今も昔も存在する。しかし、林業の場合、そうした科学者の意見が悲劇をもたらしかねない。森林は気候変動抑制の不可欠な要素であるにもかかわらず、林業は世界の森林の三分の二に悪影響を及ぼしている。
多種多様な生物と大量の微生物で構成されている複雑な生物共同体が、森林の生態系を維持している。そう考えると、林業はまるで、陶器屋を訪れた、暴れん坊のゾウのようなものだ。気候変動に対処する方法として林業従事者が出したアイデアは「森の交換」。目下、彼らはブナの森を外来種のセイヨウグリやテバノンスギを植林した人工林と交換しようとしている。森林はいよいよ自然とはかけ離れた人工的な形へと変化し、気候変動に耐えられなくなる危険性が高まっている。」
(ペーター・ヴォールレーベン『樹木が地球を守っている』〜「全員が同じ方向へ進む必要があるのか」より)
「頑固者集団が方向転換するかどうかを見届ける時間は、私たちには残されていない。いまこそ、森には「新しい風」が必要だ。その風は林業システム全体を変えることでしか吹かせることはできない。
じつは、もうその風は吹いている!」
(ペーター・ヴォールレーベン『樹木が地球を守っている』〜「森はふたたび戻ってくる」より)
「近年、科学者たちは、地球が地質学上の新時代に突入したとして、それを「人新世」と名づけた。この時代は、私たちが終わらせなければならない。とはいえ、私は人類や現代文明の破壊を提案しているわけではない。いまこそ、人類は自らを自然の循環プロセスの中にふたたび組み入れ、他の生物により多くの自由をあたえ、すべての生物が安心して暮らせる地球の構築を目指すべきだ、といいたいのだ。かつて、地球上の大陸の大半は森林でおおわれていた。その森林を広い範囲で再生させることは、未来への希望につながるだろう。それを実現する方法は、食肉消費量の削減などを例に挙げて説明したとおりである。近い将来、新たな地質時代として「樹木世」が提唱されることを私は願っている。」
(ペーター・ヴォールレーベン『樹木が地球を守っている』〜「森林に対する無知と謙虚さについて————ピエール・イービッシュによるエピローグ」より)
「気候変動は、謙虚であることの大切さを教えてくれる。私たち人間は、自らの「無知」と共存することを早急に学ばなくてはならない。人間は自信をもってはいけない。また、自然がもつ知識を決して過小評価してはならない。優秀なエンジニアたちとテクノロジーが生み出す解決策が地球を救ってくれると信じるのではなく、昔ながらの「慎重さと予防の原則」に従って行動しなくてはならない。人間は「無知」を受け入れ、尊重することで、よりよい道を見出せるようになるだろう。」
(齋藤雅典 (編著)『もっと菌根の世界』〜「はじめに」より)
「陸上の植物種数は三〇万種を超えるとも言われているが、その陸上植物の八割以上の種では、菌根菌という菌類(カビの仲間)が根に共生していて植物の生育を助けている。根に棲む菌根菌は植物から光合成産物を受け取る代わりに土から養分を吸収し、それを植物へ供給している。菌根菌と植物は、養分のやりとりを通して、相互に持ちつもたれつの共生関係にある。しかし、共生とはいっても、その内容は多様である。菌の種類も植物の種類も多様であるし、お互いに持ちつ持たれつの相利的な関係もあれば、中には、まるで植物に寄生しているかのような菌根菌もいる。かと思えば、懇々菌に栄養を依存してしまっている植物もいる。
このような多様な菌根世界について解説した『菌根の世界————菌と植物のきってもきれない関係』を二〇二〇年に出版した。幸いにして、多くの方々にご好評をいただき、刷を重ねてきた。そこで本書では、前書では取り上げることのできなかったエリコイド(ツツジ型)菌根の章を加え、菌根の分野で国内外の研究をリードする研究者に、「知られざる根圏のパートナーシップ」を探るために、どのように、またどのような思いで研究を進めてきたか、苦労話も含めて、書いてもらった。」
(齋藤雅典 (編著)『もっと菌根の世界』〜「おわりに————菌根菌の農林業への利用」より)
「①アーバスキュラー菌根菌
農作物を含む広範囲な植物種に共生するアーバスキュラー菌根菌には、作物の生育改善やリン酸施肥量遡源の効果が期待されている。一般的には、播種、育苗段階でアーバスキュラー菌根菌資材が摂取される。国内外の多くのメーカーがさまざまな種類のアーバスキュラー菌根菌資材を販売している。ネギのように比較的栽培期間が長く、リン酸吸収力の弱り作物への効果が期待されている。」
「畑を耕さない不耕起栽培という農法がある。耕起することにとってかえって土壌浸食を引き起こすことから開発された栽培法であるが、最近では環境再生型農業の一つとして注目されている。耕起すると土壌中に広く伸長したアーバスキュラー菌根菌の菌糸が切断されてしまうために、菌根気の働きが抑制される。不耕起栽培では、菌糸が切断されないために、菌根菌を介した養分吸収の働きが継続的に担保される。」
○ペーター・ヴォールレーベン (Peter Wohlleben)
1964年、ドイツのボンに生まれる。大学で林業を学び、20年以上、森林管理官として働いた経験をもつ。現在は、自ら設立した森林学校で、イベントや林業従事者向けのコンサルティングを行なうほか、世界各地で天然林の再生を促す活動を展開している。著書『樹木たちの知られざる生活』(早川書房刊)は、ドイツで100万部を超えるベストセラーを記録し34カ国に翻訳された。2021年に刊行された本書もドイツの有力誌『シュピーゲル』でベストセラーリスト入りを果たしている。
○齋藤雅典
1952年東京都生まれ。東京大学大学院農学系研究科を修了後、農林水産省・東北農業試験場、同・畜産草地研究所、農業環境技術研究所を経て、東北大学大学院農学研究科教授。2018年に定年退職、同・名誉教授。研究テーマは、アーバスキュラー菌根菌の生理・生態とその利用技術。農業生態系における土壌肥沃度管理。農業活動に関わるライフサイクルアセスメントなど。おもな著書に、"Arbuscular mycorrhizas: molecular biology and physiology"(共著、Kluwer、2000)、『微生物の資材化──研究の最前線』(共著、ソフトサイエンス社、2000)、『新・土の微生物(10)研究の歩みと展望』(共著、博友社、2003)、 『菌根の世界──菌と植物のきってもきれない関係』 (編著、築地書館、2020)などがある。
■セイコウエコロジアbySEIKOSTELLA
「菌根菌と根粒菌の違い|共通点と役割を徹底解説!!」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
