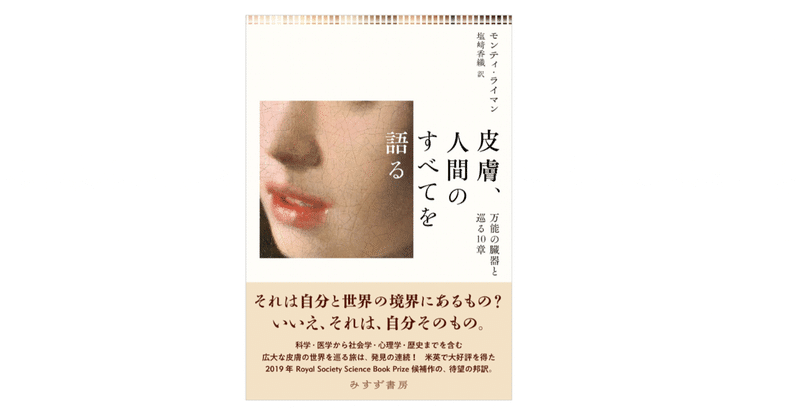
モンティ・ライマン『皮膚、人間のすべてを語る――万能の臓器と巡る10章』
☆mediopos2740 2022.5.19
生まれてくると
ひとの魂は
身体のなかに次第に
入りこんでゆき
はじめのあいだ
皮膚は魂の内と外とを
完全に分けるものでなかったのが
鏡像段階を経ながら
他者を他者として認識するようになるとともに
自分を自分として捉えるようになり
皮膚によって内と外とが
隔てられている感覚を持つようになる
逆にいえば身体が
ひとの魂に入りこんでくるともいえるが
物理的に内と外を分けている皮膚は
魂としての内と外とを分けるものでもあり
その両方の側面において
皮膚は私たちが「私たち自身」であることを
さまざまなかたちで支えるものとして働いている
以下の引用のなかでとりあげているのは
皮膚についてのさまざまな視点のうち
主に「魂の皮膚」についての視点である
創世記のアダムとエバの物語のなかでは
堕落した後には裸を恥ずかしがるようになるが
その堕落とはまさに
皮膚が自他を分けていることを意識するようになり
みずからの皮膚を覆う必要を
感じるようになったということにほかならない
そしてそれは物理的な皮膚への覆いという以上に
「魂の皮膚」への覆いということを意味している
引用のなかで
ディディエ・アンジュー
ガストン・バシュラール
ミシェル・フーコーという
フランスの三人の哲学者の
皮膚についての視点がとりあげられているが
そこで示唆されているのは
「皮膚は物質的に存在しているだけでなく、
想像上の、あるいは実在しない虚構の存在」
「観念的な存在」であるということだ
境界性パーソナリティ障害といわれるものも
皮膚による物理的な自他の境界ではなく
自他の境界は「何らかのかたちで精神構造を覆い包んでいる
心的な外皮としての皮膚」となっているのだが
それはある意味では個人的な差異にすぎず
「魂の皮膚」は誰にとっても物理的な皮膚とは重なってはいない
そしてひとがやがて死を迎えるとき
ひとの魂は身体の(皮膚の)外へと出ていくことになる
あるいはひとの身体がひとの魂の外へと出て行くことになる
その意味で物理的に存在する皮膚という境界は
肉体をもつことで自他を認識する契機であると同時に
魂の皮膚としても働きはじめ
私たちはその皮膚によって自分自身をイメージすることで
自分自身を作りあげていくのだということがわかる
■モンティ・ライマン(塩﨑香織 訳)
『皮膚、人間のすべてを語る――万能の臓器と巡る10章』
(みすず書房. 2022/5)
(「第10章 魂の皮膚/皮膚が思考に及ぼす影響————宗教、哲学、言語について」より)
「人間の臓器の中で、皮膚はスピリチュアリティに欠かせない二つの特性を兼ね備えたユニークな存在で、宗教的に特別な位置を占めている。その特性とは、物質的空間と感覚の機能だ。たとえばアメリカ先住民のナバホ族にとって、皮膚は本来の意味で彼らの居場所を決めている。人間は手足の指紋によって天地のあいだに固定されていて、「足の指にある渦巻きはわれわれを地面につなぎとめる。手の指先の渦巻きはわれわれを天につかまらせる。これがあるから、あちこちを動き回っても倒れない」という。なるほど、私たち誰にとっても、皮膚のバリアは内面の自己を宇宙の万物と隔てるものだ。それは自分以外の世界からのバリアであり、同時にその世界との接点でもある。(・・・)皮膚は神聖な空間を覆い隠すカーテンに近い。内側にある肉体という神殿を取り囲む壁ともいえるだろう。この壁はちょっとやそとのことでは決して破られない。私はたった一週間のあいだに、人間の皮膚を切った経験者二人と話したことがある。一人は肝臓外科医、もう一人は救急に担ぎ込まれたギャングのメンバーで、その直前にナイフによる殺傷事件で逮捕されていた。二人とも、初めて人の皮膚を切り開いた時のことを生々しく語ってくれた。もちろんその行為に及んだ理由はまるで異なるが、聖なる境界を越え、触れてはならないところに触れてしまったという感覚は共通していた。
皮膚は肉体と万象とを分かつバリアとして機能していながら、肉的な欲望に身を任せる私たちのきわめて重要な一部でもある。皮膚は感覚器官であり、ありていにいえば、欲望と罪と恥が入り混じるスリルと興奮に満ちた最大の生殖器だ。皮膚は性と死という人間のもろさを連想させる。皮膚がむき出しの状態でそこにあることは、創世記のアダムとエバの物語にみられるように、魂の堕落に結びつけられる。堕落前の世界で、人は恥を知らず裸だった。そして堕落したあとは、自分たちの身体を覆う必要を感じたのだ。」
「信仰をもたない人にとっても、皮膚は深く哲学的な存在だ。皮膚にはこの世のものとは思えないような感じがある。それに、身体の表面で起こる不可思議な現象は誰もが体験済みだ。恥ずかしさからの赤面、名状しがたい性のふれあい、心に響く音楽を聴いて湧き上がる身震い————これらは皮膚が私たちをさらなる高みへと連れていく方法のほんの一部にすぎない。皮膚は人間の本質とじつに複雑に絡み合い、身体の外部とはまったく異なるさまざまな形態を帯びてきた。人類は皮膚がもつ超自然的な意味について長らく考えをめぐらせてきたが、この重要な対話の概略を把握するために、三人のフランス人哲学者に登場してもらうことにしよう。
優れた精神分析学者でもあったディディエ・アンジューは、生涯の大半を《皮膚−自我》という概念の研究に捧げた。アンジューによれば、身体の表面は心の機能に一体化している。アンジューが言葉で表そうとしたのは、私たちが自分の身体を取り囲んでいると想像している象徴的な皮膚のことだ。物理的な皮膚が私たちの身体を取り囲んでいるのと同じように、私たちはみな、何らかのかたちで精神構造を覆い包んでいる心的な外皮としての皮膚があると思っている。(・・・)アンジューの抽象的な概念には、物理的・身体的な皮膚の機能が反映されている。《皮膚−自我》は私たちの思考や感覚を含み、自分のものではない観念や自我から私たちを守り、外界とかかわり、性的感覚を刺激し、私たちひとりひとりを個人として分かつものだ。(・・・)
科学的というよりはむしろ観念的な議論だが、《皮膚−自我》はパーソナリティ障害のスペクトラムとの関係できわめて説得力のある概念となっている。たとえば自己愛性パーソナリティ障害の人では、心的な皮膚が病的なまでに厚くなっているとみることができる。厚みを増した皮膚の二重構造は、自分は人より優れている、無敵であるという感覚を与えるだけでなく、他者に感情「移入」する感覚を鈍くする。(・・・)この対極に位置づけられる情緒不安定パーソナリティ障害は、境界性(ボーダーライン)パーソナリティ障害とも呼ばれる。アイデンティティのゆらぎや見捨てられる恐怖、情緒不安定といった特徴があるが、この場合の《皮膚−自我》は弱く不完全で、小さな穴がたくさんあいている状態だ。(・・・)
皮膚がどのようにして空間を隔てているのかは、現代哲学にも影響を及ぼしてきた。皮膚はいわば、身体的な自我と心的な自我がともに閉じ込めれた家のようなものだから。外界を遮断する壁としてのはたらきと、外界を取り入れる窓としてのはたらきの両方を兼ね備えている。この二重の役割は、ガストン・バシュラールの独創的な著作『空間の詩学』で次のように見事に表現されている。
・・・・・・存在の境界において、存在が現れ、かつ隠れたいと望むこの領域において、開けたり閉じたりする動作はきわめて多く、頻繁に向きが逆になり、またためらいに満ち満ちてもいることから、対の結論を導けよう。すなわち、人間とは半開きの状態である。
最後となる三人目の哲学者、ミシェル・フーコーは、哲学的な皮膚のとらえ方をさらに進め、社会的権力が人間の身体とアイデンティティの概念にいかに影響を及ぼすかを検討した。身体的な皮膚は個人と社会の両方のレベルで人間の本質と深くかかわっている。フーコーはこの認識を踏まえ、ボトックスから身体装飾に至るまで、皮膚の外見に意図的な操作を加えることは「自己のテクノロジー」であるとした。私たちは「幸福や純潔、完全無欠、不死といった何らかの状態に達するため」に自分の身体を変える。つまり、皮膚を変えれば自分が変わるのだ。
このような哲学的な見方を受け入れると、皮膚は物質的に存在しているだけでなく、想像上の、あるいは実在しない虚構の存在でもあることを認めざるをえなくなる。」
「比喩的な皮膚が物理的な皮膚を超越するもっともありふれた方法のひとつは日常の言葉遣いであることを指摘しておきたい。たとえば「皮膚が厚い→鈍感」「誰かを皮膚の下にもぐりこませる→その人のとりこになっている」「触られた→心を動かされた・感動した」「人の気持ちを傷つける」などは刺激を知覚する皮膚が私たちの感情に訴える力から派生しているし、「皮膚が硬くなっている→無感覚」や「触覚がない→無神経」は他人の感情に比喩的に「触れて確かめる」ことができない人を描写する言葉だ、また、皮膚の物語を一時的に変えるときに私たちがする「化粧(メイクアップ)」自体、信じられないほど示唆に富む表現といえるだろう。身体の表層の見た目を変えることによって、私たちは自分自身を変え————実際に「作り上げ(メイクアップ)」————ているわけだ。
(・・・)
皮膚とは、現実にそこにあるものというだけではない。それは観念的な存在だ。私たちが皮膚というものを封じ込めようとしているときに実体としての皮膚がずっと私たちを包み込んでいるのと同じように、皮膚が象徴するものは歴史の流れを決めてきたし、私たち自身の生き方にも深い影響を及ぼしている。皮膚は忘れられた臓器として長いあいだ包み紙だとみなされ、「肝心の中身」を診る医学でエコルシェの像をつくるときには剥ぎ取られてしまった。だが、そんな皮膚を見れば見るほど見えてくるんは、身体の外側に沿ってあるものこそ、人間を人間たらしめているものの本質だということだ。皮膚とがすなわち、私たち自身なのだ。」
【目次】
名称と用語について
プロローグ
第1章 マルチツールのような臓器
皮膚の構造とはたらき
第2章 皮膚をめぐるサファリ
ダニやマイクロバイオームについて
第3章 腸感覚
身体の内と外のかかわり
第4章 光に向かって
皮膚と太陽をめぐる物語
第5章 老化する皮膚
しわ、そして死との戦い
第6章 第一の感覚
触覚のメカニズムと皺
第7章 心理的な皮膚
心と皮膚が互いに及ぼす影響について
第8章 社会の皮膚
刻んだ模様の意味
第9章 分け隔てる皮膚
ソーシャルな臓器の危険な側面──疾病、人種、性別
第10章 魂の皮膚
皮膚が思考に及ぼす影響──宗教、哲学、言語について
本書に寄せて(椛島健治)
参考文献
用語解説
索引
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
