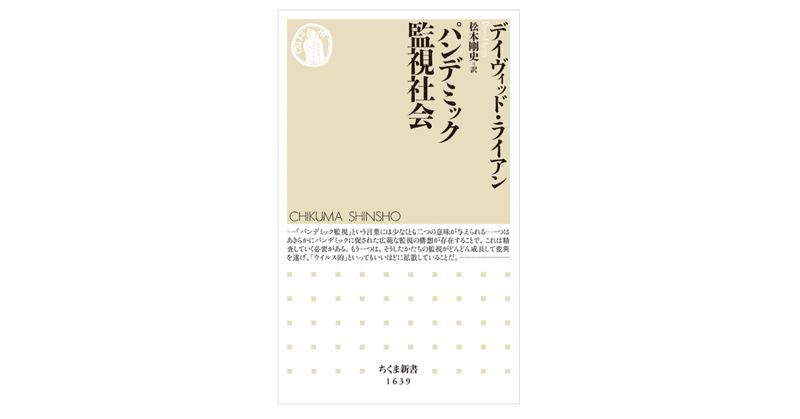
デイヴィッド・ライアン『パンデミック監視社会』
☆mediopos2675 2022.3.14
フーコーはジェレミー・ベンサムが考案した
「パノプティコン」という
囚人監視のための刑務所の設計を紹介している
それに先だって『監獄の誕生』では一八世紀の疫病と
そに対応し統制する政府とを結びつけていたが
新型コロナウイルスの感染拡大の
二〇二〇年代初頭の時点において
『エコノミスト』誌は
パンデミック監視が「パノプティコン」のように
なりはしないかと警告し
それを「コロノプティコン」としていた
しかもその「コロノプティコン」では
「多くの人たちが病や死を恐れて自らを律する」というのだ
つまりみずからすすんで監理・監視されることを望むようになる
その重要なツールのひとつがワクチンである
その際にコロナウイルスについての情報開示は少なく
その危険性と救世主としてのワクチン接種の情報のみが
政府と各種メディアから多量に露出される
もちろんそこではネガティブな情報は排されている
学校教育で教えられた情報を覚え
それをみずからに適用することしかできないとき
そうした情報は疑われることのないまま
テストに決められた「正解」を記入するように
教えられた行動へと向かうことになる
各国政府のなかでは
そうした「正解」以外を許さない体制をとる場合が
多く見られるのはいうまでもない
監理する絶好の機会でもあるからだ
政府だけではなく「アップル、フェイスブック、アマゾン、
グーグルなどの企業は、欧米社会でのパンデミックに大きく関与し」
「正解」以外の情報を排することさえ行っている
しかもコンピューターとインターネットというツールによって
現代は個人の情報がきわめて監理しやすい情報となっている
現在進行中の「戦争」もまた同様の状態である
そしてそこにも「コロノプティコン」ならぬ
「ピースプティコン」とでもいえるようなものが見られる
「ピース」とは「平和」だが
そのピースは与えられた情報だけをもとにしたものであり
与えられた「正解」とされるものへと
みずからがすすんで情緒的に意思態度を決めているのである
そこでも別の視点での情報は排されてしまうことになる
そうした「監視資本主義」のなかで
「自ら進んで監視に加わる」のではなく
たしかな情報リテラシーをもちながら
批判的アプローチをもとに
「監視」に代わる別のシステムを再構築することが
切に求められているといえる
おそらくこれからもまた
あらたな「監視システム」が与えられ
多くの人がその操作された「正解」を
みずからが進んで答えようとするだろうが
そのときまず必要なのは「正解」が
与えられたものかどうかを吟味することだろう
特定の意図のもとに与えられたものであるとき
多視点的なものを可能とする必要な情報は与えられない
そのときどうするかである
重要なのは「正解」ではなく恐れず「問うこと」なのだ
■デイヴィッド・ライアン(松本剛史訳)
『パンデミック監視社会』
(ちくま新書 筑摩書房 2022/3)
(「第2章 感染症が監視を駆動する」より)
「二〇二〇年代初頭の新型コロナウイルスの感染拡大は、いまだかつてない監視の増大の引き金となった。この突然の監視の高まりは洪水にも似て、急速かつ不意に襲いかかり、パンデミックそのものと同じように社会全体にあふれ返る。ここ数十年、データが各組織のなかだけでなく組織どうしをつないで流れる可能性が増すことで、その流動性は促進されてきた。海底ケーブルや地下ケーブルを使用するインターネットは、個人の機器かたアクセスされることで、この流れを世界規模に−−−−地球自体への悪影響を考えれば、惑星規模にまで−−−−拡大している。これは少なからず、データフローの多くを生み出すプラットフォームの力によるものだ。
(・・・)今回のパンデミックは単に医療や衛生上の事態というのにとどまらず、社会、経済、また政治にも関わる事態なのだ。フランスの哲学者ミシェル・フーコーは著書『監獄の誕生』のなかで、一八世紀の疫病へと対応と、より規律訓練を求める政府の台頭とを結びつけたことで知られる。その後フーコーは、ジェレミー・ベンサムが考案した「パノプティコン」という「すべてを見る」刑務所の設計について論じた。『エコノミスト』誌はパンデミック初期の時点でこれと同じことを案じて、「コロノプティコン」が出現するのではないか、パンデミック監視が「すべてを見る」ものになるかもしれない、と警告している。ベンサムの囚人たちは、権威を恐れて自らを律することを想定されていたといえるだろう。コロノプティコンでは、多くの人たちが病や死を恐れて自らを律するのだ。
しかしパンデミック監視を探求するうえで、その視点が唯一の、あるいは最良のものなのだろうか。フーコーが最初に監視を理解しようとした例は、刑務所ではなく、ペストに見舞われた都市だった。ウォーリック大学のスチュアート・エル丼は、これがどうしてパノプティコン以上に今日の監視社会の典型となるのかを示している。実際にフーコーの説明では、「この(ペストの都市の)監視のもとになっているのは、絶え間のない記載だ。総代から代官への報告、代官から判事あるいは市長への報告である」。これをデジタルに置き換えて読み返せば、私がこの本に書いてあることと非常によく似た印象になる。パンデミックが監視をまったく新たな局面へと押しやっているのは確かだが、その性格はまだ完全にあきらかになってはいない。
(・・・)
実際に感染して直接の影響を受けたのでなければ、大多数の人々のパンデミック体験とは、おもにロックダウンや商店の閉鎖であり、加えていうなら中流の人たちにとっては、家で過ごす時間が長くなることだった。これらは私たちの「通常の」活動や行動を制限し、いろいろな失望や不満を引き起こすだけにとどまらず、パンデミック監視をさらに増大させるための手段ともなるのだ。社会的状況としてのパンデミックは、ときにはまったく新たなかたちで、監視を家庭へと持ち込んでくる。とくに家で仕事や買い物や勉強をしたり、娯楽を求めたりすることは、雇用主、商店、学校、プラットフォーム企業による複数のモニタリングに対してデジタルな扉を開け放つことになる。」
(「第3章 ターゲットは家庭」より)
「フーコーは一七世紀に疫病のペストが流行した際の緊急措置を検討し、これは「完璧に統治された都市」という歪んだユートピアであると表現した。「ペストに見舞われた町は、全体にわたって階層化、監視、観察、文書が行き渡り−−−−−あらゆる個人の体に明確にのしかかる広範な権力の機能によって、町は身動きがとれなくなっている」。フーコーが描き出すのは、普段どおりの活動が制限された街の様子だ。「誰もが屋内にとどまるように命じられた・・・・・・細かく区分され、動きのない、凍りついた空間。個人個人がそれぞれの場所に固定され・・・・・・検査が絶え間なく機能している」。
しかし新型コロナウイルスという「疫病」では、デジタル技術によって、フーコーの言う「検査官」「民兵」「警備員」の現代版の多くが家庭のなかにまで入りこんでいる。」
(「第6章 民主主義と権力」より)
「二〇二〇年から二〇二一年にかけて、世界中の企業や政府が新型コロナウイルスと戦うための緊急対策に取り組んだ。グアテマラでが軍が、イスラエルでは治安課諜報機関のシンベトが動員される一方、公衆衛生上のルールの遵守を徹底するための警察を配備する国もあった。顔認証技術やドローンは監視に不吉な側面をつけ足し、そこまで大っぴらでない監視のための新たなデータ使用を可能にするため、また人々を自宅やコミュニティに閉じ込めるための法律や規則が急遽制定もしくは変更された。
こうした手法が以前から使われていた例もあるが、ほとんどの場合、人々は困惑しうろたえているうちに、権力は馴染みのない、あるいは強められたかたちで行使されるという思いがけない状況に置かれていた。(・・・)
世界中に共通する懸念は、こうした事態が行き過ぎて、「監視国家」を強化したいという誘惑に抗えない勢力が出てくるのではないかということだ。『エコノミスト誌』は、「すべてが統制下にある。COVID−19国家だ」と警告を発した。しかし今日のパンデミックの状況では、ショック・ドクトリンは政府だけでなく、民間企業のものでもあることを思い出す必要がある。(・・・)
アップル、フェイスブック、アマゾン、グーグルなどの企業は、欧米社会でのパンデミックに大きく関与している。」
(「第7章 希望への扉」より)
「監視資本主義の特徴とは、一般の人たちが協力して動いてくれるかどうかに依存していることだ。自ら進んで監視に加わる人たちは、プラットフォーム企業の求めるものを与え、その中毒的な性質を通じてそれを後押しできる。だが、プラットフォームに抵抗するという動機からそこに加わることもできる。これは監視の戦略に対し破壊をもたらす戦術だ。それと同じ懐疑と反発が、パンデミック監視も含めた監視全体への批判的なアプローチにつながっていく。私たちはみなこの監視に関わっている−−−−そしてその再構築に加わることもできるのだ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
