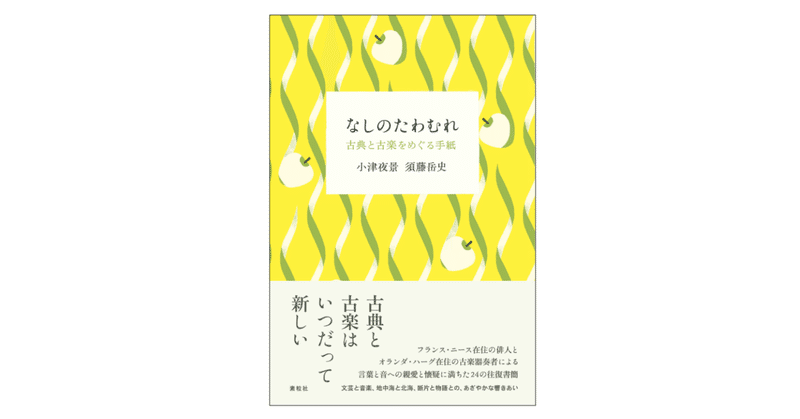
小津夜景・須藤岳史『なしのたわむれ/古典と古楽をめぐる手紙』
☆mediopos-3025 2023.2.28
フランス・ニース在住の俳人
小津夜景(おづ・やけい)と
オランダ・ハーグ在住のヴィオラ・ダ・ガンバ奏者
須藤岳史(すどう・たけし)による
言葉と音楽をめぐる往復書簡『なしのたわむれ』
ふたりの響き合う言葉は美しく深く
数々の意味深いテーマをめぐるものであるにもかかわらず
「音楽と言葉の中間ぐらいにある」
美しい「鳥たちのポリフォニー」のような手紙が交わされる
この往復書簡で響き合っている
豊かなポリフォニーについて
適切に紹介することはとてもむずかしいけれど
本書のタイトル「なしのたわむれ」は
「ないこと」(無)と「あること」(有)が
戯れているというそんな景色を表しているともいえるだろう
「不在と存在とをまたぎつつ、図として語れば地にのがれ、
地として語れば図に化ける世にも稀なるくだものに託し」
往復書簡は続けられ「問い」が深められていくようだ
(「くだもの」というのは勿論「梨」のこと)
音楽について
そして言葉について
響き合う言葉の応答によって
さまざまなイマジネーションが展開されているが
本書から感じとれたことを
ぼくなりの理解も加えながら
少しだけ紹介してみることにする
たとえば「言葉」と「意味」について
言語が発せられるとき
「ヒトの耳は意味を探してしまう」けれど
音は「言葉の外」にある何かなので
音楽を何かのための手段にしてしまわないかぎり
言葉から自由であり
言葉では捉えることはできないものを
捉えることもできる
けれども言葉は
どうしても意味を求めてしまいがちなため
その意味の内に閉じ込められてしまうことにもなる
言葉によって紡がれる物語も
「でも」「しかし」「だから」「また」「それから」・・・と
エピソードを関係づけてしまう「接続詞」があることで
「物語特有の整序性・体系性・超越性といった力」が生まれ
それが作り出す意味に閉じ込められてしまうから
言葉や音楽を
既存の意味のなかに閉じ込めないためにも
「物語から解き放たれた水平線」へと
音と言葉・物語への根源的な視線をひろげること
そうすることで
そこに「ないこと」と「あること」の戯れるポエジーも
可能となってくるのではないか
■小津夜景・須藤岳史
『なしのたわむれ/古典と古楽をめぐる手紙』(素粒社 2022/3)
(須藤岳史「第 2 信 耳は意味を探してしまう」より)
「私の住む街にはたくさんの野鳥が生息していて、裏手のバルコニーの正面のマロニエの巨木にもたくさんの鳥たちがやってきます。樹上で大合唱する鳥たちのポリフォニーに耳をすましていると、面白いことに気がつきます。やり方はこんな感じです。まずは音楽を聴くときのように各声部の線を見つけます。十を数えるあたりからは、個々の線が少し曖昧になってくるものの、まだそれらを聴き取ることができます。音楽もまた、多くの声部が同時に鳴っていても聴き取れるものです。これは声部同士が意味のようでありながらも意味の外にある「関係」だけを生むからです。対して、多くの人が同時に話すと何を言っているのかわからなくなります。耳が意味を求めてしまうからです。鳥たちのポリフォニーは音楽と言葉の中間ぐらいにあるのかもしれません。分節と未分節の汀。そこで遊ぶ鳥。そういうイメージが思い浮かびます。
そんなときにも、先に書いた「ヒトの耳は意味を探してしまう」ということについて考えてしまうのです。そして、意味の汀にあるもの、意味としてのかたちをとりそうでいて、同時に意味の生成を阻止する働きも含んでいる漠としたもの、そういったものに心を傾けてしまう自分のありようみたいなものについて考えてしまうのです。」
(小津夜景「第 3 信 なしのたわむれ」より)
「 世の中は有無のふたつをなしの木のいかに悟りてありのミの花 桃李園栗窓
こちらは「世界における有と無とをいかにして認識するか」といった文意に「なしの木」と「ありのミの花」をたわごとっぽく織り込んだ一首で、噺家ふうの転調を秘めているとでもいいましょうか。舌先三寸なくすぐりが魅力です。それから、あの一休にも「有無空の歌」と題された梨の狂歌があります。
ありの実となしといふ字はかはれどもくふうに二つの味ひはなし 一休宗純
伴信友『動植名彙』から引きました。「くふ」は「食う」と「空」の掛詞で「有りの実と梨は字が違う。けれどもたべれば同じ味しかない」という意味と「有と無は、空からみると同じものである」という意味とが重なっています。有無空という壮大な理念と俗っぽい感想との落差にこの人らしさがあふれています。
それはそうと、すでにお気づきかもしれませんが。わたしがこんなにもしつこく梨の話をしたのはほかでもない、あなたの手紙に「ないこと」が「あること」として情景をむすぶことの奇跡について書かれていたことが原因です。ただ「ない」とか「ある」とかいった話題はありふれた言説にどうしても収斂しやすいもの。そこで不在と存在とをまたぎつつ、図として語れば地にのがれ、地として語れば図に化ける世にも稀なるくだものに託し、ふだんとは異なる道筋をつけてみたかったのでした。」
(須藤岳史「第 4 信 辺境への誘惑」より)
「音は振動です。振動は離れているもの同士を結びつけます。例えば二人の人が少しだけピッチの異なる同じ音を何秒か一緒に発声すると、音は自然にひとつのピッチに落ち着きます。逆に、異なるピッチのままで発声を保持するのはとても難しいことです。音は互いに引き寄せられ、溶け合うことを求めます。
対して言葉は距離を生みます。言葉は切ること、つまり意味分節の働きにその機能を負っています。そこで言葉が獲得するのはロゴスです。そしてロゴスは形式を生み出し、普遍への無限の羽ばたきを獲得します。言葉の持つ切り離す力は、思考を、そしてその人自身を辺境へと誘います。これは結びつける力、いわば抱擁とは逆に、人を心の旅へと突き動かす力です。言葉はいくつもの角を曲がり、山を越え、岬を通って海を越え、遥か遠い地平へと私たちを運びます。」
(須藤岳史「第 8 信 詩と道と」より)
「「時」といいますと、一定方向への流れをイメージしますが、もし「時」が「解く」と同じ仲間の言葉だとするならば、むしろ一定の流れからはぐれることのほうが、より本質的な時間なのかもしれません。寄り道をすること。さまようこと。
音楽もまた寄り道や遊歩のようなもので、一定方向に流れる時間から独立しています。その自由さは音楽が音楽内の時間を生むこと。そして音楽が演奏を通して回帰し続けることに関連しているのだと思います。
芸術は進化するのではなく回帰するものであり、円環を生み続けるもの。芸術における新しさとは単に時間軸の先端にあるものを指しません。それは常に生まれ続けるものであり、誕生の瞬間への祝福そのものでもあります。」
(須藤岳史「第 15 信 うちのそと」より)
「記憶というのは概ね言語的です。夢を説明するにも、何かのエピソードを思い出すにも、多くの場合、そこに言語が介在します。さらに面白いのは音や香りは、私たちのうちにありながらも、言語の外にある何かだということです。音楽は言語では捉えることはできないゆえに、言語から自由なのですね。音楽の「ことば」で向かい合う時、「何か?」というある種の言語的な問い自体が消えてしまいます。音や香りは言語的プロセスを介さずに記憶を直接喚起します。プルーストのマドレーヌを持ち出すまでもなく、香りは記憶のフラッシュバックを引き起こしますし、また、記憶を失い、天に遊ぶ認知症の方たちが、幼少時や若い頃に聴いた音楽を耳にしたり、一緒に歌ったりすることをきっかけに、束の間の記憶を取り戻すという事例も、音楽の演奏を通して何回か体験しました。」
(須藤岳史「第 17 信 未来を読むこと」より)
「物語を紡ぐとか、エピソードに接続詞を与えることです。接続詞が生み出すのはまとまり同士の関係であり、その関係が時間の流れのなかに立体的な家を建てます。考えてみれば、私たちが「現実」と呼んでいるものもまた、かなり主観的な取捨選択を経て組み立てれらたかしりそめの家ということもできますね。
(小津夜景「第 18 信 ものがたりのはじまり」より)
「(上記第 17 信の引用部分を受けて)
のくだり、まさにこの接続詞がくせものだと睨んでいます。そして接続詞がつくりだす物語特有の整序性、体系性、超越性といった力にいかにして抗するかを、ことあるごとに考えてみるのです。」
「知と物語との共犯関係を断ち切るため、これからもわたしは言葉を書いては破り捨て、書いては引き裂いてゆくでしょう。そして貧しさを貧しさのままに、半端を半端のままに、無意味を無意味のままに、接続詞で紡ぐことなく、物語で包むことなく、ありのままの素顔を、風に散ってしまう反故をわしづかむように、そっと胸に抱きかかえるでしょう。この世で最良の物語が、物語から解き放たれた水平線からふたたびはじまることを願って。」
(小津夜景「第 19 信 隠された接続詞」より)
「「無意味を無意味のままに、接続詞で紡ぐことなく、物語で包むことなく」というお話を読んで思い出したのが、ロラン・バルトの『偶景』です。バルトは、六〇年代の終わり頃のモロッコでの印象を、物語として構成や時間軸を設けることなく、多くの断章で描いています。」
「メロディラインと数字付き低音の間にあるこの空白が、なんとなく「書かれていない接続詞」のように思えてくることがあります。書かれていない接続詞は、ある時には「でも」や「しかし」であり、「だから」「また」「それから」でありながらも、その機能は決して限定されることなく開かれています。そのために、聴き手の判断は常に保留されます。そこでは、あらゆる可能性に開かれた「見えない接続詞」が暗躍しているのです。」
「音楽の演奏においては、技術と音楽性が完全に釣り合っていることが大切だといつも思っています。
(…)
音楽と共に生きていくには、音楽とのメンテナンスが常に必要です。音楽が何かのための手段となってしまうと、遅かれ早かれ人は音楽から立ち去ることになります(もちろんその関係をごまかしながら続けていくことができる人もいるのでしょうが)。
即興演奏というのは、つまるところ、習得した様々な断片を瞬時に変形して、最もふさわしいかたちで次々と紡ぎ、織り合わせていくことです。そこではかつて習得した何かが、フロー状態において、思考を経ることなく、展開されていきます。即興演奏には、書いてある音楽を正確になぞる時(…)とは異なる一体感とライブ感があります。コントロールを超えて、自らが思いがけなく発してしまったものに驚いたりしながら、生きているこの瞬間をまるっとそのまま愉しんでいるような気分になります。
(…)
この均衡状態こそが、あなたのお手紙にあった「物語から解き放たれた水平線」で発見する世界に似ているような気がしてなりません。そこにはありのままに世界を愉しみ、世界と一体になる喜びがあります。」
(小津夜景「第 24 信 ふりだしにもどる」より)
「古典に描かれた世界は、しばしば現代人からすると奇異で非日常的に感じられますが、古典とは読んで理解するよりもまず浸るものであり、溺れるものであり、追いかけても追いかけても作品に手が届かないといった距離の感覚に圧倒されるものです。作品はいつもこちらに背中を向けています。ふとした一節に「これを書いた作者はもういないんだ!」と絶句する夜も。「ひょっとしてこの作者も、さらに昔の作品の背中を追いかけていたのかしら?」と想像する朝も。いまはその背中をわたしが追いかける番らしい。わたしは駆け出す。戻らない過去へ。すると近づく。戻れない未来に。そのとき聞こえる、現在という一枚の紙が引き裂かれる音。古人とわたしがいつかめぐりあう、時のふりだしにもどる場所、それは死です。」
【目次】
はじめに
Ⅰ
第 1 信 きらめくらくがき
第 2 信 耳は意味を探してしまう
第 3 信 なしのたわむれ
第 4 信 辺境への誘惑
第 5 信 ことばはこばと
第 6 信 音のこどもたち
第 7 信 ありやあらずと
第 8 信 詩と道と
第 9 信 存在の青い灰
第 10 信 片隅と世界と
第 11 信 ゆめにめざめる
第 12 信 この地上で
Ⅱ
第 13 信 日曜日の午後の軽い手紙
第 14 信 文と不死
第 15 信 うちのそと
第 16 信 ふわふわふうみ
第 17 信 未来を読むこと
第 18 信 ものがたりのはじまり
第 19 信 隠された接続詞
第 20 信 みえないたくらみ
第 21 信 間の呼吸
第 22 信 わたしのあだしの
第 23 信 限りない広がりと空白
第 24 信 ふりだしにもどる
おわりに
おもな引用・参考文献
◎著者プロフィール
《小津 夜景(おづ やけい)》
1973 年北海道生まれ。俳人。2013 年、連作「出アバラヤ記」で攝津幸彦賞準賞、2017 年、句集『フラワーズ・カンフー』で田中裕明賞受賞。漢詩の翻訳を添えたエッセイ集に『カモメの日の読書』『いつかたこぶねになる日』がある。ブログ「小津夜景日記」
《須藤 岳史(すどう たけし)》
1977 年茨城県生まれ。ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者。演奏活動の傍ら「望星」「三田文学」「現代詩手帖」「図書」 等に書評や随筆を執筆。共著に『未明 02』『原民喜童話集』等がある。 CD:The Spirit of Gambo “The Silver Swan”(STOCKFISCH‐RECORDS)、Le Jardin Secret “Airs Sérieux”(Fuga Libera)等。
■俳人・小津夜景さんと古楽器奏者・須藤岳史さんによる往復書簡『なしのたわむれ』(素粒社)の刊行を記念した特別対談
2022/04/30に公開済
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
