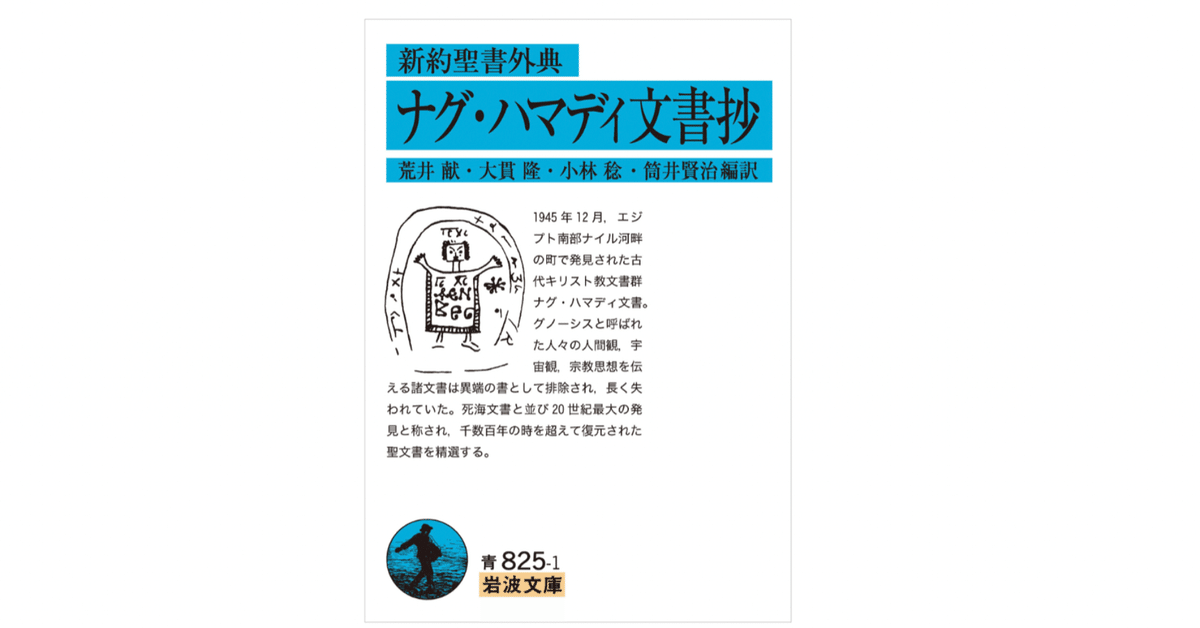
『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』
☆mediopos2622 2022.1.20
「ナグ・ハマディ文書」は一九四五年
「死海文書」はその二年後の
一九四七年に発見されており
「ナグ・ハマディ文書」の邦訳(全四冊)は
岩波書店から刊行済
(今回の文庫はそのうちの六文書を収めた抄訳)
「死海文書」の邦訳(全一二冊)は
ぷねうま舎から刊行中で
その全貌がほぼ見渡せる状況となっている
「ナグ・ハマディ文書」はキリスト教が地中海周辺地域に
ひろがってゆく時期に書かれ4世紀前半に埋められ
「死海文書」はキリスト教が成立する前後の時代に書かれ
死海沿岸の洞穴に秘匿された文書群であり
ともに当時の隠れた歴史の一端がこれで明らかになる貴重なもの
「死海文書」を残したのは
イエスに洗礼を施した洗礼者ヨハネが属していた
ユダヤ教の一派であるエッセネ派であるとされ
「クムラン教団」と呼ばれている
そしてその主な思想的特色は終末論にあり
基本的に古代ユダヤ教の文書である
それに対して「ナグ・ハマディ文書」は
部分的には二世紀の中頃にまで遡るもので
新約聖書成立の後期とも重なっている
当時は「聖文書」としても読まれていただろうが
四世紀以降は異端となっていく文書であり
その異端的要素はグノーシス主義と呼ばれている
グノーシス主義はもともと
キリスト教とは無関係な独自の宗教思想だったものが
「キリスト教グノーシス派」として
キリスト教にとりこまれたもの
「ナグ・ハマディ文書」で最初に話題になったのは
「トマスによる福音書」である
『福音書のイエス・キリスト〈5〉
隠されたイエス―トマスによる福音書』(講談社 1984/4)を
当時は「キリスト教グノーシス」といったことも
よくわからないまま興奮気味に読み耽ったことがある
研究家の荒井 献の名もそのとき初めて知る
比較的最近話題になったのは
「ユダ福音書」であり
まさに裏切り者とされているユダこそが
真のグノーシス主義者として
「裏切り」という役割が与えられた存在として描かれている
『ユダとは誰か/原始キリスト教と『ユダの福音書』の中のユダ』
((講談社学術文庫 2015/11)
これも荒井 献による著作である
なおグノーシスに関しては
比較的最近とりあげたことがある
詳しくは以下のファイルを参照のこと
(mediopos-2530 2021.10.20)
■『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』
(荒井 献・大貫 隆・小林 稔・筒井 賢治 編訳)
(岩波文庫 岩波書店 2022/1)
(大貫隆「はじめに」より)
「「ナグ・ハマディ文書」とは、一九四五年にナイル河中流域の町ナグ・ハマディに近いローマ時代の墓で発見されたパピルス写本群のことである。その二年後にパレスチナの死海沿岸で発見された「死海文書」とともに、古代末期のユダヤ教とそこから誕生して間もない最初期キリスト教の研究における世紀の大発見と呼ばれる。
おそらく後四世紀に制作されたと推定される十三の写本に合計五十二の文書が筆者されている。使われている言語は古代末期のエジプトの固有言語であったコプト語であるが、ほとんどすべての文書がギリシア語原本からの翻訳である。発見された写本は、その後ファクシミリ版で刊行された。」
「日本でも、まず主要文書の邦訳が一九九七—一九九八年に岩波書店から四冊の単行本『ナグ・ハマディ文書 Ⅰ—Ⅳ』(荒井献・大貫隆責任編集。Ⅰ 救済神話、Ⅱ 福音書、Ⅲ 説教・書簡、Ⅳ 黙示録)で刊行された。そこで未収録のまま残された文書も、二〇一〇年刊行の『ナグ・ハマディ文書・チャコス文書 グノーシスの変容』(荒井献・大貫隆編訳、岩波書店)に収録された。これによって、ほぼすべてのナグ・ハマディ文書の邦訳が出そろうことになった。」
「このたび、岩浪文庫の一冊として送り出される本書は、それら計五冊に収められた邦訳から、合計六文書を選んで新たに編まれたものである。」
(収録文書の内容)
『イエスの知恵』
「復活のイエス・キリストがフィリポ、マタイ、トマス、マリヤ、バルトロマイオスに出現して質疑応答を交わす。その全体を通して、古典的なグノーシス神話の概要が提示される。」
『ペトロの黙示録』
「内容はイエスが逮捕される直前にペトロが見た幻視である。十字架で殺されたのはイエスの模造物(肉体)にすぎず、真のイエスは「十字架の傍らで喜んで笑っている」とされる。」
『ヨハネのアポクリュフォン』
「内容は復活のイエス・キリストがエルサレム神殿の境内で、十二弟子の一人のヨハネに出現して啓示する神話である。それはグノーシス主義の数多い救済神話の中で最も代表的かつ重要なもので、論述もきわめて組織だっている。」
『トマスによる福音書』
「「活けるイエス」がトマスを初めとする弟子たち(ペトロ、マタイ)およびマリハム(マリヤ)に出現して語り聞かせたという言葉を集めたもの」
『エジプト人の福音書』
「キリストあるいはイエスに言及はあるが、きわめて影が薄い。もともとキリスト教とは無関係にユダヤ教の周縁で成立した神話が事後的にキリスト教化されたものと思われるが、その改変の程度は軽微である。(…)ヘレニズム文化圏のヘルメス文書や魔術文書と共通する点が多い。」
『ユダの福音書』
「いわゆる「裏切り者ユダ」こそが真のグノーシス主義者であり、地上のイエスも自分の本質を他の弟子たちにではなく、ユダ一人に啓示したという。イエスが十字架の受難を経て天上の郷里へ帰還するためには、ユダによる「裏切り」が必要であったという逆説。」
(「荒井献「ナグ・ハマディ文書とグノーシス主義」より)
「現有のコプト語の原本は、部分的には二世紀の中頃にまで遡ると見てよいであろう。
二世紀の中頃といえば、現行の新約聖書所収の二十七文書のうち最も後期に属する諸文書(たとえば「テモテへの第一の手紙・第二の手紙」「テトスへの手紙」など)が成立した年代である。とすれば、ナグ・ハマディ文書と新約諸文書は、その成立年代において部分的に重なることになる。しかも、キリスト教成立後、初めの四世紀頃まで、キリスト教諸教会は、それが位置する地方により、またそれが属する教派によって、現行の新約聖書二十七文書以外の諸文書も、共に信仰にとっては規範的な権威ある「聖文書」として読まれていた。ナグ・ハマディ文書の大半は、このような意味における「聖文書」、四世紀以降「正典」としての新約聖書から区別あるいは差別(排除)されていった「外典」に属するのである。」
「「グノーシス主義」とは古来、「グノーシス」偽称のゆえにキリスト教の教父たち、とりわけ反異端論者たちにより反駁され、彼らの担う正統教会から最終的には排除されたキリスト教異端の総称であった。教父たちによればグノーシス派は、同派の「父祖」といわれる「魔術師」シモンとその派をはじめとして、ヴァレンティノス派、バリシーデス派、ケリントス派、ナーハーシュ派、オフィス派(…)、バルベーロー派、セツ派などの分派に分かれた。いずれにしてもグノーシス派は、それに先行したキリスト教と異教(例えばオリエントの諸宗教)、あるいは異思想(例えばプラトニズム)との事後的混淆によって成立したキリスト教の異端である。
このようなグノーシス観は、正統教会の教父たち、とりわけ反異端論者以来の、グノーシス派に対する伝統見解であり、今日でもこの見解を基本的に採る学者たちもいる。確かにキリスト教のグノーシス派とその思想(グノーシス主義)は、キリスト教を前提とする限りにおいて、キリスト教よりも後に成立した。
しかし、グノーシス主義そのものが元来キリスト教とは無関係に成立した独自の宗教思想であったこと、そしてそれが事後的にキリスト教のテキストに自らを適合し、それを解釈して「キリスト教グノーシス派」の神話論を形成したことは、すでに確認した通りである。このことは、とりわけナグ・ハマディ文書によって実証される。なぜなら、この文書にはキリスト教グノーシス文書のほかにキリスト教とは関係のないグノーシス文書が含まれているばかりではなく、一つの文書はが次第に自らをキリスト教的要素に適応させていく過程が同一文書の異本によって後付けられるからである。セツ派などはおそらく元来、キリスト教とは無関係に、ユダヤ教の周縁で成立したものと想定される。神話の構成要素が旧約だけでほぼ十分に揃っており、新約の要素は二次的付加と思われるからである。」
