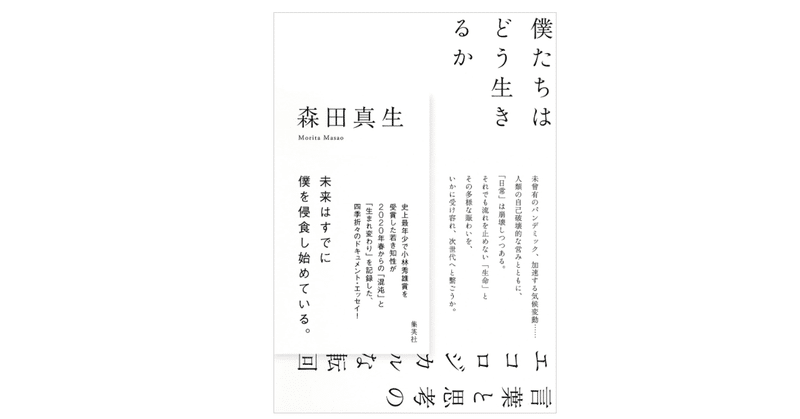
森田 真生『僕たちはどう生きるか/言葉と思考のエコロジカルな転回』
☆mediopos-2576 2021.12.5
ティモシー・モートンのいう
「エコロジカルな自覚」とは
「A=A」という「自同律」を
自明のものにしないことだという
インドの伝統的な思考に
Aでも
非Aでも
Aかつ非Aでもなく
Aと非Aのどちらでもない
といいうテトラレンマというのがあるが
モートンのエコロジカルという
エコのロジックは
一見言葉の遊びのようにさえ思える
そんなテトラレンマのようなロジックで
「言葉と思考」を転回させようとしている
それを「自覚」に導く主体は
「強い主体」ではない
主体はむしろ弱くされることで
「遊び」へと向かうことができる
主体を弱くすることで
むしろ自覚は深められ
自在で柔軟な主体となり
「環境」と響き合えるようになる
「正しさ」「正義」「真理」などは
強い主体でしか主張しえないことだが
そうすることでわたしたちは
みずからを「環境」から遠ざけてしまう
それは「環境」と「遊戯」することではなく
「環境」から必要とされるモノだけを
切り出してそれ以外を捨象するということだからだ
そうすることで
「物事の意味を一つの尺度に閉じ込めてしまう」
モートンは
「モノがモノであるとは、遊戯的である」ことであり
「そのように生きることのほうが「精緻」」だという
モノたちすべては
ほんらい遊び心に満ちている
それを狭い場所に閉じ込め
身動きをとれなくしているのこそ
「強い主体」である
「精緻」であろうとすることで
モノたちは遊びはじめる
つまり世界は遊びはじめ
わたしたちもまた囚われからはなれ
未知の現実とともに
生きる主体へとひらかれてゆく
■森田 真生
『僕たちはどう生きるか/言葉と思考のエコロジカルな転回』
(集英社 2021/9)
「同じ出来事が、人間中心的な枠組みの外では、まったく別の意味を持つ。都市のロックダウンは、人間にとってはスムーズな生活の中断にほかならないが、人間でない生物の多くにとっては、人間活動の順調な作動こそが、平穏な暮らしを疎外してきた最大の要因なのである。
同じことが、異なる存在、異なるスケールにおいて、まったく別の意味を持つ。だから物事の意味を一つの尺度に閉じ込めてしまうわけにはいかない。
同じことが別のスケールではどんな意味を持つか。これを常に想像し続ける姿勢を、アメリカで独自の環境哲学を展開するティモシー・モートンは「エコロジカルな自覚(ecological awareness)と呼ぶ。」
「エコロジカルな自覚のもとでは、僕が僕であるという「自己同一性(identity)は、もはや当たり前のことではなくなる。「A=A」という「自同律(law of identity)は、ほとんど自明な原理のように見えるが、生命にとってはむしろ、驚くべき達成なのである。
純粋に、清潔に、首尾一貫した「自己」という発想自体が、すでに現実味を失っている。自己と非自己、人間とそれ以外と、ものごとを図と地にきれいに分けられると信じるにはもはや、僕たちはあまりにも深く、他者が自分に浸みこんでいることを学んでしまっている。
前景と背景、図と地を切り分けて考える発想そのものの機能不全。ティモシー・モートンはこれを、「世界の終わり(the end of the world)」と呼ぶ、それは、終末論的で破局的な、人類や地球そのものの終わりではなく、内と外、図と地を切り分け、自分だけが安全に引きこもれる場としての「世界(world)」があると考えること自体の終わりなのだ。」
「ティモシー・モートンは今年に入って、人類学者で作家のドミニク・ボイヤーとの共著で『hyposubjects』という本を出した。これは、ハイパーオブジェクトの時代に、どのような「主体(subject)」として生きていくかを模索するかなり実験的な著作だ。
本を書くという行為そのものを編み直していこうとする二人は、一人称を共有するという遊び心に溢れたスタイルでこの本を書き勧めていく。二人の署名が「私たちは」と名乗る代わりに、「私は」と同じ一人称を分かち合うのだ。このため、「私は完全に同意だ。私はまったく同意できない」といったような矛盾した文も平気で書けてしまう。首尾一貫した一人の「強い主体」としての著書という観念を打ち破る試みである。
標題にある「hyposubject」は「hypersubject」に対置される概念だ。ハイパーオブジェクトの時代に、それでもなお意味の主宰者であり続けようとする「強い主体」を、著者は「hypersubject」と呼ぶ。これに対し、「hyposubject」とは、全体を俯瞰できない自己の弱さと不完全さを受け入れて生きていく「弱い主体」だ。」
「ハイパーオブジェクトの時代の主体は、むしろ自己を徹底的に弱くしていくしかないのではないか。本書でモートンとボイヤーはこの可能性を追求する。ここで、「遊び(play)」が、重要なキーワードになる。
「遊び」とは既知の意味に回帰することではなく、まだ見ぬ意味を手探りしながら、未知の現実と付き合ってみることである。それは、みずから意味の主宰者であり続けようとする強さを捨てて、まだ意味のない空間に投げ出された主体としての弱さを引き受けることである。意味の全貌を見晴らせないなかで、それでも現実と付き合い続けようとする行為は、自然と「遊び」のモードに近づいていく。
それはいつも子どもたちが僕に教えてくれることでもある。」
「危機においてますます意味の主導権を握り続けようとするハイパーサブジェクトの支配から自由になるためには、単純な抵抗や正義の主張だけでは不十分なのだ。既知の意味に固着せず、意味の主催者であろうとする大人たちを結果として翻弄していく子どもたちの遊び心は、これからの時代を生きる大きなヒントを孕んでいるのではないだろうか。
モートンは、子どもたちどころか、あらゆるモノが、精緻に見れば、すでに遊び心を体現していると語る。
モノがモノであるとは、遊戯的であるということなのだと思う。だから、そのように生きることのほうが「精緻(accurate)」なのだ。
(・・・)
モノはそれ自体ですでに驚くべきほど創造的で、遊戯的なのではないか。とすれば、遊戯的であることは、現実から一時的に脱線することではなく、むしろ遊戯的であることこそが現実的なのではないか。既知の意味に固着する息真面目さよりも、あらゆる可能性を試す遊び心の方が「精緻」だとモートンが言うのは、それは意識や生命すらないとされる、あらゆるモノたちに共通する根本的なあり方だからである。」
「そもそも「正しさ」「正義」「真理」などはいずれも、強い主体の言葉だ。生態学的に豊穣な網に編み込まれた僕たちにとって、最終的な真実や正しさを摑もうとするより、目の前の現実を、より精緻に把握しようと動き続けていくことの方が切実だ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
