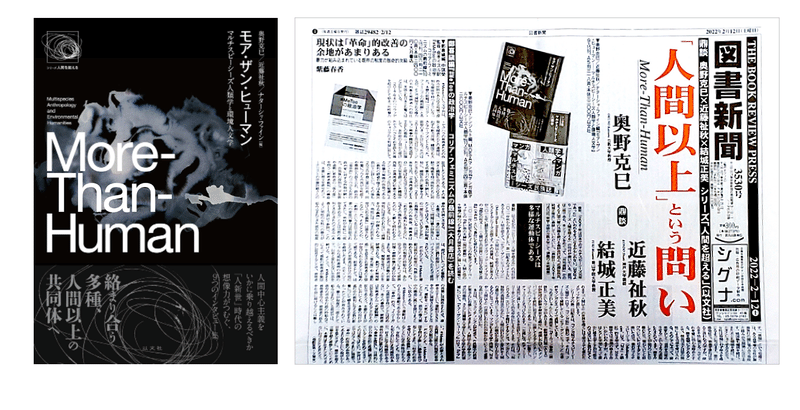
『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』/「「人間以上」という問い-More‐Than‐Human」
☆mediopos2646 2022.2.13
「人新世」という視点が
提起されるようになって久しいが
その議論のなかでは
人間から切り離されたところで
環境を論じることはできなくなっている
その意味でとくに二〇一〇年以降
人文学全体において従来の専門分野の壁を超えて
隣接分野との協働というかたちで
環境をめぐる人文学的なパースペクティブをもった
「環境人文学」が発展してきている
そんななかで人類学的な探求として
「マルチスピーシーズ(MS)人類学」関係の著作が
このところ続々と刊行されてきていて目が離せない
それは「人間という単一種から離れて、
微生物から昆虫、動植物だけではなく
地球外生命にも目を向け、多種の共同体を取り上げて
その中に人間を位置づけ直してみることを、
民族誌という人類学の強みに拠りながら探っていく」ものだ
その際気になるのが
「人間」をどうとらえるかである
人間から切り離された環境はない
と同時に
人間だけではなく人間をこえた諸存在も含めて
人間をとらえなおす必要がある
「マルチスピーシーズ民族誌」と「環境人文学」を
跨いで使われる語に「人間以上(more-than-human)」
という語があるというが
その際にとらえられる「社会性」にはいまや
人間と非人間の両方を含んだ
「人間以上の社会性」なのだという
今回ご紹介している『モア・ザン・ヒューマン』は
シリーズ「人間を超える」の第一巻目
「人間以上」ではなく「人間を超える」
という表現がなされているのは
「人間以上」ということで「人間を捨象している」のではなく
「「人間」を含みながらその外を取り込んでいる」
という視点であることを意識化するためのようだ
もはや地球には
人間の影響を受けない環境はないとしながらも
その「人間」という存在の「外」の諸存在をもふくんだ
「人類学」であろうとしているが
それは「人類−学」でありながら
「超人類−学」あるいは「拡張された人類学」
とでもいえるようなものになってきているのだといえる
その意味ではもはやすでに
現在のような狭義の人類という存在は
旧人類的な存在になろうとしているのかもしれない
「モア・ザン・ヒューマン」には
人間がもっと人間になることが求められるように
人間は自らを含みながら拡張していくような
そんな存在でなければならない
そんな課題がそこにはあるのだろう
■奥野克巳/近藤祉秋/ナターシャ ファイン 編
『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』
(シリーズ人間を超える 以文社 2021/9)
■鼎談 奥野克巳×近藤祉秋×結城正美 シリーズ「人間を超える」(以文社)
「人間以上」という問い――More‐Than‐Human
(図書新聞 2022年2月12日 所収)
(『モア・ザン・ヒューマン』〜奥野克巳「序論 モア・ザン・ヒューマン」より)
「一九七〇年代の環境哲学、一九八〇年代の環境史、一九九〇年代のエコクリティシズム、二〇一〇年代の実在論哲学、マルチスピーシーズ民族誌やアートと人類学などの研究にみられるように、二〇世紀後半から現在にかけて、社会科学を一部含めた人文学の諸領域において、人間の周囲の環境や非人間的存在をめぐって、顕著な研究の進展が見られた。こうした動きは、従来の専門分野の壁を超えた隣接分野との協働というかたちで現れることが多いが、漸次個別に発展した、小さな学際的な動きの先に、人文学全体において結わえる大きな領域横断的試みが今日、「環境人類学」として発展してきている。」
「人新世との関わりでは、人間活動の影響が及んでいない環境はもはやなく、人間から切り離したかたちで環境を論じることは意味をなさないという議論の広がりとともに、環境問題を人間の問題として考える方向性が明確に打ち出されていったとされる。環境人文学は、新しい研究対象や手法を提示するというものではない。二〇世紀後半行以降の小さな学際的動きの中で蓄積されてきた、環境をめぐる人文学的なパースペクティブが、とりわけ二〇一〇年以降に発展してきているのである。
マルチスピーシーズ民族誌と環境人文学を跨いで使われる語に「人間以上(more-than-human)」という語がある。学術用語として初めてこの語を用いた、エコクリティシズム研究者ディヴィッド・英ブラムの用語法としては、それは、物質的であるだけでなく、精神的なものを含めた存在や現象のことを指していた。
チン(マルチ・チン)は、彼女の初期の著作では恥ずかしながら、社会的なことを「人間の歴史と関係がある」ことと定義していたことを吐露している。それに続いて、「今では、それはとても奇妙なことのように思える。社会性の概念は、人間と人間でないものを区別しない。「人間以上の社会性(more-than-human sociality)」は両方を含む」と述べている。「人間以上の社会性」という概念は、人間と非人間の両方を含むのである。
チンがそのことに気づくようになったのは、ある菌類学者にインタビューした時からだったという。その研究者に研究内容を尋ねた時、「キノコの社会学(mushroom sociology)」という答えが返ってきた。チンはその後、人間だけでなく、非人間のキノコもまた社会的な存在であると見ることができるようになったという。彼女は、社会生物学者や進化心理学者を慎重に排除しているが、自然の中に社会的なものを見る研究者たちと協働すれば、社会的関係やネットワークをどのように研究するのかをともに考えていくことができるだろうと述べている。今日マルチスピーシーズ民族誌研究の第一人者であるチンにとってさえ、「人間以上の社会性」へと「改心」する契機が必要だったということは、逆に、社会的であることが人間だけに限って語られることが一般には圧倒的に多いという事実を示している。」
「人間による地球の環境変動が取り沙汰されるようになった今日、人間という単一種から離れて、微生物から昆虫、動植物だけではなく地球外生命にも目を向け、多種の共同体を取り上げてその中に人間を位置づけ直してみることを、民族誌という人類学の強みに拠りながら探っていくのがマルチスピーシーズ民族誌であった。その試みは、人類学という既存の学問の枠だけにもはや収まるものではなくなっている。他方、環境人類学は人間と人間が住まう環境や自然、生物やモノとの関係性を、今日の複雑な政治・経済・社会および科学技術をめぐる文脈の中に位置づけて、既存の人文諸学の垣根を越えて、その近未来的な展望を果敢に切り拓こうとしている。それはマルチスピーシーズ民族誌を含みながら、人新世の時代において今後人文諸学が取り組むテーマを明確に示しつつ、諸課題に実質的にあたるための手がかりを与えてくれるだろう。」
(「人間以上」という問い」より)
「近藤/今回のシリーズ名の「人間を超える」を英語にすると「Beyond the human」となり、その第一巻目が「More-Than-Human」です。この二つは同じ意味で使われていることが多いと思いますが、私は少し違うニュアンスで受け止めていました。Beyond the humanは「人間」とそれ以外の存在の間に線を引いて、その線の「外」を目指していく感じがします。それに対してMore than humanは「人間」を含みながらその外を取り込んでいるという意識があります。
MS人類学に対して「人間を捨象している」という批判がなされることがあります。確かにMS人類学はポストヒューマニティーズの影響を受けているかもしれませんが、先ほど説明したようにMore than humanという言い方は決して人間を捨象していない。それどころかアボリジニ研究の泰斗でオーストラリアのMS研究を牽引したデボラ・バード・ローズのように、ポストコロニアルの議論をうまく取り込んだうえでMS論を展開している人もいます。「MS]は、フェミニズと科学技術論、政治生態学、先住民研究、デザイン研究などのさまざまな分野の論者が化学反応を起こしているような多様な運動体としてあると思います。」
◎『モア・ザン・ヒューマン』目 次
序論 モア・ザン・ヒューマン 人新世の時代におけるマルチスピーシーズ民族誌と環境人文学(奥野克巳)
第一部 人間と動物、一から多への視点
第一章 インド中部ヒマラヤの種を超えた関係性(ラディカ・ゴヴィンドラジャン/宮本万里)
第二章 工業型畜産における人間-動物の労働(アレックス・ブランシェット/吉田真理子)
第三章 人間-動物関係をサルの視点から見る(ジョン・ナイト/合原織部)
総論I(奥野克巳/近藤祉秋/大石友子/中江太一)
第二部 人間的なるものを超えた人類学の未来
第四章 モンゴルの医療、マルチスピーシーズ・ストーリーテリング、マルチモーダル人類学(ナターシャ・ファイン/村津蘭)
第五章 森の思考を聞き取る人類学(エドゥアルド・コーン/近藤宏)
第六章 想像力を駆使し、可能性の彼方に人類学を連れ出そう(アナンド・パンディアン/山田祥子)
総論II(奥野克巳/近藤祉秋/大石友子/中江太一)
第三部 モア・ザン・ヒューマンの人類学から文学、哲学へ
第七章 外臓と共異体の人類学(石倉敏明/唐澤太輔)
第八章 エコクリティシズムのアクチュアリティ(結城正美/江川あゆみ)
第九章 仏教哲学の真源を再構築する(清水高志/師茂樹)
総論III(奥野克巳/近藤祉秋/大石友子/中江太一)
あとがき マルチスピーシーズ人類学から本書を眺望する(ナターシャ・ファイン)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
