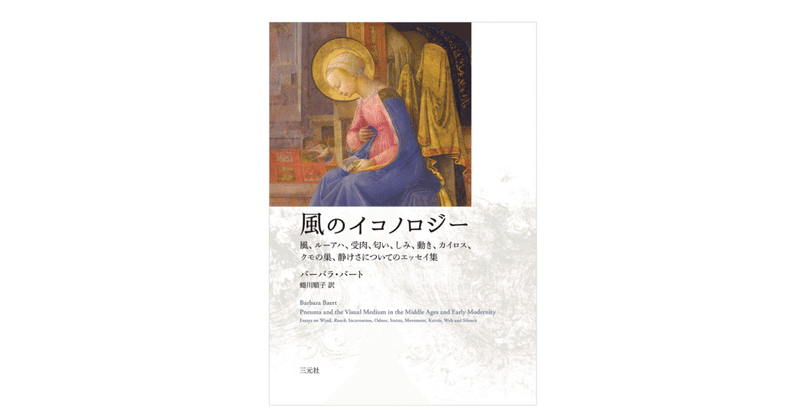
バーバラ・バート『風のイコノロジー/風、ルーアハ、受肉、匂い、しみ、動き、カイロス、 クモの巣、静けさについてのエッセイ集』
☆mediopos2859 2022.9.15
風そのものは目には見えないけれど
わたしたちはさまざまに風を感じることができるし
呼吸のようにわたしたちを貫く宇宙の息でもある
本書『風のイコノロジー』は
そんな風が西洋文化や美術の中で
どう表現されてきたのかついてのエッセイ集である
画家たちは目には見えない風の動きを
水と織物・空気と水・髪の毛と織物など
その動きのなかで描きだしてきた
また旧約聖書において
人間は神の息である「ルーアハ」によって
いのちを吹き込まれたとされるが
そのヘブライ語は
〈プネウマ〉としてギリシャ語に
その後〈スピリトゥス〉としてラテン語に翻訳され
その〈スピリトゥス〉である風・息・空気・霊から
さまざまな視覚的表現も生み出されてきた
「受肉」ということから
本書の第二部では「受胎告知」のテーマも
とりあげられているが
神的起源の〈ルーアハ〉に芸術的表現を与えた
稀有の画家といえばレオナルド・ダ・ヴィンチである
レオナルドに《洪水》という素描があるが
「この大洪水は、自然現象としての風を素描に変換できる、
おそらくただひとつの技法において記録されたものである」
「レオナルドの素描家としての気質は、
「風の素描家気質」であり、それゆえに、
そのようなイメージ言語の起源まで遡る」
芸術の過程はレオナルドにとって
宗教や哲学と境を接している
「芸術的なものそれ自体の〈プネウマ〉を伴う」
創造力を含んでいるのだ
レオナルドは自然現象そのもののなかにある
神的起源の〈ルーアハ〉の秘密に迫ろうとしたのだろう
その意味で「風」はその根源において
線的時間であるクロノスを超えた
「風の時間」としてのカイロスとともにあるのだともいえる
その時間は「流動ではなく、
流れの中断であり、時間の裂け目」であり
そこから「かなたにある言表不能な神秘への口が開かれる」
目には見えないけれど
目には見えないからこそ
自然現象としての風も
私たちに生命を与える息としての風も
時間を超えた永遠の場所から吹き込まれる「風」としての
神的な〈ルーアハ〉をその起源としてもっているのだ
■バーバラ・バート(蜻川順子訳)
『風のイコノロジー/
風、ルーアハ、受肉、匂い、しみ、動き、カイロス、 クモの巣、静けさについてのエッセイ集』
(三元社 2022/8)
(「〈プネウマ〉 ――日本の新しい読者に向けた四つの回想」より)
「その一:視覚芸術が風を表現し喚起し示唆するやり方は、諸感覚の人類学や、それらの視覚媒体への変換に関する根本的な考えを、呼び起こします。風は、全身が感覚器官である身体の上で戯れるひとつの自然現象です。風は触れることができます。風は聞くことができます。風は薫りを運びます。風はわたしたちを包み貫く宇宙の息です。風は養い、また、破壊するのです。
わたしたち自身の身体でさえ風を作り、吸い込みます。風はわたしたちの身体に出入する息や、わたしたちの器官が放つ気体とも関係します。風は貶められたもの(卑しめられたもの)——放屁——でもあり、気高いもの(高められたもの——わたしたちが息する空気——でもあります。わたしたちの身体には、第三の風(三種目の風)があります。ギリシャのアリストテレスの哲学において、〈プネウマ〉(気息)の概念は、息や精神の中心にあります。文字通り生命に不可欠なエネルギーであり、脳を占めて、思考や知覚や運動を担う気体なのです。この不可欠なエネルギーは、誕生時に授けられ、呼吸によって補充され続けます。
その二:風そのものの表現や視覚性は逆説的なものです。風は目に見えない無数の指先でわたしたちの皮膚を愛撫します。(イタリアには、この触れたか触れないかの感触を表す〈スフィオラーレ〉という言葉があります。これは微風にのって他の花に触れるような花粉を蒔く、花の中の雄しべに由来します。)風はまた直接的な情感でも現れます。風は生命をもたらします。木々は風のおかげで音を立て、語りかけます。身体そのものと風との関係は、とくに複雑です。身体は自然界の媒体であり風の中に立ちます。逆に、風は身体そのものを媒介として用います。風は空気、酸素、息です。風は口にも肛門にも関係します。風は身体に入り、更新された生命の精髄のように再び現れます。セム族あるいはホメロスの叙事詩的知のモデルにおいて、人間は生命の精髄を定義し特定しようとしました。はじめは、〈ネペシュ〉と〈ルーアハ〉、あるいは〈アニマ〉と〈アニムス〉に区分されていましたが、後に、〈スピリトゥス〉という単一概念で統一されました。
その三:人間と環境、人格と身体とのこの複雑な相互関係において、風は太古の昔から、見えるものと見えないもの、死と生、精神と身体の関連を通して考えることを可能にする、魅惑的なモデルであり続けてきました。風はこうした根本的な二元性を繋ぐ狭間にあるものなのです。
風は実際計り知れないものです。それは触覚に先行しますが、触覚なしにすまされるものではありません。風は人生の気まぐれさをわれわれに認めさせます。あらゆる儀式は風を招くためのもので、風のエネルギーは、香りやダンスやその他の心理活性的療法のように、「一である」という前言語的状態へ戻りたいという願望を抱かせるのです。
その四:このささやかな回想で、風が、通時的ではなく、すなわちクロノス(あるいは、われわれの現行の直線的モデル)に向かうのではなく、創造されて、かつ創造する循環的運動の時間感覚を含むことに触れておきます。この「風の時間」は、人生は気まぐれで変わりやすく予測できないという確信に繋がり、この制御不能性に、美や、不滅に関する認識が含まれるのです。宇宙的時間の受容は、さまざまに方向を変えながら繋がっている、毛糸玉を端までほどくような時間経験の広がりを意味します。これは、宇宙的空間における人間の運命を示し、それを分析し、定義し、把握できるものにする、もうひとつの風の時間のために道を拓くことなのです。これが前髪をなびかせながら素早く動くカイロスに特徴的な微風です。」
(「荒ぶるのは風 ――序に代えて」より)
「視覚芸術が風を表現したり、想起させたり、示唆したりするやり方は、感覚や感覚由来の視覚媒体を扱う、人類学の基本的な発想に関連する。風は、まるごと感覚器のような身体の上で戯れる自然現象である。風は触れることができる。風は聴くことができる。風は香りを運ぶ。風はわれわれを包みこみ、われわれを貫く、宇宙の息である。風は養い、また、滅ぼす。
われわれ自身の身体でさえ、風を創りだし、また吸いこむ。風は、身体が吐きだしたり取りこんだりする息や、われわれの器官が発する気体にも関連付けられる。肛門からの放屁のような風なら低められ、呼吸する息なら高められる。われわれの身体には、第三の風もある。ギリシャのアリストテレスの哲学において、〈プネウマ〔気息〕pneuma〉と呼ばれるその風概念は、呼吸にとっても精神にとっても中心をなす。それは文字通り、生命に必須のエネルギーであり、脳に充満し、思考や知覚や運動のために重要な役割を果たす気体である。この必須エネルギーは、誕生時に与えられて、呼吸のたびに活性化され続ける。」
「本書が注目するのは、風や〈プネウマ〉や動きが美術史的解釈に与えた衝撃である。言葉を変えるなら、風はその視覚媒体それ自体について何を語りうるのか? 風はやってきて、流れ、繋げ、方向を変える——つまり、風は気まぐれなのだ。この気まぐれさゆえに、風は、聯想や自由や不意といったものに特有のい解釈学を出現させる。となると、こうした気まぐれさに関するイコノグラフィーは、可能なのだろうか? われわれを包み込み、貫きながら、われわれの身体に拘わらないこともあるこの自然現象は、どのようにして図像に留められたのだろうか? 風の力は結局のところ、揺れる木々、波打つ草原、はためく布を通して、間接的にしか見ることができないとすれば、いかにして風は、イメージの理解を膨らませたのであろうか? 視覚的〈プネウマ〉の問題なのだろうか? 風は諸芸術において、内容の問題なのだろうか。それよりむしろ、形式的作用に関する事柄なのだろうか?」
「第一部では、宗教体系によって異なる風概念の、文化人類学的原型を扱う。」
「第二部ではおもに受胎告知の主題に焦点を合わせる。」
「第三部では、前二章の隅に隠れていた風の亡霊を扱う。時間を示すものもあれば、単なる神人形的世界を超えて吹く風の切り子面を出現させるものもある。この最終章に収めた章では、風の奥底の解釈学、そのもっとも深いところで生じる渦巻きに触れる。ここには、踊るニンフ、レオナルドの〈スフマートsfumato〉、カイロスの急去来、アラクネのクモの巣が含まれる。」
(「第一部 風/〈ルーアハ〉/〈プネウマ〉をめぐる簡潔な人類学」より)
「風を研究することは、われわれの感覚の世界に対する関係を研究することである。この関係は、風を通してみるなら、三つの特殊な性格を帯びている。第一に風は、われわれの情緒に触れ、情感を解き放つ。風は、反大脳あるいは前大脳的なもので、きわめて直観的で感覚的な認識によって処理される。第二に風は、視角を最上位とし嗅覚と味覚を最下位におく、古典的でヘレニズム的な感覚のヒエラルキーに、したがわない。匂いや触感や味による、いわゆる「下位」の認知法は、風によって活気づけられる。風に関連する書力を扱う人類学の領域では、おもな注目点は、匂い、音楽、ダンスにある。風を研究することで、諸感覚の脱落や混合(共感覚)、そして、感覚序列の偶発性に対する洞察が得られる。最後に、風は力を与える。それはエネルギーの源である。(…)このことも、なぜ風が本質的に生命の現れ(生命の息)とみなされるのかということを説明する。風を活性化し、風を生み出すために、嵐に先立つどのような力も
必要ない。風は常に原初的で、繰り返し起こりうるものである。このことは〈ルーアハ ruach〉というヘブライの基本的な原理を思いおこさせる。」
「概念の翻訳が意味の変化を引きおこし得ることは、よく知られている。これがまさに、ヘブライ語の〈ルーアハ ruach〉の翻訳で起こったことである。〈ルーアハ〉は〈プネウマ pneuma〉としてギリシャ語に、その後〈スピリトゥス spiritus〉としてラテン語に翻訳された。この〈ルーアハ〉〈プネウマ〉〈スピリトゥス〉の連鎖は、聖書のテクストや注解に深く根差し、「風」という概念をいくつかの方向に広げる一方で、本来の含意を別のものに限定した。」
「風は、環境や信仰との関係において、人物やその身体を定義する人類学的諸分野に属する。ヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語の認識モデルにおいて風は神の原初的力を、また、キリスト教においては聖霊すなわち〈神霊 Spiritus Dei〉を発する生命の精髄を、もたらすものである。」
(「第三部 空気と動きの解釈学」より)
「風は、水と織物、空気と水、髪の毛と織物といった異なる物質間で、間を超えるような移動を可能にする。絵画的レベルで、〈各部分〉の融合は液体、絵の具、顔料の中で生じる。画家が、流体と絵筆をたださばくだけで、空気、水、織物を生み出す技巧に、同時代の観者は感嘆する。」
「風の——モチーフと〈パトス patoth〉の間の——解釈学は、身体を通して、身体から作動する自然現象と関わり、人間の想像力と宇宙の創造力の間に一定の関係を構築する。風は、連想的に連繋し、気まぐれで、とりわけ実りの多い創造的力を反映する。風、息、空気によってもたらされる創造の過程は、全感覚器に作用し、他の芸術的パラダイム以上に、絵画的媒体についての自己省察の能力を示している。特定の場合に、レオナルド・ダ・ヴィンチの視角芸術に関する懸解と同じように、この自己省察は急進的に、絵画や素描へ降りてくる〈プネウマ pneuma〉となる。」
「カイロス、あるいは好機としての風を振り返ってみよう。語源的にも暗喩的にも、カイロスは「分裂」、標的、移行、通貨、開口部を通る進入などの分野で活躍する。ここから類推されるように、カイロスは求められるけれども、突然になすすべもなく飛び去ってしまう。彼はこうした性質を風と共有し、同じようにどこからともなく現れ、あっという間に消えてしまう。彼の揺れている前髪から、彼が風によって後ろから前へと進められていることがわかる。風と同じように、カイロスは自ら動いて移動する。彼は自力で動きながら空間を前進する。彼は風の原型的擬人化として、天使や精神の一門に属する。しかしながらカイロスは、風の諸相を人間の運命と結びつけ、また、運命の輪や、風車のように風からエネルギーや有効性を引き出す動的な輪と結びつける。要するに、カイロスの章は、人間の生命や運命を構造化するさまざまな派生物において、風がその解釈学的帰結に達する点まで、われわれを導いたのである。」
「人間と環境、人格と身体の、この複雑な相互関係において、風は太古より、目に見えるものと見えないもの、死と生命、精神と肉体の間の関係を通して考えることを可能にする、魅力的なモデルであった。風は、これら基本的な二分法を繋ぐ裂け目の組織である。キリスト教において、この二分法は、神学や図像解釈学の基盤となっており、それが受肉であった。聖処女への受胎告知は、あまりに深く、理解を超え、同時に根本的に革命的な出来事である——神は神的地位を失うことなく、そこで身体を帯びることを望んだ——ため、この逆説を類比的に具体化した自然の形における理解を、自らもたらしだだけである。これを拡張することで、この逆説は、視覚芸術が可能にし、まためざされたものの主題、視覚的であることそのものの神秘となるここでわれわれは、風がその解釈学的位置を占める最初の強力な瞬間の目撃者となる。人文主義において、風は絵画におけるプネウマ的なものに繋げられる。風は視角における挑戦となる。風は、媒体に忠実に、線とパレットによって間接的に把握されなければならず、そのもっとも深い秘密を、この視覚芸術にもちこむ。それはそのアニミズム的過去、原初の叫び、〈ルーアハ〉なのである。見よ! 今あなたは生きる! レオナルドはこの神的起源の〈ルーアハ〉に芸術的個性を与えたいという願いを、他のどんな芸術家たちより強く、視覚的に表現した。」
「(風はある種の時間を如何に多く含んでいる)それは、通時的ではなく、それゆえクロノス(あるいは現行の線的時間モデル)には向けられておらず、むしろ、創造されかつ創造する時間の循環運動を示唆するような時間である。この「風の時間」は、生命はきまぐれで、変わりうるもので、予測不能である一方、この制御不能性が、あた美を含むという確信、つまり、何も過ぎさるものはないという認識に結びついている。宇宙の時間を受け入れることは、毛糸玉を端までほぐすような時間経験の広がりを意味する。これは、宇宙空間における人間の運命を示し、それを孤立させ、それを定義し、そして把握できるものとする、もうひとつの風のために道を拓く。それは、前髪をなびかせながら素早く動くカイロスを示すそよ風である。
この第二の風の時間は、流動ではなく、流れの中断であり、時間の裂け目である。ベールは引き裂かれ、かなたにある言表不能な神秘への口が開かれる。」
《目次》
〈プネウマ〉 ――日本の新しい読者に向けた四つの回想 7
荒ぶるのは風 ――序に代えて 11
第一部 風/〈ルーアハ〉/〈プネウマ〉をめぐる簡潔な人類学 19
1 風と環境、風と声、風と匂い 21
2 〈ルーアハ〉(RWH) 31
3 ヘレニズムからキリスト教へ ――〈プネウマ〉から〈スピリトゥス〉へ 42
4 風の図像学へ向けて 54
第二部 受肉と昇華 71
5 受肉 ――どうして、そのようなことがありえましょうか 73
6 昇華 ――天使、耳、口、光、鳩 83
7 匂い ――言葉にできないもの 106
8 染み ――〈プネウマ〉の形態としての大理石 125
第三部 空気と動きの解釈学 149
9 動きと図像解釈学の起源 151
10 レオナルドの〈プネウマ〉的形態 166
11 カイロスあるいは好機 180
12 最後の契約 ――クモの巣の網 198
嵐の前の静けさ ――結びに代えて 207
著者あとがき 221
訳者あとがき 227
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
