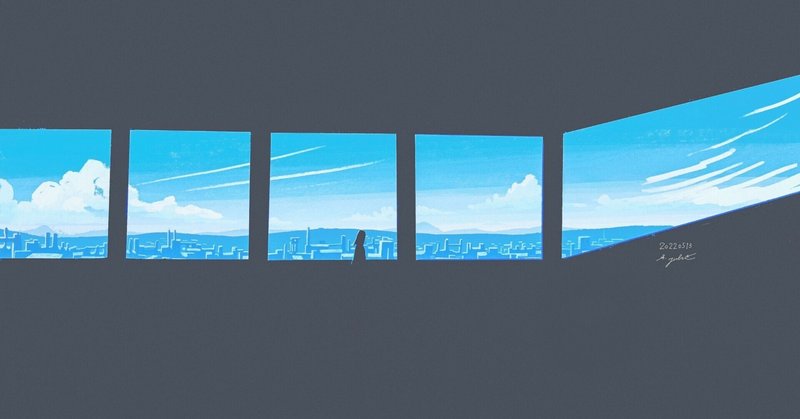
駐車場と青空の話
立体駐車場の、灰色の柱の向こうに、広い青空が見えていた。響いていた靴の音、乾いたコンクリートの香り。そんな景色ばかり、いくつも覚えている。
―――――
人混みが怖くて、駅をまともに歩けなかった。
中学生の頃の話だ。
駅も繁華街もデパートも、あの頃はとても怖かった。
そうなる少し前から、中学校には行けなくなっていた。
なんとか行けた高校は、通信制だった。
平日にも時間があったから、よく母に連れられて、遠くのショッピングモールに行った。
1時間も車に乗るのに、買うのはくだらない、小さなものばかり。あるいは、2人で適当に選んだ映画を、ほとんど誰もいないシアターで眺めて過ごした。人のいないショッピングモールなら、人混みに怯えていたわたしにも歩くことが出来た。
当時のことを思い出すとき、頭をよぎる景色はいつも、お店ではなくて、ショッピングモールの駐車場だ。そうでなければ、車の窓から見ていた海のこと。
立体駐車場は、どこも薄暗くひんやりしていて、ひどく無機質で人工的だ。でも、なぜかそれが好きだった。あの寂しさが好きでたまらなかった。
屋外ではないけれど、屋内と呼ぶにはどこか頼りない、あの殺風景な空間が。
立ち並ぶ柱の向こうには、いつも、広い広い空が見える。遠くの山々や、街並みも。
雨の日には、山には薄ら靄がかかる。
晴れた夕方には、建物の輪郭や停まっている車のフロントガラスが、日を浴びて金色に光っていた。
母と2人で買い物から戻って、明るかったショッピングモールから、車に向かって歩いていく。青空がとても綺麗だった瞬間を、今でもはっきり思い出せる。
あの青空の下のどこかでは、父が仕事をしていたり、兄が机に座って勉強をしている。昔仲の良かった友人たちは、当たり前に授業を受けて、知らない誰かと笑いあっている。
それを想像すると、平日の昼間にこんなところにいて、ぼんやり過ごすだけの自分が惨めで情けなくて、余計に外の世界が眩しく美しく見えた。
でも、どこか清々しい気持ちがあったことも、やっぱり覚えている。世の中の平均的な「普通」からは外れてしまったけれど、何も自分を急かさない。誰もわたしを責めない。
そういう、自由な時間を許してもらったことが、本当にありがたかった。光や風を浴びて、ゆっくりじっくり好きなだけ、思考を巡らせる機会があるということが、なにより幸運で幸福だと思った。
大抵、そういうとき、わたしと母の手元からはパンの香ばしい匂いがしていて(なにも買わなかった日にも、とりあえずおいしいパンだけは購入して帰っていた)、その香りと、駐車場の中を通り抜けていく風と一緒に車に乗り込んだ。
ぐるりと方向が変わって、見える景色が変わる。さっきまで、他人事のように見ていた明るい空の下へ、車は走る。
あれから何年か経って、家族と離れて暮らすようになって、今では人がたくさんいる場所も歩けるようになった。車も、車の免許も持っていないから、駐車場に行くことはすっかり無くなった。
あの頃のわたしに言わせるなら、たぶん今のわたしは、あの日羨ましがった青空の下の人間だ。過去の自分はいつでも、無機質なコンクリートに立って空を見ている。
でもね、と、心の中で過去に向けて語りかける。
きっと他の人の心にも、本当は、あのがらんどうの駐車場はあるんだと思う。同じ明るい場所にいる時は、そんなことはわからないけれど。
あの日より強くなったわたしが、それでも尚、迷いや痛みを抱えるように。
誰もが、届かないものに想いを馳せる。
誰もが、周りの眩しさに立ち尽くすこともある。
それでもみんな生きていくんだなと思ったら、なんだかもう、とても愛おしい。駐車場から見ていた世界の全てが。ひとりぼっちだと思い込んで寂しがっていた自分のことも。
今のわたしが、あの場所に立ったら、広い景色と灰色の柱や壁に、何を思うんだろう。案外、あの頃より空っぽの心で、風に吹かれていられるかもしれない。そうだったらいいのに。
日が沈む。
夕暮れの光の中で、記憶の中の自分が、バタンと音を立てて車のドアを閉めた。
2022.5.14
幸
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
