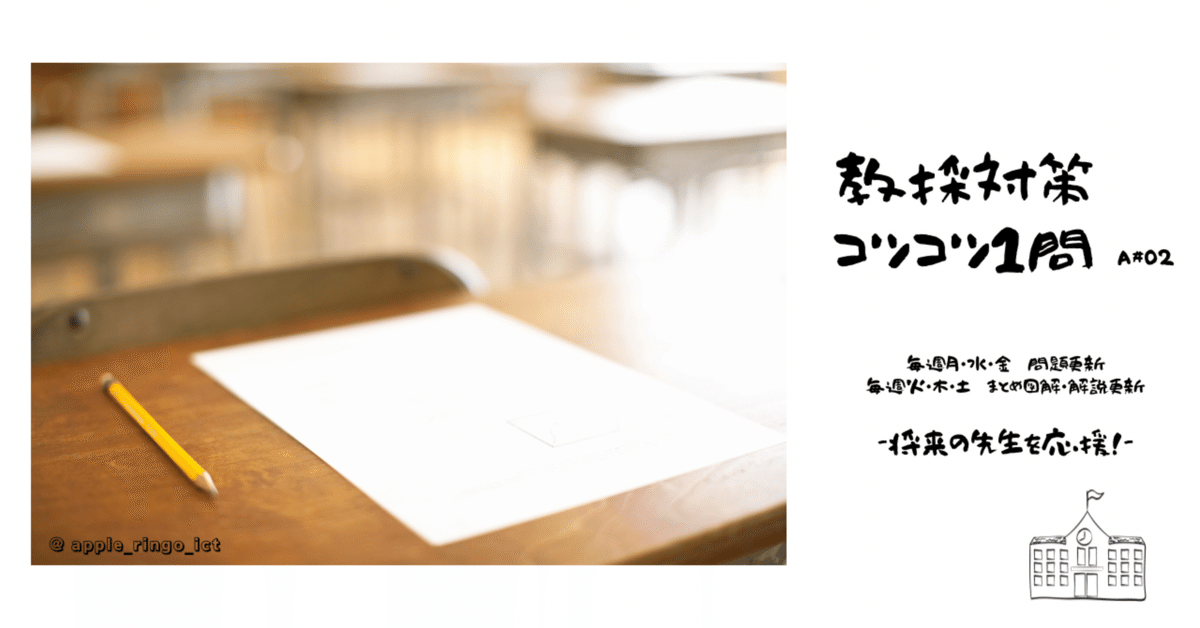
教採対策コツコツ1問 A#02 教育原理(生徒指導提要と校則)
昨日の教育原理の問題の解説です。
生徒指導提要に関する問題でした。
解答(令和5年度採用 沖縄県教員採用試験問題より)
次の文章は、生徒指導提要(平成22年3月文部科学省)の生徒指導に関する法制度の一部である。 文中の( )にあてはまる語を、それぞれ次の1から5までの中から一つずつ選び、記号で答えよ。
1 校則の根拠法令
校則について定める法令の規定は特にありませんが、判例では、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲内において校則を制定し、児童生徒の行動などに一定の制限を課することができ、校則を制定する権限は、学校運営の責任者である校長にあるとされています。
裁判例によると、校則の内容については、学校の専門的、技術的な判断が尊重され、幅広い( 42 )が認められるとされています。( 43 )上合理的と認められる範囲で、校長は校則などにより児童生徒を規律する包括的な権能を持つと解されています。
( 42 ) 1 自由 2 裁量 3 選択権 4 主体性 5 役割
答:2 裁量
( 43 ) 1 法律 2 道徳 3 社会常識 4 社会規範 5 社会通念
答:5 社会通念
生徒指導提要は、「生徒指導のガイドブック」とされる手引きで、今回12年ぶりに改訂され、早ければ来月にも公開される予定です。日常の児童生徒との関わり方から不登校・いじめへの対応など、学校現場で起こるさまざまな課題に対する指導方法や心構えが約280ページにわたり記されています。
実は、私もつい最近の報道までは、このような国で定めた手引きの存在があることを知りませんでした。子育てする親にも参考になるような内容も載っていたりするので、興味のある方はぜひ読んでいただけたらと思います。
今回の改訂のポイントについて、教採の時事対策として確認しておきたい内容、以下の3点、特に校則についての内容だと思います。(来年度は内容含め頻出の予感ですね。)
1.「校則を学校のホームページ等で公開すること」
2.「校則を制定した背景について示すこと」
3.「校則を見直す場合にどのような手続きを踏むべきか、その過程を示すこと」
学校の行きすぎた校則の設定が問題となったりする中、その透明性を高める見直しを進めたいという意図が見えます。
児童や生徒が校則の見直しに参加することに、教育的な意義があることについても触れられています。自分達も関与して作った校則だから守る、といった意識の醸成には良い方向に働くかもしれませんね。
どのように現場に賽が投げられ、それをどう我々教員が落とし込んでいくのか。世間の注目、ということになると思いますが、学校現場が、忙しい勤務の中でどう実施できるのか、果たして、優先順位の高いものとしてすぐ手をつけていけるのかは、(少し)私の周りでは話題になっています。(校則の見直しまでは現実問題必要かもしれないが、HPでの公開・更新の手間のかかる作業までやはり現場任せなのか..など。)
他にも、様々な項目が掲載されており、存在を知った今回、しっかり生徒指導について考えてみようと思いました。
読んでいただいているみなさん、これまでの経験・自分の学生生活の中で、生徒指導や校則に納得いかなかった、こんなブラック校則がある!(お子さんの現在の学校のことでも構いません)エピソード、ぜひ聞かせてください。
本日もご覧頂き、ありがとうございました♪
最後に宣伝。
本日見事創部が叶った “note大学 教育・子育て部”についてです。
note大学 教育・子育て部【子どもが笑顔でみんなも笑顔】

↑ 私の思いも書いた、部員募集記事。
note大学の学生の皆様、ぜひnote読んで、入りたい方は、募集掲示板にコメント下さい!
教員採用試験関係の記事、情報提供も充実したいと思います!
現部員の皆様は、宣伝よろしくお願いします🙇♂️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
