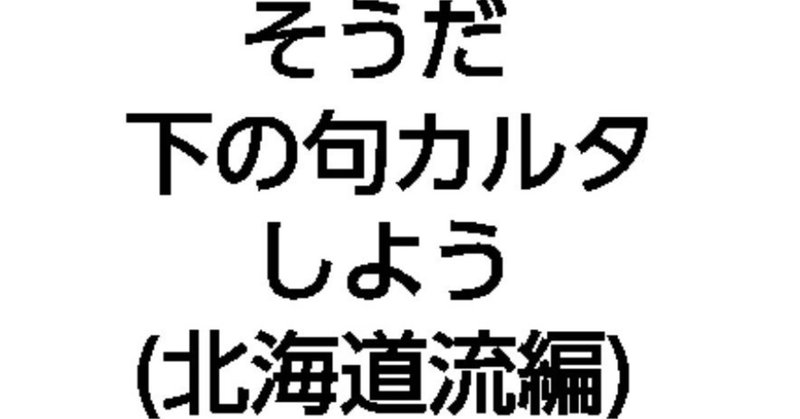
そうだカルタしよう。①
オッスオラ見習い歌人。あまのの弟子。(大嘘)
おふざけは1行目だけにして、はじめまして、ビショップと申します。先日、きつねこプロジェクトさん、ヒライデホンさん、霧島龍さんなどによって行われたツイキャスにて
「木札歌留多とはなんぞや?」
との疑問を受けましたので不詳わたしくし、自称「北海道のやばい人」が解説の任を勝手に志願しnoteをまとめている次第でございます。
ルール説明①「まず木札歌留多ってなに?」
北海道に伝わる伝統的な遊びです、北海道内なら知らない人はほとんどいません。道東部で盛んですが、道北部や道南、道央でもやはり行われているようです。
主に冬場にやります。室内競技ですので夏もやりますが、最も盛んになるのはやはり冬場ではないでしょうか。
木製の札に墨で「小倉百人一首」が変体仮名で書かれています。
選者の藤原定家はみなさんもよくご存知ではないでしょうか?
え?知らない?
大丈夫です。のちのちこのnoteに「ズバリ!人気札10選!」などと題してまとめておきます。
ルール説明②「人数は?どうやってやるの?」
北海道木札歌留多の公式大会における最低必要人数はこちら
読み人:札を読み上げる人です。人によって読み方が違うので選手を苦しめるのか否かを握る運命の人です。読み上げ方についても後ほど。
選手:最低四人〜最大六人。
(公式大会では六人でなければ出場不可)
木札歌留多は競技としての側面が強いので選手という表記にしてあります。三人1グループのチームになり、2チームで札を早く自陣から無くした方が勝ちです。お互いのチームの人数が合っていることが重要になってきます。
選手のポジショニングについて
まずは下図をご覧下さい。

○守り(親とも呼ばれる事も)
味方チームの中で一番多く札を持つ係の人です。向かい合う形で敵の突きがいますので、その人から札を守って先制的に取っていく、という役割を持っています。
○中堅
中央部分を担う人です。基本的に5枚札を持つのですが、チームによっては守りと札を分け合って守りの負担を軽減する作戦や、中堅の人が取りやすい札を持たせ、相手の中堅をどんどん突いて取る。などといった戦法も見られます。
そのチームの特色が出るポジションと言っても良いのではないでしょうか。
○突き(攻めと呼ばれる事も)
相手チームの守りが持つ札を取りに行く人です。この人も基本的に自札5枚を持つことが決まっています。
突きの人にも特色があるのです。
ルール説明③「競技進行はどうするの?」
まずはじめに、100枚ある札を2チームで50ずつに分けます。
50枚を守りの人が自陣の自分のポジションに並べます。
そこから中堅、突きの人が5枚ずつ取り、並べ、競技開始の準備が整います。
大会では同時に何チームもの対戦が組まれて行われるのですべてのチームが準備を終えるまで作戦会議や、札の並べ替え、チーム内での相手の札の位置や自重札が2箇所に分かれていないかなどを確認します。
競技開始とともに両チーム互いに礼をし、お願いしますと言って始めます。
下の句カルタは下の句のみを読み上げるので読み人は「わがころもではつゆにぬれつつ」をはじめの空札(からふだ)とし、読み始めます。
その後、読み人が引いた順に札が読まれ、それを選手が取り、というのを繰り返し、先に自陣から札を無くす、ゼロ枚にした方が勝ちとなります。
以上で簡単なルール説明を終わります。
難しい単語などは次のnoteへ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
