
個々に良いことは全体にとって良いとは限らない~合成の誤謬~
今日は前職の監査法人でお世話になっていたパートナーの方とランチです。
その方がとてもグルメな方で、今回は何と白金のフレンチに行くことに。
私なんかが行くのはお門違いとは思いつつも、せっかくの機会なので堪能してこようと思います。
さて、今回は「合成の誤謬」という言葉について書いてみようと思います。
1人1人は正しい行動をしているはずなのに…
学校の野球部に、バッティングセンスの高い選手が何人もいるとします。その全員がホームランバッターであり、将来プロ野球の一軍で大活躍が期待されるほどのレベルです。
しかし野球は様々な技術を必要とするスポーツです。
バッティングでいえば高打率をキープすることも大事ですし、逆に送りバントなどで確実にランナーを進塁させる人材も必要です。盗塁のため足の速さに自信のある選手、守備に絶対の自信のある選手、チーム全体をまとめるキャプテン的なスキルを持った選手、色々なスキルを持った選手がバランスよくかつ協調性を持って集まらないと、かえってチーム全体として強いものにはならないですよね。
このように、個々の部分が正しいからといって、全体も正しくなるとは限らないという状態のことを「合成の誤謬」と言います。もともとは経済学用語のようですね。
今の日本経済はまさに「合成の誤謬」の状態
この「合成の誤謬」、まさに今の日本経済がこの状態にあると言えるのではないでしょうか。
「失われた30年」と言われるように、日本の賃金は全く上がっていません。新聞やTVでは賃上げが進んでいるように言われますがそれは一部の体力のある大企業だけで、日本の企業の9割を占める中小企業では賃上げがなかなか進んでいないのが現状です。
このような状態の中、各家計ではどのような行動をとるでしょうか。
給料は上がらない、でもインフレで物価は上がり続けている……将来に対する不安は募るばかりの中「余計な出費は少しでも抑えて将来に備えよう」という発想になります。
この行動自体は、個々に見れば正しいように思われます。
しかし、これをマクロ的な視点で見た場合、果たして正しいと言えるでしょうか。
お金は国の経済の血液のようなもので、その流れが滞ればたちまち体調は崩れ、よどんで濁ったものになってしまい、末端まで酸素も行き渡りません。
個々の家計が出費を抑れることでお金の循環が止まり、流れるべきところにお金が流れなくなる。
すると国全体としての景気が悪化し、それがまた給料に跳ね返って家計を圧迫する。
家計が圧迫されるとますます消費行動は起こらなくなる……
まさに「合成の誤謬」状態です。
これが続いてきたのが、「失われた30年」と言っていいのではないでしょうか。
お金を正しく循環させるには
でもこの「合成の誤謬」状態が理解できたとして、各家計単位ではどうしようもありませんよね。火の車なのに「もっとお金使え」なんてのはどだい無理な話です。
ではそのような状態で誰がお金を正しく循環させることができるのか。
それはもちろん政府です。
政府は国債を発行して日銀に引き受けてもらえば資金を調達することができますから、政府自身が必要なところにお金を流して資金循環の呼び水にするのです。
※財政法第4条の関係でそう簡単に国債を発行できない、という話はありますが、これはまた別の論点となります。
また滞った消費を循環させた大きな要因の一つとして、消費税があります。
導入以来段階的に引き上げられて現在10%にまで上がっていますが、なぜかIMFがこれを20%にまで引き上げるべきだとか言っています。完全に内政干渉ですよねこれ。
このおかげで消費が冷え込んでいるにもかかわらずこのような発言をすることには何かしら意図を感じざるを得ませんが、まずはすべての消費行動に課せられる税金である消費税の減税から着手するのが一番手っ取り早い方法でしょう。
私たちもついつい買い控えをしたり、少しでも安いものを求めて奔走しがちですが、お金は「どう貯めるか」ではなく「どう使うか」が大切。
無理のない範囲でいいものにしっかりとお金を払ってお金の循環をよくすることが、結果として私たちの給料に跳ね返ってくるのだと理解すれば、時間はかかるかもしれませんが日本経済も少しは上向くと信じています。
~編集後記~
・ペン字
・中国の古典である「大学・中庸」読了。一人一人が「誠」の心をもって徳を高めることが聖人君子への道であり、お金はあくまで結果であることが教えられていました。いい本でした。
・図書館でIPO検定試験を勉強
・たくさん愛でた後に撫でるのやめたら目線で訴えかけられました
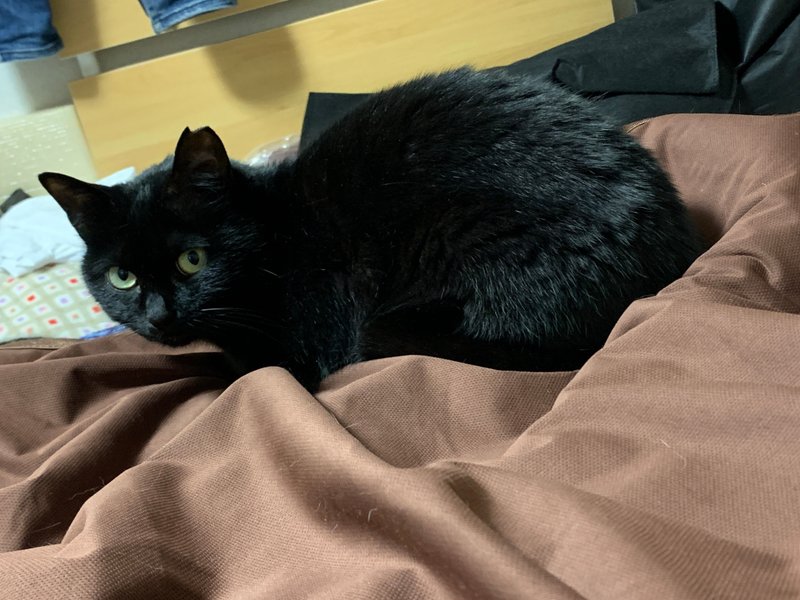
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
