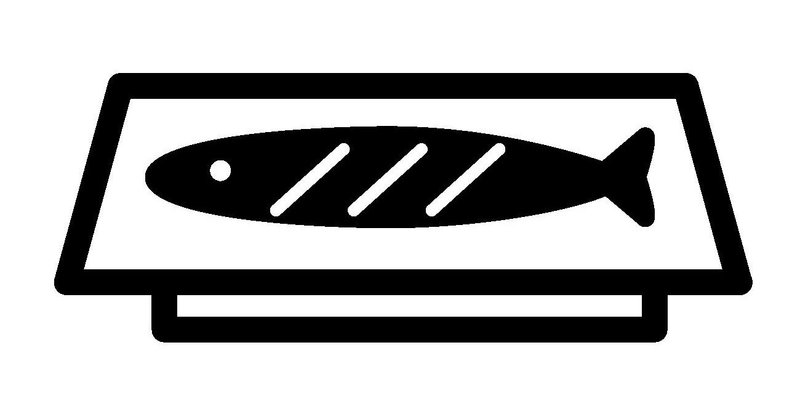
秋刀魚の味
サンマと聞いて「テレビでヒーヒー笑っているおじさん」と連想する人もあまりいなくなってしまった程の未来、日本の食卓からは秋の味覚であるサンマは完全にその姿を消していた。食卓だけではない、かつてそんな魚が海を泳いでいたことすら、ほとんどの人はとっくの昔に忘れてしまっていた。ある年を境にサンマはこの地球上からこつ然とその姿を消してしまったのである。
サンマが居なくなってしまったことに最初に気がづいたのは、もちろん漁師たちであった。ありえないほどの不漁に疑問を感じた漁師たちは、漁業組合を通して詳細な調査の必要を国に対して訴えかけた。
国から調査の依頼を受けた回遊魚の研究を専門とする近代大学のO教授は、原因は温暖化による海流の変化だろうと予測し、調査の範囲を日本近海から遠洋へと徐々に拡げていった。しかしどこまで範囲を拡大しても、サンマの群れどころか、ただ一匹のサンマさえ発見することはできなかった。
O教授は調査の範囲を地球全体にまで拡げてみたが結果は同じであった。世界中から集められたデータは、もはやこの地球上にはサンマが存在しないことを示していた。
パニックを恐れた日本政府は、サンマは歴史的不漁によって値段が高騰しているというニュースを流してこの事実を隠蔽した。そして歴史的不漁はその後何年も続き、次第に、新しくなった年号に違和感を感じなくなるように、人々は少しずつサンマの味を忘れていったのである。
ところがである。とっくの昔に人々の記憶からサンマが忘れ去られた今頃になって、突如として一匹のサンマが発見されたのだ。現場はとある水産加工現場の古い冷凍庫だった。近々解体の決まっていたその冷凍庫で準備作業をしていた作業員が、配管に詰まった金属の棒のようなものを取り出したところ、それはほぼ完璧な状態で冷凍保存された一匹のサンマだったのである。
サンマは貴重な標本として、ひとまずはO教授の研究室に運ばれたが、水産加工会社がその権利を主張したため二枚に降ろされ、骨と身の付いた資料価値の高い側が標本とされ、残りの身の部分は水産加工会社に戻されることとなった。
水産加工会社の商品開発部ではバイオテクノロジーを駆使して、戻された半身から新たに一匹のサンマを培養することに成功した。そして工場ラインでの製造を開始し、奇跡的に蘇った幻の味として販売を始めたのである。
初めのうちサンマと聞いて懐かしがるのは高齢者ばかりであった。しかし口当たりの良い味付けに慣れた現代人は、そのほろ苦い香ばしさに戸惑いつつも、なんとなく、かつてそうであったように、サンマは日本の食卓に欠かせない食品として復活していったのだ。しかも工場ラインで生産される培養サンマは、脂の乗ったまるまると太った旬の状態で生産され、私達は旬のサンマを一年中食べることができるようになったのである。
しかし、死んだ魚から再生できるのは、所詮は死んだ魚でしかなかった。日本の食卓に帰ってきたサンマではあったが、海の中を泳ぐサンマの姿はもう二度と帰っては来なかったのである。
(2020年10月ssgへ投稿したものに加筆修正)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
