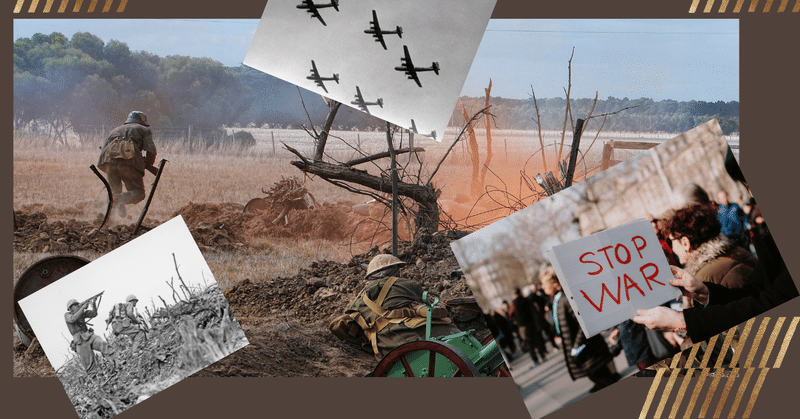
憲法の空文化
歴代天皇と日本国憲法前文
茅ヶ崎市立西浜小学校に通っていた半世紀ほど前、5年生と6年生のときに担任をしてくれたのは、茅秋という号で書家としても活躍していた中原先生だった。
中原先生は,前衛書道の書家で、ほぼ毎日発行していたガリ版刷りの学級通信でも個性的な字体を駆使してカラフルな紙面をつくっていた。書き取り相撲というバトル形式の漢字の授業で私たちのやる気を引き出し、私がふざけて書いたデタラメ書体の書道作品を褒めてくれた。
選挙の開票速報を見続ける授業とか,札幌オリンピックを観戦する授業とか,観音開きのテレビを生かした(?)授業もしばしばしてくれました。
どこから借りてきたのか、イエスかノーでボタンを押すと即座に結果が集計される装置を使って授業をしてくれたこともあった。
なんでもみんなに聞いてかまわないと言うので、男子が次々に集計結果が映し出される機械の前に立ち、「ぼくのことを好きな人?」という質問を女の子たちにぶつけたことを覚えている。
そんな中原先生がよく言っていたのは、小学校高学年というのは記憶力がいちばんある年頃だから、たくさん勉強していろんなことをどんどん覚えなさいということだった。
自分が小学生の頃に暗記したという歴代天皇の名を諳誦して聞かせてくれ、その気になればきっとできるから、君たちも日本国憲法前文を暗記してみなさいと言った。
素直な少年だった私は、先生の真似をして日本国憲法前文を暗記し、返す刀で歴代天皇の名を暗記しようと試みた。
ただ、日本国憲法前文は暗記できたものの,歴代天皇の名は「一条・三条・後一条・後朱雀・後冷泉・後三条…」あたりのリズムの悪さ,語呂の悪さに堪えかねて挫折をした。
今思えば私の父や大江健三郎と同じようにジュブナイルと言える年代で敗戦を迎えた中原先生は、歴代天皇の名を暗記させられる教育と、日本国憲法前文を暗記させられる教育を相前後して受けた世代だったわけで、そういうねじれを私たちはそのまま受け止めていたことになる。
中原先生にあおられて日本国憲法前文を丸暗記した小学生の私は、当然のことながら平和憲法についても学んだ。
丸暗記した日本国憲法前文を諳誦するときの高揚感は、憲法九条の条文を読むときの私の気持ちの高ぶりにそのままつながっていった。
そういう小学生の私にとって、自衛隊は明らかに違憲だった。
中学生になり、語彙力や読解力が高まった(はずの)私にとっても、自衛隊は明らかに違憲でした。
大人たちの中にもそう主張している人たちがいたが、現実問題としては自衛隊は合憲であると見なされ続け、今日にいたっている。
一票の格差については、「違憲」ないしは「違憲状態」という最高裁判決が何度も出ている。
憲法学者の木村草太は、「不気味な「火事」の例え話 国燃やす憲法の空文化」という記事の中でこう言っていた。
市民が憲法違反を放置すれば、権力の側は、憲法に違反しても大丈夫だと学習する。憲法を平然と破った前例ができることは、憲法を破る心理的抵抗感を弱め、憲法規範の力を縮小させてしまうのだ。
そうなると何が起きるのか。表現の自由の保障や裁判所の独立など、他の憲法条項の力も縮小するだろう。これは権力にとって好都合なので、政府は、さらに憲法の空文化を押し進める。他方、市民が憲法の力を回復しようとしても、表現の自由などの武器は失われている。憲法規範は、一度空文化されると取り返しがつかないのだ。
【木村草太の憲法の新手】(13)
これは今回の安保法制についての記事である。
1972年から9回も最高裁が違憲または違憲状態と判断したのに選挙は無効にならず誰も責任を問われていないとしたら、一票の格差問題における事情判決の法理適用も「憲法の空文化」に加担してきたという話になる。
憲法はもうとっくに「空文化」してしまっているのだ。
高等学校の国語教科書に載っている「「である」ことと「する」こと」という文章の中で、丸山真男はこう言っている。
「国民は今や主権者となった。しかし、主権者であることに安住して、その権利の行使を怠っていると、ある朝目覚めてみると、もはや主権者でなくなっているという事態が起きることは十分にありうる」というわけです。
これは、大げさな威嚇でも、空疎な説教でもありません。ナポレオン3世のクーデターから、ヒットラーの権力掌握に至るまでの西欧民主主義の血塗られた道程がさし示している歴史的教訓にほかならないのです。
「自由を祝福することはやさしい。それに比べて自由を擁護することは困難である。しかし、自由を市民が日々行使することは、さらに困難である。」という言葉があるように、いつの間にか、自由の実質がカラッポになってしまう危 険性は、極めて現実的にありうることです。
自由は置物のようにそこにあるのではなく、現実の行使によってのみ守られる。言い換えれば、日々自由になろうと努力することによってはじめて、自由でありうるということなのです。
問題は、日々「現実の行使」に努めているのが主権者の一部に過ぎないのであれば、「自由の実質がカラッポ」になることを回避することは難しいということだ。
「現実の行使」をしない他者に対して強圧的になったり攻撃的になったりすることなく、いかに「主権者としてのわれわれ」を立ち上げることができるのかが問われているわけだが、世の中の動きを眺めている限り、その方途は容易に姿を現わしてくれず、ただただ私は茫洋たる世界にじっと目を凝らすばかりだ。
未
※ 2015-08-14 憲法の空文化―戦後70年をめぐる随想(3) による
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
