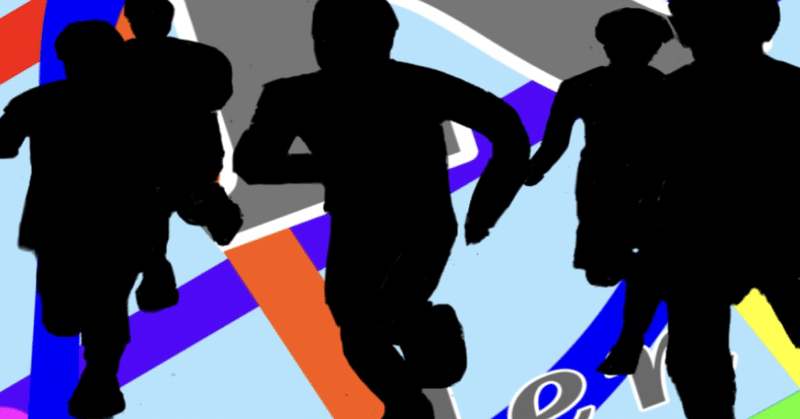
「学校非公認 R駅伝部」第1話
例えて言うならそれは「黒い弾丸」だった。
黒いユニフォームで大きい選手達の間を駆け抜けて行く小さい弾丸。
あの日、それを目撃したことが1人の少年の人生を全く違うものに変えていった。
夏の日照りと暑さが続いているのに、名目上「秋」を名乗っている9月上旬のある日のことだった。
「お母さんの友達の息子が出るから」という理由だけで、少年は学校を休んで行った皮膚科の帰り道に、中学校駅伝大会の応援に連れて来られてしまった。
駅伝には全く興味がない。
2区と5区の選手が通過する駅伝コースの沿道で、少年は人ごみの中、ただひたすらゲーム画面に目を落としていた。母親は隣でずっと友達とのおしゃべりに夢中だ。
”お母さんの友達も息子が出ているレースなら、もっと一生懸命見ていればいいのに。太陽に照らされてゲーム画面が見にくいし、早く家に帰りたいんだけど。”そんな思いが少年の心に浮かぶ。
「うちの子のチーム、どうせ後ろの方だから。アハハハ。」
とか言って、全然駅伝に関係のない話ばかりしている。
「こちらは中学校駅伝大会の広報車です。間もなく選手が来ます。皆さん、ご声援をお願い致します。」
少年はアナウンスの声に反応して、何となく顔を上げた。
遠くの方に2台の白バイの後から走ってくる選手達が見えてきた。その姿がだんだん大きくなってくると、先頭集団の4人とその少し後方から1人の選手が追い上げてきているのが見えた。しかし少年にとっては知り合いが走っているわけでもない、何の関わりもないレースだ。
誰が勝っても別に何とも思わない。
再びゲームに目を落とそうとしたまさにその時、「弾丸」が少年の目に入った。小柄で黒地に白で「KAMIWADA」と書いてあるユニフォームを着た選手。おそらく1年生だろう。身長が周りの選手に比べて明らかに小さい。それなのに自分より大きい選手を2人、3人とごぼう抜きしていく姿に目を奪われた。周囲の歓声も途端に大きくなる。
「すげぇ……。」
間近を通り抜ける時の荒い息。鼓動の音まで聞こえてきそうだった。顔を激しく歪めながら、もうすぐ着く中継所へ向けてさらにスピードを上げた。
「PAUSE」が点灯したままのゲームを片手に、中継所まで続く沿道を少年は吸い寄せられるように走った。
「ちょっと、どこ行くの?」
後ろの方で母親が声を掛けた気がしたが、少年は立ち止まらずに黒い弾丸を追い駆けた。もっとその走りを見たかったのかもしれない。この先の結末を知りたかったのかもしれない。しかし確実にそれらとは違う何かしらの感情が少年の心に去来していた。
中継所付近の歓声は遠くからでも耳が裂けるようだった。
後方から見ると「黒い弾丸」は集団をすべて抜き去って、次の走者に襷を渡したように見えた。それと同時に崩れ落ちそうになったところをチームメイトがかろうじて支え、中継所の奥へと連れて行く。遠目にそれを見た少年はさらに歩を速めた。
中継所に着いた時、「黒い弾丸」は人の往来の邪魔にならない木陰で、荒い息と共に横たわっていた。
「お前どんだけ速えぇんだよ!今飲み物持って来るからここで待ってろ。」
弾丸を支えていたチームメイトが去って行った。少年は大の字になって天を仰いでいる弾丸の方へと歩いていく。
少年の影に気付いた弾丸は、少しだけ目を開けて少年の方を見た。目が合った途端、少年はふと我に返った。
なぜここに来たんだろう?全然知らない人に話しかけようとして来たのか?「速かったですね!」とか「感動しました!」とか伝えるために?そういうことなのかもしれないけど、それも何か違う気がする。ただ何となく…なぜか…。でもどうしよう?絶対変な奴だと思っているし、今走ったばっかりで疲れているのに、”何だ?このガキうぜぇ。”とか思っているかもしれない。
そんなことが少年の頭の中を駆け巡る。その光景はオドオドしている挙動不審者そのものだ。
「どうした?見知らぬ少年よ。」
まだ整わない息をしながら笑顔で弾丸が発した言葉だった。
……え?
何かの台詞でも言ったのだろうか?それともこういう言い方をする人なのか?
その言葉の風変りさと話しかけられたことへの驚きが挙動不審に輪をかけ、少年の心は半ばパニック状態になった。
そんな少年の様子を見た弾丸は視線を空に向けながら言った。
「少年、走るって楽しいぞ。一緒に駅伝やろうぜ。」
満面の汗と笑みが輝いて見えた。
「……!!」
少年の心に雷鳴が響いた。半パニック状態なのに落雷に見舞われ、少年の開いた口は閉じる意思と声を出すスキルの両方を失ったようにパクパクさせているだけだった。
「飲み物取ってきたぞ〜!…ってお前誰としゃべってんの?知り合い?」
あ、ヤバい!
チームメイトが遠めから声をかけてきた瞬間、はじかれたように少年は後ろを向き走り出した。
バカじゃないの?俺、なんで行ったんだろう?全然知らない人なのに。
走りながら少年は恥ずかしさで耳まで赤くなっていた。
でも……。
「一緒に駅伝やろうぜ。」
黒い弾丸の声が少年の心の中で何度も鳴り響いていた。
それから1年7か月後、少年は神羽田(かみわだ)中学校に入学した。少年の名前は葛西直進(かさいすすむ)。直進の住んでいる所から言えば、西積(にしぜき)中に進むのが順当だったが、隣の神羽田中に進むことを決めた。それは「黒い弾丸」の言葉がずっと直進の心を支配していたからだ。
駅伝を見に行った当時、直進は運動を自主的にすることがほとんどない小太りでゲーム好きの小学生だった。しかしあの出会いの後、直進は毎朝のジョギングを欠かさず行うようになり、体型もスリムになっていった。校内の持久走大会では4年生まで最下位争いをしていたのが、6年生では賞状をもらうほどに成長していた。それもこれも「黒い弾丸」と一緒に駅伝をしたい、という真剣な思いからだった。
クラスでの自己紹介が始まった。
小学校の友達はみんな西積中に行ったから、当然クラスは知らない人ばかりだ。
知らない環境に飛び込んで行くのって、ゲームの新しいステージに入ったときみたい!直進はワクワクしていた。
いくらジョギングするようになったからと言っても、ゲームをやめたわけではない。思考回路はやはりゲーマーだった。
「西積小から来た葛西直進です!中学校では陸上部に入って駅伝を頑張りたいです!」
なぜかクラスがザワザワしている。何か変なこと言ったかな?直進は不思議に思ったが、担任の先生がすぐにその謎を解き明かした。
「葛西くん、この学校には陸上部はないんだが…」
「……え?」
周りのクラスメイトのうなずきがその言葉の正しさを証明していた。
「でも、俺は一緒にやろうって誘われたからこの学校を選んだんです!ないわけないじゃないですか!!」
「まぁ駅伝部はないではないが、駅伝大会の前に1ヶ月だけ活動する臨時部活だしなぁ。何かの間違いじゃないのか?はい、葛西君座って。自己紹介次。」
頭が真っ白になりながら着席をした。
どういうこと?黒い弾丸は何に誘ってくれたんだ?今まで毎日俺は何のために走ってきたんだ?頭を抱えている直進を遠くから見ている視線があった。
休み時間、直進の前に突然人影が現れた。
「お前、ちょっと来い」
直進は制服をつかまれ、人気のないところに連れていかれた。
ヤバい!どうしよ?何か俺悪いことしたっけ?でも何で俺なんだ?コイツは不良なのか?よく分からん!でも入学早々ナメられるわけにはいかない!
「なんだよ!はなせ!」
つかまれた手を振り払い、やったこともないファイティングポーズをとって威嚇しようとしたとき、そいつは声を発した。
「なぁ、お前、誰に誘われたんだ?」
突然のことに直進は戸惑った。
「え?」
ファイティングポーズ終了。
「さっき言ってただろ?一緒にやろうって言われたって。誰にだ?」
さっきの自己紹介のときのことを言っているんだ、と直進はすぐに分かった。この人は何かの真相を知っているのか?
「黒い弾丸。」
「え?黒い弾丸?なんだそりゃ?」
直進はそう呼んでいたが、自分の中で勝手に呼んでいただけなので当然通じるはずがない。
あっ!と思ってすぐに言い直した。
「おととしの駅伝大会で2区を走っていた人。」
「黒川先輩が?先輩に言われなかったか?勧誘のこととか駅伝のこととかは誰にも言うなって!」
即答で名前が出てくるなんて。何かを知っていることはまず間違いない。
「え?そんなこと言われてない。…てか、何か知ってるの?…えーと」
「俺は大崎天翔(おおさきたかと)。じゃあお前もこれ持っているか?」
天翔は一枚のチラシのようなものを出した。
「R駅伝部?何?これ?」
「持っていないのか?黒川先輩は渡さなかったか?」
「渡されていない。」
あの時の状況から言って、何かを渡すことは不可能だっただろうな、直進は頭の中の記憶をたどった。
「これを持って行かないと入部できないって言われたぞ?」
R駅伝部の紙をヒラヒラさせながら、天翔がいぶかし気に眉をひそめた。
「え?でも何ももらわなかったよ。ただ『一緒に駅伝やろうぜ』って言われただけで。」
自分で「持って行かないと入れない」と言いながら、天翔は直進の言葉を聞いて納得したようにうなずいた。
「黒川先輩ならやりかねないな。そうか。それなら俺と一緒に来ればいい。今日の部活見学に。」
やっぱり駅伝部はあるんだ!
どん底まで落ちた直進の心は急浮上をはじめた。
「え?部活見学?やっぱり駅伝部はあるんだね?」
「ホントに何も知らないんだな。黒川先輩だからな。仕方ないか。俺もそんなに詳しくないけど…」
黒い弾丸は黒川先輩って言うのか!苗字まで黒なんだ、と直進は変な感心をした。それと同時に、話を聞いた限りでは黒川先輩はドジ?なのか?それとも抜けキャラ?天然?などと、ちょっと失礼な想像もしていた。
天翔の説明によると、R駅伝部とは正式に認められた部活ではないらしい。現在の3年生が、近くの小学生が出るマラソン大会、記録会などで有望だと思う人に声を掛けて、速い人たちを集めている。学校の部活は「歴史伝承部」というほとんど活動のない文化部に所属し、放課後から夕暮れまで本格的に中〜長距離の練習をする。目標は全員で中学駅伝大会に出場してタスキをつなぐこと。
「それがR駅伝部だそうだ。」
「おお〜!!なんかすげぇ!…でもRって?」
「名前のことまでは知らねー。今に分かるだろ。」
「それもそうだね!!」
「しかし、『黒い弾丸』って…お前のネーミングセンス…。」
天翔は今まで我慢していたのが堪え切れなくなったように吹き出した。
「なんだよ!ユニフォームが黒くて弾丸のように速かったんだからいいじゃん!」
直進が顔を赤らめながら反論したとき、チャイムが鳴った。
「もう休み時間終わるぞ。」
天翔は半笑いのまま教室の方に向かい始めた。
直進は無言で後を追った。赤らんだ頬はまだ収まっていない。だが、直進の心は高鳴っていた。「正規の部活じゃない」というところがさらにワクワクさせた。内緒で作った秘密基地に友達と行くような、そんな落ち着かなさを感じていた。
歴史伝承部は活動を視聴覚室で行なっているらしい。活動と言っても、週1回1時間だけ強制参加だが、それ以外はフリー。なんともゆるい部活だ。
2人は放課後に視聴覚室へ行った。
「おお!部活見学か!!入りたまえ!!」
顧問の先生がハイテンションで迎えてくれた。
見たところ、部員は結構多い。一旦は運動部に所属したけれど、いやになったり、ついて行けなくなったりして、この部に転部する人が多いらしい。
「初めから歴史伝承部に入ろうとする生徒はほとんどいない」という噂話を、さっき隣の席の人が言っていた。先生の喜びもそういうところから来ているのかもしれない。そんなことを思いながら中に入ると、こちらを見て手招きする人がいた。
「大崎!こっちこっち。」
天翔はそれに呼応するように奥にいる先輩達の方へ向かった。直進も天翔について行く。
「よく来てくれたな!この卓が例の集まりだ。」
そこには4人いた。今声をかけてくれた人と何かの作業をしている人は名札の色から3年生らしい。ただ座ってこっちを見ている残りの2人は2年生のようだ。
「……で、もう一人は?」
声をかけてきた3年生は不思議そうに直進を指さした。名札に「田村秀」と書いてある。
「はい!葛西直進と言います!よろしくお願いします!」
直進は緊張気味に名乗った。だが、
「おお!そうか!よろしくな!」
…のような、直進が期待した返答は帰ってこなかった。
「…。」
数秒の沈黙の後、
「葛西?…リストにないな。大崎、友達連れて来るなよ」
秀は天翔をとがめるように言った。
「いや、違いますよ。コイツは黒川先輩に誘われたって言ってました。」
今日会ったばかりなのにコイツ呼ばわりかよ!
直進はちょっとカチンときたが、連れて来てもらったんだから大目に見ようと思い、怒りを抑えた。
「颯志が?お~い、颯志ぃ。そうなのか?」
紙に向かって何かを書いていた人が顔を上げた。
「何用だ?秀(しゅう)?」
クセのある喋り方。こちらの話を聞いていなかったようだ。秀はもう一度問い直した。
「お前、この葛西って1年を誘ったのか?」
颯志は直進を見た。
あの時の「黒い弾丸」だ!
直進の心にあの衝撃が蘇った。今は身長も伸びているし、あの時より大人っぽい顔になっている。でもこのクセのある喋り方、横たわりながら送られた視線。わずかな時間の出会いだったのに、昨日のことのように覚えている。
「ん?知らぬな。」
と、颯志は即答して、すぐ作業に戻った。
ガーン!
その言葉に直進は頭の中が真っ白になった。
直進の顔色の変化を見た秀は、気遣うような声で、
「ここに誘ったときはこの紙あげてるんだけど、君は持ってる?」
と言いながら、さっき天翔が持っていた紙を見せた。
「いえ…ないです。」
秀はもう一度リストに目を落とし、2、3度うなずいた。
「それじゃあ誘われてないってことになるな。悪いけど。大崎から何を聞いたか分からないが、ここのことは忘れて欲しい。すまないが他の部を当たってくれ。」
「…なんで?」
直進の返答に、その卓に座っていたメンバーがみんな直進の方を見た。
直進は目を伏せていた。顔を上げれば言いたいことが言えない気がした。
「俺はあの時『一緒に駅伝やろうぜ』って言ってもらって、毎日1年以上走ってきました。あの言葉がなければ絶対やっていないし、この中学校にも来ていません。友達がたくさんいる学校の方が良かった。でも、この人と一緒に走りたい!そう思ったから1年以上朝練をしてきたし、この学校にも来ました。それなのに……。」
小声だが近くの人には聞こえる声で、つぶやくように言っていた直進がバッと顔を上げた。
「そんなのないじゃないですか!!!!!!」
机をバン!と叩いて叫んだ。
その音と直進の声に、視聴覚室にいるみんなが振り返った。
「どうしたぁ?そこ!何をおしゃべりしてる?」
顧問の先生がこちらに向かってきた。
この状況に、颯志がスクッと立ち上がって、顧問の行く手を遮った。手には作業をしていた紙を持っている。
「九戸先生。我らは、桶狭間の戦いで信長が勝ったのは偶然ではなく必然だったというテーマで話し合っていたのであります。こちらの見学生、葛西君は今川義元を敬愛しており、私が『信長は義元に勝つべくして勝った』と話すと激高してしまい、皆の注目を浴びる結果になってしまいました。歴史好きなあまりの所業。お許しくだされ。」
陣形図らしい紙を見せながら先生に説明をしていた。
「そうだったのか。活発に議論するのは大いに素晴らしいが、大声は慎めよ。周りの迷惑になるから。」
「はっ。御意にございます。」
先生は去り際に、
「その返事、いいね!」
と、ご機嫌な顔で去って行った。
「よくそんな話がとっさに出ますね。黒川先輩。」
半ば感心したように、半ばあきれたように隣にいた2年生が口を開いた。名札には「稗貫一成」と書いてある。
「俺は今ちょうどそれについて考えていたからな。」
颯志はまた机に向かう。
「颯志が歴史好きで助かったわ。」
何か書いているとは思っていたけど、真剣に部活をやっていたのかよ!とツッコミたかったが、秀は苦笑いするだけにした。
1つの危機を脱した和やかな雰囲気とは対照的に、直進は手をプルプル震わせて立ち尽くしていた。
その姿に気付いた秀が、顧問の先生の方を見ながら話しかけた。
「今はまずい。今日は4時から練習を始めるから、その時に聞こう。葛西って言ったな?お前もまず座って落ち着け。」
その言葉に直進は従った。だが、手は強く握りしめられたままだった。
歴史伝承部の活動が終了し、学校から1km程度離れた公園に集まった。
遊具もなく殺風景だが、一周500mのランニングコースがある公園。この場所がR駅伝部の活動場所のようだ。
そこに20代半ばくらいの男がいた。
「お!大崎来たか!」
天翔を見るなり、その男が声をかけた。
「伊坂さん。よろしくお願いします。」
「…で?え~と……?」
伊坂と呼ばれた男は直進を見て一瞬固まった。
「田村ぁ〜!あと1人はだれだぁ?」
秀がここまでの経緯を話した。
「なるほど。でもそれは黒川が悪いだろう。いたいけな少年の心を弄んで。」
ちょっといたずらっぽい笑みを浮かべながら伊坂は颯志を見た。
「いや、俺は誘った記憶がない。」
さらっと言う颯志。
「いえ!確かに一緒に…」
直進が反論しようとしたのを伊坂が制した。
「誘ったにしろ、誘ってないにしろ、実際この活動を知られたわけだろ?入ってもらった方がいいんじゃないか?口封じのためにも。」
「口封じ」という表現に直進はビクッとした。
よく刑事もので悪役が言うやつだ!何かされるのではないか?と、ちょっと身構えた。
「待って下さい。今までスカウト制で活動してきたのは、知っている人が最小限の状態を作りたいからというのもありますが、練習の質を下げたくない、というのが大きな理由です。」
秀が理路整然と反論した。頭の良さを感じさせる喋り方だ。伊坂はその意見にうなずき、直進に視線を移しながら問いかけた。
「まぁ確かにそうだけどな。ちなみに君のタイムは?センゴとか。」
「センゴ?」
直進には聞きなれない言葉だった。
「ああ、1500m走のこと。」
伊坂が言い直した。
「1500mですか?測ったことありません。」
直進の返答に伊坂はちょっと意外そうな顔をした。ここに誘われる連中はそれなりの成績を持っている人ばかりだ。1500mを計測したこともない人が誘われるわけはないのだが。
「じゃあ何かの大会でのタイムとか順位とかは?」
「3位でした。」
直進は自信満々に言った。
「お?何の大会?どこかの市民マラソン大会とか?」
各地で行われているマラソン大会は、参加者や参加規模にもよるが、かなりレベルが高い場合が多い。入賞は県内、場合によっては県外の小学生アスリートが独占するケースも多い。その中で3位であればかなりの実力と言えるが…。
「いえ、学校の持久走大会です。」
周囲が笑いに包まれた。なぜ笑われたのか直進には理解できなかった。
「持久走大会…かぁ。いや、それでも3位は素晴らしいよ。学校によっては速い子がたくさんいる場合もあるしな。どこ小出身?」
「西積小です。」
「西積小で持久走1位だったのは、斎藤くんかな?」
「そうです!なんで知っているんですか?すごく速いんです。」
「市陸にセンゴで出ていたからね。タイムはえーっと…」
スマホで調べているようだ。この伊坂さんっていう人はこういうデータを集めているのだろうか?
「斎藤君、市陸(市で開催される小学生陸上大会の略)のセンゴ6分8秒。持久走大会で斎藤君と君の差は?」
「斎藤君はダントツでした。最初からずっと。」
周りの空気がシラけていた。これも直進にはなぜなのか理解できなかった。
直進の表情で何となく悟った伊坂は、直進に説明するように言った。
「君と一緒に来た大崎は、1500mを5分切るくらいで走るんだよ。ここにいる人たちはみんな小学校のときそれに近い速さだったんだ。君がダントツに速いと言っていた斎藤君より1分くらい速いんだよ。」
直進は茫然とした。
「え?でも、市陸にはそんな速い人は…。」
直進は天翔の方を振り返った。
「あぁ、俺、市陸は100mに出た。センゴは県大会なかったからな。」
そんなに速いのに1500mに出ないって、なんで?本当に速いの?そんな人今まで聞いたことないんだけど。ウソ言ってるんじゃない?そうだ!そうに決まっている。そんな速い人この辺にいるわけない。小学生で斎藤より1分以上速いなんて!俺をあきらめさせるために言っているんだ。そうに違いない。
信じられない。
直進の顔は明らかにそう言っていた。
その様子に、伊坂はこう提案した。
「実力を見たいから1500m全力で走ってみてくれ。今日はTTやってもらおうと思っていたからちょうどいい。みんなそれぞれアップしてTTの準備。」
「お、珍しい。伊坂さんのメニュー指令!よし!皆の者TT準備~~!」
颯志がみんなに向かって叫んだ。
「TT?」
直進は何のことだか分からない。
「タイムトライアルの略称だよ。タイム測るからガチで走れってこと。」
秀が教えてくれた。
途端に直進の心臓が高鳴った。
持久走大会のときよりも俺は絶対に速くなっている。みんながどれだけ速いか知らないけど、今なら斎藤ともいい勝負ができるはずだ。だから、きっと大丈夫!
みんなをアッと言わせてやろう。そしてR駅伝部に入るんだ!
ずっと練習を続けていた直進には確固たる自信があった。
胸のドキドキが強く鳴り響くのを直進は心地よく感じていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
