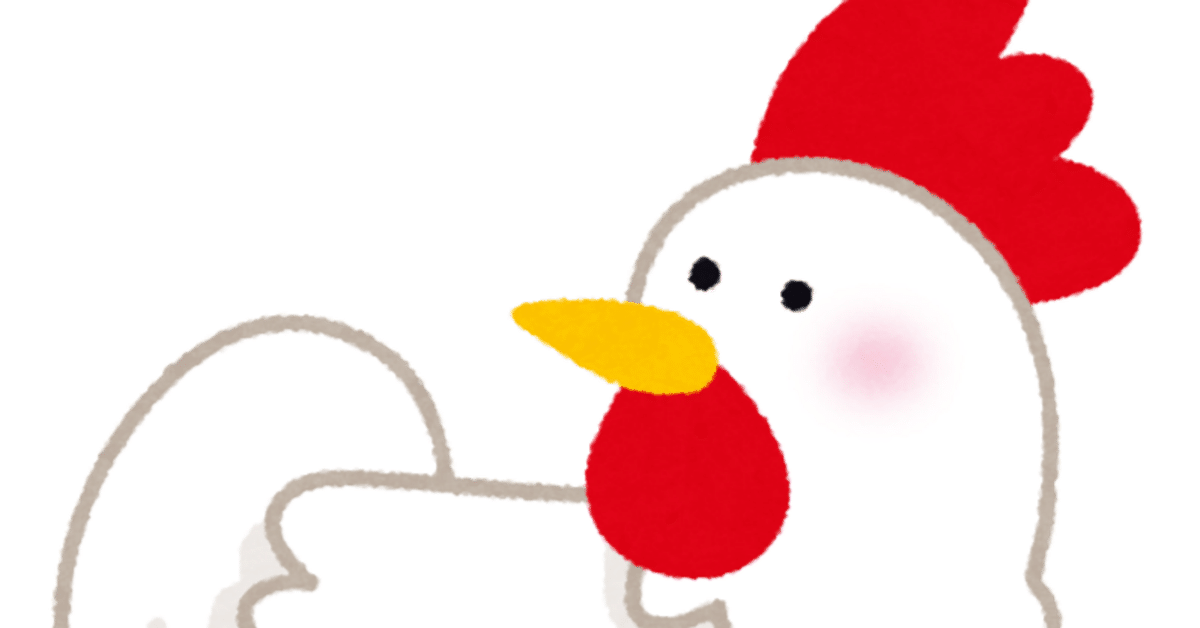
農業景況調査(令和5年7月調査)から見える本音と建て前 透けて見えるまだ気づきに至らないこと
日本政策金融公庫が農業景況調査を行い、人材育成をテーマに調査をしました。
農場を見ている者からの私見ではありますが、本音と建前が透けて見えたと感じます。
畜産業のうち養鶏を専門に見ておりますので、その分野についてお話しします。
調査は本年7月採卵鶏100の企業について行われています。
日本政策公庫を利用している企業になりますのですべてではありませんが、農林水産省が公表している畜産統計調査令和5年2月時点のうち採卵鶏農家は約1690戸といわれますので、全体の約7%の声となります。
まず基礎資料から紹介されています。
採卵家の常時従事者数は5名未満が多い順に全体の38%、次いで20名以上32%、14名以下13%と続きます。
これは、採卵鶏の生産状況と比例できます。
現在採卵鶏農家の8割は10万羽以上の鶏を飼養しています。
その8割のうち50万羽以上飼養している農家は33%となり、10万羽農家の約4割は50万羽以上と更なる大規模農家と見ることができます。
これは実感として感じると思います。
皆さんの農場は10万羽程度でしょうか、近隣はもっと大きい飼養羽数ではないでしょうか。
効率化を進めた結果、10万羽の農場より30万羽、50万羽、70万羽という規模が一般的なのではないかと思います。
大規模化されており効率化が進んでいますが、羽数が多くなるほど一定数の人員確保は必須になります。
よく言われますが、10万羽飼養について作業員1名、集卵作業に1名が最低必要になります。
このため交代人員を含めれば最低4名以上いないと人員不足になり作業が過密化します。
このため50万羽飼養であれば作業員最低5名以上で交代要員含めて10名以上で堆肥処理担当を含める、集卵作業員4名以上交代要員含め8名程度は必要になります。
ですが、これでは作業の過密化は避けられず欠員が生じると農場運営に不自由さが見られもう少し多くなり、不足分を外国人技能実習生といった外国人材に頼ることが多いと感じます。
これを知ると、常時従事者数38%と最多の5名以下の場合、傾向とすれば飼養羽数10万羽未満と30万羽程度の中規模農場のデータ、20名以上となる32%では50万羽かそれ以上の大規模農場のデータとして研究することができるでしょう。
それでは、大規模農場と中規模農場の人材教育はどのように取り組んでいるのかという視点で見ていきます。
多い順に
作業現場に精通し、管理監督ができる人材が68%、現場作業の遂行能力を持つ人材が52%、経営判断を担える中核人材31%と何らかの教育をしていると答えます。
反面、人材育成の取り組みなしが11%、専門的資格などを持つ人材は0%となります。
設問では、採卵鶏を含めた常時従事者が多い(今回は20名以上)企業ほど、作業現場に精通し、管理監督ができる人材が83%、現場作業の遂行能力を持つ人材が59%と管理監督を含めて作業できる人材を育てているということになります。
これも一般的なことですが、多くの農場は現場遂行力をまず育てていると思います。
作業ができなければ農場運営に支障が出ますから当たり前の物です。
これが遂行能力を持つ59%の人材育成の話になります。
採卵鶏の場合、成鶏業務と育雛・育成業務では作業するポイントは違います。
これ以外にも堆肥処理のための人材が規模が大きくなるほどその施設や管理をする人材が必要になります。
このため、多くの農場は所属される農場で作業ができるよう、基礎的な技能を教えるわけですから、教えるために管理監督できる人材を作る(一般的に経験豊富な人材が登用される傾向が多い)ことになり、これが生産課長や農場長、生産部長とされる監督人材になります。
特に注目する事項になる、
取り組みしているものを挙げてもらうと複数回答で、社内での勉強会実施が全体の52%、社内コミュニケーション充実約44%、業務マニュアル整備活用40%、社外研修会活用23%、高度な役付けと権限の付与22%となります。また意外に少ないのはジョブローテーションが約10%となります。
では取り組みに対し有効であると尋ねると、
ジョブローテーションが75%、より高度な役付け・裁量の付与66%、社内勉強会53%、社外研修52%、昇進基準の明確化50%と続きます。
これをどう見るのかと言うことですが、育成や成鶏といった、総合的に飼養管理を出来る人材を育てることが農場(企業)にとって有益と考えているということがわかります。
その通りで、今の時代成鶏のみの飼養管理をする農場は規模が大きくなるほど少なく、幼雛から成鶏までの一貫生産が一般的です。
これは、コスト削減の要素もありますが、自社の高度化した衛生管理を徹底していますので、得体のしれない衛生管理が不明な農場から買い付けることによるリスクを低減しているとも言われます。
ですから、成鶏だけ知っていては、将来育雛・育成の管理が十分できないという不安があるわけです。だからローテーションしてまんべんなく作業を教えるのでしょう。
その次の
役付けと裁量付与ですが、これも教えることや農場を任せるということから与えるもので今の採卵鶏では一般的です。
経営者の多くは全ての農場を見ていることは不可能です。
点在した農場、社外との折衝、経営といった様々な課題に取り組むため目になる人材を農場に置くわけです。
そのために責任者と区分わけをしてその者に役職を与え・権限を付与するわけです。
そして、社内勉強会を開き、課題を検討させて共通認識を図り農場へフィードバックしていき農場が更に発展していく仕組みを作ります。
そして社外研修を取り入れて違う視点から課題を検討させて認識して大きく発展させます。
さて、これを見るとよく考えているな、その通りだ、養鶏家の励みになるといった見方もできるでしょう。
でもここでは、経営者の本音が透けて見えます。
それは、取り組みしているものという設問の実施物です。
さきほど、取り組みをしているものを複数回答で示した、社内での勉強会実施が全体の52%、社内コミュニケーション充実約44%、業務マニュアル整備活用40%、社外研修会活用23%、高度な役付け最良の付与22%のところです。
これを見ると、ずばりお金をかけない取り組みということです。
お金をケチることが悪いということではありません。
効果よりは身近な物だけで人は育つと考えているということです。
この発想は、昭和から平成中期の時代までは有効でした。
人が潤沢にいてその中から数名が大きく育つことができる時代でした。
それをバックアップできる人材が農場にいて、とても良い農場人材サイクルが回っていた時代の考え方です。
でも今の時代、人にものを教えるほどの人材が抜けていき、以前であれば作業についてくることができない人材が残り ものを教えて行くことになり、改善していたことや出来ていたことができなくなり、人を多く補充して回し、それでも厳しいので更に人を補充し派遣労働者といった、期間従事者も確保して農場を回すようになった農場もあり、お金をかけない取り組みを何も疑いなく進めた結果、農場そのものが劣化したというところも散見します。
その程度になると、社内で勉強会やコミュニケーションから新たな知見は生まれにくいと感じます。
いくつかそんな困難に至った農場の勉強会やコミュニケーション会議に参加したことがありますが、まあ残念な内容と言えるものでした。
何が問題なのか論点がなく、問題解決の道筋が立てられず、皆の前で話すことが仕事になっているというところも多く、そこから知見が生まれるとは言えないのが実情と感じます。
でも役職者選びには熱心で、以前とは明らかに劣化した状況の理由に、教え手(役職者)の力量が不足しているにもかかわらず、教えるから役職や権限を与えてしまい、新たな知見が生まれないどころか、作業員と同じ作業を高時給で一緒に働くという始末に至り、問題を認識できず繰り返し何らかの課題にぶつかりその場をやり過ごすという感じの農場もあります。
社外研修会に参加するといっても採卵鶏に関した研修は一般的には存在せず、唯一種鶏メーカーの養鶏スクール程度ではないでしょうか。
それも初歩的な物ですから、農場に準じた現場目線の物ではありません。
特に技能に関する研修はまず存在しません。
農場により作業が異なるから等理由はあるでしょうが、現実は教えることができる人材や組織が存在していないと言えます。
弊所が設立した目的はここにあり、技能を失った農場では、鶏を見て育てることはできなくなり、行き当たりばったりの管理で、運が良ければ生産も良く、そうでない場合はそれなりにの生産になり、相場で経営が大きく左右されて、力尽きてしまうという農場を1つでもなくそう。
そういう理由もあり設立しています。
養鶏はコストを削減しているだけでは繁栄できない産業といえます。
鶏を見て感じて改善することで、鶏が持つ最高のパフォーマンスを引き出すことが養鶏の真の生業ではないかと感じます。
しかし現実は、社外研修の費用から見ても割高かつ身にならないと感じてしまい、社外研修のメリットとなる部外者目線での農場課題がわからず、何もしない、できないになり鶏の性能に依存した飼養管理になります。
ですから、運が良ければ高産卵が期待できるロット、残念なロットと運しだいの農場生産となり高卵価であれば問題にはなりませんが、相場安になると収益に直結するため神経質になるぐらい問題視します。
だから、効果があると感じた取り組みを尋ねると、ジョブローテーションが75%、より高度な役付け・裁量の付与66%、社内勉強会53%、社外研修52%、昇進基準の明確化50%となるのでしょう。
ジョブローテーションは先ほど説明しました。成鶏だけではそれ以外の部門生産に影響を与えます。
役付け・裁量権付与についても十分な教え手、管理者としての能力があればとても良いものです。
社内勉強会も組織そのものが相応な力量があれば後輩への知識経験を伝えるとても良い制度です。
社外勉強会も、第三者視点の課題を検討させて農場の力にさせるうえではとても有用です。
そして岡目八目的目線があり現場が気づけない問題や課題を提示して一緒に考えてくれます。
そして、昇進基準の明確化はとても大事なことです。
多くはこれを開示するような農場はまずありません。
これは、昇進の多くは経営者の独断で決めるということが多いからと言えます。
ですが弊害として優秀かどうかまで判断できないということも多くあります。
それは全ての従業員まで把握できず、耳ごごちの良い人材からの情報で決めてしまういわゆる「曇った眼鏡で物を見てしまう」というのが原因です。
その失敗原因のほとんどは、役職を与えた人材の選定を間違えていることが要因です。
本当の大規模農場になると、経営者以外に事業部長といった経営一族ではない優れたブレーンがいるはずです。
その人の基準で決めるというと事もあり、優秀な従事者を拾い上げるようなこともでき、偏った目線で決めて後々まで苦労する残念な農場とは異なる企業もまた存在します。
このためにも昇進基準は明確化し開示していることがとても大事なのです。
では、人材育成に取り組む上での悩みを聞くとまた面白い回答を見ることができます。
採卵鶏では育成を担う社内人材が不足している55%、時間の余裕がない47%、社内ノウハウが不足27%と今お話ししたようなものが回答として表れています。
つまり今の時代、人はそれなりにいるのですが、令和になりいわゆる人を育てるような人材が会社から去り、本来伸びるはずであった人材がそれなりで成長が止まり、仕方なく役職を与え、やる気(能力を引き出してほしいという願望)を上げるために賃金を多く支払い何とかお金で解決したいという苦労している図が見えます。
また人により能力差が大きいことから、仕事ができる人(ノウハウを多く持つ者)が退職しそれが伝承されないことで、今までできたこともできなくなり、1人で作業できるものも2名以上必要とした無駄作業が増えていき昔と違うと感じる農場も多くあります。
これは大規模農場だけではなく、中堅規模も同じと感じます。
育成する人材をぞんざいに扱った、ノウハウを持つものを大切に扱わなかった、代わりはいくらでもいると信じていた慢心という、人が潤沢であった時代の弊害、権限を与えた者の能力まで比較できないという選択ミスも加わり農場の劣化が進んだところもあります。
これを立て直すのも大変なことではあります。
だからこそ弊所の設立理由もあるのですが、よくお話ししますが「農場から失ったノウハウは二度と戻らない」と言います。
これは、まさに人材育成の悩みという答えそのものです。
教え手がいなければ何も教えることはできません。
できるのは妄想から生まれた技法の普及、無駄とわからない思い付きの技法、そもそも鶏を知らないことからの経済的損失という弊害だけになり、
昔できていたことが今はもうできないという状態になるのです。
日本政策公庫の調査は現場の問題に対し今という姿を現す調査としてとても良いものです。
では、農場である皆さんはこの調査から見て「養鶏の鏡である・参考になる・いやたいしたものだ」そんな程度で見ていては少し残念なことです。
回答したその先には皆さんも感じるでしょう、本音が透けて見えているのではないでしょうか。
では、みんなと同じで安心したではなく、その本音が同じならうちは何をしていこうかという違う気づきがあっても良いのではないでしょうか。
これから先、人はそれなりに確保はできるでしょう。
でも本当の人材は、農場を盛り上げてくれる技術を持ち、人を育て、そして経営者の子や孫まで教えることができる先生のような存在の農場ではないでしょうか。
そんなことで時間を割けない、お金がない、そもそも人は何もしなくても育つという昭和の論理ではこの先も心配です。
是非、公庫の調査を皆さん見て感じて、うちはどうなのかという視点で新しい問題を発見してください。
その課題の答えは必ず農場にあります。
それを見つけて対処して農場を今以上に大きく育てていきましょう。
きっと参考になるヒントがあるはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
