
ファンなヤツになる方法
【1993年に新潟日報でスタートした連載を原文のまま掲載】
"Funny"という言葉を研究社の英和辞典で調べると、おもしろい、おかしな、滑稽な、とある。語源はいうまでもなく”Fun”だ。戯れ、とかおもしろみ、などと訳されている。
ニュアンスとしては、おもしろ楽しい、という感じだと思う。語感もふぁんふぁんという、なんとなく弾んだ感じがする。日本語には少し訳しにくい言葉だという気がする。
ハワイの書店で”How to be funny”という古いペーパーバックを見つけた。日本語に訳すとすれば、「おかしなヤツになる方法」だ。「あなたがファニーかどうかのテスト」「学校でファニーになるには」「ディナーのテーブルでファニーになるには」「ジョークの言い方」というような章があって、結構笑えた。例えば、「足が四本あって2つのグローブをしているのは?」というクイズの答えは二人の遊撃手、だったりする。
全体がジョークだから、マジで読むと腹が立つかもしれない。この本の通り振る舞ったら、確かにファニーにはちがいないけど…。
しかし、それにしても、この本を本気で買い求める人たちがいるんだろうか。
おそらくアメリカじゃいないだろうと思うが、日本だったら分からないな。会社の課長さんなんかが、部下とうまくやりたいのだけれどどうも、とか思って、いわゆるハウツーものの本として買い求めるかもしれない。
子供だったらどうだろう。僕が小学生だったころ、こういう本を見つけていたら、多分、喜んで読んでいたと思う。なにしろそのころの僕は思い付いたダジャレをメモ帳に書き留めておいたりするヤツだったのだ。ほかにもノートにコマ割りしたギャグ漫画を書いて級友に見せたり、紙芝居を披露したりしていた。人を笑わせる事が好きだったのだろう。
しかし、今考えると、僕自身パフォーマンスはどうも苦手だったようだ。書く、という行為を通さないとダメなのだ。メディアが介在しないとどうも力を発揮できない。書き留めたダジャレだって一度もタイミングよく口から出たことはない。
だれにでも覚えがあると思う。クラスにひとりかふたりは必ず、ひょうきんで、人を笑わせ、注目を集める男の子がいたものだ。自然に、何の疑いもなく振る舞って、それがおかしい、極端にいえば存在自体がおかしい、つまりナチュラルにファンなヤツ、である。
僕はそういう人間にあこがれていたのかもしれない。そして、一応努力したが、なれなかった。自分で奇抜だと思うことをやったって、それはただ奇抜な行為でしかない。やはり、ファンは頭で考えるものではないのだ。例えば林家三平、あるいは長嶋茂雄といったような人間になろうと思ってもなれるものではない。彼らを解説しようなんて事も無理だ。
もともと日本では、ナンセンスとかギャグといったものが日常に溶け入っていない気が僕にはする。いまだにそれは芸だと思っている人が多いみたいだ。奇抜なものを含んだ日常は楽しい、というふうにはならず、ファンと日常は分離したままだ。ファンという抽象を日本語に訳しづらいのも仕方ないことなのだろうか。
それでもファンとは何かときかれたら、僕はこう答えるしかない。「僕の大好きなもの」
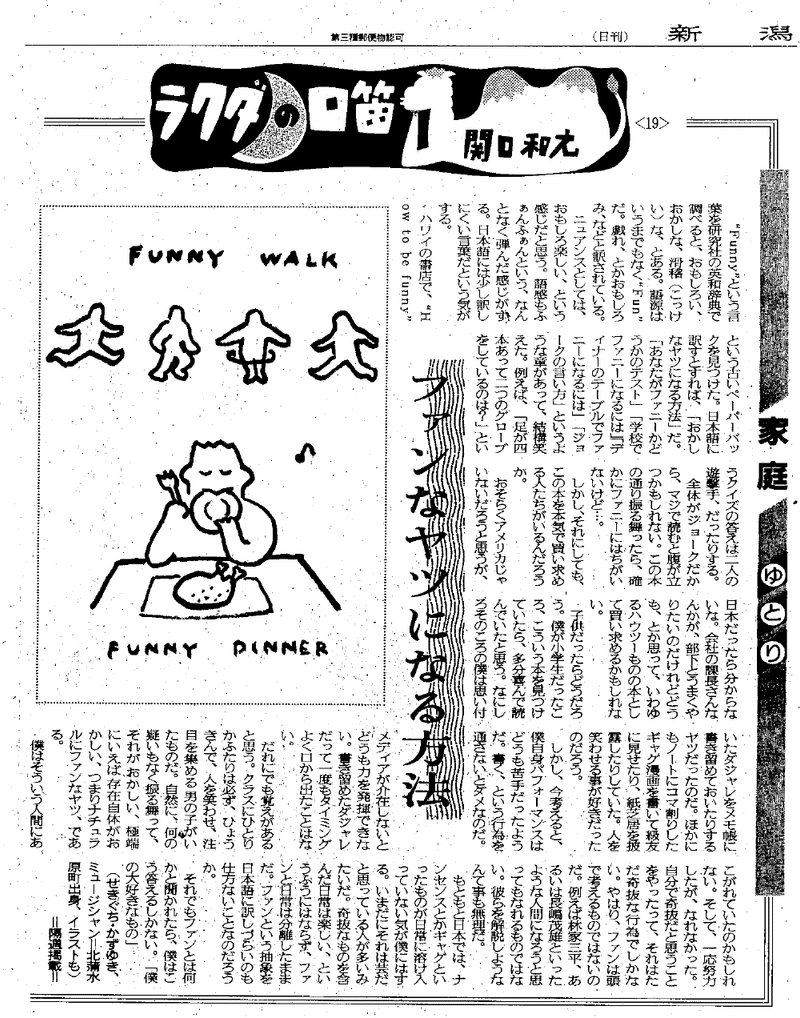
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
