
【AI初心者向け】なぜ今AIに触れる必要があるの?
ChatGPTの登場から1年半、AIは私たちの日常へ!
2022年のChatGPT登場は、まさに世界を揺るがす大事件でした。まるでSF映画の世界から飛び出してきたような、高度なAIとの会話に、多くの人が衝撃を受けたのをあなたは覚えているでしょうか?
それから約1年半。AIは、私たちの生活や仕事に、どれほどの影響を与えているのでしょうか。
「AIが人間の仕事を奪う…?」
「AIに支配される未来が来る…?」
そんな不安の声も聞こえる一方で、
「AIってなんか面白そう!」
「AIを使って、もっと便利な暮らしがしたい!」
と、未来への期待感を持っている人もいるかもしれませんね。
そこでこの記事では、AI素人でもわかるように、
AIによって私たちの生活や仕事がどう変わるのか、そして、
私たちがAI時代を生き抜くために何をすべきなのか、
具体的な例を交えながら分かりやすく解説していきます。

Part 1: ChatGPT登場から、日本はどう変わった?
ChatGPTの登場は、AIが一気に身近になった象徴的な出来事でした。
テレビやインターネットでは連日AIの話題が取り上げられ、今までAIに興味のなかった人も、「なんか面白そう!」と感じるようになってきたかもしれません。
例えば日常ではこんな光景を見かける機会が増えたのではないでしょうか?
ECサイトで買い物をしようとすると、AIがおすすめ商品を教えてくれる。
企業のホームページで質問を入力すると、AIチャットボットがすぐに回答してくれる。
ニュースコラムにもAIという単語がよく入るようになった
そう、ChatGPT以外にも、AIは既に、私たちの日常生活の様々な場面に進出しているのです。
特に日本では、下記のような変化が見られます。
AIへの関心の高まり: ChatGPTの登場をきっかけに、AIを使ったサービスを試す人が日々増えています。 画像生成AIで遊んだり、AIチャットボットと会話したり、今までにないエンタメを楽しむ人が増えています。
AIの浸透: カスタマーサービス、小売、金融、医療など、様々な分野でAIの導入が進んでいます。 例えば、銀行ではAIが融資審査をしたり、病院ではAIが画像診断をサポートしたりするなど、AIは既に「なくてはならない存在」になりつつあります。※参照 https://hgpi.org/en/research/hc-survey-2023.html
国のAI戦略: 日本政府は「AI戦略2022」を策定し、AI人材の育成や、企業がAIを導入しやすい環境づくりなどを進めています。 また、地方自治体レベルでも、AIを活用した地域活性化の取り組みなどが行われています。※参照 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/aistrategy2022_gaiyo.pdf
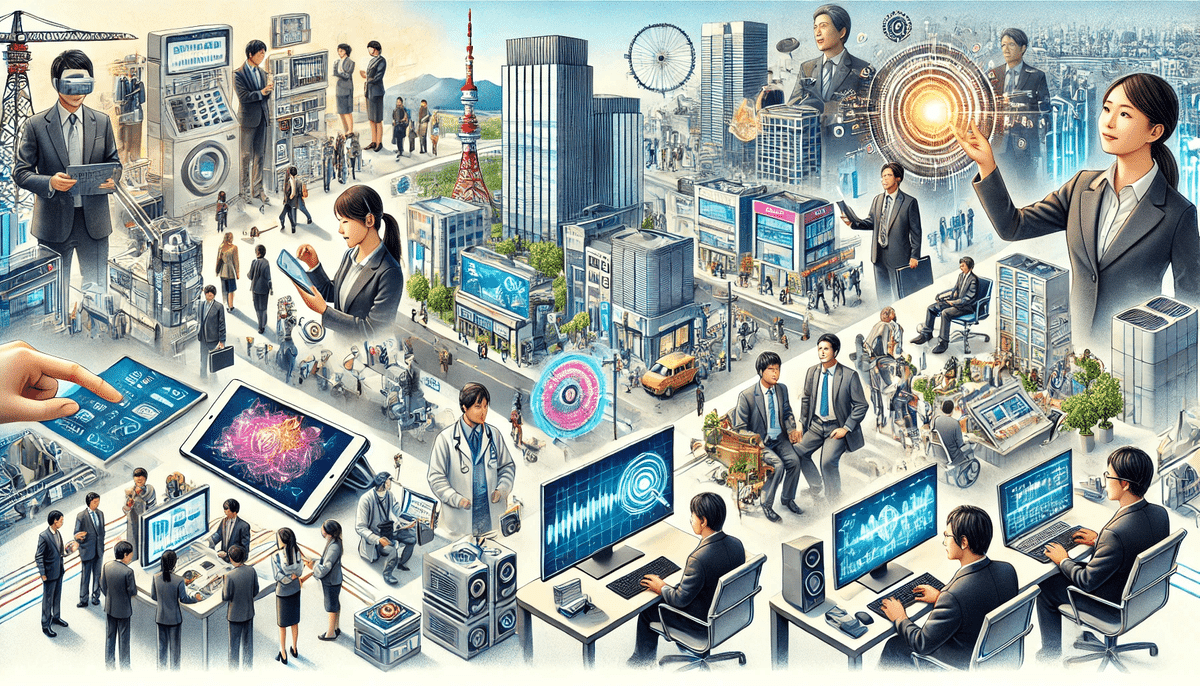
Part 2: AIを「使う側」と「使わない側」で、これからどんな差がつく?
とはいっても、「正直、自分には関係ないかな…」
なんて思っていませんか?
そんな方はちょっと待ってください!
AIを積極的に活用する人と、そうでない人の間には、今後様々な面で大きな差が出てくる可能性があります。
具体的には…?
1. スキル&キャリア:AIを使いこなせる人が圧倒的に有利に
AIを使いこなすスキルは、もはや専門家だけのものではありません。 WordやExcelのように、誰もが当たり前のようにAIツールを使いこなす時代がやってきます。
AIを使いこなすスキルは、これからの時代の「読み書きそろばん」:就職活動でも、AI関連の知識やスキルがあれば、企業にとって非常に魅力的な人材として評価されるでしょう。
AIが人間の仕事をサポート:AIは、単純作業を自動化するだけでなく、データ分析や文章作成など、より高度な業務もサポートしてくれるようになります。AIを使いこなせる人は、AIに任せられる仕事はAIに任せ、人間にしかできない、より創造的な仕事に集中することができます。
新しい仕事が生まれる一方で、AIに代替される仕事も:AIの開発や運用、AIを使ったサービスなど、AIによって新しい仕事が次々と生まれています。一方で、AIに代替される仕事も出てきます。重要なのは、時代の変化をいち早く察知し、新しいスキルを身につける柔軟性です。
AIを使いこなせない人は取り残される:AIを使いこなせない人は、新しいスキルを身につける機会を逃し、キャリアアップの道が閉ざされてしまうかもしれません。
2. 情報収集&学習:AIを使いこなせば、効率的かつパーソナルな学びが可能に
AIは、膨大なデータの中から、あなたの興味やニーズに合わせた情報を提供してくれます。
AIがパーソナライズされた情報を提供:AIを活用すれば、効率的に情報収集したり、自分に最適な学習方法を見つけたりすることができます。
深い理解と批判的思考力が重要に:AIが出す情報が必ずしも正しいとは限りません。情報を見極める「批判的思考力」や、自分で深く考える力がますます重要になります。AIが出してきた情報を鵜呑みにするのではなく、「本当にそうなのか?」と、常に疑問を持つことが大切になっていきます。
AIを使いこなせない人は、情報の波にのまれてしまう:AIを使いこなせない人は、自分に必要な情報を取捨選択できず、情報の波にのまれてしまうかもしれません。
3. ライフスタイル&エンタメ:AIを使いこなせば、生活はより便利に、エンタメはより豊かに
AI搭載の家電やサービスが普及することで、私たちの生活はより便利で快適になります。
AIが日々の生活を豊かに:AIを活用する人は、最新のテクノロジーをいち早く享受し、より豊かなライフスタイルを送ることができるでしょう。
エンタメの選択肢がさらに広がる:AIによって、音楽、映画、ゲームなどのエンタメコンテンツは、ますます進化していきます。AIを活用すれば、自分だけのオリジナルコンテンツを楽しむことも夢ではありません。
AIを使いこなせない人は、便利な生活や新しいエンタメを体験できない:AIを使いこなせない人は、AIがもたらす便利な生活や新しいエンタメを体験する機会を逃してしまうかもしれません。
AIは、私たち人類にとって大きな可能性を秘めています。
それを使いこなし、その恩恵を最大限に享受できる人と、そうでない人の間には、今後ますます大きな差が生まれていくでしょう。 あなたは、どちらの未来を選びますか?

Part 3: AIによって私たちの未来はどうなる? 5つの分野で起こる変化
さてまだまだ発展の続くAIですが、それらはまるで蒸気機関やインターネットのように、社会全体を大きく変えていく可能性を秘めています。
特に大きな変化が起こりそうな分野を5つ、具体的な例を挙げながらわかりやすく説明します。
1.仕事のあり方:
変化: 単純作業やデータ入力など、ルーティンワークはAIやロボットが代替するようになり、人間の仕事はより高度で創造的なものへと変化していきます。
具体例:
事務職:書類作成やデータ入力などの業務はAIが自動化し、人間は顧客対応や企画立案など、より高度な業務に集中できるようになります。
製造業:工場ではロボットが製品の組み立てや検査を行うようになり、人間はロボットの管理や工程改善など、より高度な業務に携わるようになります。
医療現場:AIが画像診断や検査データの分析をサポートすることで、医師は患者とのコミュニケーションや治療方針の決定など、より人間的な業務に集中できるようになります。
2.医療:
変化: AIによる病気の早期発見、診断の精度向上、治療法の開発などが進み、より効果的で個別化された医療が実現します。
具体例:
がん治療:AIが患者の遺伝情報や検査データに基づいて、最適な治療法を提案してくれるようになります。
創薬:AIが膨大な量の化合物データの中から、新薬候補となる物質を効率的に探し出すことで、新薬開発が加速します。
ヘルスケアアプリ:AIが個人の健康状態や生活習慣を分析し、パーソナライズされた健康アドバイスを提供してくれるようになります。
3.教育:
変化: 生徒一人ひとりのレベルや学習進度に合わせた個別指導が可能になり、より効果的で効率的な学習が実現します。
具体例:
個別学習システム:AIが生徒の学習状況を分析し、苦手分野を克服するための最適な学習プランを作成してくれます。
オンライン教育:AI tutor が、生徒一人ひとりのペースに合わせて、丁寧に指導してくれるようになります。
教育現場の負担軽減:AIが採点や成績処理などの事務作業を自動化することで、教師は生徒と向き合う時間に集中できるようになります。
4エンタメ:
変化: AIによって、よりリアルで没入感のあるエンターテイメント体験が可能になります。また、個人の好みに合わせたコンテンツが提供されるようになります。
具体例:
ゲーム:AIがプレイヤーの行動を学習し、より手ごたえのあるゲーム体験を提供してくれるようになります。
映画/ドラマ:AIが個人の視聴履歴に基づいて、おすすめの作品を紹介してくれるようになります。
音楽:AIが個人の音楽の好みを分析し、オリジナルの楽曲を自動生成してくれるようになります。
5.社会問題の解決:
変化: AIを活用することで、環境問題、貧困問題、犯罪問題など、様々な社会問題の解決に貢献できます。
具体例:
環境問題:AIが都市の交通渋滞を緩和したり、工場のエネルギー消費を最適化したりすることで、CO2排出量削減に貢献します。
貧困問題:AIが貧困地域の経済状況を分析し、効果的な支援策を提案してくれるようになります。
犯罪問題:AIが防犯カメラの映像を解析し、犯罪の発生を予測したり、犯人を特定したりすることで、犯罪の抑止に貢献します。

Part 4: 私たちは何をすればいいの?AI時代に生き残るための4つの戦略
さてここまでAIのこれからについて見ていきましたが、AIは一過性のものではなく、確実に生活に入ってくるものです。
避けては通れないからこそ、AI時代を生き抜くためには、うまく付き合っていく方法を学び、自分自身の可能性を広げていくことが重要です。
まだまったく触ったことがない!あんまり知らない!という人は
具体的には、以下の4つのポイントを意識してみましょう!
1 好奇心と学習意欲を持つ:
AIについて「怖い」「難しそう」と決めつけずに、まずは「面白そう!」という気持ちで情報に触れてみましょう。
オンライン学習サービスやセミナーなど、AIについて学べる機会はたくさんあります。無料のものも多いので、気軽に試してみてください。
ChatGPTなどのAIサービスを実際に使ってみて、AIの可能性を肌で感じてみましょう。
2 AIを「使う側」になる:
日常生活に取り入れてみる: スマートスピーカー、翻訳アプリ、ナビゲーションアプリなど、AIを使ったサービスはたくさんあります。まずは、自分が「便利そう!」と思ったものから使ってみましょう。
仕事で活用してみる: 業務効率化アプリ、データ分析ツール、プレゼンテーション資料作成ツールなど、AIを活用できるツールはたくさんあります。積極的に活用することで、仕事の質と効率を飛躍的に向上させることができるでしょう。
自分だけの使い方を見つける: AIは使い方次第で、可能性は無限に広がります!
3 人間らしさを磨く:
創造性を活かす: AIにはない、人間独自の創造力や発想力を活かせる分野に目を向けましょう。 アート、デザイン、音楽、文芸など、AI時代においても、人間の感性が求められる分野はたくさんあります。
コミュニケーション能力を高める: AI時代においても、人と人とのコミュニケーション能力はますます重要になります。 相手の気持ちを理解する力、自分の気持ちを伝える力、チームで協力して仕事を進める力などを磨きましょう。
4 変化を恐れずに、柔軟に対応する:
新しい働き方を受け入れる: リモートワーク、フリーランス、副業など、AI時代には働き方も多様化していくでしょう。 従来の働き方に固執せず、新しい働き方を受け入れる柔軟性が求められます。
スキルアップを続ける: AI技術の進化は非常に速いため、常に新しい情報を学び続けることが大切です。 オンライン学習サービスや書籍などを活用して、常にスキルアップを心がけましょう。
変化を楽しむ気持ちを持つ: AIによって社会は大きく変化していきますが、それをネガティブに捉えるのではなく、「変化を楽しめる」柔軟な思考を持ちましょう。
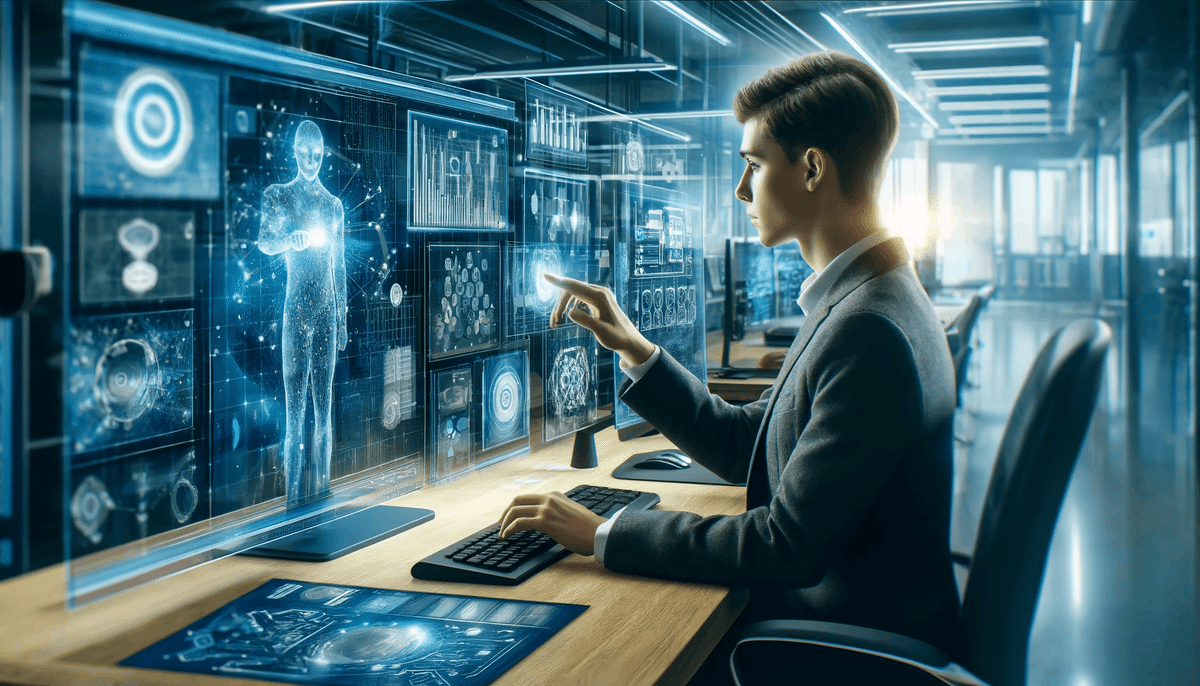
まとめ|AIは、私たちを脅かすものではなく、より良い未来を創造するための強力なツールです。
いかがでしたか?
今回はAI初心者向けの記事を書いてみました。
気づいた方もいるかもしれませんが、実はここまでの記事5000文字あるのですが、大半をAIによる執筆をベースとしています。
かかった時間は手直しや修正含めて1時間くらい。
これからはこんな風に記事を書いていく時代になっていきます。
AIが書く記事ってウソなんじゃないの?
って疑う人もいるかもしれません。しかし、それは1年前の出来事で、日々進化しています。
もちろん完璧ではありませんが、そういったミスを防ぐためにいくつか思考錯誤すれば、嘘というのもある程度防ぐことができます。
こんなに簡単な事はありません。こんな世の中になっていくんです。
だからこそ、今触っておくと、差をつけることができます。
ぜひちょっとずつ試していきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
