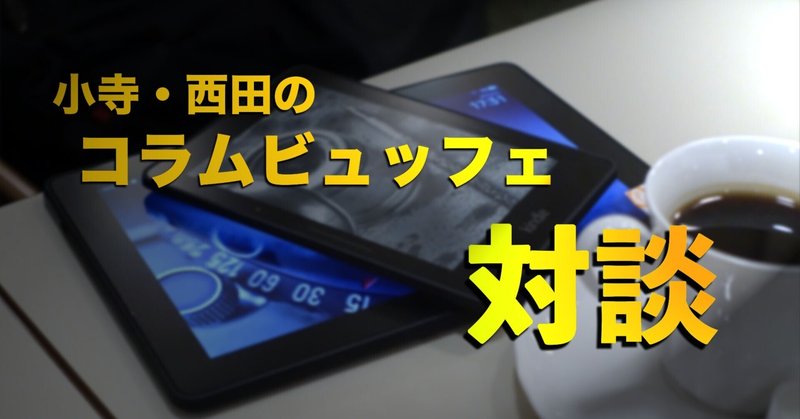
GLOCOM豊福先生に聴く、「どうなる? AIと教育」(4)
毎月専門家のゲストをお招きして、旬なネタ、トレンドのお話を伺います。
今回の対談は、国際大学 グローバル・コミュニケーション・センター准教授・主幹研究員の豊福晋平先生にお願いしている。
GIGAスクール構想によって、学校にネットとPCが潤沢に入ってきた。当然校務のIT化もスムーズになるはずだが、実際には成績表管理など一部がIT化されただけで、授業がアナログなために、先生が二重負担になっている。
先生の負担の多さは、AIによって解決できる見込みがあるのだろうか。
(全5回予定)
小寺:先ほどのファクトチェックっていうところで、今僕がやってる方法があって。先生、ChatALLっていうアプリってご存じですかね。
豊福:あ、見たことないです。
小寺:ChatALLっていう一種のフロントエンドがあって、そこに対話型のAIを何種類か選んでプリセットしておくと、質問を1個投げるだけで、複数のAIに同時に質問が投げられて、同時に回答が返ってくるんですよ。で、今、僕、BingとBardと、それからChatGPTを3つ並べて、同じ質問を入れて、どういう差が出てくるのかでファクトチェックしてるんですけど。
豊福:面白いですね。
小寺: 1種類のAIに頼るのって非常に危険だと思ってるんですよね。みんなChatGPTにすごく注目してるけど、そうじゃなくて、複数のAIを走らせて、横並びで差を見ていかないと。そのズレの中で、「学習のネタが違いますよ」「参照元が違うと結果がこうなりますよ」みたいなところがわかっていくっていう、そういう視点がすごく大事のような気がするんです。
豊福:おっしゃる通りです。僕、今使ってて一番使い出があるなと思ったのはBingのAIかな。Bingはちゃんと参照元を教えてくれる。
で、Bardはすぐに投げ出す。「わかりません」っ。お前、いい加減にしろよと(笑)。そういうのを見てると、ふんふんって思って、楽しいですよね。
小寺:楽しいですね。これまで僕は散々Google検索とかを使って文章とかの参考資料を探したりしてきたんですけど、検索では探しづらいタイプの情報があるんですよ。この用語が最初に出てきたのは何年頃ですか、みたいな、「初出を探す」のは検索しづらいんですよね。
豊福:難しいですね。
小寺:でも、AIに投げるとわりとその辺を簡単に出してくれるので、そういう使い方は便利だなと思ってるところなんですけど。
豊福:背景も含めて拾ってくれると、「ああ、これがこういうふうに繋がったのか」っていうのが見えてくるんですよね。
小寺:うん。あと、ネットで主張してる――ちゃんとしたメーカーなのに、「これを私たちが世界で最初に発明しました」みたいに説明してるんだけど、本当かな?と思ってAIに「これの発明者は誰ですか?」って質問するとですね、「定かには決まっていません」って3つダダッと出るという(笑)。
豊福:ははは(笑)。
小寺:これそのまま鵜呑みにして記事にするとやべえやつじゃん!みたいなのがわかるとか、そういったファクトチェックにもAIって使えてたりするので、ある意味そういう、その人が主張してることの裏取りにも使えたりもするという。
豊福:これも“ある程度”ですけどね。
小寺:ただやっぱり、疑ってかかるべきところを、本当かな? って逆にAIに調べてもらうという使い方は、1つ情報社会としての成長があるかもしれないなという気がしています。
豊福:おっしゃる通り、おっしゃる通り。
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
