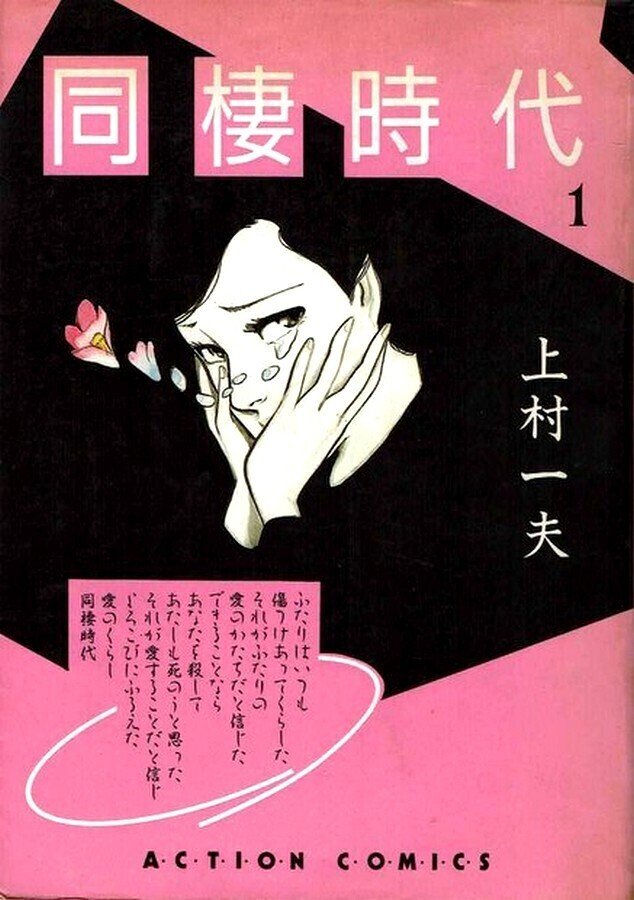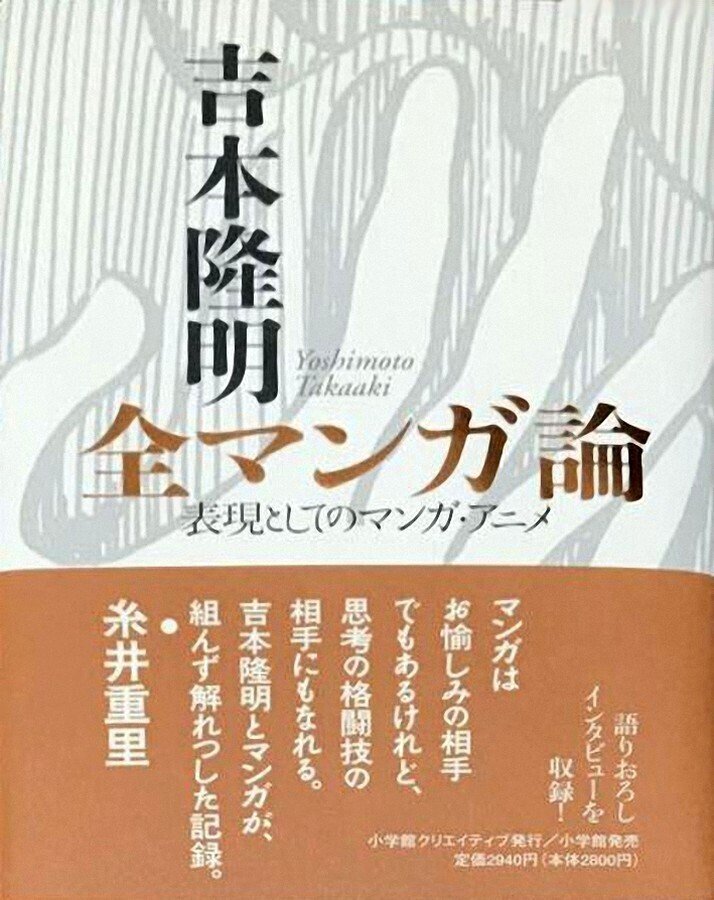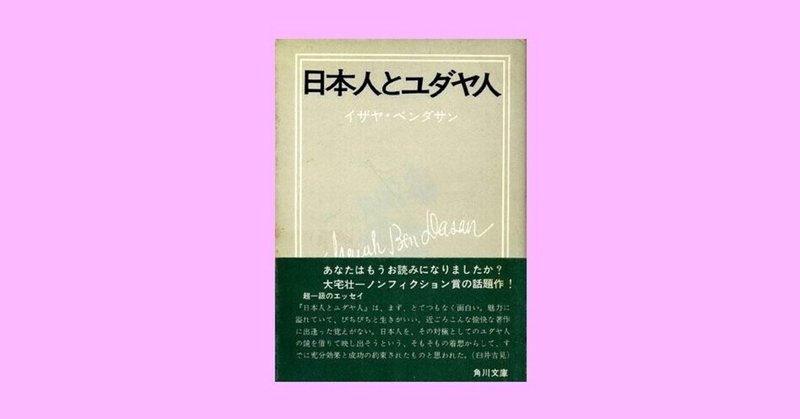
「日本人とユダヤ人」講読
野阿 梓
目次
趣意書 ←(もう少し詳しいこの「講読」の内容)
第一講 ヘルツェル ←(シオニズムの親玉)
第二講 ベンダサン ←(偽書だの何だのと言われた著者の秘密)
第三講 地の民 ←(ベンダサンでも間違うこともあるんだ的な内輪話)
第四講 クロノスの首 ←(プラド美術館で見たゴヤの画を思い出しつつ書いた)
第五講 ギデオン ←(って誰?)
第六講 ゼカリヤ ←(って誰?)
第七講 ミロバン・ジラス ←(って誰?)
第八講 パウロ ←(イエスとキリスト教は無関係。で、キリスト教を創った人)
第九講 ヤムニア会議 ←(旧約聖書を編纂した会議。だけど旧約って何?的な)
第十講 ヒルレル ←(イエスの師らしいが、日本では誰も知らない。誰それ)
第十一講 モーセ ←(紅海真っ二つの人。でも、フロイト晩年の妄想がスゴイ)
第十二講 ロープシン ←(昔の五木寛之△ー。でもって元ネタはもっと△ー)
第十三講 ニケーア会議 ←(キリスト教がキリスト教になった大昔の会議らしい)
第十四講 ディプロストーン ←(いまだに謎な言葉で誰に聞いても判らん)
第十五講 ハジ・アミン・アル・フセイニ ←(アラブの偉い人だったがテロの親玉)
第十六講 ソロバン ←(誰も知らないけど私の父親って算盤の名手だった話)
第十七講 ダビデとヨナタン ←(今ならBLだけど。しかしそもそもダビデって誰?)
第十八講 ハムレット ←(ハムレットって、こんなお芝居だったんだぁっ!?的な)趣意書(2)
5
日本人特有の健忘症について、一つだけ事例を挙げます。直に政治的な出来事は、いたずらに無用な論争をまねきかねませんので、ポピュラーソングにしましょう。
(ちょっと脱線しますが、面倒だと思う方は、飛ばして先に進んでも結構です)
ユーミンの名曲(歌はバンバン)に「『いちご白書』をもう一度」(※3)があります。あの曲の元になったのは六八年に実際に米国ニューヨーク市はコロンビア大学であった学園紛争で、その映画化が七〇年公開の「いちご白書」なのです。
※3 https://www.youtube.com/watch?v=jMnSqIAhuWo
残念ながら現在DVD化はされていない。ところで、映画では、なぜか舞台は西海岸、サンフランシスコの大学になっていました(六四年に加州バークレー大学で学生が構内で政治活動を行う権利を主張して紛争があったので、制作者の意図としては、それと関連づけ、リスペクトしたのかも知れません)が、骨子は同じです。
ユーミンの曲は今も歌いつがれているナンバーでも、しかし、映画のタイトルとしては聞いたことのない人が多いでしょう。この映画じたい、あまり封切り当時から有名ではなかったからです。地方によっては、曲のヒットによって再上映されたほどですが、それでも知る人ぞ知る作品でした。原作となった、紛争の当事者である元学生ジェームズ・クネンが書いた同題のノンフィクションが角川文庫から出ていたことすら、記憶している人は少ないでしょう。
そもそも、原作まで遡ってもタイトルの意味さえ、今となっては理解不能です。
これは、六八年当時のコロンビア大の学長の発言が由来とされています。私がその頃、読んだ記事では、「学生は赤(=共産主義)がかったことを口にしても、中味は真っ白(=体制よりのスタンス)だ」といった揶揄の言葉だった。というものでした。しかし、ウィキペディアの「いちご白書」での学長の説明は違います(ここは英語版でも同じ内容ですから正しいのだ、とは思われます)。
後に八八年に学長が語ったところによれば、「大学の政策に関して、学生の意見は尊重するが、合理的な説明がない場合は、学生の多くがイチゴが好きだ、というのと同じで自分には意味がない」という意味だったのだ。とのことですが、これは二〇年後に聞いても、なにが何だか、まるで意味が通じません。まだ私が読んだ説明の方が筋が通る気がしますが、それほど曖昧なものになってしまっている、と言えるでしょう。
一つだけ確かなのは学長が学生たちを侮っていたことです。連中はシュプレヒコールは上げても大した抗議活動などは出来ないだろうと、内心、高をくくっていたのです。それは、まんざら、根拠がないとはいえず、コロンビア大学はアイヴィ校であり全米でも特に優秀な学生(六割が院生)の集まる世界的にも有名な私立の研究大学でした。いわば超エリート階級の子女の集まりだから、まさか彼らが、ここまで反体制的な示威活動をするとは思っていなかった。そう侮って、学長も、そのような偏見で学生を見ており、つまりは目を曇らせていたのでしょう。こうした侮りと時代の読み違えが、のちに大きな齟齬となり、悲劇的な対立につながっていきました。
実際のコロンビア大学紛争は、大学の拡張政策により、NY黒人地区(ハーレム)の公園を更地にして大学の施設を造る、という横暴な計画に同大学生らが反対の抗議行動を起こしたことに端を発します。公民権運動がピークを迎え、キング牧師が暗殺される前後だったことで、アフリカ系学生が激昂していたことも見逃せない要因でしょう。また紛争の前段としては、大学が国防総省のシンクタンクである国防分析研究所(IDA)と提携して軍事研究を進めていることが暴露され、おりしも激化しつつあったベトナム戦争とあいまって、大学の立場が問われた件で、自分たちの大学が戦争に加担している、それへの反発や抗議が学生側に有りました。
そして、黒人系学生協会(SAS)と白人系が多かった民主社会学生同盟(SDS)が闘争路線で対立し、それぞれ別の施設(ハミルトンホールと記念図書館)を占拠するにいたりますが、どちらもNYPDにより排除されます。特に記念図書館を占拠したSDS側は甚大な被害を出して数百名が逮捕される結果となりました。
コロンビア大でのSDSの指導者だった学生、マーク・ラッドは、この敗北の後、より過激な武装組織、ウェザーマン(この名はボブ・ディランの歌詞にちなむ)を組織し、地下に潜りましたが、逮捕されています。紛争後、コロンビアをはじめとする十二の大学はIDAとの学際協力を終了せざるを得ませんでした。しかしながら、まちがいなく、同年、フランスに発した五月革命の狼火は確実に新大陸を把え、コロンビアを始点として全米に広がっていったのです。その火は欧米、日本と全世界に広がり、スチューデントパワーと呼ばれるようになります。紛争に参加した学生は自らの体験を「いちご白書」というノンフィクションにまとめました。
これを元にフィクショナルな映画の内容は、いたって普通のノンポリ学生だった主人公が、ふとしたことからデモのリーダー格である女子学生に引かれて学園紛争にコミットしていく。そして最後の抗議デモの排除まで、彼女を恋人として支え行動をともにします。ヒロインを始め、俳優も全て学生とほぼ同じ年齢でキャスティングされて、監督もまだ二十代と、同時代性をかもし出している。そういうベトナム戦争のさなか、アメリカで苦悩し反逆する若者に寄りそった、反戦、反体制、そして、なにより瑞々しい青春映画でした。
6
またまた個人的な話ですが(これは私の講読ですので、以下、やたらめったら個人的な話が多くなります。あしからず、ご了承ください)、私は、七〇年に高校へ進学して、すぐ不眠症となり(朝六時に起きなければ登校できないのに、朝六時に就眠する昼夜逆転の生活ゆえ)、入ったばかりの高校を不登校でドロップアウトしかかっていました。いや、当時はまだ「不登校」とか「登校拒否」といった言葉もなかった時代でしたから、私は世間に対して自分を説明できなかったのです。そこで不眠症から不安神経症になり、世間と完全に断絶した生活となりました。それで将来になんの展望もない鬱屈した日々のせいか、昼も夜も徘徊するか、映画を観るか、やることが他になく、この映画は気に入って映画館で三回ほど観ました。だから、割りと細かいシーンまで記憶しています。
「いちご白書」は、米国では、「明日に向かって撃て」や「イージーライダー」などと同じ、アメリカンニューシネマにカテゴライズされている作品です。私は大好きな映画ですが、しかし、主役のブルース・デイヴィソンは、ほとんど大抜擢の新人でしたし、ヒロインのキム・ダービーこそ一五歳からキャリアを重ね、前年には「勇気ある追跡」でジョン・ウェインと競演していますが、演技は巧くてもハリウッド的美人女優さんではなく、全体に地味目な作品です。それでもカンヌ映画祭で審査員賞を受賞したのは五月革命が海を越えた、との判断でしょうか。本国アメリカでの評価はよく判りませんが、少なくともわが国では、おそらくユーミンの曲に引用されなかったなら、今なおスカパーなどでの再放映もなかっただろうと思われます(ごく最近も、「ザ・シネマ」で何度か放映されています)。
ユーミンは私と同い年(五四年生まれ)ですから、いくら彼女が早熟な音楽の天才でも、実際に六八年から七〇年にかけての大学紛争やバリケードなどを実体験した年齢ではありえません。おそらく周囲にいた(であろう)少し年長の全共闘世代の誰かからエピソードを聞いて、あの作詞となったものと思われます。
しかしながら、曲のリリースは七五年です。映画を観た人にとって、「たった五年後」の回想なのです。信じられますか。いくら政治の熱い季節で濃密な時間だったとはいえ、たった五年前の出来事をあれほどノスタルジックに歌い上げるのは、そしてそれで興行的に成功するというのは、希有なことではないでしょうか。
少しイジワルな目線でこの歌詞を注意深く見ると、荒井由実は巧妙に設定をしつらえているのが判ります。
まず、今は(理由は判りませんが)別れてしまった学生時代の恋人の思い出でもあります。青春です。同棲していたかどうかは不明ですが、おそらく男女の仲だったのでしょう。しかし、今はもう切れている関係です。しかもまだ男は結婚はしていないみたいだから、思い出は思い出にとどまり、過去が「家庭」に生ぐさい影を落とすこともありません。
そして、なにより、二人で共感しながら一緒に観た映画から当時を回想する歌詞です。感情移入して涙ぐんでいる恋人の横顔を視ている男の目線があります。薄闇の中で静かに清らかな涙を流している女の横顔は美しく、エロティックです。
ユーミンの抉るエロティシズムは、いつだって核心をつきながらも、非常に表現が婉曲な印象を与えます。生々しい言葉や、泥沼の男女関係などを直接的な描写はけしてしません。
男の恋人の女性の「素直な横顔が今でも恋しい」といささか未練がましい、その男子学生は、しかし、七〇年当時に流行ったスタイル、「無精ヒゲと髪をのばして」いますが、特に決まった政治セクトに属していたわけではなさそうです。「学生集会にも時々出かけた」、とあるので、いわゆるラジカルノンセクトだった、と思われます。今なら「意識高い系」な学生でしょうか。
そして卒業が迫って就職が決まると長髪をカットし、彼女に「もう若くないさ」などと言い訳している。いつでも、どこにでもいる学生像ですが、しかし、ここには語られていない重要な点があります。彼は、そうしたことが可能な程度には、「政治活動に深くは関わっていなかった」のです。
もし、この歌の語り手の男子学生が、闘争に深入りして、どこかの政治政党の青年部や下部組織にいたら、とてもこんな呑気なことは言っていられません。七〇年当時は、すでに革マル派と中核派その他が「内ゲバ」を起こして死者もでていました。そういう現実の殺伐とした生々しい世界からは離れた、つまりは、ごく普通の学生だったわけです。そして恋人とも、「授業を抜け出して二人で出かけた」と言うのですから、おそらく二人は同じ大学に通う学生同士でしょう。しかし将来を約束したわけでもない。そうした、いわばセーフティネットを周到に張り巡らせて、この歌は描かれている。実に巧みだと言うほかありません。
ユーミンのセルフカバー
7
そうはいっても、しかし、今となっては見えにくい、七〇年当時の、学生同士のカップル、ということ自体、希少な存在だったことを見落してはならないでしょう。
今の若い人には想像しにくいと思いますが、当時、大学生というのは、わりとエリート的存在でした。それも特に国立大学の学生だと超の付くエリートです。団塊の世代ですから総数は多いため、受験競争も激しく、また、個人や家庭環境の知的水準と裕福さがなければ、なかなか到達しがたいハードルでした。なにより、当時は、大学進学者の数が今よりずっと少なかったのです。数量より質的に、だから競争はいっそう熾烈だったのです。
文科省の統計資料「e-Stat 学校基本調査」を元にした「社会実情データ図録」の「高校・大学進学率の推移」(※4)を見ると、七〇年度には、高校への進学率こそ八二・一%ですが、大学への進学率(短大を含む)はまだ二三・六%と低かったことが判ります。うち、女子の比率は男子より低く、二〇%を切っていました。若者が百人いて、その内、四分の一以下の割合です。女子だと二十人弱しかいない。
今は(平成三〇年度の統計では)、五四・八二%で、女子が上まわっています。半世紀で、社会状況が大きく変化したことが、この一事をとっても、わかるでしょう。
逆に言えば、総合大学内での女子学生の数が圧倒的少ないから、自然と男子学生と付き合う確率も高くなるわけです。どちらも絶対的総数が少ないので、そういうカップル自体が多くなかった。すなわち、七〇年当時に、二人の男女が学生同士で付き合う、というのは、それだけでもう、少子化の今とは全然、違う環境であり状況だった。そう考えてください。
ちなみに四年制大学への進学率が五〇%を超えたのは、つい最近であり、二〇〇九年のことです。たった十年前の出来事なのです。日本で高校や大学への進学率が高まったのは、高度経済成長により七〇年代半ばを過ぎてからで、それから急速に高くなっています。しかしながら、今から半世紀前の七〇年に、ユーミンがその五年後に歌った内容は、まだまだ稀な「例外的なケース」だったと言えるでしょう。
※4 https://honkawa2.sakura.ne.jp/3927.html
その一つの証左に、これは七〇年に、マイナーではあるが、若者文化の一つであったマンガ雑誌「ガロ」に一年間ほど連載された林静一「赤色エレジー」の主人公たち二人が、両方とも同棲しながら働いているのと対照的です。年齢的に、おそらく高卒で社会に出たのだと思われます。
これもまた、今ではマンガ自体の存在は忘れ去られて、それに触発されたあがた森魚の同名の歌曲の方が有名だと思われますが(あがたの歌は六〇万枚のヒットでした)。とにかく、そこで、アニメータの下請け作業をしながらマンガ家を目指している勤労青年の一郎と、やはりアニメータとして働きながら組合闘争をしつつ、一緒に住んでいる女性、幸子の若い男女二人の「同棲」が描かれます。
この「同棲」という新しい「愛の形」は、さらにこれにインスパイアされ、商業誌で七二年から七三年にかけて、上村一夫「同棲時代」に引き継がれ、ヒットしました。ドラマや映画化され、いっときの徒花とはいえ、社会現象にもなりました。そこでも、しかし、同棲している二人は、それぞれが、やはりイラストレータや広告会社の社員として働いています。学生ではない、労働者であることが、掲載誌の「漫画アクション」では「リアル」だったのかも知れません。七二年には、挫折したアンポ闘争の記憶や、連合赤軍事件で、退潮していった学生運動の傷痕は深く、市民社会の方も一気に醒めて、引いてしまった背景も大きいでしょう。
しかし、なにより、これは、描き手の上村一夫自身が、武蔵美を出てマンガ家になる前に広告代理店でバイトしていた(その間に、生涯の親友となる阿久悠と知り合い、彼の原作による作品なども手がけた)、苦学生だった彼自身の経歴も関係していると思われます。やはり七〇年の時点で、自活していない学生の身で同棲している関係性、というのは、苦労してきた上村にはリアリティがなかったのでしょう。上村自身、戦前の生まれ(四〇年)で、デビューした六八年で二八歳だったので、察するに、上村には、学生運動へのシンパシーがまるでないのです。
前述の林静一は、日本が敗戦を迎える四五年に満州で生まれ、敗戦後の混乱で父と姉を失ない、母親と二人だけで四七年に日本に引き揚げています。後にアニメータとして入社した東映動画では、四一年生まれの宮崎駿と同期でした。まだ戦争の暗い影が色濃く落ちる生活が、マンガ誌のインクから黒くにじみ出るようで、まるで世代がちがうのです。当然、見ている世界も、まったく、ちがう。
七〇年に「赤色エレジー」を発表した時、林は二五歳でしたが、あがた森魚が歌ったように、そこで描かれた「同棲生活」とは、「二人で布団はひとつ」「裸電灯、走馬灯」という困窮生活です。「新しい愛の形」などといったキレイ事では、とてもすまされない。
それでも、「同棲」という生活形態は、学生、労働者の枠を超えて、当時の若者文化としては、既成の価値観や習俗に捕らわれない、という反俗精神に呼応したと思われますし、それゆえ時代の徒花としてでも、花開いたのでしょう。しかし、内実は、貧しさゆえの社会の底辺での男女の結びつき、といった色彩がつよい。二人で暮らしているのに布団は一つしかない。七〇年当時で天井灯に蛍光灯がないのはともかく、裸電球にかぶせるシェードすらない世界です。若ければ貧苦にも耐えられる、とはよく言われますが、貧乏だからこそ、くっつくしかなかった大都会の片隅に生きる、地方出身者である男女二人の生活だった、というのが実態でしょう。
当時、リアルタイムで「ガロ」を読んでいた私は、ラストで二人が別れてから、主人公の一郎が、白黒が逆転した画面で、(明日になれば忘れられる……昨日も、そう、思った……)と内的独白する、あまりの暗さにメゲました。これはもう、精神的に追いつめられ、自殺一歩手前の心理状態です。
幸子は幸子で、彼女の父親は希死念慮があり、それは戦争で死ねなかったことへの贖罪のようでもあり、母親からは田舎での何度もお見合いの勧めを受けて断っている。他方、一郎は、故郷の父親が死んで、夢をあきらめ稼業を継ぐため帰郷するしかない。二人とも、どんづまりで、展望のない未来しかないので、明るくなる材料がないのです。そして、戦争を肌で体験してはいないにせよ、林も上村も、その負の遺産は重く受けついでいて、それが七〇年当時の、若い貧しい労働者の現実でもあったのだろう、と思われます。
8
上に引用した「社会実情データ図録」の別な統計「結婚した男女の出会いのきっかけ」によると、恋愛結婚が見合いを上まわったのが、ようやく六五年から六九年にかけてで、恋愛結婚が過半数を超えたのは、七〇年代以降のことです。
だから、決して誇張ではなく、林静一や上村一夫が属していた世代は、まだまだ古い因習的な日本社会だったと言えます(啓発され歌曲にした、あがた森魚の方は全共闘世代ですが)。上村作詞で、映画の主題歌となった大信田礼子の歌「同棲時代」は、フォークというより、少し暗めのムード歌謡のようでした。
一方、五四年生まれのユーミンは、そうした戦前や戦中派、またその後の「フォーク世代」のジメついた世界から断絶し、一歩先んじて、より明るく、開かれた性と愛の世界、今までとは全く異なる男女の関係性の社会を見据えていました。だからこそ、「赤色エレジー」や「同棲時代」とは懸け離れた、本当に新しく明るい男女の世界を描きえたのでしょう。ニューミュージックとはよくぞ名付けたと思われます(ユーミンは自分がその命名者だと断言しています)。
良家の子女なのに、十代から、かつて六本木野獣会の拠点だったキャンティに出入りし、一四歳で作曲した曲を三年後にプロに楽曲提供するほど早熟な天才で、恐るべき子供(アンファンテリブル)だったユーミンは、上述したような貧しさとも無縁であったし、また天才的才能に恵まれていたので、何にも足を取られることなく、むろん、戦争の影も知らないで、思う存分、その才気を開花させることが可能だったのです。
ともあれ、そんな男女の関係性の中で、「『いちご白書』をもう一度」の歌詞では全てが過去となり、セピアカラーの「思い出」に美化され、ソフトな要素に満ちている。上村一夫なら描いたであろう「妊娠」や「生理」の問題なども、全くスルーされており、二人の過去はただ美しいだけで、よけいな夾雑物はいっさい無い。だからこそ、普遍的な曲でありうるとも言えるのですが、ちょっと出来すぎかな、と思わないでもない。
さらに感心するのは、歌の内容が、一種の「額縁」に入れられていることです。間接話法とでもいうのか――すなわち、過去に観た映画が、今、リバイバル上映されている。それも「雨に破れかけた街角のポスター」とあるので、きっと名画座などで、もう数日は経っているのでしょう。そもそも、公開当時ですらそんなにヒットした映画ではなかったのです。だからこそ、恋人と二人だけの感傷に彩られる。そして、あの遠い日の恋人も、どこか遠い町で、このリバイバル上映を観ているだろうか。こう問いかけることで、個人的な記憶が、聴く人すべてに共有され、広がりを持ちます。もう「思い出感」満載です。過去を直接、思い出すのではなく、その当時に観た学生運動を描いた映画が再上映でまた来る、という枠組みに入れられて、回想にもワンクッション置かれている。しかし、何度も言いますが、これは映画の封切りから、たった五年後の話なのです。
私はまだ鮮明に憶えていますが、映画「いちご白書」は、大学当局が導入した警官隊と州兵によって、学生が次々に逮捕されるシーンで終わります。講堂を占拠し、同心円を描いた大きな人間の輪となって、ジョン・レノンの反戦歌「平和を我らに(Give Peace a Chance)」を歌いつつ、非暴力の座り込みをする学生たちが一方的に蹂躙される、圧倒的な暴力が支配するラストシーンです。
それまでは、どこかのんびりとして、大学紛争を舞台にした青春映画のようだった作品がここにきて急激に一変します。主人公は警棒で殴られ血を流し、隣りにいて抱き合っていた恋人とも引き離されて、警官たちに連れ去られます。そのストップモーションから切り替わってエンドロールにかぶさるようにして、ジョニ・ミッチェルが作詞作曲し、バフィー・セントメリーがカバーした「サークル・ゲーム」が映画全体を締めくくるようにエンディングに流れます。「And go round and round and round in the circle game」のリズミカルな歌詞が、バフィーの少しハスキーでいて透きとおるような声に乗って木霊する。これは映画の冒頭にも全曲流れたのと同じ曲ですが、あの暴力的排除の後では、意味合いがまるで異なっている。このラストは、何度見ても、とても切なく、やるせなく、つらいものです。
「いちご白書」を、一度でも観た人なら、誰でも、そのシーンを、この曲を、瞬時に思い出すでしょう。しかも五年後の、「額縁」に入った情景として。これが例えば、中島みゆきなら、「いちご白書」といった固有名詞は、たぶん避けると思います(中島の「りばいばる」という楽曲がそれを証明しています。そこでは「忘れられない歌がもう一度はやる」と抽象的です)。さらに言えば中島みゆきならば、同じ七五年にコンテストでグランプリを受賞した「時代」にせよ、誰が聞いても、そこで「今日は倒れた旅人たち」というのが、おそらくは、かつて学生運動で挫折した若者たちだ、とは思っても、そうは書かない。さらに、中島の世界では、学生同士が「アベック」(カップルの当時の言い回し)である、というのも無いでしょう。中島とユーミンは二歳しか違いませんが、東京と北海道の差なのか、両者の間には、なにか決定的に異なる感性の差がある。どちらが好いとか、違うとかいう問題ではない。ただ、中島みゆきの世界では、「『いちご白書』をもう一度」は絶対にありえないのは、わかる気がします。ユーミンの世界だからこそ、これが成立する。そして、そういうふうに無造作に見えるほど具体的かつ絶妙な固有名詞を出してくるところが、ユーミンの上手いところでもあります。
9
聞き手は、この「額縁」効果により、たとえ映画を観なかった人でさえ、(ああ、自分にも同じような出来事があったな)、という美しく飾られ、時間に濾過された思い出だけにひたって、安心して聴くことが出来る。そういう策みが、この曲には有るのです。もとより計算されたものではない、ユーミンの優れた直感によって選び採られた言葉であり、その世界でしょう。ですが、結果的には、そうした、安全地帯におかれることで、歌は同世代の人たちを代表して、一切が過ぎ去った75年に、あるいは今にいたるまでも、万人の共感を得ることができたのは確かだと思われます。この曲が大勢のアーティストにカバーされ、今もなお歌い継がれているのは、その証左でしょう。
選び抜いたコトバの力によって、たった五年前の出来事が、あたかも十数年前のセピアカラーの思い出であるかのような印象で、懐かしい青春時代のレクイエムとして描かれている。そういうシーンやコトバの切り取り方をした荒井由実(当時)は、確かに天才的だったでしょうが、この歌の成功はそればかりが理由ではない。
現実問題として七五年の日本においては、連合赤軍問題などが影響して、急速に失速し衰退していった七〇年アンポ闘争に携わった学生らが、当事者であればあるほど、それを思い出に変えてしまいたい、敗北した闘争の過去を癒やしてもらいたい、という潜在的な願望があったと思われます。その切実な時代的な「思い」を美事にすくい取り、哀切なメロディーと美しい歌詞によって優れた鎮魂歌にした若き日のユーミンは本当に天才としか言いようがありません。しかも、自身が実際には当事者ではない世界を歌っているのですから、いくら取材したからといって、その豊かな想像力、コトバ選びの巧みさには脱帽するしかない。
「『いちご白書』をもう一度」はオリコンチャート一位を獲得し、七五万枚売れたそうです。いかに同世代の共感を得たかを物語っていますが、しかし、七〇年当時二三歳だった学生でも、七五年には、まだ二八歳です。もっと若い人もいただろうし、いくらなんでも五年前の出来事を大過去の時制で語るのは早すぎるでしょう。しかし、これは決して特殊な例外ではありません。たった数年前の、それも青春に刻みこまれたはずの出来事でさえ、あっさりと忘れしまうことは、いかにも現代日本的な現象なのです。
が、しかし、この日本人独自の健忘症は、当たり前ですが、大きなデメリットにもなります。まず、伝統がまったく受け継がれない。特に革新系の人たちに共通した通弊ですが(保守派・守旧派は、それじたいに伝統がありますから、物ごとはキチンと受け継がれていきます)、ちょっと前の出来事が、その委細はすぐに判らなくなってしまう。社会的な引継作業がなされないのです。このため、年若い人ほど、ちょっと前のことが理解できなくなる。
さすがに二〇一九年現在で、二〇一四年頃のことが過剰に懐かしい、と言う人は余りないでしょうが、では十年前だったらどうか。NTTドコモが〇七年に全てのサービスを終了したポケベルは、九〇年代に最盛期を迎えた、ある時代の少女たちには特に「使いこなす」ことが世代の証しのような通信手段でしたが、今や憶えている人すら少ない。ポケベル事業はその後も東京テレメッセージが継続しましたが、時の趨勢はすでに携帯電話に移っていました。NTTが撤退した翌年、スマホ、というかiPhoneが日本でリリースされたのは〇八年です。それ以前は携帯とPHSしかなかった(もっと前の昭和の御代には、携帯そのものがなかった)。〇九年にアンドロイド携帯が発売されて、今は、有って当たり前のスマホですが、実際には、十年前の日本にはなかった機器ですし、それがずっと以前から有ったように錯覚してしまう、そういう世界なのです。
もっと古く、といっても、せいぜい九〇年代の映画やドラマを見ていると、オフィス場面などで非常な異和感を憶えることがあります。登場人物たちが働いている職場でPCモニタがCRT(ブラウン管式)なのです。CRTがLCD(液晶)モニタに切り替わったのは、大体、ゼロ年代初頭で、むろん、急激に一変したわけではないため、作品によっては異和感を憶えるシーンも出てくるわけです。これ以前の、PCの歴史などを細かく語るつもりはありませんが、マイクロソフトのウィンドウズPCが普及したのが九五年以降であることは憶えておいてもいいでしょう。今、目の前にあって、有るのが当たり前のものは、実は、ごくごく最近、導入されたものが少なくないのです。
それほど、オフィス空間の変遷は技術の進化にともない急変しています。当然ながら、ドラマにもそういう技術革新は反映されており、たとえば「24」のジャック・バウアーは、携帯がない時代には生まれなかったでしょう。技術より目に見えにくい思想の世界になると、話はもっと複雑です。七〇年当時の政治情勢や、その背後の政治思潮は、今の若い人たちの目には、おそらく非常に奇怪千万なものに映るのではないか、と思われます。
しかしながら、これらの変化は、時系列の変化にともなう自然なもので、今、挙げた携帯の例をとると、たとえば八〇年代の映画やドラマを見ていて、もし「主人公がケータイを持っていたら、こんな状況に陥るわけはない。圏外とも思えないし、なぜ使わないんだ。アホなのか?」などと言えば、それは自分の無知=アホさを晒けだすだけで、あまり意味がある言動とは思えません。あらかじめ公開年を知っていれば、それくらい判るでしょう。事前の知識がなくとも、前後の脈絡から、ある程度は見当がつくはずです。たとえ二〇世紀の世界には携帯電話がなかった、という知識がなくても、しばらく見ていれば、そういうものだ、と思い当たると思います。しかし、表面的には大した差異がない事がらとなると、話は別です。
またぞろ映画の話で恐縮ですが、八八年公開の映画「ダイハード」で、主人公を演じたブルース・ウィルスが、犯人側が持参した携帯用無線機(ハンディトーキー)で犯人のリーダーらと連絡を取り合うシーンがあります。そのウィルスが、NTTドコモが九一年にリリースした携帯電話「ムーバ(Mova)」のCMに起用されたことを記憶している人もいるでしょう。ムーバは言うまでもなく、第一世代のアナログ式携帯電話でした。この間、たった数年の差ですが、「ダイハード」の主役だったウィルスが使っていたのは携帯用とはいえ無線機(トランシーバ)で、ムーバのCMで使っていたのは携帯電話なのです。この差は、後になって(DVDなどで)映画を見た人には、判りにくいかも知れませんが、見た目を超えて、歴然としたテクノロジーの大差があります。無線機は強力な電波で双方向通信が可能な機器で二台あれば使えますが、携帯電話は基地というインフラがないと通信が不可能です。両者は似て非なるものなのです。
しかしながら、今の若い人が、冷戦構造がいつ頃なくなったのか正確に知らなければ、それ以前のスパイ映画などを見た場合、そこに異和感以上の奇妙な感覚に襲われることは充分に考えられます。もっと思いこみの強い人ならば、ある映画を見て、「これはおかしい、間違っている」と断じるかも知れない。これが映像のない本、特に歴史的な思想書なんかだったりしたら、もっと強いギャップを感じるかも知れません。時代背景を知らなければ、これは当然といってもいい。
マリー・アントワネットを引くまでもなく、知らない、ということは、その人の環境次第ですから、仕方がないことです。しかしアントワネットよろしく、そういう無知による誤解から発して、チグハグな結論や推論を導き出さないともかぎらない。もとより無知は責められるべきことではありません。説明しない方が悪いのです。ただ、説明抜きで、いきなり、そういう世界と直面したら、若い人は、異様な感覚と疑念とに見舞われるでしょう。
.
.
付記:
以上のようなことを統計資料まで引用して言ったとしても、ユーミンの「「いちご白書」をもう一度」の価値は何も変わりません。優れたものです。
しかし、これだけは言っておきたい。上記の統計値は、もっと大きな別な変動が背後にあるのです。ただ、男女の恋愛観や結婚へのモティヴェーションがどうこう、といったものではありません。それは、まず社会全体の人口動勢です。
吉本隆明に「全マンガ論」(小学館 〇九年刊)というマンガやアニメについての論考をまとめた本があり、その中で「ちびまる子ちゃん」について語った中に少し堅苦しい言及があります。このマンガが一九七四年から七六年にかけての時代設定(いわゆるサザエさんシステム)であることは、言うまでもなく読者には了解されていると思います。それを踏まえて、隆明は、
「産業でいいますと、サービス業とか小売業・流通業といった第三次産業が半分以上を占める社会に転化したのが、このあたりです。七五年あたりから先進国は消費社会といえる状態にはいっていったとかんがえると、だいたいにおいてまちがいないでしょう。産業的には資本主義社会の初期から興隆期にかけて、製造業と農業・漁業・林業という第一次産業とが相対立し、製造業中心の社会だったんですが、そういう社会のイメージが通じなくなったことを意味しています」(七二頁)
一マンガ作品論から、いきなり経産省的マクロな視点が導かれます。
隆明は、作者さくらももこが、そうした統計値などからではなく、おそらく作家的直感で、七五年前後という作品の時代設定をしたのだ、ということは承知している。その上で、七五年がどういう年だったか解説しているのです。
すなわち、七五年に、日本の産業構造の逆転が起きた、と。これは厳然たる事実です。いわでもの説明をすると、第一次産業とは農林水産業、つまりお百姓さんや漁師さん。第二次産業は、いわゆるブルーカラー。そして第三次産業は、いわゆるホワイトカラーのサービス業を指します。モノを造るのが第一次、第二次産業の人たちで、モノは造らないがその再配分や情報生産で収入を得る、その他の人たちが第三次産業。そう言ってもいいでしょう。そして今や第三次産業の就労人口は全体の七五%を占めています。
そして、この逆転が起きたのが、おおむね七五年頃なのです。
ユーミンがデビューしたのは七二年ですが、最初はパッとせず、ドラマ主題歌の「あの日にかえりたい」で七五年にオリコンチャート一位となり、一気にヒットしたとあります(私は高校時代は不眠症で暗黒期だったので、音楽は一切聴かず、五年間の流行歌を知りません。七四年にやっと山口百恵の名前を聴いたほどです)。
大学に入ったのが七五年だったので、その年末に知り合いから「ムスリム」と「コバルトアワー」のカセットをダビングして貰ったことにより、強く憶えているのですが、中でも「ルージュの伝言」は最初、聴いても、とっさに意味が判らず、二度目に聴いて意味が判り、驚いたのを記憶しています。
要は新婚の若い女性が亭主の浮気に怒って家出する、という話なのですが、こんな場合、行き先は普通、自分の実家でしょう。少なくとも、七〇年以前なら、そのはずです。それをこの女性は「亭主の実家」に行く途中なのです。そして明日の朝、「ママから電話で叱ってもらうわ、マイダーリン」とあるところを見ると、彼女は姑を信頼し、姑からも彼女は信頼されているようです。
通常なら「由実さん、浮気は男の甲斐性と言うでしょう。貴女が我慢しなさい」とか言われるところですが、違う。七五年の時点で、この現代日本に生きている若い女性が、本気で亭主の浮気を亭主の実の母親から叱ってもらう積もりでいる。
「ルージュの伝言」とは、そういう意味の歌詞なのです。これは当時の私には非常に衝撃的でした。七五年の現在に、こんな新しい世界観を持った女性のシンガーソングライターが出現しているのだ、と。大げさではなく、本当にショックを受けました。
ユーミンの感性はともかく、その感性の背景にあるのは、七〇年から七五年にかけての、日本における産業構造の大きな変動です。
国勢調査を基にした統計によると――、
七〇年には、一五歳以上就業者の割合が、第一次産業:一九・三%に第二次産業:三四・一%で合計五三・四%。第三次産業:四六・六%でした。これが、七五年には、第一次:一三・九%、第二次:三四・二%で、第三次:五二・〇%と完全に逆転しています。
巻末の初出一覧によれば、隆明が「ちびまる子ちゃん」について書いたこの文章は九〇年一二月ですから、そこで語った統計値は、美事に当たっている。のみならず、九〇年時点では同じ統計値は第一次:七・二%、第二次:三三・五%(合計四〇・七%)、第三次:五九・四%になっていました。
この数値は、ユーミンや私が生まれた頃、すなわち五五年時には、第一次:四一・二%、第二次:二三・四%(六四・六%)、第三次:三五・五%だったのです。つまりお百姓さん等だけで、社会を支える労働者の四割もいた。対してサービス業などは三割五分でしかなかった。それが私たちが成人する頃には、つまり二十年間で逆転していたのです。二〇一〇年には、この比率は第一、第二次の合計価が二九・四%に対して第三次は七〇・六%に達しています。
隆明は、続いて日本における女性の「未婚率」にも言及しています。この文章が書かれた九〇年より前のデータで「現代用語の基礎知識」から引用されていますが、氏は、二十歳から二十四歳の女性の未婚率の推移から、その半分以上が未婚、という状勢は五〇年頃からだと言います。五〇年が五五・二%、六〇年が六三・三%、七〇年は七一・七%、八〇年には七七・七%で、先進国の中でスウェーデンに並び、多いとあります。当然のことながら、その背景には、若い女性が「今は結婚したくない」という気持ちがあるわけで、その更に背後には、もっと大きな社会的変動があります。しかし、表面的には、それは女性の権利の拡大、いわゆる女権闘争になります。
フェミニズム運動の「はしり」とも言うべき「ウーマンリブ」運動の起源は、日本では、六〇年代後半の全共闘運動にあり、前線の街頭デモに男子学生が闘い、後方で女子学生らがおにぎりを作らされている実情への「否定(ノン)」から発生したと言われています。「女性は男の奴隷ではない」。この言説が、やがて政治活動を離れて、社会全体に広がってゆくわけです。しかし、実際には、それはキレイ事でした。現実はもっと生ぐさい、陰湿なものだったのです。
私たちは、すでに非合法時代(戦前戦後)の日本共産党で、「ハウスキーパー」という制度の名の下に、女性党員や女性シンパが、男性党員の身の回りの世話や性処理までさせられていた、いわば性的に搾取されていた歴史を知っています(日共中枢は権力の逆宣伝だと否定しているが、多くの反証から、今では存在したと思われている)。
そして今となっては、それが全共闘時代でも同じだったことも、判っています。彼らはバリケードの中で、彼女たちを慰安婦とか、もっと酷い差別的呼称で呼んでいたそうです。
私は、こうした左翼運動の奥底にある、どこか非人間的な側面が、彼らが口にする理想や思想とは相反するものとして、非常に溶き合えないものを感じます。むろん生まれ年に依るのですが、ユーミンが大学(多摩美)に進んだのが、学園紛争の終結した七二年だったことは、むしろ幸運だったように私には思えます。
それはともかく、一つの歌の背後にさえ、このように大きな世界規模での変動があるのです。
当然のことながら、上述したような経済成長による生活様態の変化は、先進国と呼ばれる国々だけの現象であって、その裏面では、(当時の)第三世界の搾取がありました。今でいうポストコロニアリズムです。第三世界とは、冷戦下で東西両陣営の枠外だった、アジア、アフリカ、南米などの発展途上国を指しますが、七〇年代においてさえ、米ソとその陣営諸国は、かつての植民地を搾取し続けていました。
穀物メジャーはアフリカの最貧国に、その国民が食べるのではなく牛の飼料としての穀物を作らせ、買い上げる。遺伝子組換え技術による種子や種苗を与えて選択の余地がない、しかもその先祖伝来の土地を耕してきた人々の口には入らない作物を作らせることで、時には飢餓を招いたりもしている。よく言われるように、一個のハンバーガーを作るためには三トンの水が必要です。パンの材料の小麦のみならず牛の飼育に厖大な水が要るからです。これを仮想水と言うのですが、日本は世界最大の仮想水輸入国になっています。
科学や技術の発展にともない、搾取はより巧妙かつグローバルになっています。そうした背景をともなって、わが国のような、一部の先進国では自国民の食糧を他国からの輸入に依存し、それゆえに、自国の農業が衰退する結果になります。今や日本の食料自給率(カロリーベース)は先進国の中でもダントツの最下位になっています。世界史的にみても、こうした事例は帝政ローマと現代日本だけだそうです。
だからといって、では先進国はそのような社会変動で、なにもかも手に入れることが出来たか、というと、むろん、そんなことはなく、この大きな社会構造の変動は、のきなみ先進国における少子高齢化を招いたのです。
これは今や世界的に「移民問題」となって、その国家の主体民族の「種族的生命線」を脅かすものとして、季節労働者や移民の排除など、深刻な人種的対立を招いています。しかし当然ながら、これは自然にそうなったわけではありません。
「特殊合計出生率」という数値があります。一人の女性が出産可能とされる十五歳から四十九歳までに産む子供の数の平均を示す人口統計上の数値です。
説明を読むと、とても難しい数式などが出てきますが、要するに、この数値が「2」だと、人口は横ばいとなり、「2」を切ると、その国の人口は将来的に減少する。ということになります。
これが七五年に、日本で「2」を切ったのです。つまり、この年は日本の少子化にとって、見えざる分水嶺と言えます。
しかし問題はもっと以前からあったのです。
静岡県立大学学長の鬼頭宏氏によると(※1)、日本では、七四年に出された「人口白書」(※2)において、昭和八十五年すなわち二〇一〇年に日本の総人口がピークを迎え、その後は減少することを予測していました。そしてこの予測はピタリと当たり、国勢調査によると、二〇一〇年に日本の人口はピークとなり、その後は下り坂になります。
※1) https://www.recruit-ms.co.jp/research/2030/opinion/detail31.html
※2) https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1974/dl/03.pdf
ところが、四十数年も前にそうなることが判っていたにも関わらず、これに対する対策が取られたのは、ようやく九〇年代に入ってからだったのです。これには理由があり、七二年にローマクラブの「成長の限界」が出されています。「人口増加や環境汚染などの現在の傾向が続けば、百年以内に地球上の成長は限界に達する」という警鐘です。ローマクラブはスイスの民間シンクタンクに過ぎませんが、この報告書は当時、世界的な注目を浴びました。
そこで、七四年版「人口白書」では、この数値を上げながらも、なお出生率を下げた方がよい、といった政策になるわけです。十八世紀に書かれたマルサスの「人口論」は、医療の進歩や人工肥料による克服があってさえ、世界史的にはおおむね正しいことが自明なので(全ての国々が化学肥料を使うことは不可能ですし、医療は富める国や福祉国家でしか、国民全体に行き渡ることはありません)、世界的人口増加は世界的食糧危機によって必ず阻まれる。地上の資源が有限だとすると、先進国の人口増加政策は、やがて世界の資源を必ず食いつくす。結果、第三世界は人口爆発を起こす。そういう理屈での、抑制案の提唱なのです。
これは「成長の限界」にもとづく真剣な議論の回答でもあり、事実、七五年から世界の先進国では、ほとんどが「特殊合計出生率」が「2」を切っていきました。
むろん、他にも理由はあるのですが、女性の「未婚率」が高い、ということは「女性の活躍」と同時に「晩婚化」を意味しますし、それは必然的に「少子化」へ繋がります。しかし七〇年代前後から八〇年までくらいは、有限な資源を先延ばしに使うためには、人口抑制が必要だ、といった思潮が世界レベルで支配的だったのです。グローバルな趨勢がそういう状況ですから、日本政府が何も手を打たなかったとの批判は、当たらないでしょう。
とはいえ、現在の予測では二〇六五年にわが国は総人口が八八〇八万まで減少し、出生率は一・三九と低水準のままだろう、と言われています。七四年に、そこまでの予想はしていなかったにせよ、目の前にある資源を、未来に絶やさぬために節約して、それより先に国家が滅んでは元も子もない。それでなくても食料自給率が最低のわが国では、今や六割を輸入に頼っており、第一次産業の割合は五%(内、農業従事者は二九〇万を切っています)という実情では、自給率を急に上げるのは不可能です。現時点で輸入が途絶したら、その年の内に大半の日本人は餓死するでしょう。
そうならなくても、たとえば国立社会保障・人口問題研究所が出した「日本の将来推計人口」(一七年(※3))によると、百年後(二一一五年)までの人口の急落を示していますが、これは、いくつかの条件付きの仮定の数値が上げられています。条件によりますが、百年後には日本の人口が五〇〇〇万ほどになる、とのグラフがあります(数値での表示はない)。
この社人研が上げた条件付きの数値を元に、さらに将来を推定すると、どうなるか。という、おそらく個人的な推論だと思うのですが、産経新聞の論説委員を経て、現在、大正大学客員教授の河合雅司氏の主帳では、三百年後にわが国の人口は四五〇万にまで減少する、と言います。私は福岡県に住んでいるのですが、今の県人口が大体五一〇万です。それより下回る! 他の例では、某国で弾圧を受けているチベット族が四五九万(一七年時点)の由ですから、迫害されている少数民族より少ない。
小松左京氏の「日本沈没」で日本列島が沈没した後の、世界中に離散した日本人の数は八千万人でした。氏は当初、六千五百万人の予定だったのが、あれこれ思案して多めに助けたのです。しかし、この試算だと列島が沈没しなくても、いずれ日本人は滅んでしまうことになる。
まあ、これは統計の魔術による机上の空論にすぎないので、三百年後のことなど、本当のところ誰にも判りはしませんし、二〇一〇年代の産経新聞紙上で少子高齢時代を煽って書いていた、河合教授が、さらにセンセーショナルな数値を上げた本「未来の年表」(講談社現代新書 一七年刊)の販売促進のためにネットで語ったのであろう、この推算値が、どれほど精確なのか、理数に暗い私には判断がつきませんが、たとえ予測値の一つだけとしても、背中が薄ら寒くなる、恐るべき数値ではあります(河合氏は「あまり知られていないが、この社人研の推計には続きがある」と称して、これらの推計値を上げているのですが、私が社人研サイトにアップされた翌一八年度のPDFファイルを一覧しても、三百年後の推算値は載っていませんでした)。成否の判断はともあれ、将来への警鐘としての働らきは認めるに吝かではないので、記しておきます。
※3) http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp
※4) https://gendai.ismedia.jp/articles/-/51994
日本での少子高齢化社会は、核家族化がその原因だ、とか言われていますが、これも疑わしいのです。実際には、日本の核家族化は、一九二〇(大正九)年には始まっており、六〇年代に急増しています。その時代に少子高齢化が問題になった話は聞いたことがありません。
先述の鬼頭氏によれば、英仏などの国では、かれこれ五百年間ずっと核家族社会の伝統がありますが、巧く機能していました。問題はだから、別にあると思われます。少子化問題は、なんらかの社会の変動でしょうが、その対策には、家族制度や働き方に対する意識を、まず変革しないと、社会のシステムは変わらない。
ならば、それに見合った社会システムの変化が当然、求められるのですが、日本では、その手当が非道く遅れているのです。だから核家族で、共働きとなると、家事や育児までが、同じく働らいている女性の肩に被さってくる。性差の役割教育が長年にわたってなされた悪しき結果です。
これに対抗して、DINKs(ダブルインカムノーキッズ=二つの収入、子供なし)は夫婦二人の裕福は保証しますが、全国民がそれをやると亡国の論になってしまう。個的な対症療法でしかありません。
そうではなく、夫婦二人で働らき、同時に育児も家事も共同でやる、という(特に男性への)意識教育を先にやらねば、どうしようもない。否、それよりもまず、子育てに対して許容的な社会システムが必要なのです。それが成されれば、意識の変革は付いてくるはずです。存在が意識を決定するのですから。
大家族ではなく、核家族でもいい。その代わり、夫婦二人で一人か二人の子供を育てる。というよりも、たった二人きりでも子供が育てやすい社会を作る。そうした優しい社会システム全体の改革がないまま、いたずらに危機感だけ煽っても意味がありません。意識より、まずシステムを変革すること。
この観点は、今の政権与党も野党にもないように思えます。挙げ句の果てに、そうした歴代政権の無為無策を棚にあげて、やれ結婚しないで子供を産まない女性はどうだとか、LGBTは生産性がないだとか、差別的発言にシフトしたところで何の解決にもならない。
核家族で共働きなら、当然、家事や育児は平等に分担すべきなのに、現実はそうなっていない。それが判っているから、女性は仕事に専念して子供を産まないだけです。それを女性だけ攻撃するのは、それこそ生産性のない、国を滅ぼす暴論でしかないでしょう。
「ジェンダーギャップランキング」は、スイスの世界経済フォーラムが毎年公表している男女格差を表す指標ですが、二〇二〇年に日本は一二一位と先進国の中で最下位でした。さらに英国のエコノミスト誌が発表した「女性の働らきやすさ」指標でも日本は先進国を中心とした二九カ国の内、二八番目、ワースト二位です。それ自体、私たち日本人は世界に対して、恥ずべきことです。
しかし、これは特定の誰かの発言がどうだとか、官僚や企業が「男社会」だから、といった要約ですまされる話ではありません。今この瞬間にも、生まれてきた子が女子だったら、その母親が、我が子は不幸な未来を背負わされたも同然である、と悲しむような社会であってはならない。
この泥沼から脱却するには、社会システム全体を根底から見直し、改善しなければ、誰も子供を産んで育てたいと思わないのは当然なことであります。それはすなわち、三百年先はともかく、最低でも十年、あるいは五十年先の日本が、亡国につながるのだ、という認識を持って取り組むべきです。
ユーミンの歌が半世紀前に切り拓いたような、まったく新しい家族観。あるいは男女に共同の自由。真に男女平等の意識改革。そうした建設的な展望が、可能性としも、もっと意欲的に国政、ないし民間レベルで広がるような社会システムを作る。そうすれば意識は自ずと変わる。そんな社会でないと、いつまで経っても特殊合計出生率は上がらないでしょう。国が、民族が衰滅する前に、まず国民の意識が変わるような社会に変えないとダメなのです。
(2021/03/06/2021.03.09 追記)
PREV | NEXT
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?