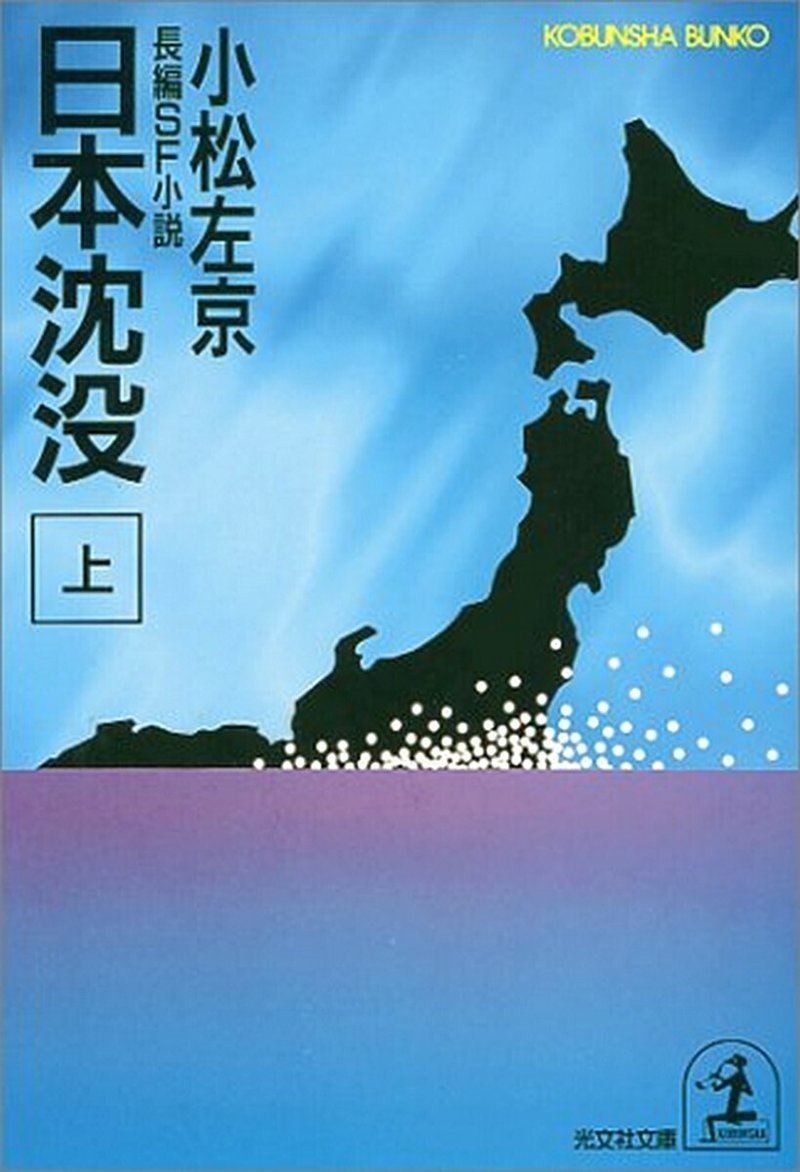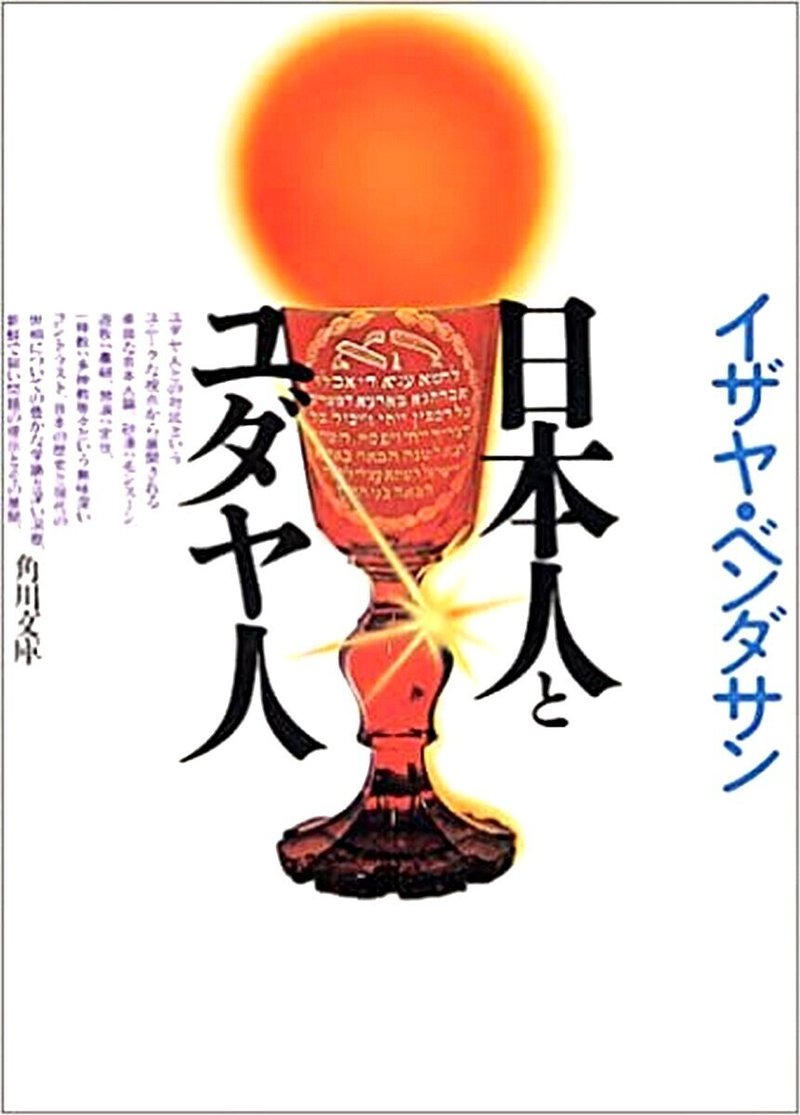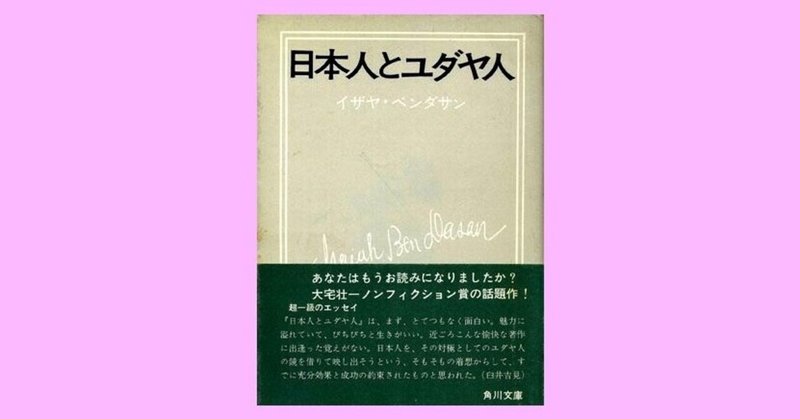
「日本人とユダヤ人」講読
野阿 梓
「日本人とユダヤ人」は、一九七〇年に発売され、総計三〇〇万部を超える一大ベストセラーとなった本です。刊行から五〇年経った今も新刊本が買えるロングセラーでもありますが、めちゃくちゃ面白い本なのに、当時も今も不明な点が多いという謎な本です。これをサブカル観点から講読という形で語り、既読の人も未読の人もその面白さを伝える。というのが本講読の目的です。
講読するのは、ふだんSFや「やおい(801)」を書いている私、不肖・野阿梓です。別にSFや801が好きでなくても、もとより野阿梓作品に興味がなくても、十分に楽しめます。そのように書きました。むろん、私の作品のファンならば、野阿梓という作家が、いかなる精神的トンネルをくぐって、今日にいたったかが判る。そういう内幕的お話でもあります。要するに、知的興味がある人なら、全方位的に面白い、そんな楽しい「読み物」です。肩肘はった「白熱授業」なんかではありません。でも、結果は、それと同じくらい楽しみつつ深い真理にたどり着ける。そういうお話です。
全体の構成は以下です。
元の本は全15章ですので、基本的に1章から1つキーワードを拾い上げ、それは70年当時、私にも判らなかった言葉だったり、中には今もって理解不能な用語だったりします。理解する、しない、よりも、いかに面白く読むか。そういう趣旨です。マジで本当にいまだに判らない固有名詞などもあるのですが、それを面白おかしく論じていく。そういう楽しい講読です。大学の論文講読の見てくれを取りつつ、名物教授の授業さながらに、笑いあり、知的興趣あり、少しマジメな論文あり。どうか、野阿ワールドをさまようように、私が熱中した「日本人とユダヤ人」の世界を楽しんでほしい。そういう「講読」です。では、さあ、いってみよう!
まずは、「日本人とユダヤ人」講読の目次です。趣意書をのぞけば、ほぼ原著の章立ての通りにしています。手許に本を持っている人は、照らし合わせて読んで見ましょう!
目次
趣意書 ←(もう少し詳しいこの「講読」の内容)
第一講 ヘルツェル ←(シオニズムの親玉)
第二講 ベンダサン ←(偽書だの何だのと言われた著者の秘密)
第三講 地の民 ←(ベンダサンでも間違うこともあるんだ的な内輪話)
第四講 クロノスの首 ←(プラド美術館で見たゴヤの画を思い出しつつ書いた)
第五講 ギデオン ←(って誰?)
第六講 ゼカリヤ ←(って誰?)
第七講 ミロバン・ジラス ←(って誰?)
第八講 パウロ ←(イエスとキリスト教は無関係。で、キリスト教を創った人)
第九講 ヤムニア会議 ←(旧約聖書を編纂した会議。だけど旧約って何?的な)
第十講 ヒルレル ←(イエスの師らしいが、日本では誰も知らない。誰それ)
第十一講 モーセ ←(紅海真っ二つの人。でも、フロイト晩年の妄想がスゴイ)
第十二講 ロープシン ←(昔の五木寛之△ー。でもって元ネタはもっと△ー)
第十三講 ニケーア会議 ←(キリスト教がキリスト教になった大昔の会議らしい)
第十四講 ディプロストーン ←(いまだに謎な言葉で誰に聞いても判らん)
第十五講 ハジ・アミン・アル・フセイニ ←(アラブの偉い人だったがテロの親玉)
第十六講 ソロバン ←(誰も知らないけど私の父親って算盤の名手だった話)
第十七講 ダビデとヨナタン ←(今ならBLだけど。しかしそもそもダビデって誰?)
第十八講 ハムレット ←(ハムレットって、こんなお芝居だったんだぁっ!?的な)
目次
趣意書 ←(もう少し詳しいこの「講読」の内容)
第一講 ヘルツェル ←(シオニズムの親玉)
第二講 ベンダサン ←(偽書だの何だのと言われた著者の秘密)
第三講 地の民 ←(ベンダサンでも間違うこともあるんだ的な内輪話)
第四講 クロノスの首 ←(プラド美術館で見たゴヤの画を思い出しつつ書いた)
第五講 ギデオン ←(って誰?)
第六講 ゼカリヤ ←(って誰?)
第七講 ミロバン・ジラス ←(って誰?)
第八講 パウロ ←(イエスとキリスト教は無関係。で、キリスト教を創った人)
第九講 ヤムニア会議 ←(旧約聖書を編纂した会議。だけど旧約って何?的な)
第十講 ヒルレル ←(イエスの師らしいが、日本では誰も知らない。誰それ)
第十一講 モーセ ←(紅海真っ二つの人。でも、フロイト晩年の妄想がスゴイ)
第十二講 ロープシン ←(昔の五木寛之△ー。でもって元ネタはもっと△ー)
第十三講 ニケーア会議 ←(キリスト教がキリスト教になった大昔の会議らしい)
第十四講 ディプロストーン ←(いまだに謎な言葉で誰に聞いても判らん)
第十五講 ハジ・アミン・アル・フセイニ ←(アラブの偉い人だったがテロの親玉)
第十六講 ソロバン ←(誰も知らないけど私の父親って算盤の名手だった話)
第十七講 ダビデとヨナタン ←(今ならBLだけど。しかしそもそもダビデって誰?)
第十八講 ハムレット ←(ハムレットって、こんなお芝居だったんだぁっ!?的な)趣意書(1)
1
イザヤ・ベンダサン著「日本人とユダヤ人」(※1)は、一九七〇年に山本書店から出版され、翌年には角川文庫に入り、総計三〇〇万部を超える一大ベストセラーとなった本です。
※1 https://www.amazon.co.jp/dp/4043207018
(今後、こういう形で、注釈を付ける予定です。今となっては入手が可能なのかどうか、判らない資料も多いと思いますので、書物ならAmazon やその他、購入可能な版元の書籍情報、ネット上の資料はそのURLを付して、できるだけ読者の便宜を図っていきたいと思います)
以下は、非常に個人的な話になりますが、ちょうど70年に、私の母親が知り合いから山本書店版を借りて読んで、「これ面白いよ」と私にも勧められた記憶があるのです。ちなみに母は一九二一年(大正10年)生まれで、山本書店店主の山本七平氏と奇しくも同じ生年です。戦前に洗礼を受けている山本氏と異なり、母は無宗教でしたが、創立したての玉川学園女子部で青春を送ったため――クリスチャンだった小原國芳氏が、官学に対抗して創設したばかりの私立玉川学園では、自由な教育を目指していたこともあり、特に宗派を定めず、キリスト教的な教育をしていたことから――、クリスチャンではなかったけれど、聖書に親しみ、他の人よりはキリスト教に関する知識はありました。
が、しかし当時、反抗期だった自分は母親からそれを又借りして読むのを潔しとせず、その時は拒んだのです。ところが、私は70年にミッション高校に入学した後、不眠症にかかって不登校になってしまい、いきおい日常生活から遊離してしまいました。そこで異端的文学や教説に耽溺しつつあった私は、読むべくして、その文庫版を自分で買い求めたのです。ユダヤ教に関する知見は、必然的にキリスト教とは相反せざるを得ません。だからミッション校に通う高校生としては、この本は異端的です。しかし、それだけではありませんでした。とにかく、問答無用に面白かったのです。しかも何度読んでも、毎回、どこか別の場所に新しい面白さがある。以来、これまでに、私はこの本をザッと百回以上、読み返していると思います。
71年に文庫版を買って、私は表紙がボロボロになるまで読んだのですが、それは引越の際に見失い、その後買い直しました。今、手もとにあるそれは、奥付によると、昭和60年で68版発行とあります(その後、この講読のために本を探していて偶然、前の版も見つけました。昭和46年9月30日が初版の刊行日なのですが、私の購入したのは同年10月25日の第三版でした。三版というより三刷でしょう)。最終的に何版までいったものか。今では元の文庫版は絶版ですが、「角川文庫ソフィア」という代替の文庫や「角川oneテーマ21」という二〇〇四年に出された新書が新刊で買えます。つまり今にいたるもロングセラーでもあるわけです。
浮き沈みの激しい出版界で、半世紀にわたってベストセラーであり続ける。もしくは、半世紀たってもまだ店頭で買うことが出来る。そういう本は珍しいでしょう。ベストセラーの宿命的欠陥は、一時の流行りで、ブームが過ぎたら、誰も一顧だにしない、という傾向があるから、なおさらです。私の知るかぎり、当時のベストセラーで半世紀の星霜をたえて、今もなお新刊が入手できる本は、これと小松左京さんの「日本沈没」くらいではないか、と思います。これは最初、上下巻のカッパノベルズでしたが、今でも小学館の文庫版が新刊で入手可能です。
思えば、「日本人とユダヤ人」と「日本沈没」のどちらも、日本人の根源的なところに深く鋭く問いかけています。ノンフィクションとフィクションの差こそあれ、たがいに深い部分で通底した似通ったテーマを持っている。さらに言えば、「日本沈没」という本は日本民族が祖国(どころかその土地)を喪失して、ユダヤ人のような「さまよえる民族」となる物語です。
当初、小松さんは三部作を構想し、刊行された第一部では、日本人が日本という諸島領土を失ない、第二部では「さまよえる民族」となり、第三部で日本民族の問題が世界の問題となっていく。つまりユダヤ化とイスラエル化になる。そういう構想だったそうです。かたや、「日本人とユダヤ人」は最初から「さまよえる民族」だったユダヤ人と日本人の問題をあつかっているので、この二冊はコインの裏表のように対照的ですらある。全く異なる地点から日本人の、有りうるかも知れないユダヤ化について言及しているわけです。
その意味では、二つの本が半世紀にわたって生き延びているのは、歴史の必然なのかも知れません。
2
当時、小松左京さんが「日本沈没」を書いてベストセラーになって少し後の頃、ハードボイルド作家であり、かつては「EQMM(エラリークイーンミステリマガジン=現在の早川ミステリマガジンの前身)」誌編集長でもあった生島治郎氏が、ミステリ専門誌「小説推理」に連載していた対談を本にした上下二巻の「生島治郎の誘導訊問」というものがあるのですが、その上巻に当たる「眠れる意識を狙撃せよ」(74年、双葉社刊)で、ホスト役の生島治郎氏とゲストの五木寛之氏とが対談していて、そこで「日本沈没」を取り上げていました。当時、五木氏は、休筆宣言して充電期間だったので、わりと勝手なことを言っているのですが、その箇所だけ引用します。
「五木 あれはぼくのいう、集団的な神話みたいなものにつながるところがあるんですよ。そこが面白い。日本人全体が感じている、もし日本人が日本から追われたらどうなるだろうという、そういう潜在的に持っている恐れみたいなものに、あの構想は触れているんだ。ぼくは朝鮮から追われて日本にきたから、流民としての経験があるんでピリッときたんだけれども、あの小説がいちばん面白いというところは、そこです。
生島 それともう一つ、『日本沈没』があれだけ売れているというのは、日本というのは島国であって、鎖国でなくなってからも鎖国だったわけだよ。
五木 うん。
生島 それが、これだけインターナショナル・コンセンサスが生まれ、交通網が発達してくると、島であることに意味がなくなるわけだ。そうすると、日本民族は、島が沈没しなくたって流れて行かなきゃいけないわけだよ。
五木 もしあの本がベストセラーになったとすれば、日本人にとって島がなくなるという根源的な集団の恐怖に触れたところがあるからですよ」
――と語り合っている。
日本人が原初的に持つ、「この国土が無くなったら、俺たちはどうなる」という無意識の深層に眠る恐怖を爬羅剔抉(はらてっけつ)した、だから「日本沈没」は売れたのだ。という二人の作家の感覚は鋭い。これはお二人とも、昭和一桁生まれで、戦時中に植民地(五木は生後まもなく朝鮮半島に渡り、生島は上海生まれ)で育って、日本が戦争に負けたあと、地獄のような「引き揚げ」を体験しているからこそ、だと思われます。対談時の二人はともに、また四十歳ほどです。ゆえに自分とはジャンルの違う作品に対して、「日本人が国土喪失したら一体どうなる」という架空のSF作品に対し、これだけ共通した認識で深い洞察をなしえているわけで、この二人の発言には重みがあります。特にハードボイルド作家の生島氏と異なり五木寛之氏は、伝奇ロマンめいた作品もあり、SFの読者にも、馴染みがあるでしょう。
しかし、五木氏に関しては、「日本人とユダヤ人」の後段でも取り上げられていますから、そこで詳述することにして、今は、ただ、「日本沈没」が書かれた頃に、非常なる読み巧者でもある、当時の流行作家二人が、ともに同じ主題からそれを論じていた、という事実を指摘しておきたいのです。まだそういう言葉がない時代に、今のグローバリズム社会を予見し、そこで日本人が(流民ではないにせよ)、流れゆく民族として、いかに身を処していくべきか、といった先見性に満ちた問題提起を作品の真のテーマだと捉えている。それは優れた同時代の評言だったと思います。
ただ、惜しむらくは、「日本沈没」は紙媒体以外にも、複数の版元からキンドル本(※2)で今は入手可能ですが、「日本人とユダヤ人」はいまだに電子書籍化されていません。この文章をまとめるためには、電子書籍の方が何かと便利だろうと思い、私はネットを探して、この本がいまだに電子化されていないことを初めて知り、少し茫然としました。残念なことですが、おそらく版元は、これを電子書籍で読む読者層を想定していないのではないか、と思われます。米国なら、とっくに電子化されているはずです。なによりフォントの大きさなどを自由に変えられる電子書籍は高齢者に最適な読書環境を提供できるので、米国では特に部厚い本などは軒並み電書化されているのです。しかし、今の日本では、売れる電書は若者向けのマンガがほとんどですので、そうはなっていない。実に口惜しいことですが、いたし方ありません。未読の方は、ぜひ、活字本で読んでください。
※2 https://www.amazon.co.jp/dp/B009KZ593O/
3
ともあれ、それほどに、「日本人とユダヤ人」は示唆的で、多面的で、また多くの矛盾を孕んでいる。超絶面白本なのです。この本を読んだ、という方は(私をふくめて、ですが)、おそらく、自分の理解している範囲内でしか、読んでいない。たぶん、いや、きっと(私がそうしたように)判りづらい箇所は飛ばして読んでいる。それでも、なお面白いのが、この本の困ったところでもあります。
そういう書は、あまりないでしょう。文中に判らないことが多くあるのに、それを越えて幅広い読者を獲得した、などという本は、ほかに聞いたことがありません。ハイデガーの哲学書のように、難解な本は難解がゆえに一般には読まれないのが現実です。
一般の読者にとっては、俗耳に入りやすいことが、平易な文章で書かれていて、しかも、判らないことがあっても、読み手サイドが、すでに知っている知識の範囲内で、ロジカルに処理出来る。そういう本が売れるなら判ります。だが、この本は、そうではない。難しい箇所は、本当に、特殊なジャンルへの深い狭い学知を持った専門家やよほどの知識人でないと判らないことがある。だのに、全体が面白いから、そこはスルーしても読めてしまう。そういう希有な奇書であり、またそれゆえに、いまだ普遍的名著なのです。この二つの要素をかねそなえ、さらにベストセラーになった、というノンフィクションは、おそらく、これだけでしょう。そこだけ見ても、非常に特別な、しかも希少な本だ、ということが判ると思います。
この本は、刊行の翌年(角川文庫入りした年)の71年に第二回「大宅壮一ノンフィクション賞」を受賞しました。この賞は、だいたい歴代の受賞者がルポライターとか、そういったノンフィクションの著作を専門にしている人が多いもので、全く無名の素人が書いた本が受賞対象になることは滅多にありません。それも凄いことですが、なによりも、この本の刊行によって、版元の店主(社長)であった山本七平氏を論壇に送り出した功績があります。それまで全く無名の、キリスト教関係の地味な出版社の社長だった人が、にわかに一論客として脚光を浴びたのです。
しかし、この講読では、著名になってからの山本氏やベンダサン氏がからんだことは捨象します。あくまでも、まったく無名の人が書いた「日本人とユダヤ人」だけを対象にして、その細かい注釈を付けていきたいのです。
しかしながら、一九七〇年当時でさえ、15歳の高校生には、いかにミッション校の生徒とはいえ、聖書学やユダヤ文化論に深く根ざしたこの本の真価をまっとうに評価するのは困難きわまりない大変な作業でした。当時の私は、やたらと背伸びしたがる子供だったのですが、それでもミドルティーンの付け焼き刃では、いくら背伸びしても、ちょっと歯が立ちませんでした。
いや、今でもなお、時おり再読すると、判らないことが出てきます。それくらいには、このたった二五九頁しかない文庫本には、途方もなく深甚な叡知と、そしてある種の「策み」とが混在して潜んでおり、しかもそのアリアドネの糸を待つ深い濃密な迷宮の奥に、思いもかけない知の宝物が詰まっているのです。そういう意味では、この本は今もってなおも、隠された宝の山であり知の宝庫です。70年当時、15歳の高校生にはとうてい手も足も出なかった。そして今でも、これで正しい認識なのか、時々、読み返して不安に思うことがあります。
つまるところ、読者の知的水準を自ずから量るような、これは、試金石的な本なのです。
出版されて、およそ半世紀がたっていますが、この本の価値は、すこしも衰えていない。そう断言できます。つい先般、あるポリティカルフィクションの中で、この本の一節を丸ごと書き写した、としか思えぬシーンを見かけました。書き手は新進気鋭(たぶん、ガンダム世代)の冒険小説家で、参考資料にも書名を上げておられたので、おそらく盗用とか剽窃するつもりは微塵もなく、純粋にリスペクトなのでしょうが、丸々、文章を引用するのも、どうか、と思ったものです。しかし、それくらい、つまり、半世紀前の記述が現在でもそのまま通用する。それほどには、普遍的な知が豊富に満載された書であるわけです。
とはいえ、70年当時の私が、いや、現時点での私自身ですら、いささか戸惑うほどには、この本には、いたるところに、読者を選ぶような、難解なタームが頻出します。それはしかし、たとえば同時代の吉本隆明の思想書のように、そこに書かれた哲理と書き方が難解なのではなく、当たり前のように平然と提出されている固有名詞などが、70年当時も今も、多くの日本人には、「ちょっとこの意味が判らない」とか「このなんとかいう人物は誰だっけ」とか「この固有名詞は一体どういう意味なんだろう」と思わせる、そういうトリッキーな罠が、いくつも仕掛けられているからです。
4
隆明の思想書を読んで判らない、というのは、わりと当たり前の話で、著者がわざとそのように書いているからです。隆明の思想が元々ひどく難しい上に書き方や術語も難しい。それゆえ一般読者には、すんなりとは理解できない、であるの対し、「日本人とユダヤ人」が難しい、というのは、単に読者の側に、そのジャンルにおける理解に足る知識がないだけのことが多いのです。だから、それを補っていけば――この本は、実際、三〇〇万部も売れているにも関わらず、その延べ三〇〇万人の読者の大半が、この本の半分も理解できていないだろう、と私は思っているのですが――、それを正すことが可能でしょう。単なる知識の不足は、それを補えばいいだけなのですから。
しかし、「知識を補う」ことは、ただ「知識を増やす」だけでいいかと言うと、そうでもない。今はネットがありますから、判らないことは、検索すれば、昔よりは簡単に出てくるものもあるでしょう。しかし、表面的に理解しても、それが「判った」とは言えないこともあります。背景となる世界の状況やその歴史的な思潮などを理解してはじめて、「判る」ことが、世の中には在るのです。要は、知識と知恵とは違うのだ、と言い換えることもできます。知恵とは、つまり、知識の体系です。個々の知識をいくら沢山知っていても、思想は読み解けない。それは思想とは、そうした知識を秩序だったシステム(体系)の中に組み入れて成り立っているからです。雑学と教養のちがい、と言ってもいいでしょう。
そういう知識の体系を得るには、とにかく本をたくさん読むしかない。それも青春時代の濫読期だけでなく、その姿勢を大人になっても続けることが必要になります(でないと新しいモノやコトに置いてかれてしまうので)。それは本が好きなら、誰でも若い頃は本は読むでしょうが、一生、それを持続するのは困難です。
二十世紀までは、そうした知識体系(=教養)をそなえた人間のことを「知識人(インテリゲンチャ)」と称していました。今や絶滅危惧種です。私の知っている範囲では、大岡昇平氏がそういう知識人の最後の一人だったように思います。氏が晩年に記した日録「成城だより」を読めば、ソシュールから萩尾望都、ポップミュージックや映画にいたるまで幅広いジャンルを的確に押さえている知的好奇心の広さに誰もが一驚するでしょう。今日、このような人はいません。
しかし今や、そればかりではありません。
最初の刊行から現在までの半世紀の間に、私たちが生きてあるこの世界は大きく変動してしまいました。私が十五歳の子供だった頃は、米ソ冷戦の真っただ中にあり、日本では五五年体制と呼ばれる、自民党一強で野党は社会党が最大を誇っている、そういう政治構造が盤石でした。当時は、どちらもこの情況がいつまでも続くのではないか、と思われたものです。
しかし、ご存じのように、その後、ベルリンの壁が崩壊し、東欧に革命が広がり、ついにはソ連がアッサリと解体してしまった。一九一七年のロシア革命から始まるソ連という社会主義帝国は、七〇年保たずして、91年に崩壊したのです。同時に、未来永劫につづくかに思えた鉄壁の米ソ冷戦という世界構造は、まるで砂上の楼閣のように、あっけなく崩れ去りました。他方、中国では毛沢東が文化大革命を推進して、価値の大転換が起きている。ベトナムではいつ終わるか不明な(結局、75年には終わるのですが)今でいう非対称戦争が続いている。世界中が混沌の世紀でした。
世界だけではありません。日本でも、また五五年体制という盤石に思われた政治構造がありました。これは一九五五年(昭和30年)に自由党と日本民主党という二つの保守党が合同し自由民主党を結党して、同時に左右に分裂していた社会党が再統一したことで生まれたことから、そう呼ばれます。
ところが、バブル崩壊後の93年の総選挙では分裂した自民党は大敗し、同時に社会党も惨敗。政局は四分五裂となりました。結果、あれだけ堅牢にみえた自民党政権が無数に分裂し、万年野党のように言われた社会党の隆盛と衰退に際して、連立政党を模索する自民の延命と迷走。さらには社会党系の民主党など多くの新党による政権奪取。ついには分派した自民系新党と社会党などの合意による細川連立政権の樹立。言い換えれば(残存する)自民党初めての下野、という事態になりました。
三八年間つづいた五五年体制もまた、こうして砂のように崩れ去ったのです。
バブル経済崩壊後、つかの間の「いざなみ景気」も過ぎ去り、リーマンショックなど、何度かの経済危機に見舞われた挙げ句、今の若い人たちは「失なわれた二〇年」という不幸な時代を生きています。
私たちが、子供のころに、これは永遠に続くかと思えた冷戦構造と同様、今の若い人たちは、生まれた時から続く、ゼロ金利経済と就職氷河期が永遠につづくように思えるでしょう。
どうしてそうなったか、などと問うことすら空しい。だから問いただすこともしない。つまるところ、原因が判ったところで解決されるべくもないので、判らないまま、放っておかれる。
これでは今、二十代の若い人たちにとっては、たった半世紀前の出来事や情勢が見えなくなってしまっている、と言わざるをえません。というか、関心もないでしょう。選挙権(投票)の年齢を十八歳に引き下げた直後こそ、五〇%を超える投票率=政治的関心が高まったものの、その後は衰退気味です。少子高齢化によってシルバーデモクラシーと呼ばれる高齢者に偏した政治や社会が台頭してきていますから、数では負ける以上、この政治的無関心は当然とも言えます。
そうした状況において、ほんのちょっと前の出来事が、オンリーイエスタディのことであるがゆえに、かえって判りづらくなってしまっている。年表にあっても、実感として理解できない。そういうことが実態として在ります。本を読めば判るとは限らない。歴史の教科書に書かれているからといって、その当時の出来事が肌で感じられるか、というと当然、そうではない。あまりにも近すぎるために、かえって見えづらくなって、要は「判らない」。それが「現代史」なのでしょう。
しかも、これは日本人特有の欠点であり、ある時は長所でもあるとは思うのですが、とにかく物ごとを忘れるのが異様に早い。実に数年前のことがノスタルジーの対象になってしまうほど、忘れっぽいのです。
どれくらい忘れっぽいのか、次の項で見てみましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?