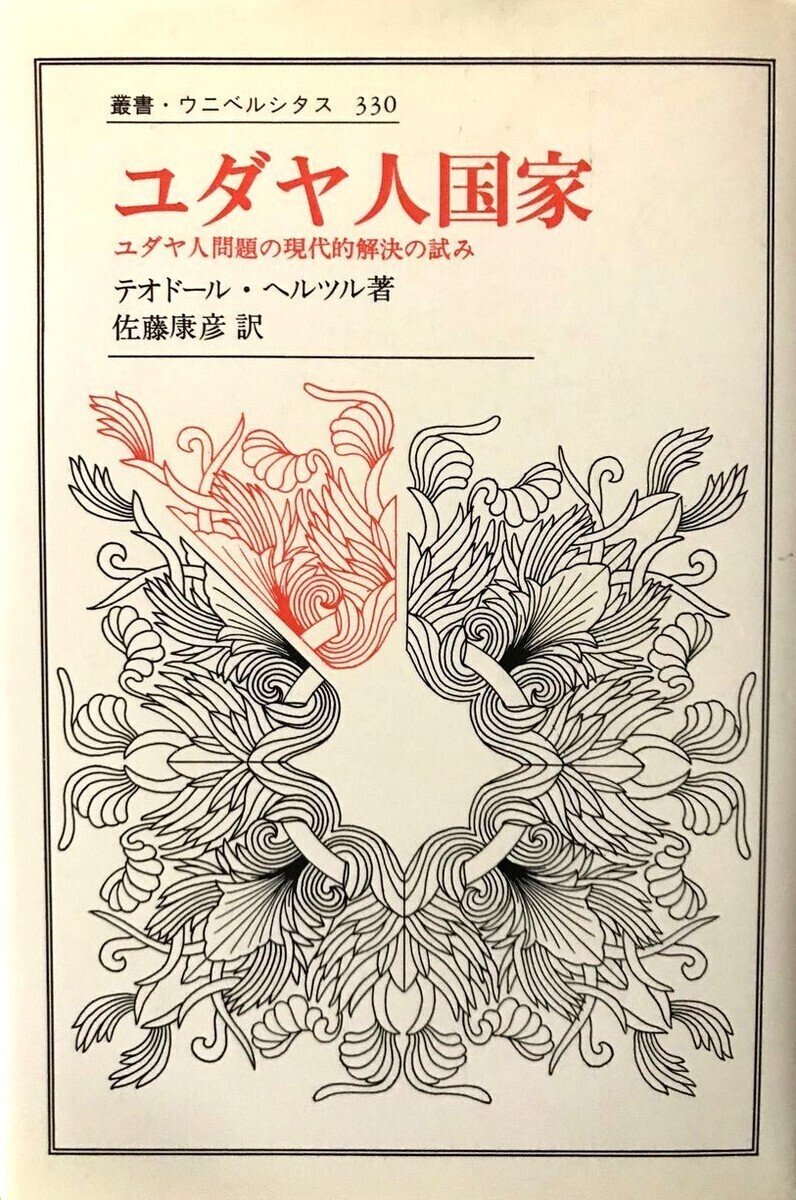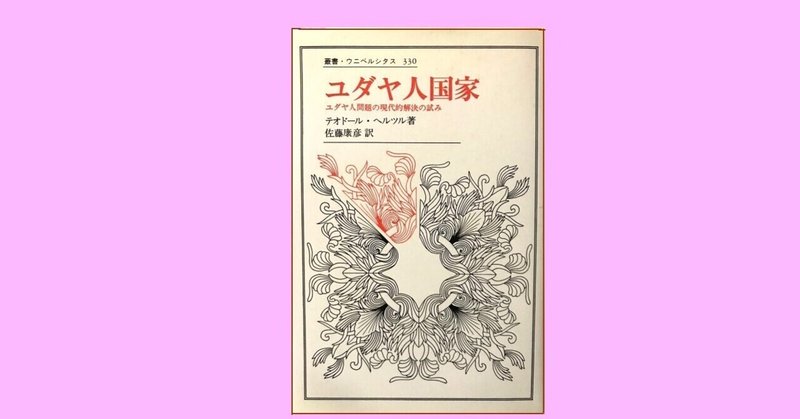
「日本人とユダヤ人」講読
野阿梓
第一講 ヘルツェル
1
まず、「日本人とユダヤ人」全体の構成を目次から見ていきます。
「はじめに
1.安全と自由と水のコスト(隠れ切支丹と隠れユダヤ人)
2.お米が羊・神が四つ足(祭司の務めが非人の仕事)
3.クローノスの牙と首(天の時・地の利・人の和)
4.別荘の民・ハイウェイの民(じゃがたら文と祝砲と西暦)
5.政治天才と政治低能(ゼカリヤの夢と恩田木工)
6.全員一致の審決は無効(サンへドリンの規定と「法外の法」)
7.日本教徒・ユダヤ教徒(ユーダイオスはユーダイオス)
8.再び「日本教徒」について(日本教の体現者の生き方)
9.さらに「日本教徒」について(是非なき関係と水くさい関係)
10.すばらしき誤訳「蒼ざめた馬」(黙示録的世界とムード的世界)
11.処女降誕なき民(血縁の国と召命の国)
12.しのびよる日本人への迫害(ディプロストーンと東京と名誉白人)
13.少々、苦情を!(傷つけたのが目なら目で、歯なら歯で、つぐなえ)
14.プールサイダー(ソロバンの民と数式の民)
15.終りに――三つの詩
あとがき――末期の一票>」
「日本人とユダヤ人」は以上の構成から成っています。
(なお、第二章のサブタイトル内にある差別用語は、七〇年版のもので、違う版では異なっている由ですが、私が所持している版はこれなので、歴史的な学術的引用として、そのままに表記します。これ以外にも、七〇年当時の表記には、現在では、不都合なものが在るかも知れませんが、現時点での観点から原文の改竄は出来かねますので、ご不快ありましたら、不悪、ご了解ください)
これらの中で、当時や今も、私や年若い人たちにとって難解なタームを残らず拾い上げて、それを全部、判りやすく解説する――なんていうことは、とうてい不可能です。ほとんど、私の分だけでも、もの凄く膨大な量になるでしょう。それだけやったとしても、まだ私が理解できていないタームは沢山あるのです。
ですから、そう――各章に一つか二つ程度のキーワードを拾って、それを細かく分析し、解説を加えることで、講読に代えたいと思います。その程度ですら、私にとっては、かなりの重労働です。できるかぎり、今様の若い人たちにも判るように、平易なスタイルを心がけたいと考えていますが、時として、ちょっとヘヴィな内容にまで踏みこまざるを得ないこともあるでしょう。これは、あらかじめご了解ねがいたいと思います。この本は、本当に一筋縄ではいかない。そうそう読み手も楽ができるような本ではないのです。
では、第一章から始めます。(「はじめに」や「扉」には、さしたるキーワードがないため省きます)
これは初回に限り、あらかじめ第一章でのキーワードを予告しておきますと、「テオドール・ヘルツェル」と「イザヤ・ベンダサン(の正体)」の二つです。それぞれ「講読」の第一、第二講に相当します。
冒頭から、七〇年時点で、二〇年以上も昔の話が語られます。つまり一九五〇年より前です。おそらくは、商社マンだった日本人K氏は「貿易再開に備えて渡米した」とあります。そのK氏のお話です。
まず、当時、連合国に負けた日本では連合国代表の米軍に占領・支配されていました。軍のトップであるGHQ(ジェネラルヘッドクォーター)が渡航制限をしていて、敗戦の年である四五年から五二年のサンフランシスコ講和条約(日米和平条約)が発効するまでの七年間にわたり、日本人の海外渡航は制限されていました。
(なお、以下の年代につきましては、特別に意味がある場合をのぞき、原則的に西暦表記に準則し、下二桁で表すことにします。すでに昭和が終わり、平成もすぎた今、昭和歴は、そこに何か格別の意味がない限り、本購では省きますので、よろしくご了解ください)
ただし、その頃からすでに東西冷戦は始まっており、それにともなって、日本は自動的に米国サイドの「西側陣営」に組み込まれました。そこで、四七年(昭和二二年)に疲弊した欧州の復興計画である米のマーシャルプランが発表され、ついで、と言ってはなんですが、日本もそれに準じて、それまで課していた対日経済封鎖を緩和し、制限付きで民間貿易を再開したのです。だから、おそらく、その直前の話だったと思われます。ついでながら、これは貿易従事者など一部の例外規定ですから、普通の日本人がレジャーとしての旅行で渡米する、などといったことは、たとえ渡航費用を捻出する豊かな財力がある人物でさえ、まず、当時は考えられなかった時代です。
2
細かくいえば、GHQによる日本の「占領(Occupied)」は四五年から四七年までです。しかし、実質は、講和条約の発効である五二年まで、連合軍(米軍=GHQ)の支配は続いたわけです。
そうした困難な中、商社マンは、戦後はもとより、戦時中も危険な大陸や南洋へと雄飛し、あるいは馬賊に襲われ、あるいは制海権のない海でボカチン(米軍の潜水艦による魚雷攻撃などで沈没すること)を喰らいながらも、営々たる努力をつづけていました。戦争と商売は別、というか、むしろ戦時下だからこそ、商売は盛んにやる(儲けも大きい)。それは戦争中も敗戦後も同じです。誰も手を付けてないのだから、ハイリスクではあっても、ハイリターンが望める。ならば、とばかりに身の危険を顧みず、K氏のような人が、南洋や大陸ではなくアメリカに渡り、いずれ再開される貿易に備えるための実務にたずさわっていたわけです。
さて、以上のような背景ですが、対日感情が悪化の極みにあった米国はニューヨークで日々、神経をすり減らしたK氏が、唯一、心を休める場所は宿泊していた高級ホテル・アストリアの部屋だけだったそうです。そして隣りの部屋にはユダヤ人家族が住んでいました。宿泊ではなく、ホテルに居住していたのです。そして、次第に仲良くなるにつれて、逆に、いろいろと疑問も出てきた。迫害の歴史は判る。だが、いつまでもホテル住まいをして、(海外に移民として出た多くの日本人のように)現地に溶けこまずにいるのは、むしろデメリットなのではないか。そう思ったK氏がそのことを訊きます。そこで、キーワードの一つ目です。
そのユダヤ人の主人は、「外なるゲットーを出れば、内なるゲットーに入らねばならない」という言葉を口にします。それがどういう意味かは、その時点ではK氏はまるで理解できませんでした。ただ、その言葉は、なにか深く心に残った。そして帰国してから、イザヤ・ベンダサンと出会い、そのことについて訊ねた。それがK氏とベンダサンとの出会いだったそうです。
この出会いの真偽は、この際、問いません。実際にそういうことがあったかどうか、それに対するアンチからの悪意に満ちた批判も私は目にしましたし、対する再反論も目にしています。しかし、ここでは、それらは全て捨象します。キーワードと出来事じたいは、関係ないからです。それに続くフレーズを読めば、「外なる/内なるゲットー」の意味は読んで理解できます。だから何の問題もありません。
そして、これはこの章だけのことではなく、この講読においては、キーワードは単一の用語だけではなく、出来るだけ、その用語を含む前後のフレーズをまとめて切り取ることにします。そうでないと、十全な理解がおぼつかないこと多いだろうからです。該当箇所は、次の通りで、角川文庫版(以下、文庫版)の16頁末尾から17頁にかけてです。できるだけ短く切り取りますと――、
「『内なるゲットーと外なるゲットー』と言ったのはユダヤ人国家の父、テオドール・ヘルツェルである」
さて、テオドール・ヘルツェルとは一体、何者なのでしょうか?
今では、通常のラテン文字表記のカタカナ語化だと「ヘルツル(Herzl)」が多いと思われますが、ここはベンダサンの書いた表記の通りにしておきます。これは、古い表記法とかではなく、実際には、ヘルツェルの生まれたハンガリーや移住したウィーンでのドイツ語表記と、ヘブライ語表記を併せたような折衷的表記が、テオドール・ヘルツェルなので、この表記の方がふさわしいからです。以下の講読でも、できるだけ文庫版の表記を優先し、次に人口に膾炙した表記を心がけるつもりです。ご了承ください。
簡単に言えば、ヘルツェルは近代シオニズムの祖です。イスラエル建国の父でもあります。
私の手もとにある「リーダーズ英和辞典」(第三版二〇一二年)によると――、
「Theodor Herzl (一八六〇―一九〇四)〈ハンガリー生まれのオーストリアの著述家。近代シオニズム運動の創始者〉」
――と短く記されていますが、七〇年当時に、どれだけの日本人が彼の名を知っていたか、判りません。当時、私は初耳でした。まあ、十五歳の高校生は基準にならないとしても、しかし大半の日本人にとっても、あまりなじみはなかったのではないでしょうか。
彼が記した「ユダヤ人国家」(原著はドイツ語で「Der Judenstaat」) 法政大学出版局 九一年刊」(※1)によって、それまで祖国なき民族だったユダヤ人は、初めて具体的なユダヤ人自身による建国のプログラムを掴んだのです。
※1 https://www.amazon.co.jp/dp/4588099469
なお、シオニズムの元となった「シオン(Zion=英語では、ザイオン)」というのは、古代ユダヤ王国の地名であり、ソロモン王時代の神殿の丘の別名として名高い名前です。神殿が破壊され、祖国が滅び、流亡の民となったユダヤ人にとって、聖なる地名であり、いつの日にかここに帰ってこよう、という細い希望の光でした。文庫版六五頁に「シオンを慕いて涙流しぬ」とある通り、その名は国を喪なった全ユダヤ人の新生イスラエル建国の象徴であったのです。
3
七九年のアニメ「機動戦士ガンダム」に「ジオン公国」という宇宙コロニー国家が仇役で登場しますが、おそらく、これに由来するものでしょう。もっともアニメでは、別にジオンの国民はユダヤとは全く関係ない上に、逆にジオン公国軍はほぼナチスドイツそのままの顔立ちでしたので、いわば敵味方を足して二で割ったような凄い設定です。おそらくジオンの名は単に語呂が良かったので採用したもの、と思われます。
しかしながら、日本では、こうした野放図な設定でも誰も文句は言いませんが、欧米ではそうはいかないでしょう。映画「マトリックス」シリーズ(九九―〇三年)でも、地下都市「ザイオン」は特別な意味を持つ聖地であり、地底に潜みレジスタンスを続ける人間たちの最後の砦の名だったことを思い出してください。すなわち、聖書を読む民(クリスチャンならびにユダヤ人)にとっては、語呂が良いから、という理由以上の意味が、この地名には有るのです。特に、シオニスト、とかシオニズム、といった用語になると、イスラエルの敵勢力には全く異なる政治的意味合いを帯びますので、注意が必要です。アニメの設定をどうこう言うつもりはありませんが、言葉には力があります。それだけに使うには留意が必要で、安易な用法は危険です。
これから転じて、シオンの丘はユダヤ人の国家の象徴となったわけです。その名を冠したシオニズム、という思潮と運動とは、古代に失なわれた祖国を奪還し、いつの日か、約束の地へ還る。出来れば、イスラエルの地=パレスチナに自分たちの国家を建設しよう、という数千年にわたる文化的ムーブメントでした。常に民族意識の強いユダヤ人にとって(むろん、そうではない穏和派のユダヤ人もいるのですが)、熱狂するにたる民族意識発揚の思想の源泉です。
しかしながら、ヘルツェル以前のシオニズム運動は、なんら具体性を欠いたもので、実現可能なプログラムではなかったのです。今、現代に生きる私たちの目で「ユダヤ人国家」を読むと、かなりの国際的な無知と無神経な倨傲と、冷徹な現実を無視し大ざっぱな楽観主義のように思えるのですが、それでも、驚くべきことに、ディアスポラ(民族離散・放浪)から数千年たっても、ヘルツェルがこれを記すまでは、こうした初歩的な啓蒙文書さえ、一つもなかったのが現実でした。
これに関しては、本書の後半で、このように書かれています。文庫版、第五章「政治天才と政治低能」です。
「ユダヤ人は、契約が先に来るから、まず既得権を作りあげるという離れ業ができない。これのごく初歩がかろうじて出来たのがヘルツェルであり、その時やっと、イスラエル共和国が約束されたのである」(九五頁)
現時点で、パレスチナ紛争の渦中にあり、公然の噂として核保有国でもあるだろう軍事国家イスラエルを知っている私たちは、十九世紀末の国際状況が判りません。七〇年当時でさえ、たった6日間の電撃戦で終結したため、「六日戦争」とも呼ばれる六七年の第三次中東紛争のすぐ後で、パレスチナ問題は、最大の被害者であるパレスチナ難民を置き去りに、米ソ冷戦構造の代理戦争の様相を呈していましたので、日本では左翼勢力がイスラエルに対して批判的でしたが、実態や全貌を掴んでの批判ではなかったのです。さらに、ナチスのユダヤ人大量虐殺の記憶はまだ残っていて、迫害された民族が、やっと祖国を取りもどした、という「物語」が幻影となって、現実を掩い隠していたきらいもありました。それゆえ、どうしてイスラエルが建国されたか、といった大元の議論は忘れ去られていたように思います。
しかし、こうした記述を読むと、どうやら、ヘルツェルの書なくしては、当時のシオニスト(熱烈なユダヤ人の民族主義者)でさえ、建国は不可能だったようです。
また映画の話で、しかも私は、それを小屋で観たわけではないので、すみませんが、七〇年代初頭にTVで放映された「栄光への脱出(原題英語: Exodus)」という映画を思い出します。六〇年公開の作品で、当時子供だった私は映画館では見るべくもなく、確か七二年に「日曜洋画劇場」で(元のフィルムが三時間を超えた、おそろしく長尺だったため)、放送枠をオーバーして放映されたのを見たように記憶します。二週に分けたのかも知れませんが、よく憶えていません。とにかく長く、ひどく喉が渇く内容でした。
この作品は、監督のオットー・プレミンジャーや主役のポール・ニューマンを始め、主要陣をユダヤ系で固め、英国委任統治時代から、不法移民船を無理やりパレスチナに輸送するなど、ハリウッドの(お金が取れる)問題児プレミンジャーならばこその、活劇をふんだんに活かした、露骨なまでのイスラエル翼賛映画でした。
しかし、そういうことは、当時、二度目か三度目の高一だった(私は、不眠症で二度留年しています)私には、そこまでは判りませんでした。いかに往年のハリウッドがユダヤ人支配が強かったにせよ(都市伝説のように囁かれるこの話は、二〇世紀初頭に創業したハリウッドを代表する主要な映画会社の創立者が全てユダヤ系であることから、ほとんど事実だと言ってもいいでしょう)、あまりにも明らさまなイスラエル擁護作品だったのです。しかも作劇上、とても巧妙な。
たとえば、軍事組織ハガナーに属する主人公の父は、敬虔なユダヤ教徒で穏健派で、先住のアラブ人との共存を願っているなど、宥和政策の体現者です。しかし、彼の弟はパレスチナ人と徹底抗戦を叫び、英国統治時代からのユダヤ人軍事組織ハガナーから分離独立した過激軍事組織イルグン(エツェル)のリーダーで、兄弟は義絶しています。主人公は仲立ちとなって兄弟の共闘を持ちかけるのですが、ついに彼の父と叔父の兄弟が和することはなく、その後、叔父は独立前に英軍に捕らえられ、射殺されてしまいます。
この挿話は後述の話を勘案すると、元々ハガナーから派生して分裂したイルグンの排除に理由づけを与えたようにも受け取れます。また、キプロスに抑留された不法移民船エクソダス号をパレスチナに回航させるべく、主人公は活動するのですが、この船の処遇に際して、過剰に同情的な英国の将軍がいたりなど、今にして思えば、あまり現実には有りそうにない設定が目立ちます。
なお、分裂したイルグンとハガナーですが、前者の出身者としては、皮肉なことにサダト大統領と歴史的握手を交わしたベギン首相がいます。彼はイルグン時代に、デイル・ヤシン作戦の指揮者だったと言いますから、歴史は判らないものです。後者の出身者としては、ラビン首相、隻眼の将軍ダヤン、また右派からシャロン首相などがいます。第二次大戦が始まった三九年には、ハガナーは二千名規模でしたが、ほぼ十年後の四八年、第一次中東戦争の直前までに、世界各地からの義勇兵(元大戦中の将官が多数参加)によって七万五千人規模になっていたと言います。開戦と同時にハガナーが主体となってアラブ連合軍と交戦に入ります。停戦期間中に、ようやくイルグン残党なども含めたイスラエル国防軍が創設され、主体としてハガナーも、この軍内に再編されました。
4
それはさておき――、
イスラエル建国時の内紛において、イルグンは、ハガナーと指揮系統を統一すべく命令され、それに抗命したため、ハガナーによって制圧され、少なからぬ人間が粛清されました。しかし、後年、指揮系統の統一だけが理由ではない、さまざまなイスラエル上層部の策謀が暴露されました。その中の一つにイルグンの評判を決定的に落とした「デイル・ヤシン事件」があります。
これは建国寸前の時点で、イルグンがエルサレムに近いアラブ人の村デイル・ヤシンを襲って百名から二百名の村民を虐殺した、というものです(人数には諸説あります)。これは、確かにイルグンが関与した、弁解の余地のない非武装民間人の大量殺戮事件なのですが、これによって恐慌をきたしたアラブ人が数十万単位で難民化し、ヨルダンなどに流れました。地図を見れば一目瞭然、死海をはさんでイスラエルのすぐ隣りがヨルダンであり、しかもエルサレムは死海のすぐ近くですから、そこで何か起きたら、それは周辺のアラブ系住民は、ヨルダンへ逃れるでしょう。
しかも、「デイル・ヤシン事件」の本当の狙いはそこにあり、イスラエルからアラブ人を大量に排斥するために起こした、というのです。イルグンの残虐行為は初代のイスラエル首相ベングリオンも承知していた、と言われています。彼はイルグンを非難し、ヨルダン国王に謝罪しているのですが、それもまた偽装工作の一環だったことになります。
また、実は、同様の作戦にはハガナーも協力しており、デイル・ヤシン事件以外にも、おびただしい数の村落において、無数の民間人の殺戮やレイプを起こして、アラブ人のパニックを煽り、結果的に、その地のアラブ人たちが難民化して出国するよう誘導した、と言われています。故意に難民を作り出して、その空いた土地に移民で増加したユダヤ人を入植させる、という悪辣な政策による作戦だったわけです。
映画「栄光への脱出」には、(当然ながら)そういう闇の部分は描かれておらず、ハガナーは、あくまでも主人公の敬虔主義的な父親が体現するパレスチナ人との宥和を心がけている、といった立場でした。原作小説には、反英、反アラブ主義がより濃く滲んでいたそうですが、プレミンジャーは全くの娯楽作品としても通用する、しかしつい最近の(中東戦争に関しては、継続中の)題材を映画化したことになります。それなりにリアリスティックでした。
今でも私は、その場面を憶えているのですが――かねてからゲイの噂があった――サル・ミネオ扮する少年兵が、イルグンに入隊するシーンでは、どうやってナチの強制収容所から生きのびたか、査問されるのですが、美少年だった彼が苦悶の表情で「彼らは自分を女として扱った(つまり生きのびるためにナチ将校らの稚児となった)」と自白するシーンは、TVで見た映画は印象が薄くなるのが常なのですが、私は鮮明に記憶しています。一緒にTVを見ていた父が、「地下組織での入党には、こうした自己批判をまずやらせるのが常識だ」といったことを述べたのも憶えています。私の父は、戦後、一時期、共産党に入党していたことがあり、レッドパージ以後の非合法時代も知っていたのです(組織内にスパイが入っているのが明白な時期に、上部から党員名簿を提出しろ、という理不尽な命令が来て、キャップとして、全員逮捕されて沖縄送りになるからダメだ、と抗命したら党籍を「除名」されたそうです)。
そういう家庭内の空気の思い出もふくめて、私には、「栄光への脱出」は、印象深い映画でしたが、当時は、赤狩りで追放されたはずのドルトン・トランボを脚本に起用したプレミンジャー監督の演出手腕もあってか、私にはリアルな現代劇を描きつつも、欧米ではない荒々しいイスラエルの土地を舞台の明るい娯楽大作、というふうに思えたものです。まあ、ものを知らない高校生だから、仕方ありません。今の時点からもう一度、見直せば、さすがに、そういう風に見ることは不可能でしょう。
しかし、こうした(ハリウッド・ジューのバックアップあっての)イスラエル翼賛映画が作られるには、まず、「ユダヤ人国家」が何としても独立国として建国されねばならなかったのだし、それには、ヘルツェルの書が必要不可欠に重要な働きをしたのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?