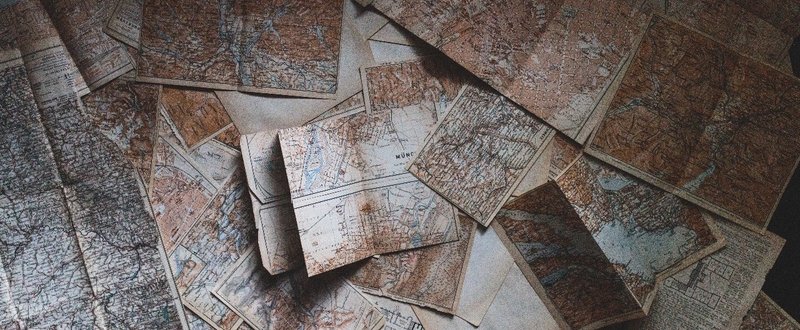
「出来る!」人になるための「言語化」メモ
これらを読んでどう考えるか/感じるかはそれぞれのご判断にお任せします。
私自身共感か同意するかはよく解りませんが、少なくとも、これらの発言に「刺激を受ける」のでまとめてみました。
「おぬし、出来るな!」
と、言ってもらうためにはやはりアウトプット/言語化が大事だということ。
「ブログを半年、毎日書き続けて気付いたこと」榊原(@ms_rebirthink)http://rebirthink.jp/archives/1870
インプットした情報が
頭をぐるぐる回って、アウトプットの形になるまでの
時間がどれぐらいかによって決まるんですけど、
この長さは訓練次第でどうにでもなる。
ブログって考えながら書けるから、
最初は遅くてもいいんですよ。
あとで追記・編集していてもいいし。
ポイントは、自分が感じたこと、思っていることを
言語化する訓練を続けていれば、
インプットとアウトプットのタイムラグが短くなるということです。
タイムラグが短くなるのは大きい。
私も「書きたいことは沢山ある」で書きましたが、頭で思い浮かんだことに対して「書く」ことが追い付かないですし、インプット量を増やせば増やすほど、アウトプットする上でごちゃごちゃして引っかかってくる。
上記の方法が優れているのは、素早くアウトプット、形にしていくことで、その混乱や渋滞を防ぎ、「鉄は熱いうちに打て」を実現しやすくなるだろうと考える。
また、トレーニングでも、教わった瞬間にただ見て頷いている/メモをとることより、身体を動かし、実践していく方が早く身に付くことは間違いない。
ただただ思い浮かべているだけでは人に伝わりませんし、自分でも漠然としたモノでしかないでしょう。
言語化しただけでは足りず、次は「記事化」することで、しっかりとした体型だったものが誕生していきます。
囲碁でも出てくる「言語化」。
ちなみに、囲碁には格言でも「上手」「下手」と表現し、単純に「上手=段級位が上」「下手=段級位が下」を指す場合も多いです。
教育などでもよく言われる「教えることでむしろ自分の学びにもなる」と通じる考えでもあるのですが、自分より上手でない人と打つことで、確かに実戦では学ぶことは少ないかもしれませんが、感想戦などで「言語化」していくと、学びが随分変わっていきます。
その勝負を分けたのはどこなのか?
ここをしっかり「言語化」すると良いですね。
ここから古いですが、自分の過去ツイートより。
「言語化」出来る領域とし難い領域に付いてツイートしています。
そして、その「し難い」領域を言語化するためにはどうするか?
羽生さんの著書にある、「深い理解と洞察」が必要になるんですよね。
結び
タイトルにある「出来る人」の定義は多くあり、それそのものを論じるにはこの本稿の趣旨から外れるので今回はしません。
「出来る人」になるために、先ずは「言語化」することが大きな構成要素の一つ、成長する為の方法と言えると思います。
その理由についても順を追ってまとめていったと考えます。
もちろん、流れを追っただけで、深く論じている訳ではないので、不足感はありますが、流れを追うためにはその不足感には目をつぶり、「流れ」だけを着目していって欲しいと思います。
少しでも成長/出来る人になっていけるよう、参考になれば幸いです。
ご相談、執筆/教室/講演/講習等のご依頼はこちらから。
神屋伸行:フェイスブックページ
ヘッダー画像はBeautiful Free images|Unsplashさんよりお借りしました。
いつもご訪問、お読み頂きありがとうございます。 すき(ハートマーク)を押して頂いたり、コメントやSNS等にシェア、サポート頂けると励みになります。サポート、応援頂いた分は必ず、活動する中でみなさんにお返しして行くことが出来ると思います。今後もお付き合いを宜しくお願い致します。
