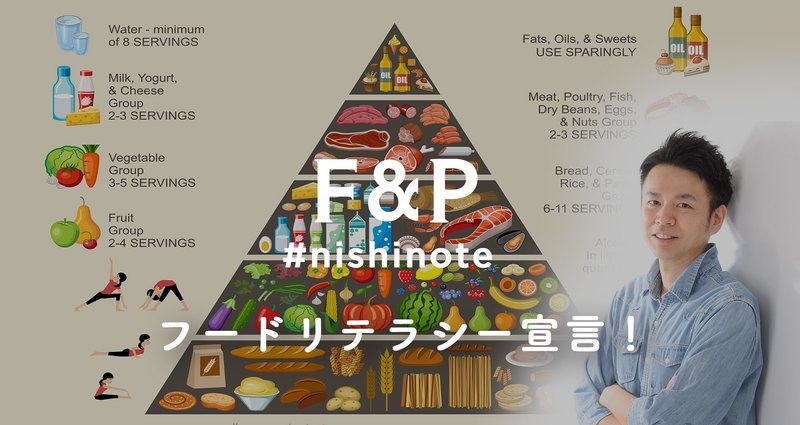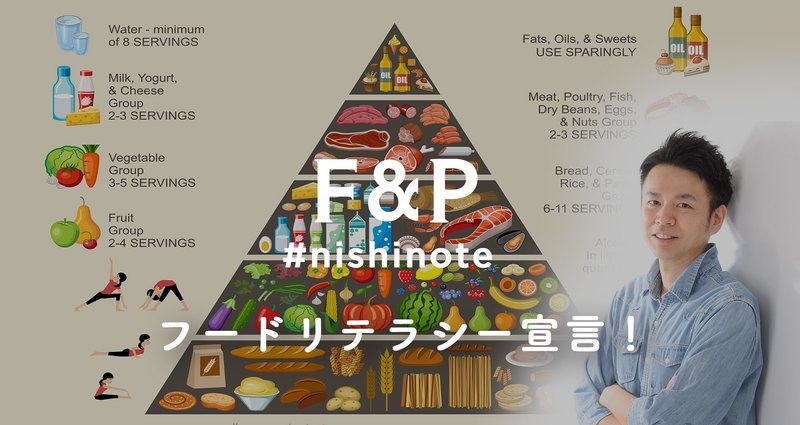先進諸国と日本の食意識格差
ここに、「日本人の食意識」を示す興味深いデータがあります。
1934年に非営利団体として設立された国際的なデータ・マーケティング機関である「GfK」は、2014年に17カ国 23,000名のインターネットユーザーに対し、身体の健康を保つために日常的にどのようなことを行っているかを尋ね、その調査結果を発表しました。
グローバル (17カ国計) の結果をみると、「十分な睡眠をとる」が65%、「健康的な(栄養のある)食事をする」が58%、「運動をする」が59% だったのに対し、