
イマーシブシアターと自由
先日、イマーシブシアターの魅力について語るnoteを書いた。
この世界に少しでも多くの人が出会ってほしいという願いを込めて、自分が思うイマーシブシアター世界の魅力を7つに分けて、自分なりに言葉を尽くして紹介した。
このnoteを書く作業は楽しかった。自分の中の熱い思いを取り出して眺めながら、誰かに届くようにと言葉を与えて整理して記していくのは楽しい。大好きな作り手や作品たちのことも例として紹介できたのも嬉しかった。
楽しく書き進めながら、しかし同時に、誰かにおすすめするための言葉だけではなくて、自分にとってのイマーシブシアターって何なのだろう、どうしてイマーシブシアターの世界にこんなにも心惹かれるのだろう、ということをもう少し突き詰めて言語化できないものか……ということも考えていた。
もちろんnoteに書いた魅力たちも確実に自分にとってのイマーシブシアターなのだけど、じゃあどうしてそれらを「魅力的」だと感じるのか。「たしかにそれは面白いだろうね」と一見してわかる部分だけでなく、水面下に隠れて見えない部分をもっと掘り下げたい。
個々の作品や体験の素晴らしさはもちろんありつつも、そこには何となくイマーシブシアターに通底する思想というか、原理というか、核のようなものがある気がしてならない。だからこそ、特定の作り手というよりも(もちろん特に好きな作り手はいくつかあるけれど)、「イマーシブシアター」そのものにどうしようもなく惹かれている自分がいるのだと思う。その核のようなものにもう少しだけスポットライトを当ててみたい。そういう気持ちがあった。

その後、たまたま人に薦められて読んだ、観劇や芸術やエンタメとはおよそ関係のないある本が、自分に言語化のための補助線を与えてくれた。
その補助線とは、「自由」。
拍子抜けするくらいありふれていて抽象的で、でもすこぶる大切なこの概念を、今になって自分の中で180度、と言ってもいいくらい大きく捉え直すきっかけを、この本がくれたのである。
そしてそれが、「自分にとってのイマーシブシアターの核のようなもの」に通じていると気づいた。
このnoteではそのことについて書きたいと思う。
ひたすらに自分の内面的な思考の話だし、抽象的なことも多いのでうまく伝わるかもわからないけれど、もし興味のある方がいたらお付き合いいただければと思います。
---
ふたつの「自由」
2024年春に自分が出会ったのは、本当にざっくりと言えば、人類社会の現在と未来について世界的な経済社会理論家が論じた本だった。
地球や自然を人類に適応させようとしてきたこれまでのシステムには明らかに限界が来ている。これからは逆に、人類が地球に適応するように、発想を変えていく必要があるのではないか。
人類と地球の関係についての発想を変えるとは大仰な話に聞こえるかもしれないけれど、身近なところでは私やあなたの身体一つとってもそうだ。
たとえば我々人間は、一人一人誰にも侵されることのない確固とした主体、「自己完結型の自分だけの島」であるという前提のもとに生きている。でも、自分の身体だと思っているものも、実はたくさんの微生物との共生の場になっているし、身体を構成している細胞組織は、実は何年かごとにすっかり入れ替わっていたりする。

そういうふうに、人間も他の生き物や有機物無機物と同じように、地球の生物圏に組み込まれていて、さまざまな相互作用のつながりの中で存在している。このことを出発点として社会を組み直していく時代が来ているのではないか。
普段はあまり読まないタイプの本だったのだけれど、多かれ少なかれこの本が問題としているような危機感や違和感は自分も持っていたから、とても共感しながら読んだ。
さて、この本の中には、「自由」という概念の変化についても書かれている。
地球を人間に適応させようとしてきたこれまでの時代、技術や経済の発展こそが正義であり、そのためには地球を使い尽くすことも厭わなかった、いわゆる「進歩の時代」、自由とは以下のようなものだった。本書に登場する言葉ではないが、仮に「オールドタイプの自由観」としておく。
◾️オールドタイプの自由観
まず、自立した個人がいる。
自立した、自律的な個人は、生まれながらに自由である。
他人からinterfereされることなく、望む選択を行い、望む行動を取り、望む生き方をすることができる。
ただし、その自由が他者の自由とぶつかり合う場合がある。その場合には調整が必要となる。
とりわけ多数の他者の利益、すなわち公共の福祉に反する場合、自由は制限されることがある。
この限りにおいて、個人の自由は保障される。
ふむふむ、まあそうですよね、という感じではないだろうか。少なくとも自分はそうだった。
しかし、この自由の概念、今の若い人たちの一部の中では、変わりつつある、これからも変わっていく、とこの本は言う。
どう変わっているのか。
生まれた時からインターネットに囲まれて育った若者たちにとって、最も自由が奪われた状態とは何かというと、「インターネットにアクセスできない」ことである。自分だけがSNSに接続できないという状態に陥った場合、それはまさに致命的な不自由である。
つまりこれからの時代においては、世界のすべてにアクセスできること、瞬間ごとに世界に参加すること、これこそが自由である。
そしてこの自由とは包摂の原理に基づくものである。
これを読んだ時、目から鱗が落ちた。
それまで当然のように教わり、当然のように自分のものとしていた自由の概念というのは、まさにこの前者のオールドタイプの自由観だったからである。そしてその自由観に対する違和感が、年齢とともに大きくなってきていたからである。
一人の人間として、生まれながらにして自由であり、誰にも奪われない自由を持っている。他人に迷惑をかけない範囲で、他人を害さない範囲でその権利を行使することができる。
フランス人権宣言が言うように、「自由とは他人を害さない全てのことをなし得ることである」。
これは今までこの社会の中で少なからぬ年数を生きてきた自分にとって、当然のように、生きるための根本を為す大事な考え方のひとつだったように思う。
ただ、大きくなるにつれ、「他人を害さない範囲で」というのがいかに難しいかということを知る。自分が「これは他人を害さないだろう」と思う範囲のことをしていればいいわけではまったくない。様々な人がいて、育ってきた環境、持っている性質、過去の傷、考え方や価値観、当然ながら一人一人が違っている。自分という一人の人間には想像の及ばないものもある。自分にとって何も問題のないことが、ある人には大きな刃になったりする。
それでも最大限に注意を払い、害さないように気をつける。無知は怖い。いろんなことを知ろうとする。想像しようとする。すべてを想像することはできない。誰かを害さないで自由を実現することは、この世に生きている限り不可能なのではないか……。
そうしているうちに、恥ずかしながら、何となく「自分の自由がすごく狭まっている」ように感じる。自由ってけっこう小さい範囲のものなんだなあと思うようになる。しょうがないのだとわかりながら、幼い頃の自分は、自由という言葉に対してもっとのびのびと翼を広げるようなイメージをしていたことを思い出す。
思い出しながらも、こっちの道で正しいはずだと、細心の注意を払って自由の行使をする。自由と自由は衝突し合う。
平等ではない社会の中で、それでも平等を実現するためには、個人の自由は制限される。
それでいいのだ。それがあるべき社会。自由と平等は両立しにくいものなのだ。とずっと思っていた。
自由という概念に対するモヤりとしたものを抱えながら、それでも正しい道は絶対にこっちだ、と頭で考えて、理性的に無意識の「我慢」をするような態度で、ずっと生きてきた。
ちょっと考えればわかることだけれど、そういう無意識の「我慢」は、「我慢」である限り、抑えきれずに表出してしまうことがある。自分が安定している時には理性で難なく抑えきれていたものが、何かの拍子に自分の中のバランスが崩れると表に出てきてしまう。
まったく持続可能ではない、問題だらけの認識だということはわかっていながら、かと言って他に「自由」をうまく取り扱うことのできる考え方を持てていなかった。この「我慢」をもっと自然にできるようになることが重要で、もっと我欲を捨てたり、逆に利他の精神を持ったり、そういうふうに自分を律していくことが必要なのだと考えてそう試みていた。
また、そこから派生して、自由意志と自己責任というものに関する違和感もあった。
自律的な責任ある個人が持つ権利が「自由」なのだとしたら、その人の持つ自由な意志でもって自由に選択したことには、その人自身が責任を負うべきだ、という発想が出てくる。むしろ他の人が関わるべきではないと。
あなたが自由に選択したことなのだから。私は関係ないと。
でも、真に自由な選択ができる人なんて実は限られた幸運な人だけだし、自分が自由な選択をしていると思っていても、周りの様々な環境や、少なくとも育ってきた環境から完全に自由な人なんていない。大きくなるとそういうことがよくわかってくる。そう考えると、独立した自分だけの自由な選択なんて、「自由意志」なんて、存在しないのではないか。自由意志が存在しないのなら、自己責任だって幻想なのではないか。
「自己責任」という思想の持つ危険な側面は、個人主義の現代社会の中で無視できないほど大きくなっている。「自己責任」は都合良く利用され、本来担うべき責任から逃げおおせるための、助けを求める人たちを放っておくための、格好の口実になる。実際に社会の至る所でそうなっている。
自由意志も、そこから自然発生する自己責任も、どうにもおかしい。賛同できない。でも同時に、自由は不可欠だ。この矛盾のようなものをどうすればいいのだろう。整理をつけることを長らく留保したまま今に至っていた。
こうした無理や違和感が生じていたのは、そもそものオールドタイプの自由観では自由の捉え方に無理があるからなのだと、あの本を読んで気付かされた。
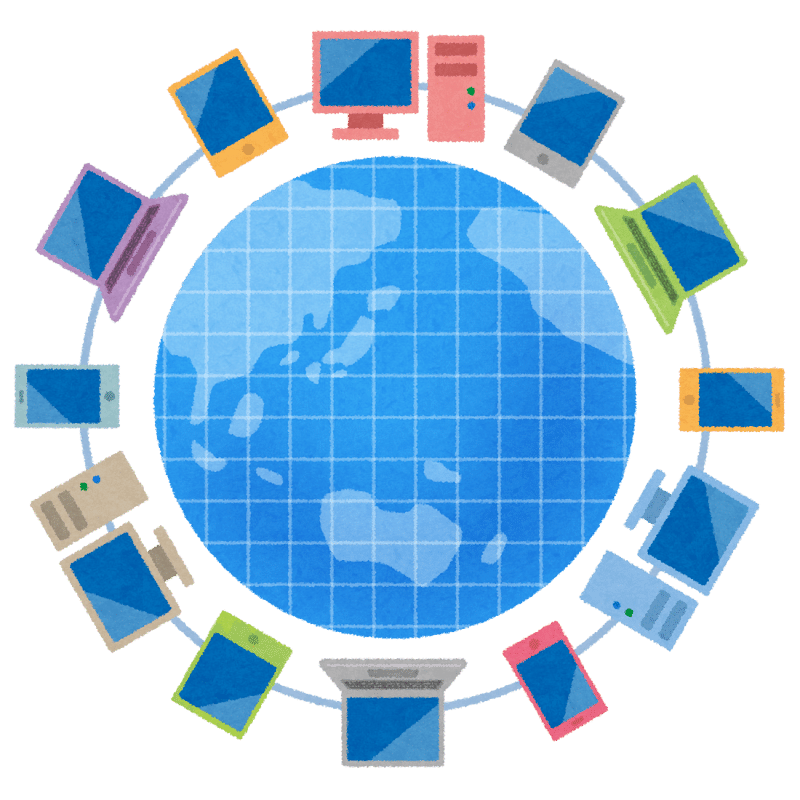
新しいタイプの自由観を、これもここでの造語で「ニュータイプの自由観」と呼んでおく。ロボットアニメとは関係ない。改めて自分の理解を説明すると、以下のようになる。
◾️ニュータイプの自由観
個人とは、世界の中で他の存在と共生し、関係性の中で存在するものである。したがって自由とは、そもそも排他的な、自律的な個人なるものに立脚するのではない。
自由とは、膨大な時間、生々流転する膨大な関係性の中で、個々人がそれらに「「包摂されている」」という状態、そのように感じられることからこそ始まるものである。
若者たちにとってインターネットへアクセスできるか否かが死活問題であるように、包摂されている世界に対して開かれていること。言い換えれば、瞬間ごとに世界に参加しているという実感を伴えることそれ自体が、自由である。
これはややもすれば全体主義的に見えるかもしれないが、そうではない。何か特定の主体のために参加すること、つまり何かを頂点とする垂直な構造のもとに組み込まれることは、ここでいう参加ではない。特定の主体ではなく、あらゆる水平的な関係性の中に自然に存在していること。
それぞれの存在が世界に包摂されていること。自由意志かどうかは問題なく、というか、真の自由意志というものはなく、自律していると思っている個人も時間や空間の関係性に規定されて存在している。こうした前提から出発し、そのような個人同士を尊重し合っている状態。それが自由。
この前提に立てば、「私の自由とあなたの自由がぶつかり合う」「ぶつかり合うときに自由は制限される」というような発想自体が成立し得ない。そのようにして自由を表現すること自体ができなくなる。
なぜなら、それぞれの存在(というのも様々な関係性に規定されるあやふやなものだが)が世界に包摂されている状態こそが自由であるから。自由は決してゼロサムゲームなのではなく、包摂によって如何様にも形を変える、世界に満ちている気体のようなもの。個人個人が「持っている」、質量や大きさを伴った何かではないから、「ぶつかり合う」とか「制限する」というような言葉では表現できない。
この(自分にとっては)新しい自由の解釈を手に入れたとき、色々な違和感が一気に氷解するのを感じた。そうやって考えていいんだ…!と、霧が晴れるようだった。
同時に、自然とイマーシブシアターのことを考えていた。
補足:言葉と表象について
自由という言葉にふたつの意味があり得るなんておかしい、と思われるかもしれない。
でもよく考えてみると、言葉というのはそもそも権力的な装置である。「これこれの状態をAという言葉で呼ぼう」という取り決め(表象)がなされた瞬間に、これこれの状態はAに固定される。
表象はたくさんの人間が共通言語を持ってコミュニケーションを取るためには非常に便利な装置だけれど、その過程で削ぎ落とされるものも多い。大切な人が亡くなったとき、一般的に人は「悲しむ」とされている。おおむね同じような悲しみが想定されて「大切な人が亡くなった悲しみ」という表象が使われる。でも実際に大切な人が亡くなった悲しみ(「大切な人」というのも表象だ)を目の前にしたとき、それが他の人の感じるそれと同じものだなんてどうして言えるだろう?果たしてそれを同じ言葉で括ることなどできるのだろうか?
このように、言葉による表象は、本来便宜的に行われているものにすぎない。端的に表現されるときほど、削ぎ落とされているものは多い。蛇足だが、自分が心揺さぶられるものに出会ったときに長文を書いてしまうのには、このことが関係している。
翻って「自由」という言葉は同じように、本来広範な意味を含み込み得るかもしれないものを、あえてオールドタイプの自由のみに限定して(教育や社会で)これまで使用されてきた、という見方ができる。
だからこそ、自分(たち)はこれを自由と呼ぶのだ、と宣言することには何ら不都合はないし、むしろ大きな意味があると思う。
イマーシブシアターと自由
「現実世界を飛び出して、物語世界の一部になる」。
これがイマーシブシアターの根源であり、世界の深みに降りて行くための切符のようなものだと、件のnoteでは書いた。
イマーシブシアターでは、物語の世界がまるで現実に存在するかのように空間が作られ、その中を登場人物たちがまるで現実に存在するかのように行き来する。そして自分自身も、その世界の中で半ば自由に動き回り、登場人物たちや世界自体と相互にやりとりをする。
自分もその世界の一員になる。瞬間ごとに世界に参加している。イマーシブシアターという形式自体が、その場にいる全員の「参加」を前提としている。
ただ「参加」というだけならば、割合多くのコンテンツに当てはまるかもしれない。「参加型」と呼ばれる体験を提供するものも増えてきた。自分もいくつか参加してみたことがある。
でも「参加」を謳っていても、「参加」を前提としていても、本当の意味で全員が参加している場合というのはそう多くはない。
たとえば、角が立たないようにエンターテイメントから離れて「飲み会」を例にとると、飲み会に「参加」しているはずなのに、なんだか疎外感を感じるとか、つまらない、帰りたい、と思った経験はわりと多くの人にあるのではないだろうか。
なぜそういうことが起こるのかと言えば、これは個人的な考えだが、「自分はここに参加している」という実感は、その世界・場所から自分が包摂され、尊重されているという実感とともにあるものだから、だと思う。ある種の飲み会は、一部の参加者以外のそういうものを犠牲にして、成り立つ場合がある。

翻ってイマーシブシアターでは、「自分はこの世界に参加している・属している」という感覚が非常に強い。と、少なくとも個人的には感じる。
もちろん作品や周りの様子やその日の体調や、いろいろな要素によって変わりはするけれども、時には現実世界以上の強さで、その世界に属しているという感覚を抱く。
この要因になりうるイマーシブシアターの特徴としては、
・作品の多くが非日常的であること
・限られた空間の中に世界観が凝縮されていること
・登場人物と同じ目線で世界を見られること
・少人数であること
・演者が観客を巻き込む力
・他の人たちと視線が合うということ
・世界に対して働きかけられること
などなど、いくつも考えられそうではある。
でも最も重要なことは、「一人一人がその世界の中で過不足なく存在を認められている」ということだと思う。
目の前で悩み喜び悲しむ登場人物たちに、一人一人が寄り添い、対等に視線を交わし、コミュニケーションを取る。誰に寄り添ってもいい。寄り添わなくてもいい。登場人物たちは、言葉がなくとも、視線で自分の存在を肯定してくれる。存在が許されている。私たちは、ありのままの状態で、その世界の中に居場所がある。
もう少し言えば、「他でもない私がそこにいたからこそ」登場人物にこういう感情が芽生えた、世界がこのように変わった、ということが起こりうるのが、イマーシブシアターだと思っている。
このことについては、先のnoteでちょっとうまくまとめられた気がするので引用する。
発話や行動や目線を通じて世界に干渉する時、あなたは世界から一人の存在として認識されています。そこでは、今まで「見る」だけの存在だったあなたは「見られる」存在にもなっていて、「見る」と「見られる」がフラットになります。
世界の一部であるあなたは、今や世界から認識され、世界に影響を与えることができる。その時、他の誰でもない「あなただから」世界はこう変わった、他の誰でもない「あなたにこそ」呼びかけている、ということが起こります。
あなただけが見た景色から紡ぎ出されたあなただけの物語は、世界の側からの「あなただから」「あなたにこそ」という呼びかけにも彩られるのです。
「あなただけの」「あなただから」「あなたにこそ」という個別性は、どうしようもなく本名のあなた、生身のあなたと結びついていて、現実世界に戻ってからも胸の奥でじんわりと脈打ち続けるでしょう。
「あなたじゃなくてもいい」「代わりはいくらでもいる」、労働者、母親、客、国民……記号や数字として否応なく消費される現実世界に戻ってからも、あなたという個人に呼びかけ続けるでしょう。
現実世界から離れて飛び込んだはずのフィクションの世界、その深層で、本名の自分に巡り合う。
不思議なようで必然な、イマーシブシアター世界の唯一無二の醍醐味です。
演者はもちろん、参加者どうしで影響を与え合うこともある。
イマーシブシアターに参加すると、演者(キャスト)が演じている登場人物たちのことだけでなく、周りにいた他の参加者たちのことも、無意識のうちに記憶に残っていることに気付き、驚かされる。
別の日や別の現場で見かけた人のことを「なんだか知っている」という気持ちになる。
劇場で観劇した後、自分からほんの数十センチの隣の席に座っていた人の顔さえ覚えていない(というか見てさえいない)のに、イマーシブシアターでは、再会すると何となくわかるくらいにまで記憶に残る。ただの他人とは思えない感覚。
それは自分が世界の一員として、同じように世界の一員である他の参加者たちのことも認識しているからだろう。互いにそういう認識が行われることで、世界に参加している感覚というのは一人一人の中でさらに強まっていく。
劇場で隣り合った人のことは、同じ世界の一員として見ていない。居酒屋で隣のテーブルの人たちのことは、同じ世界の一員として見ていない。コンビニのレジの人は、言葉は交わせど同じ世界の一員として見ているかというと、怪しい。(レジカウンターというのは象徴的な装置だ。)
そういうふうにして、自分(たち)とそれ以外を区切りながら、我々は日常を生きている。これが積み重なっていくと、現実世界に参加しているのかどうか、社会なるものに参加しているのかどうか、という問いかけ自体が薄れていって、実際のところよくわからなくなってくる。
このあたりに、少なくとも自分にとって、イマーシブシアターが現実世界を超えて特別な世界であると言える所以がある。
そしてイマーシブシアターに参加した後、心が満たされたような気持ちで生活に戻ることのできる理由がある。
「誰もが世界の一部である」という根本原理に基づいて、演者どうし、演者と観客、観客どうし、それぞれがそれぞれを認識し、肯定し、寄り添う。そこに、真の意味での「参加」が生まれる。言い換えれば、一人一人が世界から包摂されている。
ここでようやく先ほどまでの話に戻れば、これこそは新しい意味での「自由」である、と思う。
イマーシブシアターの世界の中では、一人一人が「自由」である。
これは、「自由に動き回り、自由な角度から見聞きすることができる」というようなイマーシブシアターの形式を表す表現としての「自由」とは少し位相が異なる。
「自由に動き回り、自由な角度から見聞きすることができる」「どう行動するかはあなた次第」と言う時、そこには「あなただけの」という「排他性に基づく」自由が想定されていると思う。
もちろんこれもイマーシブシアターにおける重要な要素で、件のnoteでも多くの文字数を割いたところである。
一方で、この自由はまさに前半で説明したところのオールドタイプの自由であるから、他者の自由や公共の福祉と衝突した(しそうな)際に、制限されることになる。
その制限は、具体的には作り手によるルール、監視、受け手による「自己規制」といった形で表れる。
・ルール
公演にもよるけれど、観客が自由に行動できることの裏返しとして、「ただし、これはダメです」というルールが冒頭で細かく説明されることが多い。「この範囲内での自由です」ということを示しておかないと収拾がつかなくなることは容易に想像できるので、当然必要なものだろう。ルールの濃淡や導入の仕方は公演によって異なり、それが見どころの一つでもある。
・監視
それでも何か逸脱行為があった場合に備えて、会場内に「その世界の住人ではない人」、有り体に言えばスタッフが配置されている公演が多い。
空間内に監視カメラが設置されている公演もある。これもセーフティネットとしては当然あり得る措置だろう。特に空間が入り組んでいる場合など、演者の安全面を考えれば必要になってくると考えられる。監視カメラをあえて観客から見えやすいように設置しているケースもある。
・受け手による自己規制
これは非常に範囲の広いもので、一括りにするのは乱暴かもしれない、という前提付きで。
ルールの範囲内で自由に行動できる、という建前はありながら、実際にはなかなかそうはいかないことも多い。後ろの人の視界を遮っていないか、演者の動線を邪魔していないか、物理的に邪魔してはいなくても今この引き出しを自分が開けていたら目障りではないか。注意することがたくさんある。
演者や他の観客に配慮して行動する、といったことから、もっと厳しく、他の観客との兼ね合いで、自分がどうしてもやりたかったことを我慢する、他の人の体験を邪魔しないようにとにかく存在感を抑制する、自分の動きを後から猛省する、というような、自分で自分の「自由」を制限しにいくような部分が、日本のイマーシブシアターの観客(特にリピーター)にはよく見られるように個人的には感じる。かく言う自分自身も、同じような感覚を多かれ少なかれ持っている。
これらは、あの形式の公演を滞りなく成立させるには必要なこと、だとは頭でわかりつつ、一つの没入体験として見たときには、正直なところ、窮屈に感じる部分もないわけではない。
それでもなお、自分がイマーシブシアターにこんなにも心惹かれる理由は、この自由と諸々の制限が、他ならぬニュータイプの自由によって下支えされているからだと思う。参加者の自己規制については、大元を辿れば「同じ世界の住人として、それぞれの存在を尊重しているからこそ」生じているものでもある、と言えるかもしれない。イマーシブシアターが「他ならぬあなただけの物語」と言う時、それはあなたが持っている(排他的な)自由、のことを指しているだけではなく、どんな感じ方も肯定される、あなたの感受性はありのままで肯定され、世界から包摂されている、ということも、同時に表明されているのではないか、と思う。
これは自分にとっては非常に重要なことで、巨大な意味を持つ。
冒頭でも書いたような、あのnoteでは説明しきれていなかった、自分が感じるイマーシブシアターの核のようなもの、それは、「イマーシブシアターの世界は、オールドタイプの自由だけではなく、ニュータイプの自由の可能性にも満ちているということ」だと思われる。
そろそろまとめよう。
イマーシブシアターにおける自由として、「好きなように行動し、自分だけの物語を紡ぐ自由」がある。これは大きな大きな魅力である。ただ、この自由はオールドタイプの自由であるが故に、制限を伴う。それは時に窮屈さを生むことがある。
これを根っこから支えるかのようにして、もう一つの自由がイマーシブシアターの世界には満ちている。それは、排他性の原理に基づかない、新しい自由である。新しい自由は、それぞれが所有するものではない。一人一人の持ち物である自由がひしめき合って、ぶつかり合うから規制し合う、というものではない。
一人一人がこの世界の一員であることを認識し合い、存在を肯定し合い、尊重し合うこと。瞬間ごとに世界に参加しているという実感を持てるこも。世界から包摂されていると感じられること。そのような自由である。
寄り添った誰かと気持ちが触れ合うたびに、誰かと目が合うたびに、誰かに笑いかけてもらうたびに、自分の役の名前を呼んでもらうたびに、空間に満ちた空気にふと不思議な心地良さを感じるたびに、この自由を確認する。
自分だけが紡いだ物語が、それがどのようなものであったとしても、世界から肯定され、包摂されていると感じる。そこには確かに自由がある。
新しい自由のあり方に支えられて、作り手がそれぞれに持てる魅力を存分に生かした、唯一無二の世界を作り出す。
イマーシブシアター世界の中で、私は、私たちは、自由に存在し、登場人物たちと同じ空気を吸い、泣き笑い、目線を交わす。そんなフィクションの世界の中で、無意識のうちにふいに本名の自分と出会い、その存在をあるがままに肯定されて、優しく包摂されて、また現実世界へと戻ってくる。
このプロセスこそが、イマーシブシアターに参加するということだと自分は思う。
これからの現実世界では、若者たちの求める新しい自由のあり方が、これまでの自由のあり方に取って代わる動きが出てくるかもしれない。人間が互いを認め合いながら伸びやかに、しなやかに生きることを志向するならば、きっとそうなる。
もしそうだとすれば、一足先駆けて未来の世界を素敵に煮詰めて提示しているのがイマーシブシアターだと言ってもいいかもしれない(ちょっと大袈裟だろうか)。
いずれにしても、様々な作り手の様々な作品が生まれてくる中で、イマーシブシアターが優しい包摂の原理に基づく新しいタイプの自由をこれからも保ったまま、文化として発展していってほしいと、一ファンとして思う。その中で、イマーシブシアターが多くの人のものとなるにあたっての明確な課題、すなわち参加者の多様性の担保という部分を、もっと押し広げる契機も生まれてくるかもしれない。
自由を奉ずるイマーシブシアターがどんな未来の世界を見せてくれるのか、目撃するのが楽しみでならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
