
勉強方法 さらに詳しく!
こんばんは。
出願も終わり、あと2ヶ月!いよいよですね!!
当然今年の合格のために皆さん頑張っていらっしゃると思いますが、そこで気になるのは
「結局どういう勉強をどのぐらいやれば、合格できるの?」
ではないかな?と思います。去年私がそうでした。
生活スタイルやお仕事、ご家庭環境、もともとの知識などが一人一人違うので、一概に これだけやれば絶対合格! なんてことは言えませんが
ひとつの例として、私の勉強法を改めて振り返ってみようと思います。
この記事の詳細バージョンといったところです。
あくまで一人の体験談として、ご参考になれば幸いです。
基礎情報・基礎学力
20代 元OL
偏差値58程度の高校・大学を卒業
一般企業を数年経験し退職、フリーターになりアルバイト中(1日6〜8時間)に資格試験を受験。
試験前1ヶ月は丸々お休みをいただき、勉強時間をしっかり確保しました。
家族がいるので朝昼晩のご飯づくり、掃除洗濯買い出しペットのお世話などの家事をやりつつ、お休み期間は1日8〜9時間は勉強できました。
ここまで時間が確保できる方はこの試験受験者にはなかなかいらっしゃらないと思うので、恵まれていたと思います。
社会人の方やお子さんがいらっしゃる方の参考にはなりにくいかもしれませんが・・・m(__)m
(Ⅰ)教職教養 勉強方法
● LEC これだけ覚える 教員採用試験 教職教養
読み込みを2〜3周しました。
1周目:全ページ じっくり読み込み わからない言葉は調べながら
2周目:全ページ 読み込み 苦手ページに印をつける
3周目:苦手ページのみ 読み込み&赤シートで確認
● 学習指導要領 総則 解説
こちらも2〜3周。
1周目はひたすら重要そうな文章にマーカーを引いて読み込みました。
2、3周目は1周目よりもじっくりではなく、流し読み+マーカー部分をじっくり。
● ポケットランナー 教職教養
4周しました。でも時間もかかるしそんなに点数とれなかったし、4周もする必要なかったかも・・・と思います。
1周して間違えたところだけもう1度〜2度解いて、時間があれば最後にもう1周くらいでもいいかなと思います。
● 教職教養 よく出る過去問224
こちらは息抜きとして1〜2周。
問題と解答解説が見開きになっているので、電車や食事中などに手軽に目を通すことができました。
● 過去問5年間分
トータル10回くらい解いたと思います。
最後の方はもう答えを覚えてしまっていてあまり意味ありませんでした笑。
なので、要所要所で確認テストとして時々解くくらいでいいと思います。
1回目:最初の力試し
2回目:LECと指導要領読み終わってから
3回目:いろんな問題集とかやってから
4回目:直前の確認テスト
5回目:4回目の復習
・・・くらいでよかったかな、と。
(Ⅰ)対策はこれくらいです。
(Ⅱ)小学校全科 勉強方法
● LEC これだけ覚える 教員採用試験 小学校全科
こちらも教職教養と同じく、読み込みを2〜3周しました。
1周目:全ページ じっくり読み込み
2周目:全ページ 読み込み 苦手ページに印をつける
3周目:苦手ページのみ 読み込み&赤シートで確認
ただし、一般知識の一部は早い段階で捨てました。図工の美術史とか、国語の古文とか・・・
苦手な部分に時間をかけるより、学習指導要領部分に集中しました。
● 学習指導要領 解説
前の記事と同文ですが、載せておきます。↓
よく「丸暗記するしかない」と言われていますが、物理的に無理です。わたしは、「せめて2周はすべき」だと思います。
1周目は時間をかけて、とにかくきちんと読むこと。ページ数が多いので圧倒されますが、意外と同じような文章が繰り返し出てきます。何回も「さっきも同じこと書いてなかった?」となります。
全教科すべて読み込むには心が折れますが、1周目をしっかり読み込んでおくことで、2周目3周目がぐっと楽になりました。
そして、参考書や問題集をやり込んでいくうちに大事な箇所がおのずとわかってきます。
おすすめの進め方は
1周目:読みながら大事そうな文章にひたすらマーカー
↓ 参考書、問題集、過去問など解いてみる
2周目:理解が進んだ上でやはり大事だと再確認した文章や語句をチェック
↓ 参考書、問題集、過去問など
(余裕があれば)
3周目:試験直前にチェックしたキーワード付近を重点的に読み込む
です。ちなみに暗記ペン(濃い緑のやつ)で最初やってましたが、結局暗記なんてできず、読みにくくなっただけだったので、普通のマーカーをおすすめします。
教科によって何周するか違っていいと思います。私の場合は
要領:1周&前文は重要語句を暗記
総則:2周
生活:5周(Ⅲで選択したため)
国語:3周
体育:3周
家庭科:3周
図工:3周
外国語:3周
総合:2周(Ⅳ対策)
道徳:2周(Ⅳ対策)
特別活動:2周(Ⅳ対策)
でした。各教科によってページ数の違いはもちろんですが、読みやすさも違いました。
個人的に読み進めやすかったのが国語。分厚いのですが、集中すれば6〜7時間?で1周できた記憶があります。
読むのに時間がかかったのはやはり総則です。
そしてそれぞれの教科で特に読み込むべき箇所は
生活:全部!
国語:学年ごとの内容の違い
体育:学年ごとの内容の違い
家庭科:各単元における内容の詳細
図工:学年ごとの内容の違い
外国語:外国語、外国語活動の違い
です。例えば図工で「絵具は低学年?中学年?高学年?」とか
体育で「ボール遊びは低学年?中学年?高学年?」とか
このあたりはしっっっっかり覚えておいた方がいいです!
ランナーなどの問題集でこの類の問題があるはずなので、そこを完璧に仕上げることをお勧めします。1、2問は必ず出る問題です。
● ポケットランナー 小学校全科
4周しました。が、こちらも一般知識の一部は捨てました。
個人的に国語・図工の一般知識は範囲が広すぎるので捨ててもいいのかなと思います。(図工の版画とか工法とかの基礎知識部分は捨てないです!美術史とかのことです)
● 過去問5年間分
教職教養と同じで、トータル10回くらい解いたと思います。
前述したとおり、要所要所で確認テストとして時々解くくらいでいいと思います。
(Ⅲ)生活科 論作文 勉強方法
● 学習指導要領 解説
トータル5周しました。
5周というと 多!!と思われるかもしれませんが、生活科は案外とても読みやすいですし、2周目からは流し読みで大事な箇所だけ読んでいました。
読み進めていくうちにおのずと大事な部分やキーワードがわかってくるので、それらをアンダーライン&付箋に書き留めて壁に貼っていました。
また、「なぜ○○なのか。○○にはどういった配慮が必要か。200字で説明しなさい」という問題が過去に多くあったので、150字〜200字くらいで詳しく説明している部分を意識して探し重要マークをつけて、覚えるようにしていました。
(昨年度の試験でいう問1の(3)、配慮すべきこと、対応例 の問題です。)
正直、この学習指導要領さえしっかりマスターできていれば、他の勉強はあまり必要なかったかもしれません。。。
● 生活科の教科書
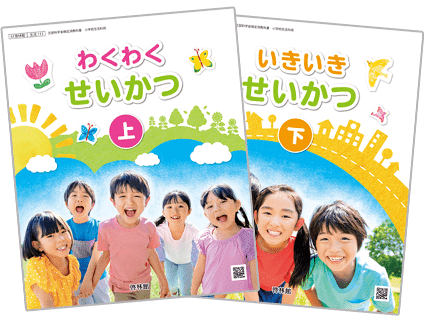
書店で購入し1〜2周読みました。
自分が授業しているイメージをしながら読み進めたり、実際にどういった活動が予想されるかを各単元4〜5個あげて具体的な内容を考えたりしました。
正直、なくてもいけたな〜と思います^^;
● NHK for school おばけの学校たんけんだん
学校で具体的にどういった授業をするのか、各単元ごとにストーリーでわかりやすく作られています。
授業のイメージや子供たちの反応が全く想像つかない!という方は、息抜きがてら見てみるといいと思います。
小画面表示(?)ができます。休憩中、スマホで何か調べ物をしながら〜とかLINEしながら〜とかでも隅っこで小さな画面で動画を見ることができるので、おすすめです。
(Ⅳ)教職教養 論作文 勉強方法
Ⅳは下記の記事に合格再現論文とともにかなり詳しく載せております。
有料にはなってしまいますが、それなりに充実した内容だと思いますのでよろしければご覧ください。
ちなみに参考図書は 手取り足取り特訓道場です。
この本の使い方は下記の有料記事の無料部分に軽く書いてありますので、よろしければご覧ください。
ちなみに有料部分は実際の論文練習の添削・修正です。添削は論作文が得意・もし採点経験者にお願いしました。第4弾まであります。
思い出せる限り、せいいっぱい詰め込みました。
どなたかの参考になれば幸いです^^
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
