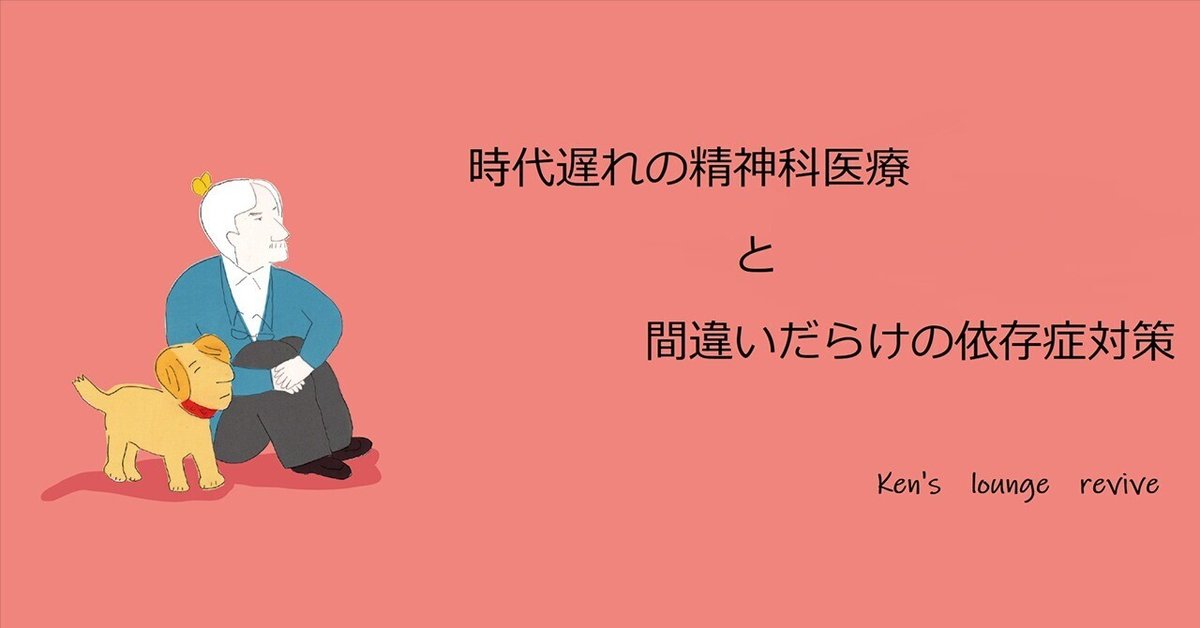
「レガシー」とやらについて②
◎レガシー(legacy)「遺産」、「伝統」、そして「次の時代に受け継がれていくもの」を指す。
▶次の世代に伝えておきたい物語
▼これが依存症治療事始めかな
●ある夜の当直で・・・・・・
「先生、昨日入院した患者さんが眠れなくて、落ち着かないのです」と、西脇病院の当直室で休んでいた私に、夜勤の看護師がその患者の診察を求めてきた。1972(昭和47)年の寒い師走の夜であった。寝ついたばかりの私はしぶしぶ起き上がり、パジャマの上にそのままズボンとセーター、そして白衣を身に着けて、その患者の入室している保護室(現在の隔離室)へと向かった。
薄暗い保護室の中では一人の男性が、確かに落ち着きなく狭い室内を動きまわり、意味不明のことを口走り、私の問いかけには関心を示さない。夜勤の看護師によると、前日アルコール中毒(現・アルコール依存症)で入院してきた患者だそうである。私は鎮静効果のある筋肉注射を打つようにその看護師に指示し、そそくさと当直室に戻り、まだぬくもりが残っている布団に潜り込んで再び眠りに入った。
私はその年の6月に医師免許を取得、まだ医師になりたての研修医の身分であった。当時は、今のようなしっかりとした研修医制度がなく、新米の研修医が一人で病院当直が可能であった。
翌朝には、私は研修先の地元の大学医学部附属病院に出かけ、その後、その患者とは数年間、診察の機会はもちろん、会うこともなかった。
それが、末さんとの最初の出会いであった。その後、彼は翌年の1月に退院したが、2月には再入院して8月まで入院。そして、その翌年の1974(昭和49)年の9月から1975(昭和50)年3月、さらに1976(昭和51)年2月から6月まで計4回の入退院を繰り返している。
▼黎明期
●夜間集会の幕開け
私が、彼を再び診察したのは3回目の入院、それも退院前のことであった。当時私はまだアルコール依存症の治療に関心を寄せてはいなかった。ただ、長崎市の保健所で断酒会の例会が月1回開かれていることを情報として知っていた。そこで、彼にその例会参加をすすめてみた。彼は退院後、そのすすめに応じて例会に参加するようになった。だが、彼は当時、吃音がひどく、指名されてもうまく話せず、ろくに発言できないままにその例会の時間を過ごしていた。苦痛だったであろう。そして、半年近くそこに通った後、12月23日に自分の誕生日だからと、一杯飲んでしまった。それからしばらくは抑制していたが、徐々に酒量が増し、翌1976(昭和51)年2月には深刻な禁断症状(捨鉢諧謔)を呈して入院している。
その当時の私はというと、長崎大学医学部附属病院精神神経科医局からの派遣で長崎県立の精神病院に勤務していた。そこで私は、あまりにも仕事ができないのを見兼ねた副院長から、国立久里浜療養所(現・久里浜医療センター)で、その年から行われるアルコール医療の研修会への受講をすすめられた。その研修会は現在も続いている研修会であるが、その時が第1回だった。私は二つ返事でそのすすめを受け入れた。理由は研修の場が神奈川県だったからである。当時、「よこはま・たそがれ」などといった、横浜や横須賀が登場する歌がはやっており、横浜、横須賀に憧れがあった。研修で研鐙を積むという気持ちは全くなかった。
研修期間は、第1回ということあって2週間だったように記憶している。ただ、三浦半島の先端にある久里浜病院は、長崎市よりもっと田舎であった。私の横浜、横須賀への期待は見事に裏切られた。それだけではないだろうが、その研修内容の記憶はほとんどない。
ただ研修最終日に、当時の国立療養所久里浜病院の河野裕明副院長及び病棟スタッフと、退院して街で暮らしながら回復をはかっている患者OB(その多くは地域の自助グループである断酒会会員。当時は男性のみ)との懇談会が行われた。その集いにはもちろん私たち研修生も参加した。懇談会の中ほどで一人の患者OBが微笑みながら語った。「私は3年もやめたので、ぼちぼち酒を飲もうかと思っています」と。私はその頃、1年以上アルコールを断ち続け、治療につながっている患者を知らなかった。“おいおいせっかく3年もやめているのにそんなこと考えて、それを治療者の前で口にしてもいいのかい?”と思いながら、河野先生の反応を窺おうと、彼のほうへ視線を移した。河野先生も笑顔で、ただ黙ってニコニコされているだけである。別に何の指導、助言もなかった。“えーっ!これでいいのか、これでいいのだ”と思った。
その瞬間、私は"これでいいのだ"をやりたくなった。そんな思いだけで、研修を終えて長崎県立の精神病院に戻ってきた。しかし、その年の4月には長崎大学医学部附属病院精神神経科へ再び帰らなければならなかった。この病院は総合病院である。精神科病棟は50床あまり、アルコール依存症者の入院は年に数人である。だが、私は“これでいいのだ”をやってみたかった。大学医学部附属病院の精神科病棟では無理である。ただ、この病院に勤務していると週に1日は、民間精神病院に非常勤で勤務することができる。そこでは当直も行わねばならなかった。そこで、私はその非常勤の勤務先を、当時父が経営していた西脇病院にした。そして、当直の夕食後から消灯までの時間を利用して“これでいいのだ。”を始めることにした。それが40年続いている夜間集会である。
そのヒントとなったのが、日本精神衛生会の季刊広報誌「心と社会」に掲載されていた作家・なだいなだのコラムだった。彼は作家かつ精神科医で、久里浜方式の創設者の一人でもある。国立療養所久里浜病院を退職した彼は、執筆活動の傍ら週に2回、非常勤医師として東京都内の精神病院でアルコール依存症の治療に携わっていた。
コラムには、非常勤の勤務医としてでき得ることが書かれており、それは精神病院職員に負担をかけないことが大切だとして、外来通院を意識して治療を進めているとのことだった。なるほど、将来、西脇病院を引き継ぐ身であるからといって、週1回の勤務であとは職員任せ、というのはあまりにも無責任である。しかし当時、外来でアルコール依存症の治療を行うといった発想は、長崎県内の精神科医の誰にもなかった。
そこで始まった夜間集会、入院中のアルコール依存症患者を一人ひとり診察するだけの時間が足りないのを補うためという側面もあったが、夕食後に皆で集い語り合ったことが、退院後の患者の拠り所や居場所の提供となった。結果、その後40年間継続することとなっている。この夜間集会は、当時の私がその用語すら知らなかった「ピアサポート」事始めであったようだ。そして、末さんもこのピアサポート事始めのときからの参加メンバーの一人であった。
▼回復の道筋
●末さんの歩み
末さんの話に戻そう。彼は西脇病院に入院する前は、長崎湾外にある高島炭鉱で働いていた。当時は石炭から石油へのエネルギー転換の時期で各地で炭鉱の閉山が続いていたが、高島炭鉱は良質の石炭が採掘されることから操業を継続しており、まだ活気があった。そこで彼は家庭をもち一男一女をもうけた。ある夜、娘が発熱した。妻は娘を島の診療所に受診させようとするが、酒に酔った彼は受診させる必要はないと妻の訴えを拒み続け、翌朝やっと診察が受けられた娘は大学病院へと転送されたが、脳性麻痺となり、右半身の機能が不十分で、知的発達も滞った状態で今日に至っている。この娘に対する申し訳なさ、不憫な思いから酒量がますます増え、入退院を繰り返してきた。そして、深刻な禁断症状(捨鉢諧謔)を呈して入院、その急性期症状が改善した後、夜間集会の立ち上げに参加している。
彼は退院後、生活保護を切り、兄が営むハマチ養殖業の手伝いを始めた。しかし、夜間集会や地域断酒会に出席するための時間が欲しいという理由から、ハマチ養殖の自営を決断した。武士の商法といったところであろう。ずいぶん苦労したようである。朝早くから夜遅くまで海に出かけ、また、陸に上がると出荷のためにトラックを回すといったことを一人でやっていた。資金繰りが悪くなって困り果てた時期もあったようである。だが、そんな合間を縫うようにして、断酒会に通い、夜間集会にも近隣の仲間を誘って参加してくれた。
そんな彼の頑張りもあって、出荷前にわざと餌をやらずに身を絞めた彼のハマチが評判を呼んだ時期もあった。私も何度か彼の養殖場を訪れたことがある。養殖場のそばで釣りをすると、養殖場にまいた餌が網から漏れ出て、それを狙って天然魚が集まってくる。面白いように釣れる。痛快であった。釣りの後は、近くの海岸で彼が釣った魚をすぐに刺身にさばいたり、鉄板の上で丸ごと焼いてもらったりして食べた。実においしかった。一緒に連れていったまだ小さかった私の子どもたちも、今でもそのときのことをよく覚えている。よほど楽しかったのであろう。
しかし、1990年半ばに、それこそ苦労をともにした末さんの妻が倒れた。一命は取り留めて順調に回復はしたものの、無理の利かない身体になってしまった。もちろん人を雇う余裕などない。人出が足りない。加えて、大手の水産会社が養殖業に参入してきて、経営が成り立たなくなった。そこで、2000年に入ってまもなく、廃業した。末さんは最近になって当時を振り返り、その廃業の決断の後押しをし、その時期を支えてくれたのは、彼の息子であったと語っている。
三十数年来、月に1回、第4日曜日に、地域断酒会の例会場として西脇病院の一室を提供している。それは末さんが断酒を始めて間もない頃のことで、吃音はかなり改善していた。だが、まだ今のような流暢な語りではなかった。しかし、過去の自己の体験とその時点での思いを必死に発表している姿を覚えている。そんな末さんと彼の妻との間に挟まれてチョコンと座って、テーブルの上に置いてある菓子とせんべいの盛られたお皿をじーっと見つめている男の子がいた。末さんのまだ幼い息子であった。息子は私の出身高校に進学した。私は先輩ということで保証人を引き受けることになった。そしてその後、息子は都内の大学に進み、就職した。末さんの自慢の息子であった。
ところがある日、末さんが西脇病院を訪れ「先生、今日は診察ではありません。息子が、会社を辞めて、海外青年協力隊で中米の開発途上国へ漁業技術を指導に行くと言っているんです。どうしたらいでしょうか」と、おろおろした表情で、せっかく集会で自らの体験を語ることで治っていた吃音がぶり返したような口調で語ったのであった。「息子は親の背中を見て育ったんだよ。行かせてやりなさい」と返答した私も、その開発途上国とやらがどこにあるのか知らなかった。そこで、2人で世界地図を広げて探した記憶がある。その後、息子は帰国し、医療系の専門学校に入り、医療専門職に就いた。そして結婚し、男の子を授かった。末さんにとっては初孫である。彼は喜んでいた。本当に幸せそうであった。しかし、それからしばらくして、彼から息子の妻の死を知らされた。癌だった。
その後、彼の姿を夜間集会で見ることがめっきり少なくなった。稀に参加したときに指名してみても、発言に以前のような覇気が感じられなかった。やはり、息子の妻の死を引きずっているのかと、私も「どうなんだ」と尋ねるのを控えていた。だが実は、その頃、末さんの妻の体調が優れなくなっていたのである。彼は私にそれを語らなかった。
そして、いつの頃からか、ぷっつりと彼は夜間集会に現れなくなり、それは数カ月続いた。夜間集会では、自助グループの集まりと同様に言いっぱなし、聞きぱっなしに加えて、出るのも自由、出ないのも自由で通してきている。気にはなりながらも、私は彼に連絡をとらなかった。そして、ずいぶん後になって、私は彼の妻の死を知ることになる。
さらに数カ月後、彼は普段と変わりない様子で夜間集会に再び現れ、妻の死を伝え、以前と同じように自己の体験を語り始めた。少し変わったのは、判で押したように2週間おきの出席になったことである。それは、孫の食事の世話などで毎週家を空けられないためであった。そして、体験談の中では、亡くなった妻につらく当たってきたこと、もっと労わってやれなかったのかと後悔の想いを語る。その一方で孫の成長の様子にも細い目をますます細めて話すようにもなった。
▼切れ目のない・・・つながり
●末さんの今
長崎郊外の漁港の町で、既に中学生になった孫の成長を見守りながらの穏やかな生活を送っている。夜間集会には相変わらず、2週間に1回、顔を出してくれる。指名すると、最近では、娘に対する申し訳なさ、不憫の思いを必ず話題にする。忘れることのできない、酒の上での失敗の本当に苦い思い出であるとともに、この先の娘が気がかりであるに違いない。
あの寒い当直の夜、30歳代前半の依存症者と20歳代半ばの研修医であった2人は、1人は古希を過ぎ、もう1人も今年、古希を迎える。今少し、付かず離れずのこの切れ目ない関係を続けていきたいものだ。
「学ぶ前に幸運に恵まれていたことについて」
精神科 特集Ⅱ当事者グループから学ぶもの
26(3):214‐218,2015 西脇健三郎
★おわりに
物語の投稿から10年近くの歳月が経過している。老いた末さんと私のことは、もう語るまい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
