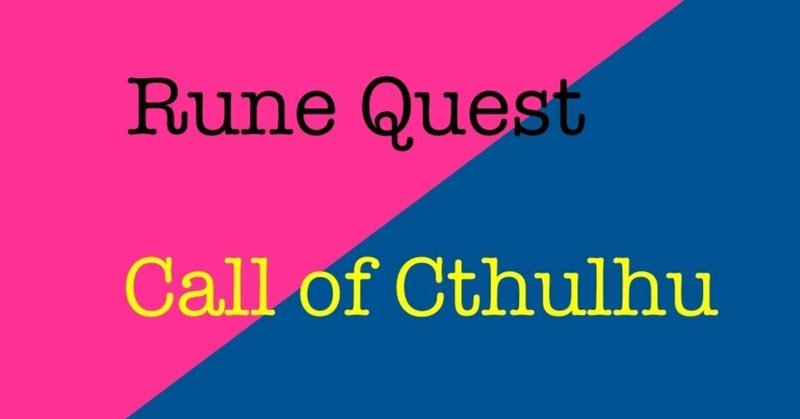
52_TRPG世代論『ルーンクエスト』『クトゥルフの呼び声』ベーシックRPの光と闇
『クトゥルフの呼び声』が2010年代以降に動画リプレイを契機に、日本TRPGユーザーの中では一大勢力となりました。「動画勢」とか「CoC界隈」というネットスラングもあるようです。2004年に『クトゥルフ神話TRPG』(第6版)が発売されるまで約10年間公式サポートが途絶えた時期を知る古参ゲーマーから見れば、万感の想いがあります。サポートが無いと言っても、実際はTRPGユーザーが遊んでいました。他のコミュニティがどうかは知りません。私の参加するTRPGサークルではセッション回数を記録し集計しています。手元で参照可能な資料は1994年度分から。25年間ずっと3強の一角を占めていました。不遇と言われる1990年代後半や2000年代前半の5年集計を見ても、総合順位2位です。すなわち『クトゥルフの呼び声』ブームとは一過性のものではなく、名作TRPGの真価が広く知られるようになった現象とも言えます。
一方で『クトゥルフの呼び声』と同じ「ベーシック・ロールプレイング」を採用していながら今や不遇となってしまったのが『ルーンクエスト』です。1994年度から1996年度はサークル内セッション回数ベスト3を維持していました。2000年頃まで根強く遊ばれていました。TRPGサークル以外を見ても、1995年のコミックマーケットでは「ゲーム(電源不要)」ジャンルで人気タイトルの1つでした。同じようにホビージャパンの路線変更の影響を受けても、その後の明暗が分かたれています。「ベーシック・ロールプレイング」系譜から言えば、『ルーンクエスト』が親です。日本語訳TRPGとしては『ストームブリンガー』も『クトゥルフの呼び声』の兄弟分です。
◆『ルーンクエスト』概要
日本語に翻訳された『ルーンクエスト』は第3版です。翻訳前は第2版が遊ばれていたようで、「第2版の方が好き」という先輩もいます(還暦近い年齢に歳月を感じます)。TRPG黎明期のシステムなので、後に影響を与えた様々な特徴があります。知的種族のほとんどが神様を信仰している濃密な多神教の世界観。武器も魔法も使えるキャラクター。リアルな戦闘システム。蘇生魔法が普及しておりPCが死亡しても復活できる死生観。腕や脚を切り飛ばされたりする派手な戦闘などが特徴です。冒険適性を考慮せず人口分布にこだわったキャラクター作成により、普通のサイコロを振れば、農民や牧夫のキャラクターになることも他システムではなかなか体験できません。やはり、最大の特徴は青銅器文明時代であり、古代ローマ帝国とゲルマン民族を連想させる世界観でしょう。安田均先生はこう評しています。
「1976年に出たファンタジーボードゲーム『白い熊と赤い月』の背景世界グローランサが実に魅力的で、その世界を遊ぶRPGとして開発されたのがこの作品だ。」
◆『ルーンクエスト』がもたらしたこと
何と言っても最大の功績は d100パーセンテージロールと技能値、いわゆる「ベーシック・ロールプレイング」です。『ルーンクエスト』初版(1978年)の後、同じシステムを採用した『クトゥルフの呼び声』(1981)が作られました。直系のシステムだけでなく、他にd100を採用したシステムは思いつくだけでも『ジェームズ・ボンド007』『ウォーハンマー』『ロードス島RPG』『メタルヘッド』『ブルーフォレスト物語』『ギア・アンティーク』『ゴーストハンターRPG』『真・女神転生II TRPG 誕生篇』『ガンドッグ』『ガーデンオーダー』などたくさんあります。d100をそのまま採用したり、アレンジして新機軸のルールを追加したり、いろいろ個性化されていますが、基本的な判定は同じです。パーセンテージという分かりやすい概念を採用したことが成功要因です。
緻密な戦闘ルールの中で、独特の行動順番決定「ストライクランク(SR)は複雑すぎて他システムに受け継がれませんでした。敏捷さ(DEX)、体格(SIZ)、武器の長さなどで行動順番を決定します。敏捷でデカイ奴が長い武器で攻撃すると確実に先手を取れます。乱数を廃して複数要素から順番を決めるという意味では『アリアンロッド』『ダブルクロス』が後継と言えるかもしれません。戦闘ルール最大の特徴は「命中部位決定表」です。頭・胴体・腕・脚などにそれぞれのHPが決められて、腕や脚を負傷しながら戦うというシチュエーションを再現できます。ただし、ランダムで命中部位を決定するため、剣道経験者などには不評でした。というか、私が苦手でした。現実の接近戦では、偶然に腕や脚に攻撃が命中することはまずあり得ません。頭、胴、利き腕などを狙って攻撃します。防御行動により逸れると有効打になりません。一方で、弓道の経験から言えば、遠距離からの射撃が狙った的の中央ではなく端に命中することもあり得ます。私のような経験1年程度の初級者は外すことが多いですが、熟練者となると正確に命中する確率があがります。というわけで、「命中部位決定表」はリアリティが薄いと感じます。でも、ゲーム的に面白いと感じる人は多いようで『ウォーハンマー』『GURPS』『ガンダム戦記』などで採用されています。誰もが魔法戦士になれるシステムも魅力でした。『D&D』『T&T』の魔法戦士は様々な制約があったのに対して、初歩的な魔法は一般人にも普及している世界。『ソード・ワールド2.0』などにも受け継がれているように思います。
最も重要な点は世界観です。架空のファンタジー世界を緻密に作り込んだTRPGとしては空前絶後でしょう。世界観資料の読み物(データ無しサプリメント)が作られたTRPGは他にあまりありません。世界観をどこまで濃密に設定するかは、アメリカ合衆国やイギリスのゲームと日本とで傾向が異なるのは興味深い点です。海外ゲームは、『ウォーハンマー』『Vampire』など世界観の構築に熱心です。『Vampire』も世界観資料の読み物がありました。逆に日本のゲームは、ユーザーが自由に設定できる余白が多めになっています。優劣ではなく「空」に意味を見出す文化の差異でしょう。『ルーンクエスト』世界観の魅力は多神教の神々だけではありません。まずは敵役です。帝国と怪物が協力関係にあるという話もありますが、混沌の怪物ブルーは個体ごとに個性的な特殊能力を持ち、病原体という共通能力を兼ね備えるため恐れられました。1990年代当時のセガサターン用ゲーム『機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY』のタイトルを借りて、まさに『戦慄のブルー』でした。
ファンタジーといえば『指輪物語』と言われる定番と異なる、植物のエルフ、機械のドワーフ、知力筋力を兼ね備えた最強種族トロウル(ウズ)など、魅力的な種族がいます。水野良先生が小説『ヘンダーズ・ルインの領主』の副主人公に採用し、『トロウル・パック』という種族サプリメントも発売された大人気種族トロウルは『GURPS・ルナル』『ソード・ワールド2.0』でも類似種族を遊べるほどに影響を与えています。ローマ帝国とゲルマン民族の対立を連想させる人間たちの対立構造も見事です。一般的なファンタジーのイメージに近い文明化され合理的な帝国と、日本でいえば鎌倉武士のような大雑把な民族とは信仰だけでなく文化面でも違いが描かれています。また、嵐神の信者と光神の信者の仲が悪く、パーティー内で妥協的に協力したり不和の芽があることも特徴です。残念なことは、熱狂的なファンがいた反面、新参者やあまり詳しくない人にとって参加を躊躇するTRPGになってしまったことです。安田均先生の言葉は長所と短所が表裏一体であることを示しています。
「神話宗教的なカルト構造を中心に、ハイファンタジー世界を扱っては、追随を許さない深みと驚異に満ちている。まさしくカルト的な人気を永年に渡って保ち続ける名作。」
◆私たちはこうして『ルーンクエスト』を遊んだ
私が大学TRPGサークルに入会したとき、同期の中でも屈指のTRPG経験者が2人いました。1人は同回生交流を活発に推進して2回生で会長になりました。もう1人が『ルーンクエスト』推進者でした。例会だけでなく同回生の間で数多くのセッションのGMをやって頂きました。重厚な世界観が人気を博し、サークル内でファンが増えていきました。1990年代前半は、ホビージャパンが『ルーンクエスト』サプリメント販売に力を入れていたこともあって、1996年度までサークル内で3大人気システムの一画でした。有志が集まって同人誌を作成し、コミックマーケットにも行きました。私が『ガープス・妖魔夜行』同人誌を作ったとき、先輩の『ルーンクエスト』サークルに委託販売していただきました。ところが、サークル有志が日本の『ルーンクエスト』主要ファンの一角を占めるようになって気づいたのです。サークルでは大人気だけど、日本全体で見れば少数派だったことに。
人によって『ルーンクエスト』の魅力と言うかもしれませんが、ルール通りキャラ作成すると、一般人になります。例えば、ダラ・ハッパの牧夫、武器の攻撃成功率は30%から40%程度。ミッションは農村のトラブル解決。何回かそういう遊び方もしましたが、同期たちは強いキャラが好きだったので、少し強めのキャラを作成して遊びました。強いキャラといえば、水野良先生の小説の影響で、トロウル専門プレイヤーが現れて、周囲の人間キャラはそれに合わせるようになりました。「グリフィン・アイランド」キャンペーンも遊びました。1番の思い出は、複雑な対立構造を生かした、PvPシナリオでしょう。偽装した混沌信者、闇のトロウル、嵐神司祭、太陽神司祭というメンバーで序盤は疑心暗鬼、中盤以降に正体を現した混沌との対決というシナリオでした。
大学卒業後、私は『ルーンクエスト』をほとんど遊んでいません。同じ背景世界グローランサ『Hero Wars』に1回参加したことがあります。背景世界の予備知識があったので、参加しやすいと思いました。2016年10月、大学TRPG30周年記念セッションで先輩の『ルーンクエスト2nd』に参加しました。大先輩プレイヤー2人、学生プレイヤー2人に囲まれて年齢構成的にもマジな2世代セッションでした。大先輩の志向に合わせた古き良きオールドスタイルを楽しみました。2018年7月、第4版記念にTGFFで行われた『ルーンクエスト』に参加しました。農村で起きたトラブル解決、牛泥棒を追うシナリオに、第4版が出てもオールドスタイルを守り続けていると感じました。一般的なTRPGユーザーにとって、「たくさん遊ぶシステム」=「好きなシステム」だと思います。私にとって、良い経験や知識を得たけれども苦手だった唯一無二のTRPGでした。『ルーンクエスト』は濃密な世界観、トロウル無双、野武士のような大雑把な価値観、青銅器文明、そういう要素が好きな人にお勧めのシステムです。
参考文献
『安田均のゲーム紀行 1950-2020』
