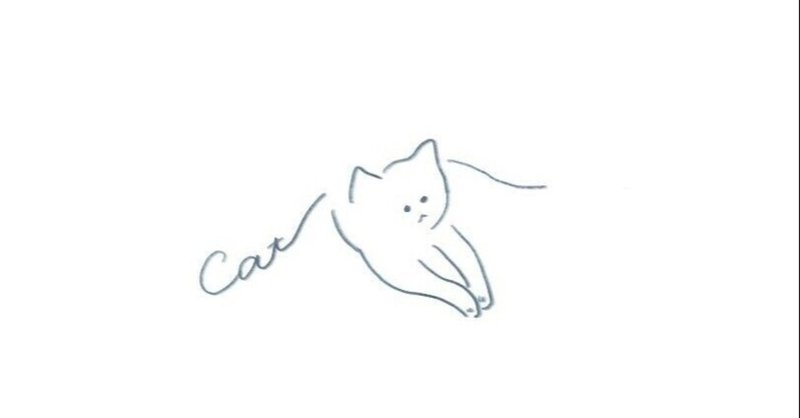
社労士合格に向けて取り組んだこと第2回「修正できるスケジュールを立てる」
にぃ猫です。こんばんは。
良くスケジュールの立て方を知りたいという方がいらっしゃいます。
基本的には、1年目と2年目以降では異なると思うし、僕の考え方がベストアンサーではないと思うのですが、参考までにお話しいたします。
1.僕のスケジュールの立て方
基本的に、大まかなスケジュールについては、資格専門学校のスケジュールに合わせた学習を行うことを心掛けました。一番最悪なのは、追い付かずに年金科目が疎かになることです。そのため、各科目を完璧に仕上げるよりも、全体把握を行うためにまずは専門学校のカリキュラムは一巡させるように心がけました。
年明けて、社会保険科目に差し掛かったところで、健康保険法の大切さを認識し、1月~3月までは健康保険法をメインに学び、同時進行で年金科目に取り掛かりました。この時の年金科目に取り掛かっていた目的は、前回書いたように健康保険法が大切だと認識していたからです。
そして、何とか講義を全て聞き終える頃には、理解不足や答練、過去問をやっていて苦手な科目が必ずあるはずです。もっと言うと、科目ごとの得意科目順と言いますか、理解度が進んでいるかを把握するようにしました。
その指標として利用していたのが「社労士過去問ランド」です。
こちらのウェブアプリは、過去問を一問一答形式で解いていくことができるのですが、その中でも優れていると思ったのは、その履歴がデータベース化されて、正解率等を可視化できることにあります。
専門学校のカリキュラムが終盤に向かい、直前期を迎える前あたりから、その結果を踏まえて、スケジュールの修正を行います。特に直前期になると、明確に復習する科目に悩みが生じます。その理由は専門学校では直前対策に移り、科目ごとの復習よりもその直前対策に一杯一杯になるからです。
しかし、テキストの読み込み・過去問については、直前対策と同時進行しなければなりません。ここら辺から、専門学校のカリキュラム通りに進めると、中途半端になる可能性が出てきます。
ここからが、スケジュールを細かく調整していく必要が生じます。
その際に「自分がどの科目が苦手で、どの論点が特に苦手か」を把握することでスケジュールの立て方が大きく変わります。
僕の場合は、「社労士過去問ランド」の正答率と、復習した時に自分が説明できない部分が重なっている部分を苦手と判断し、その部分の学ぶ時間を確保することにしました。
つまり、直前対策と苦手科目の復習、各科目のメンテナンスと、この頃辺りからは、学ぶことが増えていきます。しかし、どんなに直前対策を頑張っても、苦手科目のメンテナンスを怠ると基本学力が落ちていくと考えております。
そのことから、スケジュールを立てるだけではなく、常に立てたスケジュールを修正できる柔軟性が求められると思います。硬直的なスケジュールではなく、柔軟に対応できるようにしましょう。
直前対策との向き合い方は、後日お話しいたします。
2.初学者及び2年目以降(択一40点未満の方)向けスケジュール
基本的には、前半戦は専門学校のカリキュラムに忠実で良いと思います。そこで、社労士試験で求められる基本知識を積み重ねる努力をしましょう。
恐らく、択一40点未満の場合、労働科目で5点未満の科目もあろうかと思いますので、労働科目を疎かにするのは得策ではないからです。
そして、アウトプット(特に過去問10年分)については、カリキュラムの進捗に応じて、選択・択一共にしっかりやりましょう。労一については、過去の択一であっても、どのような統計が出題されているかを把握するために、問題を見るのは大切です。
また、選択式についても過去問。できれば15年分くらいは解いてみると良いかと思います。選択式で問われるのはどの部分かを意識してテキストを読むのと、ただ漠然とテキストを読むのでは、選択式に対する学力の向上スピードが確実に違うからです。
勉強が思うように進まないと、先に進むことに恐怖を感じる場合もありますが、一番怖いのは、学んでいないテキストが積まれていくことです。3科目溜まったらリカバリーは効かなくなるので、とにかく一巡することに命を賭けましょう。
基礎学力を積む間は各科目を完璧にするというのはあきらめた方が良いかと思います。復習を行うことで資本論点を完璧に仕上げていくものだと考えていきましょう。
基礎学力を積むまでにTwitterとか見ていると、早めに労一対策をって思うかもしれませんが、基本的に専門学校で軽く話題になる統計を読んでみるとか、Twitterで流れてくるものを見る程度で大丈夫です。いくら労一が出来るようになったとしても、肝心の基本科目で点が稼げないと意味がないからです。
ここで、テキストを理解してからアウトプットだと思う方もいらっしゃるかと思います。僕はテキストの理解は不十分でも、アウトプットを行うことでインプット以上の理解に繋がるものだと思っております。そのため、インプットとアウトプットの時期を明確に分けるのは危険です。
基本的には、同時進行でインプットとアウトプットを行い、後半でインプット重視の日とアウトプット重視の日を作る程度で良いかと思いますので、アウトプット軽視だけは控えることをお勧めします。
初学者や択一の点数が取れない段階においては、専門学校のカリキュラムこそが「型」であると思ってください。「型破り」という言葉もありますが、「型を知らずして型を破れない」のです。
3.択一40点以上の学習経験者
逆に、択一で合格ラインに近い方は、新たな年の学習ではカリキュラム+アルファの学習計画を立てることをお勧めします。早いうちから、スケジュール調整を行いつつ、能動的に学習するのがベストだと思います。
ある程度点数が確保できる方が、カリキュラム通りに学習すると、4月以降毎年同じように直前対策のボリュームで苦しむことになるのですが、それを少しでも軽くするために、早めに努力しましょうということです。
ちなみに、10月28日(合格発表前日)まで、僕はLECのカリキュラム+1科目(もしくは厚生労働白書の精読)を行っていました。
その程度の学力がある方は、既に、主だった部分はしっかりと覚えていて、ある程度テキストを読めば思い出すレベルに到達しているかと思います。
そのため、早めに「厚生労働白書」を読んだり、白書に出ている統計を軽く見る等、一般常識対策も早々に始めておくことで、後半の学習の余裕が生じます。
澤井先生がお勧めしている「労働政策研究・研修機構」のウェブサイトの中の、統計情報のページなんかもお勧めです。特に、「労働統計のあらまし」については、主だった統計の説明も書かれているので一読しておくと、統計の理解が深まるかと思います。
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/guide/index.html
そして、苦手な科目の苦手な論点を早めに確認し、専門学校のカリキュラムと同時進行で、苦手な科目の苦手な論点について、昨年のテキストで復習をしておくと尚良しです。
その場合、改正点も多く存在するのが社労士試験なので、間違えた記憶が怖いと思う方もいらっしゃるかと思いますが、法改正で全体を見ることになるので、改正点による復習以上の忘却防止に繋がると思います。
4.まとめ
最初に勉強する場合、前半戦は、基本的に専門学校のカリキュラムを信じること。後半戦は、直前対策に加えて、自分の苦手なところを学ぶための時間を確保すること。
2年目以降の方は、本試験択一40点を境にして、40点未満の場合は専門学校のカリキュラムをメインにし、40点以上の方は、後半戦のつもりで、専門学校のカリキュラム+アルファに心がける。特に得意科目だと思うものがある場合は、カリキュラムに拘らなくても良いかもしれません。むしろ苦手なところを早いうちに潰すようにする感覚で。
スケジュールというより、進捗管理は大切です。
自分の学力の把握について、卑下することも無く過信することも無く、冷静に評価し、その評価した結果をスケジュールに反映させていきましょう。
それでは、また次回のお話でお会いしましょう。
ちなみに、僕は、来年度合格を目指すLINEグループも運営しております。
現在、120名を超える受験生が参加しておりますが、このグループでは、勉強会の開催や個別相談等も受け付けております。来年の合格に向けて伴走を続け、全員が合格することを目指しておりますので、興味のある方は、下記Twitterをフォローし、コメントもしくはDMください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
