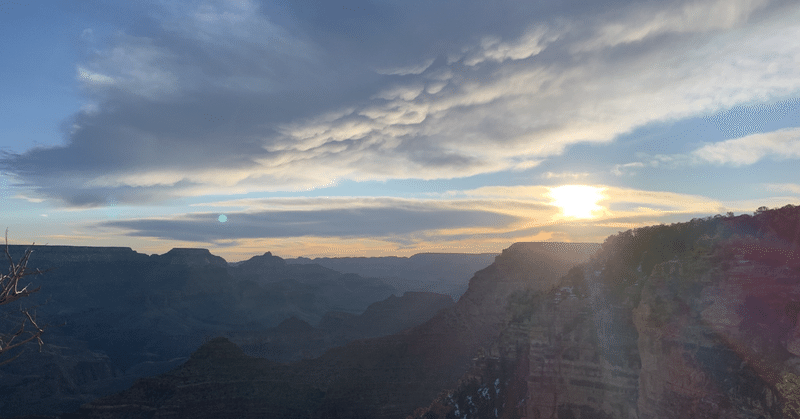
|荒行《あらぎょう》
枕
こんなわたくしでも、時には人生の意味について考えることがあります。『いったい私は何のために生きているのだろう?』『私の人生にはいったいどんな意味があるか?』と、ごくごくたまには考えます。
時としてこんな難しい問題について考えなきゃならないのは、おそらくその本源を辿ると、私が他の人とは違うからだと思われます。自分が特別な人間だと言うつもりは毛頭ありません。それどころか、私はごく当たり前のつまらない人間です。それなのに、右を向いても左を見ても、生まれてから今日まで、私は私とそっくり同じ人間というのと会ったことはおろか、見たことすらもありません。会う人会う人、見る人見る人、全員が皆ことごとく私とは違います。誰も彼もが、当然のことながら私とはまったく違う人間ばかりです。
と、いうわけで仕方がありません。必然として他の人とは違う私とはいったい何なんだろう?どうして私はこんな姿で生き、よりによって存在しているのだろう?と考えるはめになってしまいます。
もしも人類が全部私と同じだったらどんなに楽だったろうと思います。右を向いても左を向いても全部『私』。人間はみんな私とそっくり同じで、親も『私』で子も『私』、友達も全員『私』で、電車に乗っても乗客はみんな『私』。出会う人みんなが『私』で、地球上どこへ行っても誰も彼もがみんな『私』。それならきっと生きる意味について頭を悩ませることもなかったと思われます。みんなが同じ『私』なら、きっと地球のどこかで別の『私』が人生の意味について考えてくれているだろうし、そもそも人生の意味について考えようとすることだってなかったかもしれません。だって『私』がみんな生きているのですから、私が生きていたっておかしいことは何もありません。みんなと同じ私が生きることに、いったいどんな疑問が生じるというのでしょう。『僕らはみんな生きている』。それだけでいいじゃありませんか。
ところが現実の私はみんなと違います。おそらく地球上のどこを探しても私と同じ人間は一人もいません。一人もです。そうなるとやはり困ったことになります。どうしても自分の存在意義について考えなければならないからです。この広い世界にたった一人しかいない私は、いったいどんな理由があって今ここにこうして生きているのか?
おそらく考えてもわからないと思います。人生の意味を知るには、人間の寿命はあまりにも短かすぎます。比べて地球という惑星は生まれてから四十六億年、その地球のある宇宙が生まれてからも百億年が経っています。たとえそこまでいかなくても、人間だって一万年も生きることができれば、自分の人生をより高い視点から俯瞰できて、少しは人生の意味だってわかるかもしれません。ところが、悲しいかな人の寿命は長くても百年、この程度の一瞬ではとてもとても人生の意味など知る由もないこと。それはあたかも名画モナリザに自分の鼻をピッタリくっ付けて見ているようなもので、何も見えていないのと同じです。『いくら名画と言ったって、こんな近くじゃ何にも見えやしない。もう少し離れたところから見てみよう。何が描いてあるか少しはわかるはずだ』ということで、少し後ろへ下がってみようかと思った途端、死んでしまう。それが人間の寿命の長さです。人生が名画だとしても、悔しいことに自分ではそれを見ることは決してできません。
さて一方で、人生についてわかっていることもあります。人間がそれぞれみんな違うということは、人間一人一人にはそれぞれ異なる生きる意味があるはずだということです。十人十色というように、十人いれば十種類の異なる生きる意味があり、百人いれば百の生きる意味、千人いれば千の、十万いれば十万の違った生きる意味がある。現在人類の人口が七十八億人ですから、当然七十八億人の違った人間がいて、今の地球には七十八億種類の生きる意味があるということになります。
それにしても人生の意味がそこまで多くなってしまうと、大部分の人間の生きる意味はそれほど立派なものではなくなってしまうのではないでしょうか。何しろ私個人の生きる意味は、人類全体の生きる意味の七十八億分の一の価値しかありません。これでは顕微鏡で見なければ見えないほどの小さな小さな生きる意味になってしまうことでしょう。
昨日、私は、道路の真ん中でひっくり返り手足をジタバタさせている虫のカナブンを見つけました。このカナブン、このままでは車に轢かれるか、カラスに食べられるか、あるいは鬼ごっこをしている子供たちに踏まれるかして、死んでしまいます。そこで私はひっくり返っているカナブンを手に取り、近くの木の幹に付けてやりました。おかげでカナブンは自由を取り戻し、道路で死なずにすみました。
そこでふと思ったのです。
もしかしたら私の人生の意味は、このカナブンを救出したことかもしれない。もしかしたら、このカナブンを救ったことで、私の人生の目的は達成されてしまったのかもしれない。そう思いました。なにしろ私の人生の意味は、人類全体の生きる意味の七十八億分の一。恐ろしく小さいのは間違いないのですから、そういうことだってあり得る話です。私は昨日カナブンの命を救うために、約五十年前この地球に生を受け、それからだらだらと無意味な五十年間を生き、ようやく昨日人生の目的をたったの三秒で終わらせると、再び残りの無意味な人生をまただらだらと死ぬまで続ける。これが私の人生の全てなのかもしれません。
まあそれでもいいじゃないか。と思います。先ほども申し上げた通り、幸いなことに私たちは自分で自分の人生の意味を知ることはできません。だから人生の意味についてどんな妄想をしても私の勝手。自由に頭の中で勝手気ままに自分の人生の意味を創り出すことができます。カナブンを救うだけの私の人生にも、もしかしたら何か重大かつ特別な意味があると想像することだけはできます。
例えば、あのカナブンが死なずにすんだおかげで、翌朝生きて小さなフンをしたとします。そのフンが特殊な分子構造を持つフンで、その特殊な栄養が引き金となり、それを吸ったたまたま隣にいた雑草がある日、突然変異を起こし、これまでの植物の数万倍の二酸化炭素を吸収し、そこからさらに数億倍の酸素を放出する能力を獲得したとしたらどうでしょう?やがてこの植物が地球の汚れきった空気を大量に消費することで大繁殖し、その排出したきれいな酸素によって地球温暖化が解消され、ひいては人類を絶滅から救ってくれる。そんな事だって起こるかもしれません。小さなカナブンのさらに小さなフンが地球を救うのです。そしてそのカナブンの命を救ったのは、誰あろうこのわたくしであります。
永遠の因果と宇宙の長い歴史から見れば、そんなことが起こってもおかしくはありません。だとすると、ひっくり返ったカナブンを元に戻すだけの私の小さな人生にも大きな意義があったことになります。
本編
さて、
時は戦国、混乱の世。
所は美濃国といいますから今の岐阜県の山中です。
その裏寂しく山深い小さな盆地、美濃の町外れから数えて山を五つと、さらに丘を二つ越えた所に、これからするお話の舞台となる田平子村(たびらこむら)はありました。この田平子村を取り囲み、見下ろしている四方の丘陵のうち村人から「北の山」と呼ばれている小高い丘の上にあるのが、かの有名な蛙鳴寺(けいめいじ)です。ご存じないでしょうか?有名だったのはその当時、寺がまだあった戦国時代までのことなのでご存じないのも仕方ありません。その当時だって、有名だと思い込んでいたのは田平子村の住人だけだったかもしれません。田平子村の住人たちはこの寺を自分たちの菩提寺として親しみ大切にし、ことあるごとに麓からほぼ直角に伸びる急斜面の石の階段を三百一段せっせと登っては、よくお参りをしておりました。
そんな田平子村の住人にとって有名な蛙鳴寺は、村の言い伝えによると創建は古く平安時代、遣隋使に随行した僧侶の弟子、と仲のよい知り合いだった僧の随身という人が、この地を鎮めるために、高さ一尺ほどの小さな木彫りの阿弥陀様の立像を祀ったのが最初と言われています。
以来数えて五代目の住職の才遍(さいぺん)和尚がこのお話の主人公で、この方は大変に優れた僧侶で若い頃には有名な比叡山で修行し、人徳に優れ、その広い博識は海よりも深いと、もっぱら田平子村の住人からいたく尊敬されておりました。
「みんな揃ったか?」
才遍和尚は寺の小僧さんたちを本堂に集めました。この時、才遍和尚は四十五歳。若い頃自分に課した厳しい修行と白い顎髭のせいで、小僧さんたちにはお爺さんと思われておりましたが、実際はまだ四十代でした。
「はい。和尚様。四人揃いました。」
「墨念(ぼくねん)。わしは全員と言ったはずだ。わしの弟子は五人。四人ではない。」
蛙鳴寺の小さなお堂で、正座する才遍和尚とその後ろの御本尊の阿弥陀如来像と向き合い、これまた正座しているのは四人の小僧さんたち。和尚から見て右から墨念、木念(もくねん)、即念(そくねん)、鎮念(ちんねん)、皆十代前半ぐらいの年頃です。
「なぜ与太を呼ばん?」
「時間も時間ですので、与太には夕餉の支度をさせております。」
答えたのは一番弟子の墨念です。頭の回る墨念は気を利かせ、あえて頭の弱い与太を呼ばなかったのに和尚様から怒られ不満げです。
「鎮念、与太を呼んでまいれ。」
「はい。」
和尚が一番左端に座っている四番弟子の鎮念に命ずると、鎮念はサッと立ち上がり、外へ出て行きました。
才遍和尚は三人の弟子を前にそれ以上何も言わず、じっと目を瞑り、皆が揃うのを待っております。
「和尚様。私はただ、」
「墨念、言うには及ばず。わしは怒っているわけではない。」
それを聞いても墨念はまだ不満そうですが、三番弟子の即念は和尚様が怒っていないと聞いてホッとしました。
「ボクネンさんが『お前は夕餉の支度をしろ』っていうもんですからね。俺はてっきり呼ばれてないんだと思っていたもんでね。あ、和尚さん、どうも。」
与太が鎮念に向かって大声で言い訳をしながらお堂へ入ってきました。
与太を連れてきた鎮念は黙って元いた位置に正座しましたが、与太は居心地悪そうにおずおずと鎮念の隣に立ったまま座ろうとしません。
「まあいい。与太、そこに座りなさい。」
「へえ、そうですか、和尚さまがそう言うのなら、そうしますがね。だけど夕食が遅くなったって俺は知りませんよ。だいたい俺はどうも正座ってやつが苦手で。」
「早くしろ!」
墨念が叱りつけるとようやく与太も観念して座りました。
与太もまた他の小僧さんたちと同じく当時まだ十代前半。頭が弱いせいで弟子たちの中でも一番下の五番目にされておりました。名前も与太のまま。他の小僧さんたちが名前にみんな何とか念という立派な名前が与えられているのに、与太だけ頭が悪いので、意地悪で名前を与えられなかった訳ではありません。心やさしく博識の才遍和尚はそんな愚かなことをする人物ではありません。和尚はつねに弟子たちを平等に扱い、与太にも立派な何とか念という、小さな僧侶に相応しい名前を授けておりました。ところがいつまでたっても与太自身がその名前を覚えられない。与太が自分の名前を呼ばれても、本人がすっかり忘れているものですから、自分が呼ばれていることに気が付きません。誰か別の人が呼ばれているのだろうと、与太はどこ吹く風で返事もしなければ見向きすらしない。それでは困るということで、いつの間にか元に戻り、与太をみんな与太と呼ぶようになっていました。
だいたい与太という名前も本名かどうかはわかりません。本名すら与太は忘れてしまった可能性もあります。そもそも与太という名前は、落語の世界では頭の弱い登場人物に付けられるお決まりの名前です。与太が本当は何念なのか、はたまたその前の、孤児として才遍和尚に預けられる前の名がいったい何だったのかは、今となっては誰にも知りようがありません。なにしろ与太本人が全部忘れてしまっております。気がつくと与太は、与太になっておりました。
「うん。これでよい。これでわしの弟子は全員揃った。」
才遍和尚は静かにやさしい眼差しを弟子たちへ向けました。
「今日皆に集まってもらったのは他でもない。世が混乱をきわめておることは、お前たちもよくわかっておろう。目も覆わんばかりの戦乱の世だ。人が人を殺め、奪い、罵り合う、まさに今が末法の世であることは、仏の道に生きるお前たちにもよくわかっておるはず。与太、わかるか?」
「もちろんわかります。で?何がです?だいたい世の中ってのは、」
「黙れ!」
一番弟子の墨念が一喝すると、与太は黙りました。
「うん。与太、お前は後で兄弟子たちに聞くとよい。弟子たちよ。この平和な村にも、いつ兵(つわもの)どもが押しかけてきて、収奪のかぎりを尽くさんとも限らぬ。そのようなことになれば、わしたちも全員皆殺しとなるであろう。」
和尚の言葉を聞き、与太以外の弟子たちは不安げにざわめきました。与太だけは腕を組み眉間に皺を寄せ『うん、うん』とうなずきながら納得したように聞いています。
「和尚様、お言葉ではございますが、ここは御仏を祀る神聖な場、いかに兵どもが野蛮だとて、この寺を襲うことまでは、」
と三番弟子の即念。
「植林寺が焼き討ちにあった。」
植林寺というのは田平子村から丘を二つ越えた向こうにある隣村の寺で、才遍和尚の言葉を聞いた弟子たちは皆一様に息を飲みました。もちろん与太以外の弟子です。与太は相変わらず腕を組み、わかったような顔で和尚の話を聞いています。
「まさか。」
絶句したのは二番弟子の木念。
「わしもまさかとは思ったが、今朝ここに寄った旅の僧侶が教えてくれた。隣村の植林寺を襲ったのは野武士の一団だそうだ。熊蕨(くまわらび)和尚以下十人、寺の者は全員一人残らず殺されたという。弟子たちよ。間違いなく次はここ田平子村だ。もはや寺も聖域ではない。今天下はまさに地獄の業火で何もかもが焼き尽くされようとしておる。」
弟子たちに動揺が広がります。これももちろん与太以外。
「わしはな、今一度、世に仏の灯火を灯そうと思う。仏の法で乱世を治めようと思う。ついに、わしの覚悟は決まった。」
ここで間を置き、才遍和尚は弟子たちの顔を順に一人一人見つめます。もちろんそこには与太も入っています。与太は和尚様の真剣な眼差しに、自分も精一杯の真剣な眼差しで応えました。
「よいか。弟子たちよ、よく聞け。わしは即身仏の行に入る。」
与太以外の弟子たちが一斉に息を飲みました。あまりの驚きで声も出ません。今度ばかりは与太もいちおう隣にならい、驚いたふりをします。
「今すぐ支度にかかれ。」
「し、しかし、和尚様。」
ようやく一番弟子の墨念が声を出します。
「墨念。わしの決意は固い。衆生を苦しみから救うにはもはやこれしか方法はない。」
「うっ。」
墨念が涙を拭いました。若い墨念にも今が恐ろしい乱世だということはよくわかっております。和尚様が誰よりも人々の苦しみに心を痛めていることも、墨念は身近にいてよくわかっておりました。そして和尚様が言い出したら聞かないことも。
一番弟子の墨念の涙は、隣の二番弟子へと伝染し、二番弟子の涙は三番へ、三番の涙は四番へと移り、弟子たちは和尚様の前で正座したまま涙にくれました。ただ四番弟子の涙は五番弟子の与太へは移りません。与太には何が起こっているのかわからなかったからです。みんなが泣いているので、何か大変なことなんだろうとまではわかっても、中身がわからなければ泣きたくても泣きようがありません。
「チンネンさん、おめえがなんで泣いてるんだか、俺にも教えてくれねえか?俺もみんなと一緒に泣きてえんだ。」
与太が小声で、隣で泣いている鎮念をこづくと、
「うわーん。」
声をかけられたことで、鎮念の堪えていた涙が堰を切ったように溢れ出てきてしまい、答えることができません。鎮念は泣きながら自分の代わりに与太に教えてやってくれと、さらに隣の即念をこづき、与太を指さします。
「なんだ?与太。」
「ああソクネンさん、俺にはちっともわからねえんだ。その何とかって修行がよ。おめえたちはいってえなんだってワンワン泣いてるんだ?」
「そ、そんなことも、おめえにはわからねえのか!うわーん。」
即念もまた、泣くまいと必死に我慢していたのに、与太に声をかけられて一気に涙が溢れ出てきてしまいました。
「ダメだ。涙が止まらねえや。おい木念、お前が教えてやってくれ。」
「うるせえ!俺はそれどころじゃねえんだ。だって、だって和尚様がよう。うわーん。おい墨念、お前が教えてやってくれ。」
「もうよい。」
和尚様が見かねて口を開きました。
「若いお前たちが即身仏の行を知らなくてもせんないこと。よいか。この修行はわしからお前たちへの最後の教えとなるだろう。ゆえによく聞けよ。即身仏とはな、生きたまま仏となる最も尊い修行だ。それゆえに最も厳しい修行とも言える。すなわち、わしはこれから小さな箱に入る。お前たちはわしの入ったその箱を地中深く埋めるのだ。わしは箱の中で自らが仏となるまで座禅を組み経を唱え続ける。これが即身仏の行だ。」
五人の弟子は口をポカンと開けて和尚様の言葉を聞いています。
「わかったか?」
誰も返事をしません。
「わかったなら。いつまでも座ってないで、さっさと支度をしろ。」
「あのう和尚様。」
「なんだ与太?」
「みんなにはわかったかもしれねえが、俺にはまださっぱりわからねえ。」
「何がわからない?」
「和尚様は、俺たちに和尚様が座って入れるくれえの木の箱を作れってのか?」
「そうだ。」
「ああそうか。そういうことか。そういうことだってさ。チンネンさん、おめえわかってたか?」
「ああわかってたさ。」
「だけど俺にはまだわからねえ。和尚様はその箱を地中深く埋めろって言ったぜ。俺にはそう聞こえた。」
「ああ確かにわしはそう言った。」
「だけど和尚様、そんなことをしたら死んじまうんじゃねえかな?息ができねえもの。」
「息はできる。」
「いやできねえ。土ん中じゃあさすがの和尚様だって息はできねえと思うな。俺も何度か土ん中に頭をぶっ込まれたことがあるからわかるんだ。息はできねえ。」
「ただ闇雲に土の中へ入ったら、さすがのわしでも息はできぬ。ゆえに箱にはちゃんと穴を開け、そこに竹筒を挿して地上から気を取り入れるから大丈夫、息はできる。」
「なるほど。さすがは和尚様だ。じゃあ俺たちの作る木箱にはキリで丸く穴を開けて、長い竹筒を挿すってわけだ。確かにそれがありゃあ土の中でも息ができるね。だいたいそんな大事なことを和尚様も言い忘れるかねえ。なあソクネンさん、おめえは知ってたか?空気穴を開けるってこと?」
「ああ、も、もちろん知ってたさ。」
「なんだ。みんな知ってたってことか。だけど空気だけじゃだめだぜ。それで和尚様、飯はどうやって運ぶ?水は気と一緒に竹筒からチョロチョロって入れりゃあいいが、飯はそうはいかねえ。土の中の箱まで飯はどうやって運ぶんだ?」
「与太、飯はもういらぬ。水もだ。」
「すると和尚様は飲まず食わずってことか!箱に入って、土の中に埋められて、飲まず食わずたあ驚いた。そりゃあえれえ修行だ。ようやくみんなが怖気づいてシクシク泣いている意味がわかったよ。で、和尚様、それはいつまで続けるつもりだ?」
「仏となるまでだ。わしが仏となるまで修行は続ける。」
「いつ仏になる?」
「わからぬ。」
「わからねえんじゃ困るな。大事な和尚様が飲まず食わずで土ん中埋められて、仏になる前に死んじまったらどうする?」
「死にはせん。」
「いや死ぬね。」
「死なぬと言うておる。」
「死ぬさ。間違いねえ。」
「いや死なぬ!わしは仏となるのだ!」
「頑固な和尚様だ。じゃあ万が一よ、おめえ様が腹減ってよ。仏様になる前に死んじまったらどうするんだ?」
「それこそが仏となるということだ。バカ者。もうよい。時間がない。皆の者、さっさと支度にかかれ。」
才遍和尚の号令で、五人の小僧さんたちは翌朝早くから仕事に取り掛かりました。
この五人はまだよくわかってはいないようなので、ここで即身仏の行というものを改めてご説明いたします。即身仏の行というのは、生きたまま土の中の箱に座り、死ぬまでお経を読み続ける修行です。偉大な才遍和尚は戦国の世の中があまりにも不幸と苦しみに満ち満ちているのを見かね、ついに自らの命を絶つこの究極の修行によって人々を救おうと決断したのでございます。師のこの決断を、上から四番目までの弟子たちは、穴を掘り、木箱を作る作業を続ける中で、おいおい理解していきました。ところが、五番目の弟子、与太だけは結局最後まで和尚様の死の決意を理解することはありませんでした。これは与太の頭が弱かったせいばかりともいえません。才遍和尚をはじめ寺の誰もが皆『死』という言葉を忌み嫌い、あえて使わなかったせいでもあります。和尚様本人でさえ、『自分は死ぬのではない。成仏して世を救うのだ』と思い込んでいたのですから、弟子たちが『和尚様が死ぬ』と一言も言わなかったのも仕方ありません。おかげで弟子たちの中で与太だけが嬉々として作業をしておりました。
「まったく、こんな深い穴に埋められたら、並の人間だったら死んじまうぜ。」
本堂脇の開けた場所に穴を掘り、額に汗を流しながら与太はうれしそうに呟きました。隣には三番弟子の即念が、黙々と槌を振り、共に穴掘りをしています。
「なあソクネンさんよ、俺には最初からわかっていたぜ。みんなは俺のことをバカだバカだっていうけどよ、こんなバカでもすっかりわかってたんだ。俺の和尚様はただもんじゃねえ。土ん中に埋められたって生きてるんだからな。しかも仏様になるってんだぜ。驚いたのなんのって、なあソクネンさんよ、おめえもそう思うだろ?」
「・・・」
「生きたまま仏様になろうなんて、うちの和尚様でなけりゃあ誰も考えつかねえ!さすがはうちの和尚様だ。なあソクネンさん?」
「・・・」
「考えただけでもゾクゾクするな。修行が終わって穴から出てきた頃にゃあ、和尚様はもう人間じゃねえんだぜ。立派な仏様になってるんだ!なあソクネンさん、仏様っていったいどんな格好をしているのかな?やっぱり御本尊の阿弥陀様みたいだろうか?和尚様はあんな風になって箱から出てくるのかな?いったい俺はなんて声をかけたらいいんだろうな?仏様には何を言えばいいんだ?なあソクネンさん?」
「いいから黙って穴を掘れ。」
この時、即念だけでなく他の兄弟弟子が与太にしっかりと即身仏について説明をしていたならば、ずっと後になってあんなことにはならなかったはずです。もし才遍和尚自身が『自分は穴の中で死ぬのだ』とはっきり与太に伝えていたら、和尚もあんなことにならずにすんだのかもしれません。
三日後。
ついに小僧さんたちは五人で苦労して人間一人が座って入れるだけの立派な木箱を作り上げ、本堂の横に深い深い穴も掘り上げてしまいました。その間、才遍和尚はずっと本堂の阿弥陀如来像の前に座り、お経を唱えておりました。
「和尚様。準備が全て整いましてございます。」
墨念の感情を抑えた言葉に、
「うむ。」
和尚様はお経を止め、感情を抑えて答えました。
いよいよ才遍和尚が即身仏の行に入る瞬間が訪れたのです。
身を清め、正装に身を包んだ才遍和尚は、満足げにこれから自分が入る大きな穴を見下ろすと、並んで立っている弟子たちを振り向きました。
「短い間によく準備してくれた。礼を言うぞ。」
弟子たちは、与太以外必死に涙を堪えすすり泣いています。
この日、蛙鳴寺に集まったのは才遍和尚とその弟子たちの合計六人だけ。和尚はあえて麓の田平子村からは一人も呼びませんでした。呼ばないどころか今日のこの日、自分が即身仏の行に入ることすら弟子以外の誰にも言っていません。言えば、必ず反対する人が出て、時間をかけて説得しなければならなっただろうし、そんなことをしているうちに世の中はさらに荒れていってしまいます。また才遍和尚は非常に思いやりの深い人物だったので、自分のために他人を騒がせ、また悲しませたくはなかったからです。奇しくも季節は秋、村は収穫の最も忙しい時期だったこともあり、才遍和尚は幼い弟子たちだけを見守り人として、一人静かに即身仏となる決意を固めておりました。
ただもし才遍和尚がごく普通の僧侶、どこにでもよくいるこれ見よがしに自分の修行を自慢して回るようなごくありふれた坊さんだったとしたら、それからずっと後になって、あんなことにはならなかったはずです。和尚の奥ゆかしさに歯痒さを感じます。
現代の僧侶の中にも、自分の修行にわざわざテレビ局を呼んで取材させるような自己顕示欲の強い人がおります。そこまでいかなくても才遍和尚に少しでもこれみよがしな性質があり、村の人の一人でもその場に呼び、立ち合わせていさえすればと残念に思います。しかし清廉潔白な才遍和尚にはこれみよがしな性質は一切備わってはいませんでした。和尚はただただ仏のみに使える立派なお坊さんでした。
分厚い座布団をひいた木箱に入る直前、大きな穴の前に才遍和尚は弟子たちを整列させ、一人一人に一人前の僧侶になった証として新しい名を与え、一人一人にその性質に見合った公案を与え、一人一人にやさしく慈愛に満ちた言葉をかけていきました。
最後の与太にも、和尚は一人前の僧侶にふさわしい立派な名を与えました。与太がまた新しい自分の名を忘れてしまわないように、和尚は何度もその名を与太に言って聞かせ、何度も復唱させたにも関わらず、
「さあ与太、お前の新しい名を言ってみよ。」
と最後に問うと、与太は自信を持って、
「わかりました。あっしの名は与太です。」
と胸を張ったので、ついに和尚もあきらめてしまいました。そのためその時与太が授けられた僧侶としての新しい名は、今となっては知る由もありません。
続いて才遍和尚は与太にも公案を与えようとしましたが、すぐに思い直しました。
「うむ。与太、お前には公案の代わりに言葉を授けよう。わしがお前に与える最後の教えだ。よいか?」
「はい。」
最後と聞いて与太はなぜだかわからないなりに身が引き締まる感じがしました。
「与太よ。お前は誰よりも心のやさしい人間だ。それは僧侶として最も優れた資質と言える。資質、わかるか?」
「ししつ?」
「お前は誰よりも立派なお坊さんになれるということだ。」
「あっしが?」
「そうだ。」
「でもあっしは、」
「そうだ。わかっておる。お前は経も読めぬし、読み書きもできぬ。これからもできぬであろう。だがな、それでもお前は立派なお坊さんになるとわしは確信しておる。」
「あっしが?」
「そうだ。さっきからわしはお前に話しておる。だがな、与太、ただ生きているだけでは立派な僧侶にはなれん。誰だって立派な僧侶となるためにはな、修行が必要だ。」
「修行?」
「そうだ修行だ。与太、わしは今からお前に一つだけ修行を与える。お前は生涯をかけてこれからわしの与える修行を続けるのだ。」
「わかりました!だけど和尚さん、あっしは何をやりゃあいいんです?」
「それを今から言う。いいか与太、よく聞けよ。これはわしがお前に与えることができる最後の言葉だ。」
和尚さんから真剣な目で見つめられ、再び最後という言葉を聞くと、与太はなんだか悲しくなり自然と目に涙がいっぱいに溜まってきました。
「だけど和尚さん、グスン、この修行が終わったら、グスン、また穴から出てくるんでしょ?仏様になってまた会えるんでしょ?」
「ああそうだ。わしは仏となり未来永劫ずっとお前のすぐそばにおる。だがな、生きた人間として話せるのはこれが最後だ。だからよく聞くのだ。」
「グスン。はい。」
「与太、今日からお前は一人前の僧侶だ。僧侶として、困った人がいたら必ず助けなければならない。」
「困った人を助ける。」
「そうだ。これからお前は大人となり世に出る。すると様々な困難がお前を待ち受けている。お前の頭が悪いと言ってバカにする者もおる。お前の頭が悪いと言って、石を投げてくる者さえおるだろう。だがな、そんな酷い目に遭っていたとしても、お前は困った人を見たら、見て見ぬふりをしてはならぬのだ。たとえ相手がお前の憎っくき敵であったとしても、その者が困っていたら、すぐさま駆けつけ助けねばならぬ。よいか。それが、お前の僧侶としての唯一つの修行だ。それができれば、お前は必ずや人から尊敬される立派な僧となることができる。」
「困っている人を助ける。」
「そうだ。困っている人を助けなさい。これはお前の修行でもあり、わしの願いでもある。与太、頼むぞ。困っている人がいたら、必ず助けてやってくれ。」
「和尚様!あっしは、あっしは何があっても絶対に困っている人を助けます!」
ついに与太は泣き出してしまいました。つられて他の四人も泣き出しました。
才遍和尚は両手を合わせ、お経を唱え始めるとそのまま箱の中に入り坐禅を組みました。五人の弟子たちは泣きながら箱の蓋を閉め、釘を打ち、空気穴に竹筒をしっかりと挿すと、ゆっくりと丁寧に和尚さんの入った箱を穴の一番底まで下ろし、泣きながら上から土をかけ、竹筒の先端だけを一寸ばかり残して、箱をすっかり地中深く埋めてしまいました。
最後に、五人は地面に四つん這いになり、地中から突き出た竹筒の先端に耳を寄せると、中から和尚様が唱えるか細いお経が漏れ聞こえてきました。それを聞いて五人の小僧さんたちはさらにまた声を上げて泣きました。
それから数日間は何事もなく過ぎました。五人の小僧さんは和尚さんのお経が漏れ聞こえてくる竹筒の周囲に座り、一緒にお経を唱えて一日を過ごし、夜暗くなるとそれぞれ竹筒の和尚さんにお休みの挨拶をして寝床へ行き、また夜が明けるとともに竹筒の周囲に集まっては日がな一日、竹筒から聞こえるお経と共に自分達もお経を唱え続けるという生活を送りました。
時々、竹筒から和尚さんのお経が聞こえなくなると、小僧さんたちは心配そうな顔でお経を唱えるのを止め、恐る恐る竹筒に耳を傾けます。しばらくして、またか細い和尚様のお経が聞こえてくると、小僧さんたちは一先ずは安心とまた共にお経を唱え始めます。
「和尚さんはいつお経を止めるんだろうね?」
与太がいぶかしげに聞いても他の四人はお経を唱え続けています。
「お経が聞こえなくなってから一月経って掘り起こせって和尚さんは言われたけれど、どうかな?ボクネンさん、それじゃあちっと遅過ぎるんじゃないかな?」
与太は一番弟子の墨念に聞きましたが、墨念は一心不乱にお経を唱えるだけで答えてはくれません。それでも構わず与太は話し続けます。
「和尚さんは飲まず食わずでいいって言うけどさ。やっぱり少しは食べた方がいいんじゃねえかなあ。なあモクネンさん、この竹筒から何か精のつく物を流し込んだ方がいいんじゃねえか?味噌汁なんかはどうかな?」
木念もまた与太の言葉を無視してお経を続けます。
「待て!あ!あれはなんだ?」
突如として声を上げたのは即念です。小僧さんたちはお経を止め、即念の指差す方を見ると、眼下に広がる田平子村を挟んで、寺の反対側の南の丘の峰に一人の騎馬武者の姿があります。
「あれは野武士だ。」
墨念が吐き捨ているように言いました。すると向かいの丘の峰にもう一人、また二人と同じような騎馬武者が姿を見せます。最初にいた騎馬武者は後から来た騎馬武者にまず小僧さんたちのいる寺を指差し、次に眼下の盆地に広がる田平子村を指差しました。
「奴らは村を襲う気だ。」
墨念が歯軋りをしました。
「早く村のみんなに知らせないと!」
叫んだのは三番弟子の即念。その声に突き動かされてみな走り出そうとするのを、
「待て!」
止めたのは一番弟子の墨念です。
「もう間に合わない。」
向かいの丘を見ると、みるみる野武士たちの数が増えていっています。
「もう手遅れだ。俺たちも今すぐ逃げないと殺される。」
墨念は仲間の顔を一人一人見ながら言いました。ところが与太がいません。どこにいるのかと見回すと、急な石段の下から息を切らせて戻って来ました。一人だけ走り出したはいいが、誰も付いて来ていないことに石段の途中で気がつき戻って来たのです。
「おいおめえたち!何をそんなところでモタモタしている?早く村の人たちに知らせてやらねえと大変なことになるんじゃねえのか?」
「与太、俺たちは村へは行かない。」と墨念。
「どうして!早く知らせてやらねえと、和尚さんが言った隣村みてえにみんな殺されちまうぞ!」
「もう手遅れだ。与太、俺たちは逃げる。」
「モクネンさんにソクネンさん、それにチンネンも、みんなそれでいいのか?村の人たちが殺されてもいいのか?」
聞かれた三人はうつむいたまま答えません。
「与太、お前は死にたいのか?」
代わりに墨念が与太に聞きます。
「死にたかねえ。死にたかねえよ。だけど和尚様は俺に『困った人がいたら必ず助けろ』って言った。『絶対に見て見ぬふりをするな』ってな。だから俺は村の人を見捨てて逃げるなんてことはできねえ。」
「そうか、わかった。」
墨念は何かを決心しました。そんな墨念を他の四人は真剣に見つめます。
「わかった。与太、逃げようなんて考えた俺がバカだったよ。お前は先に村へ行け。村へ行ってみんなを逃せ。俺たちはこれから和尚様を掘り出して、安全な場所に避難させてからお前の後を追う。みんなで村を助けよう。」
「さすがボクネンさん、そうこなくっちゃ!俺、慌ててたから和尚様のことをすっかり忘れてたよ。そうだな。掘り出さねえと和尚様まで死んじまうからな。じゃあボクネンさん、みんな、和尚様を頼んだぜ。」
そう言い残すと、与太は長い石段を駆け降りて行きました。
「さあ和尚様を掘り起こそう!」
叫んだのは即念。ところが墨念と木念は何も言わず、寺の裏へ、村とは反対の方角へ歩き出しています。
「墨念さん!木念さん!早く和尚様を掘り出さないと!」
「即念!鎮念!行くぞ!」
怒鳴ったのは木念。
それを聞いて鎮念はおずおずと和尚様のお経が聞こえる竹筒から離れ、やがて駆け出すと先を行く墨念と木念に合流しました。
「即念、お前はどうする?」と墨念。
「俺は、俺は、」
即念はバッと地面に突っ伏し、竹筒に向けて叫びました。
「和尚様!和尚様!教えてください!私はどうしたらよいのです!」
ところが竹筒から聞こえてくるのは和尚のか細いお経の声だけ。即念の問いには答えてくれません。
「和尚様!」
「即念さん、行きましょう。」
戻って来たのは鎮念。即念の肩をやさしく抱き、
「僕はあなたに死んでほしくはありません。」
と耳元に呟きました。
「和尚様!ごめんなさい!ごめんなさい!僕はまだ死ねません!」
鎮念に促され、即念は泣き叫びながら寺の裏へと歩みを進めました。
「急ぐぞ。」と墨念。
四人の小僧さんは寺の裏から裏山へと入り、そのまま姿を消しました。以後、この四人の姿を見た村人は一人もいません。
一方、
村へと走った与太は、
「大変だー!大変だー!みんな逃げろー!野武士がくるぞー!皆殺しにされるぞー!」
と大声で怒鳴りながら、寺の長く急な三百一の石段を転がり落ちて行きました。
それを聞いた村人が、
「こいつは大変だ!みんな!逃げろ!野武士がくるぞー!」
と大声で駆け出し、それを聞いた他の村人がそれぞれ
「大変だー!」
と大声で駆け出したので、急の知らせはあっという間に村の隅々まで伝わりました。そうなると世は戦国です。田平子村の人たちだって隣の村が焼き討ちに合い皆殺しにされたのもよく知っています。普段から非常の時にはどうするか皆で話し合い、すでにしっかりと段取りはついていました。野武士どもが気勢を挙げ、丘を駆け降りるよりも早く、村人たちは大人も子供も老人も全員残らず秘密の谷に避難を終えてしまいました。
いや、一人だけ、避難しなかった村人がおります。与太です。与太だけはみんながすでにいないことにはまったく気がつかず、
「大変だー!みんな逃げろー!」
誰もいなくなった村を一人大声で走り回り、必死に避難を呼びかけています。
「大変だぞー!大変なんだぞー!みんな殺されちまうぞー!」
夢中で怒鳴っているので、村には自分以外すでに誰もいなくなったことに与太はまったく気がつきませんでした。
「おい、みんな無事に谷に入ったか?」
谷の入り口の、村を見渡せる岩陰にいるのは田平子村の中でも屈強な三人の男衆。世話役の銀蔵と鍛冶屋と牛飼いの男。三人はここで村を見張り、万が一野武士たちがこっちへ来たらここで食い止め、一戦交えようとそれぞれ、鍬や鎌で武装しています。
「ああ、みんな無事だ。一人残らず谷に隠れた。」
「おい見ろよ。」
男の一人が指差す方を見ると、百人はいるかと思われる野武士どもが村へなだれ込んでいきます。
「間一髪だったな。寺の小僧さんが教えてくれなかったら命はなかったぜ。」
「そういや、あいつはどこにいる?谷にいたか?」
「あいつって誰だ?」
「だから小僧さんだよ。与太の野郎だ。あいつのおかげで助かったんだ。与太も谷に入ったか?」
「いや、見なかったぞ。」
「与太ならいるぜ。」
「ああよかった。これで全員だ。」
「違う。与太は谷にはいねえ。」
「じゃあどこにいる?」
「あそこだ。」
牛飼いが唇を噛みながら悔しそうに顎をしゃくったのは村の方角。
見ると、男たちの目に空っぽの村の中を叫びながら走り回る与太の姿が飛び込んできました。耳を澄ますと与太は『みんな逃げろー!大変だー!早く逃げろー!』と叫んでいます。
「バカだなあいつは。もう誰もいやしねえのにまだ叫んでやがる。」
「助けに行かねえと。」
鍛冶屋が岩陰から飛び出そうとするのを、牛飼いが腕を掴んで止めました。
「もう遅い。」
野武士どもは雪崩のように村へと流れ込み、ようやく与太もそれに気がついたようです。『いけねえ!』というふうに飛び跳ねたのを岩陰から三人の男たちは見ました。
「早く逃げろ!」
大声は出せませんが、歯軋りをしながら岩陰の男たちは声に出せない声を出します。
「早く!早く!早く!与太!早く走れ!」
言われなくても与太だってそこまでバカではありません。殺されてなるものかと全速力で逃げ出しました。ところが向かった先は谷とは反対の方向。
それにしても、
方向音痴の人というのは、どうしていつも間違った方向へ行ってしまうのでしょう?どっちかわからないから適当に行ってみたら偶然正しい方向へ向かっていて、無事目的地に着いた、という奇跡が、方向音痴の人に起こることはまずありません。必ずといっていいほど方向音痴の人は間違った方向へ進みます。与太もまた例に漏れず方向音痴でした。
「バカ!そっちじゃねえ!」
鍛冶屋が小さな声で怒鳴りました。
「まったく反対に走りやがって。谷はこっちだぞ。だからあいつはバカだってんだ!寺の小僧どもの中でも一番のバカだ。」
「いや。違う。バカはお前だ。」
三人の男衆たちの中で、一番年上で村の世話役の銀蔵が言いました。
「なんだって?」
「バカはお前だってんだ。バカ野郎。」
「なんで俺があいつよりもバカだ?」
「わからねえか?いいか?あいつはわざと谷とは反対の方角に走ったんだ。」
「あ!」
「やっとわかったか?あいつがこっちに走って来てみろ。侍どももこっちへきて、谷に逃げている者もみんな見つかって殺されちまう。そうじゃねえか?ええ?あいつはな、わざと最後まで村に残ったのよ。侍どもを誘き寄せ、みんなが逃げている谷から遠ざけるためにな。」
「そうだったか。それを知らねえで俺は、すまねえ与太!頼む!逃げてくれ!お願いだから死なねえでくれ!」
もちろん与太にそんなつもりは微塵もありません。それどころか無我夢中でみんながいると思った方向へ逃げていました。ただその方向が間違っていただけです。
数名の騎馬武者が逃げる与太に気がつき、後を追い出しました。馬で追えばすぐに捕らえられるのに騎馬武者たちはあえて与太を走らせているようです。
「どこへ逃げる気か、様子を見ているんだ。」
銀蔵が呟き、他の二人もうなずきます。
やがて騎馬武者の一人が弓を引き、馬上から矢を与太へ向けて狙いを定めました。与太が西の丘へと逃げるとわかったからです。与太はもう用済みになりました。
「当たるな、当たるな、当たるな、」
男たちは矢が与太に当たらないよう必死に祈りましたが、祈りは届かず、解き放たれた矢は一直線に逃げる与太の尻を射抜きました。
尻を蹴飛ばされたかのように飛び上がり、そのまま与太はうつ伏せに倒れました。倒れたところから砂煙が上がります。
「ちくしょう!」
ところが与太は再び立ち上がり、足を引き摺りながらもまた走り出します。騎馬武者は冷徹にもう一度背中から弓矢を取り出すと二の矢を引きました。
「逃げるな!隠れろ!隠れるんだ!次の矢がくるぞ!」
男たちの心の叫びも虚しく、放たれた矢はついに与太の背中の真ん中に突き刺さり万事窮す。両手を上げて飛び上がると与太はそのまま再びうつ伏せに倒れてしまいました。もう一度立ち上がってくれるかと、男たちは息を飲んで見ていましたが、ついに与太が立ち上がることはなく、ピクリとも動くことはありません。
「ああなんていうことだ。」
倒れている与太のすぐそばを騎馬武者や足軽たちが追い越して行きます。与太にはそのつもりがなくても与太の誘導作戦は成功したのです。
野武士どもは田平子村の田畑を荒らし尽くし、食料や衣服その他価値のありそうなものを何もかも全て略奪し終えると、村にある全ての建物に火を放ち、やがて来た道を戻って行きました。が、野武士どもの誰一人として村人が逃げ込んだ谷の方へ来ることはなく、したがって与太以外の村人の誰一人として怪我をしたり、命を落としたりすることはありませんでした。
運の良いことに、与太は生きておりました。
野武士どもが去ると、村人たちは真っ先に倒れている与太へと駆けつけ抱き起こすと、与太は意識を失い尻と背中からだいぶ出血してはいましたが、幸い矢は急所を外していて、弱いながらも息がありました。
「生きとるぞー!早く!早く手当を!」
村人たちがかき集めてきた柔らかい藁の上に寝かせられ、止血され手厚い看護を受けるとやがて与太はゆっくりと目を開けました。
「み、みんな逃げろ。」
「おお、気がついたか。皆の衆、与太が生き返ったぞ!」
叫んだのは村の世話役の銀蔵です。それを聞いて心配そうに取り囲んでいた村人たちから安堵のため息がもれます。
「早く、早く逃げないと、」
「ああ、もう心配するな。みんな無事だ。」
「無事?」
「そうだ。無事だ。お前が知らせてくれたおかげで、みんな奴らが来る前に逃げることができた。」
「じゃあ和尚様も無事なんだね。ボクネンさんたちも。」
銀蔵は困ったように周囲の村人と顔を見合わせました。
「才遍和尚も小僧さんたちもここにはいねえ。」
「じゃあ寺にいるんだ。」
「わからねえ。寺の者でここにいるのは与太、お前だけだ。」
「ボクネンさんは『和尚様を掘り出してすぐにお前を追って村へ行く』ってそう言ったんだ。」
ここで村の人たちが「和尚を掘り出す」とはどういうことなのか、与太に質問して詳しく聞いていれば、後々ずっと後になってあんなことにはならなかったと思われます。ただ、村の人にしてみれば、村の大恩人が生きていた喜びで舞い上がっていたこともあり、またついさっきまで意識を失っていた怪我人の言葉、ましてや村一番の頭の弱い少年の言うことを大して気にもせず、大事なことをサラッと聞き流してしまいました。
そもそも宗教というものにはわけのわからない修行があまりにも多すぎます。「和尚を掘り出す」ような不可思議な修行を寺で行っていたとしても、村人が不思議に思わなかったのもいたしかたありません。
それよりも、与太を取り囲んでいた村人たちには、村でただ一人の怪我人に伝えなければならない悲しい事実がありました。
「なあ与太、気を確かに持って聞いてくれ。」
銀蔵が言いにくそうに切り出します。
「ここから見た範囲なんだがな、あくまでもここから北の山を見た限りではの話だけれどよ、侍のやつら、どうやら、お前の寺を全部焼き払っちまったようだ。」
「え。」
絶句する与太。それでもすぐに気を奮い立たせ立ちあがろうとします。
「うっ。」
与太は痛そうに右足の付け根を抑えうずくまってしまいました。
「起き上がるんじゃねえ。まだ立ち上がるのは無理だ。与太、寝ていろ。」
「銀蔵さん、俺は寺へ行かねえといけねえ。戻って和尚さんやみんなを助けねえと。みんな、みんな困ってるはずだ。」
「いいか、おめえの尻の傷はことのほか深え。しばらくは歩けねえぞ。」
「だけど寺へ戻らねえと。」
「だめだ!おめえの代わりに誰か人をやって寺の様子を見てもらうから、おめえはここで寝てなきゃいけねえ。おい!茂助と茂平!お前たち今すぐ寺へ行って、誰かいねえか見てこい!」
「ああわかった!」
と双子の兄弟の茂助と茂平は威勢よく返事をしましたが、二人とも腰を上げようとはしません。
「今すぐだ!」
銀蔵が怒鳴ります。
「今か?」
「俺の声が聞こえねえか?」
「じゃあ茂平、行くか?」
「今か?」
「銀蔵さんは今だと言ってるぜ。」
「早く行け!」
「わかったよ。茂平行くぜ。」
ようやく双子は重い腰を上げ歩き出しました。
「走れ!さっさと寺の様子を見てこい!与太、これでいいだろ。」と銀蔵。
「はい。すいません。」
「さあ、寝ろ。」
茂助と茂平の双子の兄弟と入れ替わりに、村人たちをかき分けて、杖をついた白髪の老人がやってきました。
「あ!長老様!」
一人の小柄な少年が、老人の姿を見てうれしそうに駆け寄ります。
「長老様!与太が!与太の野郎が生き返りました!」
すると長老、自分の足元に駆け寄ってきた少年の横っ面をパーンと勢いよく平手で引っ叩きました。
「大馬鹿者が!兆吉!このお方の名を呼び捨てにするでない!」
兆吉と呼ばれた少年は、いきなり殴られて呆然となりながら痛む頬をさすり涙目で長老の顔を見上げます。
「兆吉、お前が今ここで無事にいられるのはいったい誰のおかげだ?いや、兆吉だけではない。ここにいる者皆一人一人が、今こうして生きていられるのは、いったいどなた様のおかげだと思っておる?よいか!皆の者もよく聞け!このお方がいなければ、ここにいる者は皆一人残らず殺されておったのだ!誰一人として、生きて明日の日の出を見ることはなかったのだ!わしらが生きているのは、このお方が、自らの命も顧みず寺から降りて来てくれたおかげだ!よいか!村の衆よ!よく聞け!今この時よりこのお方を呼び捨てにする者は、このわしが許さぬ。以後、このお方のお名前には必ず『様』を付けてお呼びするのだ!」
長老はそう村人たちに向けて怒鳴ると、横になっている与太のそばに正座をし、額を地面に付けました。
「与太様、この度は村の衆の命を救ってくださり本当にありがとうございました。田平子村の長として心より御礼を申し上げます。」
と恭しく申し述べました。するとそれを見た村人たちも長老に倣い、それぞれに正座をすると額を地面に付けて口々にお礼の言葉を述べました。
その様子を与太は恥ずかしそうに眺めます。
「兆吉、来い。おめえも与太様にお礼を言え。」
銀蔵は小声で、頬をさすっている兆吉を呼び、自分の隣に正座をさせました。
「さあ頭を下げろ。」
「だって銀蔵さん、」
兆吉は泣きながら不満そうに抗議します。
「兆吉さんだって、さっき与太のことを与太って、」
「シー、黙れ兆吉。頭を下げろってんだ。」
「うわーん。」
「兆吉。もういいんだ。俺は怒ってなんかいやしないよ。」
与太がやさしく声をかけます。
「与太、様、本当にありがとう。」
「本当にもういいんだよ。」
一方、蛙鳴寺へ派遣された茂助と茂平の双子の兄弟。
息を切らしながら三百一段の石段を登り切ると、麓から見てわかっていた以上に、寺は本堂も庫裡も何もかも焼け落ちて、そこかしこでまだ火の手が燻っておりました。
「誰もいねえと思うな。」
「ああ、いるわけがねえ。寺の連中は真っ先に侍どもの姿を向かいの丘に見たんだ。与太の野郎はそれで真っ先に知らせに降りてきてくれたがよ、他の奴らは一人も村には来てねえ。間違いねえ。坊主どもは真っ先に逃げたのよ。」
「だけどよ。他の小坊主どもはともかく才遍和尚はみんなから尊敬されている立派な坊さんだぜ。逃げるなんてことあるか?」
「まあせいぜい探してみようぜ。どこかでお亡くなりになっているかもしれねえ。お前はそっちを探せ、俺はこっちを探す。」
双子の兄、茂助と別れて茂平は瓦礫だらけの、元は本殿のあった場所の横へきました。
銀蔵がこの双子の兄弟を寺へやったのは正解でした。二人とも腕利きの山猟師で、人間を含めた哺乳動物の追跡にかけては村一番の手練れでした。
茂平は瓦礫の隙間から地面を覗き込むと、ふんふんとうなずきながら様子を探っていきます。
「なるほど、寺へ登ってきた侍は五人というところか。あの階段を登るだけの足腰のある野郎どもだ。見つかったらただじゃすまねえな。だが争った跡はねえ。本堂から奪うものを奪うとすぐに火をつけやがった。お、これだ。この若けえ足跡は小坊主どもだな。この辺りにやけにたくさんあるな。あいつら、ここで何をやってたんだ?」
そこは本堂横の開けた場所、燃えかすや瓦礫の隙間から見える土には複数の足跡の他に、土の中から一寸ほど突き出た竹筒の先端もありました。もちろん、茂平にとってはまさかその下の土の中に、才遍和尚が箱の中でお経を唱え、深い瞑想に耽っていることなど、夢夢知るよしもありません。さすがの猟師茂平にも小さな竹筒の存在は目に入らず、それよりも小坊主どもの足跡を追っていきました。
「うん。一つは石段の方へ走ってる。こいつが与太の足跡だ。どれどれ他の奴らは、ふん、裏山へ一直線か、思った通りだ。逃げやがったな。だけど変だな。和尚の足跡はどこだ?この辺りにそれらしいのは見当たらねえぜ。」
すると、どこからともなく微かなお経の声が聞こえてきたような気がしました。
「なんだ?和尚がいるのか?」
茂平がもう一度耳を澄ますと、今度は何も聞こえません。
「気のせいか。どうも寺ってところはうす気味が悪い。」
気を取り直し、小坊主どもの足跡を追います。
「この先の森の中に隠れて震えてるってこともあるからな。一つ、二つ、三つ、四つ、小坊主の足跡は四つ。やっぱり和尚のはない。さてこいつらは、案の定裏山に入ったな。おーい小坊主ども!いるのか?いるなら出てこい!侍どもはもういねえ!安心しろ!」
茂平は裏山へ向けて叫ぶと、深く暗い森の中へ目を凝らし、耳を澄ませました。暗い裏山の森に動くものは何もなく、何も聞こえません。
「やはり逃げたか。はっ!」
引き返そうとした茂平の耳に再び微かなお経の声が聞こえてきました。裏山からではありません。自分の背後、本堂の横あたりからです。
「今度は確かに聞こえたぜ。」
茂平は瓦礫の山に目を凝らし、耳を澄ませました。
「おーい茂平!なんかあったか?」
大声を上げて茂助がやってきました。
「茂平、あっちには何もねえ。こっちはどうだ?」
「静かにしろ!」
「どうした?」
茂平は茂助を無視し、瓦礫の山に耳を澄ませました。ところがもう何も聞こえません。ちょうどその時風の向きが変わり、茂平から追い風となってしまったために才遍和尚の小さなお経は吹き流されてしまったからです。
「おい茂平、何かあるのか?」
「いや、なんでもねえ。小坊主どもはみんな逃げた。そこに足跡がある。おめえこそどうだ?和尚はいたか?」
「いねえ。」
「そうだろうな。いるわけがねえ。ここにいても殺されるだけだ。与太みてえに村へ走るんでなけりゃあ、誰だって山へ逃げる。」
「どうする?」
「寺はもぬけの殻だ。帰るぞ。ここはどうにも気味が悪くていけねえ。」
石段を降りる直前、最後に茂平はもう一度寺を振り返り、お経が聞こえるかどうか耳を澄ませてみましたが、才遍和尚のお経が再び茂平の耳に入ることはありませんでした。
こうして由緒正しい蛙鳴寺は終焉を迎えました。以後数十年、与太が死ぬ直前まで旧蛙鳴寺の跡地に人が入ることはありませんでした。茂助と茂平が三百一段の石段を降りたのを最後に、寺は人々の心からすっかり忘れ去られ、完全に打ち捨てられました。そうなると自然というのは実に厳しいもので、人影が途絶えた途端、寺のあった「北の山」の上はあっという間に草木が隆々と生い茂り、蛙鳴寺の残骸を、地中の才遍和尚もろともすっかり飲み込んでしまいました。
ただ奇跡的に、和尚へ空気を運ぶ竹筒の先端だけは、地表にひょっこりと顔を出したまま、草木や土がその穴を塞ぐことはなかったのです。
「まあそう言うことだ。」
茂助と茂平から受けた報告を、銀蔵が言いづらそうに与太に伝えます。
「どういうことだ?」
「だから、茂助と茂平の話では寺の人間は全員、おめえ以外、みんなどこかへ逃げちまったってことだ。」
「つまり無事だってことだな。」
「そうなるな。」
「だったらいいんだ。」
「怒らねえのか?」
「なんで怒る?」
「和尚も他の小坊主どももみんなおめえを置いて逃げたんだぜ。」
「だけどみんな死んでねえんだろ?」
「ああ死んでねえだろうな。逃げたんだから。」
「だったらいいじゃねえか。無事で何よりだ。」
「そうか。おめえがそう言うなら、俺もそれでいいけどよ。」
銀蔵は与太が妙にうれしそうなのが不思議でした。
与太がうれしそうだったのはお寺の仲間がみんな無事だとわかった以外にも原因があります。
というのも与太が怪我の手当てを受けている間、与太のところへは村人が入れ替わり立ち替わりやってきては、皆深々と頭を下げ、中には涙を流しながらお礼を言っていきました。それだけではありません。全てが焼き払われ誰もかれもが困り果てているはずなのに、みんな与太に服や柿の実や木の実など何かしらの贈り物を持ってきてくれます。怪我をした尻と背中はズキズキと痛みますが、与太は実に良い気分でした。
「和尚様はやっぱり立派な和尚様だ。『困っている人を助けろ』なんて言うもんだからさ、俺は言われた通りにしただけなんだぜ。するとどうだ?ええ?この有様よ。もう誰も俺を与太なんて雑に呼ぶ奴はいねえ。驚いたね。みんな与太『様』ときたぜ。それに見てみろよ。この贈り物をさ。ええ?殿様だってこれほどのお宝を持っている人はそうはいねえんじゃねえかな?なあ銀蔵さん?」
「なんでえ?」
「村にはもう困っている人はいねえか?」
「困ってる人がいねえかだって?」
「ああ困ってる人だ。」
「与太、じゃねえ与太様、おめえどこに目をつけてやがる?困ってる人がいねえかだと?よく周りを見てみろ。村には困っている奴しかいねえよ。みんな着の身着のまま、家も燃やされちまったし、畑も田んぼも滅茶苦茶に荒らされちまった。これからどうしようか、どうやって生きていこうか、村の者はみんな一人残らず途方に暮れてるんだ。村で困ってねえ奴が一人でもいたら見てみてえもんだな。」
「ふーん。そうか。よし!」
と言って立ち上がりました。
「あ痛たたた。」
「おい与太、じゃねえ与太様、無理をするな。動くのは傷が治ってからにしろ。」
「銀蔵さん、俺はじっとなんてしてられねえんだ。」
「どこへ行く?」
「困った人を助けるのよ。それが俺の仕事だからな。」
そう言って与太はヨタヨタと歩き出し、道を塞いでいる瓦礫の山を片付け始めました。その様子を見た村人たちも『俺たちだっていつまでもメソメソしてられねえ!働くぞ!』と口々に言い合い、与太と共に瓦礫を片づけ出します。年寄りの中には、額に汗して働く与太を見て、泣きながら手を合わせ拝んでいる人もいたくらいです。
「まったく村にも困ってねえ奴が一人だけいたよ。」
銀蔵がつぶやくと、隣にいた兆吉がいぶかしげに
「誰だ?」と聞きます。
「与太様の野郎だ。さあ、兆吉、働くぞ!みんなで力を合わせて村を立て直すんだ!」
こうして与太の人助け人生が始まります。
東に怪我をして困っている人があれば、行って代わりに家事をしてやり、
西に鍬の折れた人がいれば、行って鍬の代わりに手で畑を耕し、
北に戦さで親を亡くした子があれば、連れて帰って親の代わりをし、
南に飢えた人がいると聞けば、行って食を与え、と、まさに東奔西走、休む間もなく与太は人助けを続けました。
人助けをすればするほど、人は皆与太を好きになります。ますます尊敬もします。これまで周囲の人からバカ、バカと言われてきたのとは大違い。村の誰もが与太の姿を見ただけで、うれしそうに手を振り、「与太様、いつもありがとう」「みんな与太様のおかげだ」と言ってくれます。それだけではありません。会う人会う人が「与太様これを食べてください」「与太様これを着てください」と次から次へと食べ物や着るものまで持ってきてくれるので、与太は暮らしにも困ることがなくなりました。挙げ句の果ては、
「さあ与太様、出来上がったぞ。これで今日からおめえも寺持ちの住職様だ。」
「銀蔵さん、俺にはおめえが何を言っているのかちっともわからねえ。」
「だから、これがおめえの寺だ。俺たちみんなで建てた村の寺だ。」
「寺?」
「そうだ。寺。」
「いや銀蔵さんよ。俺は寺なんて持ったことがねえ。だから寺なんてもらったってどうしていいかわからねえ。だいたい俺はずっと宿なしだ。それでも不自由なんぞしたことはねえ。おかげさんでな。村の誰かがいつも泊めてくれるからな。」
「驚いたね。与太様よ。一体全体おめえは今日まで誰の寺を建ててるつもりだったんだ?この村で坊主と言ったらおめえしかいねえのを忘れたか?」
「言われてみりゃあそうかもしれねえ。村の若衆どもが寺を作るって言うから俺も手伝いに来ただけで、何にも考えなかったぜ。銀蔵さんよ、みんなも、これで寺は出来上がりなのか?そうかい。出来上がったんなら結構だ。銀蔵さんも、みんなもお疲れさん。昨日ちょっとばかり耳にしたんだがな、なんでもおクニ婆さんちの屋根裏でネズミどもが大騒ぎしているっつうから、俺はすぐに行ってネズミどもをどっかよそへ追い出さねえといけねえんだ。でねえとおクニ婆さん、ネズミどもに怒り狂って狂い死にしちまうからな。それから為三さんちの牛の蘭丸にはノミだかシラミだかがいっぱいくっ付いてるそうだから、これもすぐに行って潰してやらねえといけねえ。じゃあそう言うことだから、俺はこれで失礼するよ。あばよ。」
「待て待て待て。待てよ、与太様。為三の牛のノミなんぞどうだっていいんだ。そんなのは俺がさっきおめえにしたただ世間話じゃねえか。そんなことより与太様、この寺はな、おめえのだ。さあ存分に使ってくれ。」
「俺の寺?」
「そうだ。同じことをあと何回言わせるつもりだ?俺たちだっていつまでもおめえを宿無しにしておくわけにはいかねえんだ。村のみんなで話し合って決めたんじゃねえか。あの寄り合いにはおめえもいたはずだぜ。」
「俺もいたのか?」
「ああいた。村の真ん中に新しい寺を建てよう。与太様にはその寺の住職様になってもらおうってみんなで決めたんだ。そしたらおめえ涙流して喜んでたぜ。『俺でいいのか?俺でいいのかよう?』ってな。『おめえしかいねえ』ってみんなで言ったんだ。忘れたか?」
「いやどうも、覚えてねえってとこをみると、忘れたみてえだ。」
「困った野郎だ。とにかくだよ。これがおめえの新しい寺だ。俺たち素人が作ったから立派な寺とは言えねえが、それでもみんなで心を込めて作ったんだ。小さいながら一応本堂も作ったし、もっと小せえけれどおめえの寝所も作った。台所も作ったし、客を泊める客間も作った。これでお経を上げるのも寝るのも食うのも不自由しねえはずだ。」
「ここが俺の寺。」
「ああそうだ。あと百遍言えばわかるか?」
「俺が寺を持てるなんて夢みてえだ。銀蔵さん、みんな、なんてお礼を言っていいか。」
「お礼なんていらねえぜ。俺たちがおめえにお礼をしたくてこの寺を建てんだ。」
「そうかい。じゃあ遠慮なく受け取っておくよ。じゃあ俺はこれで。」
「おい与太!じゃなかった与太様!どこへ行く!」
「おクニ婆さんのノミ退治だ。」
「おクニ婆さんちはネズミだろ。そんなことより、待て!話はまだ終わってねえぜ!与太様、寺の名前とかいろいろ決めねえと!与太様!ああ行っちまった。」
その夜、与太は真新しい自分の寺の本堂にゴロンと仰向けになり、真新しい天井を眺めながら考えていました。本堂といってもまだ仏像や香台、蝋燭立てなどを備えた仏壇はなく、それどころか寺らしいものはまだ何一つありません。むき出しの檜と杉で作られた、ただの四角い十畳ほどの部屋です。それでも与太は大満足でした。
「ついに俺も寺持ちか。俺はなんて運がいいんだ。それにしても、どうしてこんなことになったんだろう?元を辿れば、そうだな、そうだ。それもこれも和尚様のお陰。さすがは和尚様だ。和尚様の言う通りに困った人の手伝いを始めたのが最初だ。するとどうだい?あれよあれよと言う間に俺みてえなバカでもあっという間に立派なお坊さんになっちまったぜ。今じゃあ住職様ときたもんだ。こないだまでの俺はただのバカだったんだぜ。いやあ、バカは今でも変わらねえか。住職ったってお経なんて一行も読めねえんだからな。大体お経どころか字だって読めやしねえ。まあそれでも書く方だけは少し、そうか、これもやっぱりできねえな。それがどうだい?和尚様の言う通りにしていたら、バカな俺でもこうして楽しく暮らしていけるじゃねえか。それどころか寺まで持っちまった。和尚様、いったいどこで何をしているのかわかりませんが、与太はこれからもお言いつけを守り、困った人を助けていきます。それでは、おやすみなさい。ぐう。
それにしても、
はて?
和尚様はいったいどこへ行っちまったのかな?他の人たちは?ソクネンさんやボクネンさんはどこに行ったんだろう?後の人たちの名前はなんだっけ?チンネン?マンネン?いけねえ、また忘れちまった。センネンかな?どうも違うな。
そういえばボクネンさんは『和尚様を掘り出したらすぐ俺たちも村へ行く』って言ってたな。いや、言ってたのはソクネンさんだっけ?どっちでもいいや。だけどどうしてだろう?どうしてみんな村へ来なかったのかな?
茂助さんと茂平さんは、侍どもが来る前に寺の者は全員裏山から逃げたって言ってたっけ。だから全員無事だってことは確かだ。それならそれでいいんだ。村へ来たらみんな殺されていたかもしれないしな。無事で何よりだ。それが一番だよ。無事ならいいんだ。さあ、もう寝よう。明日は、明日はなんだっけ?まあいいや、どうせどこかの誰かの手伝いに行くんだ。」
与太はそのまま目を瞑り、半分ほど眠りに落ちてゆきました。ところが、何かが心に引っかかり、どうにも深く眠れません。小さな釣り針が与太の袖口に引っかかり、眠りの底へ落ちていくのを邪魔しているような感じです。
「みんな無事なんだ。それでいいじゃねえか。何も気にするこたあねえ。今に和尚様がみんなを連れて村へ帰ってくるさ。だって無事なんだから。こうして曲がりなりにも新しい寺もできたことだし、これを見たら和尚様だって喜んでくれるぜ。ふふ、楽しみだなあ。さあ、明日も早え。今夜は寝よう。ぐう。
だけど、
だけどよ、あの短い時間に和尚さんを掘り起こすなんてできたのかしら?ボクネンさんだってソクネンさんだってみんな細腕だ。あの深い穴を掘り起こすなんて、やっぱり無理なんじゃねえかな。いや、よく考えてみたら、無理だと思うな。だとすると、そうだ、もしかするかもしれねえ。いや、どうにもこれは、もしかしたらだ!」
与太はパッと目を開け、暗闇に声を出して言いました。
「和尚様はまだ穴の中にいる。うん。いるね。だとすると寝てなんていられねえぜ。今すぐ石段を登って寺を見てこねえと。そうだ。あの和尚様のことだ。まだ土の中でバカみてえにお経を唱えているに違いねえ。」
「与太様!起きてるかい!」
そこへ兆吉少年が飛び込んできました。
「起きてるぜ!どうした?兆吉。」
「与太様、大変だ。すぐ一緒に来てくれ。」
「ガッテンだ!」
と叫ぶやいなや、与太は表へ飛び出しました。
「与太様!走って行っちまった。おい与太様!待ってくれ。」
兆吉も後を追って走り出します。必死になって追いつき、走りながら与太に話しかけます。
「与太様!どこへ行くつもりだ?」
「北の山だ!」
「違う!違う!そんな所じゃねえ!与太様!おれんちへ行ってくれ!俺の家が大変なんだ!」
「よし!おめえんちだな。」
与太は走りながら急旋回して、方向を変えました。
「妹が熱を出して昨日からずっと唸ってるんだ。」と兆吉。
「そいつは大変だ。」
「一番下の妹のお染だ。」
「そいつは大変だ。」
「母ちゃんが与太様を呼んできてくれって。」
「大変だ。急ぐぜ。」
「ああ与太様、頼むぜ!」
ところが、与太は急に走るのを止め、その場に立ち尽くしてしまいました。
「与太様!どうした?急いでくれ。妹が唸ってるんだ。」
「兆吉。」
「なんだ?」
「俺は医者じゃねえ。」
「知ってる。さあ行こう。」
「待て待て。おめえはまだ子供だからわからねえかもしれねえがな、医者じゃねえってことはよ、病気は治せねえってことだ。」
「ああ知ってる。さっ早く!」
「ちょっと待て。じゃあなんで俺を呼ぶんだ?お染のところへ行ったって、俺は何にもできねえぞ。」
「与太様!おめえお坊さんだろ。それも立派なお坊さんだ。妹の熱が下がるように一つお経を読んでくれたらいいんだ。」
「ああそうか!そうだな。俺は坊主だったよ。さあ兆吉!急ぐぜ!」
与太はまた走り出しました。
「そうこなっくっちゃ!」
兆吉も走り出します。ところが、与太はまた急に止まりました。
「おい今度はなんだ!」
「兆吉、やっぱりダメだ。」
「そんなこと言うなよ。妹は死にそうなんだ。だからおめえが有難いお経を読んでくれねえと本当に死じまうかもしれねえ。なあ。なんだよ?俺の妹にはお経を読んでくれねえっていうのか?」
「そうじゃねえんだ。俺はそんなことを言ってるんじゃねえ。」
「じゃあなんだってんだ?」
「俺はお経を読めねえんだ。」
「お経を読めねえ?」
「そうだ。」
「坊主なのに?」
「坊主なのにだ。」
「与太、いや与太様、おめえずっとあの北の山の寺で何をやってたんだ?毎朝毎晩お経を読んでたんじゃねえのか?」
「それが不思議なんだ。みんなと一緒にお経を唱えているとな、俺もちゃんと経を読めるんだ。ところがよ、俺一人になってみるとどうだ?あら不思議ってなもんよ、まったくもって言葉が何一つ出てこねえんだな。これはいったいどうしたもんだろうな?」
「知らねえよ。だけどみんなと一緒の時は読めたんだろ?じゃあ読めるんだよ。さあ、来てくれ。お染が待ってる。」
「待て待て待て。行くのはいいぜ。だけど行って俺の口からお経が出てこなかったらどうする?」
「出そうにねえか?」
「出そうにないね。」
「困ったなあ。与太様よ、俺もお経は読めねえが、何回かは聞いたことがある。こないだも、おキン婆さんの葬式で才遍和尚がお経を唱えるのを聞いたぜ。おめえも聞いてたろ?」
「ああ聞いた。」
「そん時だよ。お経ってのはたいてい『ナムなんとか』って言うんだ。あんまりたくさんナムって言うもんだから俺はずっと数えてたんだよ。何回ナムって言うかさ。途中で寝ちまって数えられなくなっちまったけどさ、少なく見積もっても五十や百は言ってたはずだ。だからこうしよう。与太様、おめえはお染の枕元に座って、『ナムなんとか』っておっぱじめればいい。ナムだけ言って後は適当に言っときゃあ、だいたいお経に聞こえるんだ。おっかあだっておっとうだって気付きゃあしねえよ。みんな本式のお経なんて知らねえんだからさ。」
「ああそうだな。兆吉、おめえの言う通りだ。確かにお経ってのはナムで始まりナムで終わるって誰かが言ってたのを思い出したよ。おめえ子どものくせによく気づいたな。だけどよ、ナムの次を一応考えておいた方がいいな。ナムだけじゃ済まねえんだから。兆吉、他に何を言ったらいい?」
「他はなんだっていいんだよ。適当に言っときゃ。誰もわかりゃしねえよ。うちで一番頭がいいのはお染だ。お染なら気づくかもしれねえが、今は熱で唸っているからバレる心配はねえ。」
「ああそうだな。じゃあ一つ、お経でも読んでみるか。ナムナムって言っときゃいいんだから。俺にもできそうだ。おい兆吉、何をぼうっとしてやがる?急ぐぜ。」
与太は呑気に走り出しました。
「そうこなっくっちゃ!」
兆吉も再び走り出します。
「ああ与太様、よく来てくださいました。兆吉、ご苦労だったな。」
兆吉の父が暗い面持ちで与太を迎え入れると、
「さあこちらです。」
兆吉の母がお染の枕元に与太を案内しました。
「うむ。お染、お染、元気かい?」
もちろん布団の中のお染は返事なんてできません。額に汗をかき、苦しそうに唸っています。
「これは大変だ。」
「はい。今朝からこんな感じで、山からドクダミを取ってきて与えても一向に効き目がありません。もうこうなったら神頼みしかないと、兆吉をやってご足労いただきました。いかがでしょう?こんな時に効くお経などございますでしょうか?」
「ふむ。まあ、ないことはない。」
「ぜひ一つお願いいたします。これ、みんなもお願いしろ。」
「お願いいたします。」
兆吉の父母、三人の妹たち、それに兆吉も深々と頭を下げました。
「では。エヘン、ゴホン、あ、あ、どうも今日は喉の調子が、ん、ん、」
「与太様。」
兆吉が心配そうに声をかけます。
「わかっておる。ではゆくぞ。ええ、ナームー、」
ところがその次が出てきません。与太の膝の先ではお染が苦しそうに喘いでいて、それがいかにも気の毒でかわいそうで、与太はもうお経を考えるどころではなくなってしまいました。『なんとかしてあげたい』。小さなお染のため、兆吉や家族のため、与太はお経を読まなければならない。何かお経を読みたい、読もう。ところがお経を読もうとすればするほど、与太は頭の中が空っぽになってしまい、ナムの他は何も言えなくなってしまいました。
「ああなんてこった。こんな小さな子供が苦しんでいるのに、俺はお経の一つも読めやしない。ええと、ナームー、ナームー、ああお染、ごめん。」
するとどうしたことでしょう。与太には苦しむお染の顔が、蛙鳴寺の本堂にあったご本尊様、小さな阿弥陀如来像のお顔に見えてきました。すると突如として、与太の脳裏に和尚様と一緒にお経を読んでいた、いや読んでいたふりをしていた情景がまざまざと脳裏に蘇ってまいりました。
ナムアミダブツ。
そうだ。ナムアミダブツだ!思い出した。ナムアミダブツと言えばいいんだ。与太はそれでも自信なさげに声を出してみました。
「ナームーアーミーダー、」
そこまで言って、ちらりと横目で兆吉を見ると、兆吉はウンウンと頷いています。
「ブツ?」
兆吉がさらに激しく頷いてくれます。与太は勇気づきました
「ナームーアーミーダーブツ、ナームーアーミーダーブツ、」
唱えながら横目で周囲を見てみると、兆吉も兆吉の両親も妹たちも皆満足そうに手を合わせています。熱にうなされているお染もどことなく満足そうです。
「ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、なんだ、俺にもお経が読めるじゃねえか。よし、これをお染の熱が下がるまで唱え続けよう。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、あっ!」
突然、与太は何かを思い付き、お経を止めてしまいました。空を見つめじっと何事か考えています。静まり返ってしまった与太に家族は不審な視線を向けました。
「あのう与太様、どうしなすった?」
「親父殿、お袋殿、それに兆吉と妹たち、俺はもっといいお経を思いついた。そっちでいってみようと思います。」
「はあ。」
「ではいきます。ええ、おほん、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
「あのう、与太様、」
「なんだい?」
「ええと、なんです?そのサイペンブツってのは?」
と兆吉の親父が代表してたずねました。
「サイペンはあっしの和尚様の名前、ブツは、なんだかわからねえけど、お経の最後に付ける文句だと思います。」
兆吉の両親は困ったように顔を見合わせました。なにしろ才遍和尚は、野武士どもの姿を見て、村を捨てさっさと逃げ出したと思われている人物です。村には尊敬している人なんて与太以外に一人もいません。それどころかみんな軽蔑すらしています。そんな人物の名前をお経にして唱えるなんて、どう考えても大事な娘の病気を治すには相応しくないように思えます。ところが与太はこれ以外に相応しいお経はないと言わんばかりに自信たっぷりな顔をして、一心不乱に大声で唱え始めました。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
与太は眉間に皺を寄せ、必死の形相でお経を唱えます。もう与太の頭の中にはお染の回復、それだけしかありません。お染が元気になってくれること、ただそれだけを祈り、願いながら、ただひたすら自作のお経を唱え続けました。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
するとその熱意と迫力に打たれ、兆吉も手を合わせ一緒にお経を唱え始めました。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
これを見た妹たちも小さな手を合わせ一生懸命に与太のお経を唱えます。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
もうこうなったら仕方がない。兆吉の両親もまた手を合わせ、与太の作ったお経を声に出して唱えることにしました。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
翌朝、
兆吉一家は全員その場で眠ってしまいましたが、与太だけは半分眠りながらも胸の前で手を合わせ、ひたすらお経を唱え続けていました。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
目を閉じたままお経を呟いていると、与太は何か冷たいものが、胸の前の自分の手に触れるのを感じました。何かな?と、そおっと目を開けてみると、目の前には小さなお染が立ち、こっちを見て与太の手をやさしく触っています。
「お染、起きたのかい?」
返事の代わりにお染はにっこりと笑いました。
「染!」
気配を察して目を覚ました母親が大声を上げました。この声に目を覚ました家族たちも目を覚まし、お染の周りに集まってきました。
「熱が下がった!」
お染の額に手を当てた母親がほっとした声を出します。それを聞いた妹たちは安心して泣き出し、父親と兆吉も潤んだ目を微笑ませ、にっこりと顔を見合わせました。
「はっ、そうだ。与太様!」
兆吉が振り向くと、与太は板の間ですやすやと眠っておりました。
こうして、与太はお経を手に入れ、僧侶としての第一歩を踏み出しました。
村から逃げ出した卑怯者の名前が入っているこのお経は、田平子村の人たちにとってあまり有り難くもないお経でしたが、お染が回復し実際にご利益があるということが証明された以上、誰にも文句のつけようがありません。
お経が読める与太は誰から見てももう一人前のお坊さんです。与太はこのお経を自分の寺で朝に晩に心を込めて熱心に唱え、葬式でも心を込めて熱心に唱え、祭りの日にも心を込めて熱心に唱え、豊作を願うときにも、豊作を感謝する時にも心を込めて熱心に唱え、その他、事あるごとに心を込めて熱心に唱え続けました。
最初は、与太様が唱えているから仕方がないと渋々一緒にこのお経も唱えていた村の人たちも、みんなのために身命を惜しまず一生懸命に働いている与太と、常に苦楽を共にしているこのお経にやがて心を打たれるようになり、いつしかこの経を大事にし、与太と同じくらい心を込めて熱心に唱えるようになっていきました。
ところで、
言うまでもなく与太は大事なことをすっかり忘れています。自分の新しい寺でゴロンと横になり、天井を見つめ、もしかしたら才遍和尚がまだ土の中にいるかもしれないと思い出したことなど、与太はお染の回復した喜びと、自分自身のお経を思いついた興奮ですっかり忘れてしまっていました。
実際、才遍和尚はまだ土の中におりました。だいぶ死に近づいてはおりましたけれども、言い換えれば、だいぶ目的の仏様に近づいてはおりましたけれども、厳密にはまだ仏様にはなってはおらず、まだ死にかけのやせた人間として地中深く埋められた箱の中で手を合わせ、目を瞑り、遠く細くなった微かな意識の中で、それでも与太よりも正しいお経を『むにゃむにゃ』と呟きながら、どっこい生きておりました。自分自身の名がお経となったことなどつゆとも知らずに。
お染を回復させたその後も、与太は一生懸命に困っている人のために働き続けます。残念ながら才遍和尚の存在について、その後数十年思い出すことはありませんでしたが、和尚から与えられた『困った人を助けろ』という言葉だけは片時も忘れることはなく、ただただ困っている人のために働き続けました。
奇しくも時は戦国、困った人など掃いて捨てるほどおりました。与太は戦火で荒れた田畑を耕し、焼き出された人たちに食事や寝る場所を与え、親を殺された子供たちを育てと、寝る間も惜しんで人助けに励みました。見返りが欲しかったからではありません。それもこれも尊敬する和尚様が与えてくれた自分の使命だったから、ただそれだけのために与太はひたすらに人を助け続けました。
もちろん、そんな与太を周囲の人々も放っておくわけがありません。村の人たちは喜んで自分の食糧や衣服さらには土地までも与太の寺に寄進し、与太の仕事を手伝いました。やがて与太の評判が村の外へも伝わると、寄進はさらに増え、寺はますます大きく立派に豊かになっていきました。繰り返しになりますが、与太は寄進や寄付が欲しくて働いたわけではありません。ただただ人助け、それだけのために働きました。また、くれると言うものを素直に受け取ると、くれた人が喜んでくれるからという理由で与太はおおいに受け取りました。『もらってあげるだけで喜んでくれるんだから、これが一番簡単な人助けだな』。与太はそう思い、くれるものは感謝して、なんでも受け取ることにしていました。
こうして十年が過ぎ、さらに二十年、三十年が過ぎ、ついには五十年が過ぎたある日、いよいよ与太の人生も終わりを迎えます。
「どうも今朝は調子が悪い。風邪を引いたようだ。すまんが今日の仕事は休みにして床で休むことにするよ。ナムサイペンブツ。」
与太は朝のお勤めを終えると、弟子たちにそう言って自室で横になってしまいました。その頃になると与太の志に打たれた諸国の若い僧侶たちが与太のもとに集まり、寺にはたくさんの弟子がおりました。
さあ驚いたのは与太の弟子たちです。師が仕事を休むことなど、その時に至るまで一度たりともなかったからです。それどころか、風邪を引いたところすら見たことがありません。バカは風邪を引かないと言います。与太は自他共に認めるバカだったので、生涯病気にはならないと、本人を含む誰もが信じ込んでおりました。
「与太様が風邪をお引きになられた!」
すぐさま町から医者が呼ばれました。ところが医者が診ても、どうにもやはり与太様の様子がおかしい。声をかけても目も開けませんし、返事もない。試しに肩を揺すってみても起きる気配がまったくない。『こいつは大変だ!』と医者が慌てると、あっという間に村中の者が与太の枕元に集まりました。何しろ誰からも愛された与太様の一大事です。あまりにもたくさんの人が集まり過ぎたために、与太の寝所はあっという間に村の重鎮たちで埋め尽くされました。寝所に入りきれなかった村人は、寝所の外に座り与太の様子を伺い、寝所の外にも入りきれなかった者は、寺の中に座り、ここまでくるともう与太の様子は伺いしれないないので、ただただ手を合わしお経を唱え与太様の回復を祈りました。さらに寺に入りきれなかった者は、寺の外に座り、寺の外にも座れなかった者は、村の通りに座って、手を合わせナムサイペンブツとお経を唱え、与太の回復を祈りました。
与太様がご病気になられたとの報は、やがて風に乗ってあっという間に近隣の村々や町々にも伝わり、心配した大勢の人が田平子村へと押しかけてまいりました。その頃になりますと、与太の世話になった人が田平子村だけではなく近隣の村や町にも大勢いたからです。それどころか、美濃国で与太の世話になっていない人を探すのが難しいくらい誰も彼もが与太に助けられておりました。そのため、誰も彼もが心配のあまり仕事を放っぽり出して田平子村へと向かいました。やがて村は、与太の回復を祈るたくさんの人であふれかえり、村に入れなかった人は村へと続く道に座り、手を合わせ、与太様のお経『ナムサイペンブツ』を唱え続けました。
その昔、蛙鳴寺で与太たちが野武士たちを見た南の丘の峰にも、その日は与太の回復を祈る大勢の善男善女がゴツゴツした地面に正座をし手を合わせ与太のお経を唱えておりました。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
眠っている与太の枕元の一番近い場所に堂々と正座をし、一番熱心にお経を唱えているのは恰幅のいい中年の女性、今では立派に成人し村の世話役も勤めているお染です。数十年前、与太が初めて自分のお経を唱え、必死になって回復を祈ったあの小さな女の子も今や立派な強面のご婦人となりました。あの日回復して以来お染は兄の兆吉と熱心に与太の仕事を手伝ってきました。今では五人の子供と八人の孫がいます。『今自分がこうしていられるのも与太様のおかげ』とお染は、与太が自分にしてくれたことの恩返しにと、枕元に陣取り、心を込めてお経を唱え続けていました。お染の心の中には、つい先日夫を亡くし落ち込んでいる自分を慰めてくれている与太の慈愛に満ちた顔が浮かんでおりました。
「それだけじゃない。与太様は、兆吉兄さんが亡くなった時だって家族の誰よりも悲しんでくれたじゃないか。ああ与太様、与太様、死なないでください。ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
お染は、与太の枕元で一心不乱にお経を唱え続けました。
お染に限らず、与太の周囲に集っている人々にはたいていお染と同じように与太から助けられた思い出が一つや二つ、いや最低七つ以上はありました。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
誰もが心を込めて念仏を唱えます。中にはすでに泣いてしまっている者もおりました。『まったく縁起でもない。泣くなら部屋から出て行っておくれ』。お染は苦々しく横目で睨みましたが、声には出しません。『今は与太様のご回復が優先だ。泣いている奴は後でたっぷり油を搾ってやる』。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
誰もが悲しみと不安でいっぱいのその中で、たった一人だけ満足そうな笑みを浮かべている者がおります。与太です。与太は死の床で横になり、意識を失いながらも、その顔は柔和な笑みを浮かべておりました。夢の中で自分の人生を走馬灯のように眺めていたからです。人は死ぬ間際、自分の人生で経験したあらゆる場面を次から次へと瞬時に眺めるといいます。
与太もまた死の床につき、七十余年に及ぶ自分の人生の間に見たものを気持ちよく眺めておりました。それは次から次へと現れる人々の笑顔、笑顔、笑顔、そしてまた笑顔。与太の人生は、たくさんの人のたくさんの笑顔で満たされておりました。もちろん時は戦国時代、世の中はどこを見回したって涙、涙、涙。不安と恐怖に震える顔ばかり。当然与太だってそんな顔ばかりを見てきたはずです。ところが、与太の心が記憶していたのは、自分が助けた不幸な人たちから向けられた笑顔だけでした。実に平和な男です。
こうして今、与太は夢の中でたくさんの笑顔に囲まれて、文字どおり夢のような死を迎えようとしていました。ほんのちょっと目を開けた所にある現実の世界では、自分のことを心配する数万の不安な顔に囲まれておりましたが、死にかけの与太の頭の中では、満開の花畑のような笑顔が次から次へと現れては、与太に微笑みかけてくれていました。
ところが、そのたくさんの笑顔と笑顔の隙間に、一瞬だけ不思議な情景が与太の目に飛び込んできました。それは地中から少しだけ頭を出した竹筒の先端。それがパッと現れるとすぐに消え、次にまた誰かの笑顔。一瞬、『はて?』と与太も思いましたが、再び続くたくさんの笑顔に酔いしれ、竹筒のことなどすっかり忘れてしまいました。しばらく笑顔が続くと、今度もまた地中から出た竹筒の情景が一瞬だけ現れました。ただ今度は数人の少年たちが竹筒の周囲に四つん這いになり、地面から突き出た竹筒の先端に耳を当てています。
『はてはて?この子たちはいったい何を聞こうとしているのかな?』
死にかけの与太は一瞬だけ気にかかりましたが、竹筒と少年たちの情景は今度もまたパッと一瞬で消え、再び笑顔、笑顔、笑顔。再び与太は甘美な喜びに酔いしれ、少年たちのことなどすっかり忘れてしまいました。さらにしばらく笑顔が続いた後、再び竹筒が現れました。ただし今度は少年たちがいません。見えたのは、土の中から生えている竹筒の黒い穴。
『ああ今度は俺が竹筒を覗き込む番だ。俺はこの竹筒から聞こえてくる音を聴きたいんだな。』
と思った途端、再び竹筒は消え、再び笑顔。
ところが、
『いったいあの竹筒からは何が聞こえてくるんだろう?』
さすがに今度ばかりは与太も気になって、誰かの笑顔に酔いしれることなどもうできません。死にかけながら、もう一度、与太はさっき現れた竹筒を思い出すと、その頃の情景が与太の脳裏にぼんやりと蘇ってまいりました。そこにいたのは少年時代の与太。他の少年たちの真似をして竹筒の穴に耳を近づけてみると、
『ああ聞こえてきた、聞こえてきた。なんだろうこれは?『むにゃむにゃむにゃ』、『むにゃむにゃむにゃ』。これは?お経?そうだ!これは和尚様のお経だ。思い出した!』
パッと驚くほど勢いよく目を開けた与太を、お染は見逃しません。すぐにお経を唱えるのを止め、
「静かに!」
と周囲に怒鳴り、みんなのお経も止めます。
「与太様、お気づきになられましたか?」
『与太様が生き返った!』。すでにお染の目は喜びの涙であふれ、声は喜びで震えております。
「寺へ。」
残念ながら与太は病気が治り生き返ったわけではありません。ただ人生の最後、今まさに息を引き取ろうとするその直前になり、ついにようやく一つ、大事なことを、今まですっかり忘れていたことを思い出したのです。混濁した意識の中で、与太は残された最後の力を振り絞り、その大事なことを果たそうとしていました。
「寺へ。」
もちろん声など満足に出ようはずがありません。
「与太様、なんですって?」
お染が与太の口に耳を近づけます。
「寺へ。」
「寺へ?与太様、ここが与太様のお寺です。」
与太は顔をしかめイライラと首を振ります。
「寺へ、連れて行け。」
「いやだ与太様。聞こえないのかしら。だーかーらー、こーこーが、」
与太が顔をしかめるのも無視してお染が与太の耳元で怒鳴るのを、
「蛙鳴寺じゃ!」
後ろから老人の声が割って入りました。
「蛙鳴寺じゃ。」
「なんですって?」
お染が振り向くと、そこにいたのは今や村の最長老となっていた年老いた茂平。かつて田平子村が野武士どもに襲われたとき、銀蔵と与太に頼まれて北の山の蛙鳴寺へ様子を見に行った双子の猟師の生き残りです。
「与太様、おめえは昔北の山にあった蛙鳴寺へ行きてえんだな?」
茂平がお染を押し退けて与太の耳元に語りかけると、与太は満足そうにうなずきました。
「ケイメイジ?」
お染が首を傾げます。
「お染、おめえはまだ小せえ子供だったから知らねえのも無理はねえ。与太様はな、子供の頃、その昔北の山にあった蛙鳴寺ってところで修行をなさってたんだ。」
「寺へ、連れてって、くれ。」
与太が声を振り絞ります。
「それがおめえの願いなんだな?」
茂平に聞かれると、与太はうんうんとうなずきます。
「準備にかかれー!」
お染が大声で周囲に怒鳴ると、与太も茂平もその声の大きさで自分が死んでしまうのではないかと思い、顔をしかめました。
さあこうなると田舎の人というのは仕事が早い。おまけに人手は掃いて捨てるほどあり余っています。誰ともなく神社の倉庫からお神輿を持ってくると、すぐさま神輿の上の部分を乱暴に取り除き、土台には代わりに与太様を寝かせるように分厚い布団を何重にも敷きました。その間、打ち捨てられてからすでに数十年が経つ北の山の旧蛙鳴寺は、何千という手によって大規模な草刈りが行われました。瞬く間に草木を刈り取ってみると、北の山の上にはかつて蛙鳴寺のあった空き地が現れ、年寄りたちの話し通りに寺へと垂直に上る三百一段の崩れかけた石段も出てきました。かつて与太が村人たちに危険を知らせようと命を顧みず駆け降りた階段です。人々はこの階段を叩き壊し、代わりにつづら折の道を作りました。できるだけ神輿を水平にしたまま山の上へ運ぶため、急な石の階段は不向きだったからです。
準備はあっという間に出来上がり、人々は与太を丁寧に神輿へ寝かせると、できるだけ揺らさないようにゆっくりと持ち上げました。担ぎ手の心配はありません。今、寺から北の山の上までは数万の人で埋められ、神輿は隣の人から隣の人へと手渡しするだけで途切れることなく北の山の上まで運ぶことができるほど、国中からたくさんの人が田平子村へ集まっておりました。人々はできるだけ静かに優しく神輿を隣の人へと渡していきました。こうして波ひとつない平らな湖面を舟が滑るように、与太を寝かせた神輿は人々の頭上を静かに流れるように移動していきました。
時々、誰かがすすり泣く声が聞こえてきましたが、神輿の上の与太はいい気分でした。暖かい布団に包まれ、穏やかなお日様とやさしい風に頬を撫でられながら、雲の上にのんびり寝そべっているような心地よさに、ついついそのまま二度とは覚めない深い眠りに落ちてしまいそうになっていました。
『いかんいかん。まだ死ぬわけにはいかん。』
与太は自分に言い聞かせました。
まもなく神輿は蛙鳴寺のあった空き地に到着しました。
「与太様、着きました。」
みんなを代表してお染が耳元に語りかけると、与太はパッと目を開けます。
「うむ。」
起きあがろうとする与太を三人の男衆が両脇を支え、助け起こします。すでに人払いは済んでいて、寺のあった空き地に人はいません。もちろんその周囲は数万の人が取り囲み、与太様の一挙手一投足を、固唾を飲んで見守っておりましたが、与太様の邪魔をしないよう廃墟となった空き地は空っぽになっておりました。
草木を刈り取られたばかりの空き地を、与太はゆっくりと首を回し眺めます。すると奇跡が起きました。昔そこにあった本堂や鐘撞台、鳥居が与太の目に見えたのです。そんなものはもちろん与太以外の人には見えません。これは仏様が、死ぬ直前の与太にだけ与えられた小さな奇跡でした。おかげで与太には目的の場所がすぐにわかりました。
『あそこだ。あそこだ。』
両脇を支えている手を振り払い、与太は周囲の人が驚くほどしっかりとした足取りで歩き出しました。男衆もお染も茂平も驚きながら、できるだけ与太の邪魔にならないよう、それでも与太が倒れそうになったらすぐに支えられるよう、後ろからついていきました。
不思議なことに、一歩歩くごとに与太は自分がどんどん若返って行くのを感じていました。自分だけではありません。目に見える幻の寺も一歩歩くごとにどんどんはっきりと現実の形を持つようになっていきます。
「ああ和尚様、申し訳ねえ。俺はバカだ。どうしようもねえバカたれだ。何十年も和尚様のことをすっかり忘れて過ごしちまった。どうか許しておくんなせえ。ああ、ここだ、ここだ。」
与太が何かブツブツ言っていることは、近くにいる人々にも聞こえてはいました。が、何しろ死にかけの老人の舌足らずな言葉です。その内容まで聞き取れた人は一人もいません。周囲の人は皆、与太様がお経を唱えながら歩いていると思っていました。
与太がついに見つけたのは、刈り取られた草の間からひょっこりと顔を出した小さな竹筒の先端。
「あった!」
与太はそこにひざまづき、恐る恐る耳を近づけてみました。
するとどうでしょう。聞こえます。確かに聞こえます。筒の奥から和尚さんのお経を読む微かな声が聞こえてくるではありませんか。
「和尚様、和尚様。」
声にならない声で与太が竹筒の奥へ呼びかけると、お経が止まりました。
「和尚様、和尚様、与太でございます。弟子の与太でございます。」
「与太か?」
筒の奥から弱々しく問う声が漏れ出てきます。
「ああ和尚様!生きててくださったか!どうか許しておくんなさせえ!与太は、すっかり和尚様のことを忘れて楽しく過ごしておりました。だけど和尚様、聞いてくだせえ。与太は、与太は一瞬たりとも和尚様の言いつけを忘れたことはねえです。和尚様のことは忘れても、言いつけだけは絶対に忘れなかったです。朝起きてから夜寝るまでずっと和尚様の言いつけを守っておりました。いや寝てたって、夢の中で和尚様の言いつけを忘れねえように何度も何度も繰り返してきたです。だけど俺はバカだ。言いつけだけは覚えていても、和尚様の言いつけ通りにちゃんとできたかどうかまではわからねえ。ずっとわからねえままで今日まできちまった。本当はいつも不安だったんだ。俺は和尚様の言う通りできてるかなって。怖くて怖くて仕方なかったんだ。ああだけどよかった。こうして和尚様が生きててくれりゃあ百人力だ。今、村の者に頼んで掘り出してもらうから、ちょっとばかり待っててくれ。」
「与太、そこにいるのは、与太なのか?」
筒の中から小さな声が問いました。ところがもう返事はありません。
言葉を言い終わると、与太はその生涯を静かに閉じました。筒の前に正座をし、頭を地面に付けたまま、与太は息を引き取りました。
「うわーん。」
与太が石のように動かなくなったのを見て、全てを悟ったお染が声を上げて泣き出すと、周囲にいた者もまた声を上げて泣き出し、その号泣の連鎖は北の山から村へと降り、更には向かいの山へと続く人々へとあっという間に広がり、周囲の山々は数万という人の大号泣の渦の中に飲み込まれてしまいました。
たまたま与太が向いていたのは眼下に広がる田平子村の方向でした。死ぬ瞬間まで与太様は村の平和と安寧を祈ってくれたのだと、そう勘違いした人々は改めて与太様の恩の大きさに心を打たれ、ただただ感謝の涙を流し続けました。方向音痴の与太にも、最後には奇跡が起こったのです。
山々をも揺さぶる大号泣のため、竹筒の中から再び弱々しいお経が始まったことに気がついた者は当然のことに一人もおりません。こうして、才遍和尚の即身仏の荒行が人の目に触れる機会はまたしても失われてしまいました。
人々は与太様の亡骸を丁寧に神輿へと戻すと、涙と行く時以上の丁寧さでもって村へと運び、与太の寺の本堂に安置しました。
「与太様の墓は、与太様の最後の意志を汲んで、蛙鳴寺の息を引き取った場所に作ろうや。」
最長老の茂平はそう主張しましたが、その意見に賛成した村人は一人もいません。賛成どころか、会議の場にいた村人は全員、みんなよく聞こえていたのに茂平の声が聞こえないふりをしました。と言いますのも、その頃になりますと、田平子村ではどうしたわけか北の山はすっかり縁起の悪い場所として人々から忌み嫌われるようになっていたからです。
「というわけで。与太様のお墓はこの与太様のお寺の中に作る。死んだ後もみんなと一緒にいてえってのが、与太様が元気な頃からの口癖だったからね。みんなここでいいかい?異存はないね。」
お染がまとめると、
「賛成。」
「同意。」
「右に同じく。」
「わしは反対じゃ。みんなもわかっておるはずじゃ。与太様は最後に北の山へ登られたのだ。だったら墓も、」
茂平が言おうとするのをお染は遮りました。
「はい。わかりました。みんな賛成ってことだね。伝蔵、すぐに人手を集めて境内に与太様の墓を作っておくれ。さあ茂平爺さん、疲れたろ。会議はこれでお開きだ。」
「ふん。バカどもが。」
茂平が捨て台詞を残して退席すると、お染は強硬に会を締めました。
その夜、
「北の山だって?気味が悪い。だいたいあんな薄暗い丘のてっぺんに与太様のお墓を作ったら、誰も怖がってお参りなんて行けやしないよ。与太様のお寺は、村の真ん中にあるここのお寺だ。だからお墓もここのお寺に作るべきなんだよ。そうすりゃ、みんなだってお墓参りしたい時にすぐできるんだから。そうだろ平吉。」
お染は息子の平吉にそう言いました。
「おっかあがそう言うなら、そうなんだろうよ。」
ということで、与太の墓は村の真ん中にある与太の寺に作られ、こうして再び北の山の蛙鳴寺は人々からすっかり忘れ去られ、まもなく再び寺は深い深い草木の下に、土の中でお経を唱えている才遍和尚もろとも、埋もれてしまいました。
もしもこの時、茂平翁の意見が採用され、与太の墓が蛙鳴寺の跡地に作られていれば、才遍和尚は期せずして掘り出されていたはずです。そこで掘り出されていれば、それからずっと後になって、あんなことにはならなかったのにと悔やまれてなりません。
こうして時は流れ、さらに五十年が経ちました。戦乱の世もすでに終わりを告げ、時は今や天下泰平の江戸時代となっています。
そんなある日、田平子村は恐ろしい嵐に見舞われます。嵐は三日三晩吹き荒れ、その日も朝から、真っ黒な空から激しい雨が滝のように降りそそぎ、狂ったように吹き荒れる風が田平子村の家々と田畑に襲いかかり、絶え間ない稲妻と雷鳴が血を求める鬼の咆哮のように轟いておりました。村人たちは、それぞれの家の中で身を寄せ合い震えていると、ちょうど昼頃のことです。
ドッカッーン!!!バリバリバリバリ!
明らかに雷鳴とは違う巨大な地鳴りに、村人たちは顔を上げ家族と顔を見合わせました。
「これはいかん。どこかの家が潰れたぞ。」
男衆たちはそれぞれの家を飛び出し、村の中心にある寺の境内に集まりました。
「みんな集まっているように見えるが、どうにもこの嵐で人の顔がよく見えん。」
寺の若い住職、与一は雨しぶきの中で必死に目を凝らします。
「おーい!みんな揃っているか?東の権兵衛、いるか?」
「ここにいるぞ。東は大丈夫だ。さっきの音は俺たちの東じゃねえ。」
「西の佐助もここにいるぞ。西も大丈夫だ。」
「俺もいるぞ!」
「そういうおめえは誰だ?雨で見えねえ。」
「南の権太だ。おい住職、寺は大丈夫なのか。」
「寺は大丈夫だ。なんともねえ。」
「よく見たのか?音は寺から聞こえたぜ。」
「権太よ、寺のことよりお前の集落を心配しろ。南は大丈夫なのか?」
「住職よ、おめえは寺の心配をしろ。音はそっちから聞こえたんだ。俺の南は問題ねえ。」
「おい二人とも!言い争っている場合じゃねえぞ!柴吉の姿が見えねえ。北の柴吉はどこだ?柴吉!いたら返事をしろ!」
「大変だ!柴吉がいねえ。さっきの音は北だ。北でなんかあったんだ!」
誰かがそういうと、男衆たちと住職の与一は慌てて村の北へと走り出しました。誰も口には出しませんでしたが、村で悪いことが起こるといったら、北しかないと誰もが思っておりました。
『災いが起こるのは北に決まってる。あそこは縁起の悪い土地だ。何が起こったかまではまだわからねえが、悪いことに決まってるんだ。柴吉たちが無事でいてくれたらいいが。』
戦国時代までは、田平子村で縁起の悪い場所は北の山だけでした。それが江戸時代になってくると村の北側全般が縁起の悪い場所という風に広がってきて、それが田平子村の古くからの言い伝えであると村の人々は信じるようになっておりました。大昔、偉いお坊さんがやって来て災い封じのために北の山の上に蛙鳴寺を立てたのに、その寺でさえ住職が逃げ、野武士に焼き払われたほど、北は縁起が悪い。決して近寄ってはならぬ。村人はそう固く信じるようになっておりました。
ところが、こうして田平子村の北には誰も住む者がなくなり、開墾して田畑にしようという者すらなかったのを、それでも時代がさらに平和となり、豊かになって人口が増えてくると、田平子村でもどうしても住む場所や田畑が足りなくなってきます。独立心の強い三男坊の柴吉が、居心地の悪い実家を出て、北の山の麓に自分の小さな家を建て、その周囲を耕し出した時だって、村人たちは内心顔をしかめただけで、あえて強く反対する人はすでにいなくなっていました。
「これで俺も畑持ちだ。一人前の男だ。」
鍬を持って自分の畑に立ち、そう胸を張る柴吉の誇らしげな笑顔を、嵐の中を北へと走る男衆たちは苦々しく思い浮かべていました。
「柴吉が家を建て始めとき、なんで俺は反対しなかったんだろう?羽交締めしてでも止めておけばよかった。」
走りながら与一は唇を噛みました。
嵐の中、男衆たちが現場に到着してみると、恐れていた以上のことが現実に起こっているとわかりました。柴吉の家は、大きく崩れた北の山の土砂にすっかり飲み込まれ、すでに跡形もありません。
「柴吉―!」
返事はありません。
「お花さーん!」
これは柴吉の奥さんの名前です。同じく返事はありません。
「松坊―!」
これは柴吉とお花の生まれたばかりの赤ん坊の名前です。返事はなし。こちらはまだ赤ちゃんなので仮に無事だったとしても返事はなかったかもしれません。
いずれにせよ、男衆たちの必死の呼びかけに対して返ってきたのは、雨と風と雷鳴の無情な音だけ。赤ん坊の泣き声を含め人間の声は何も聞こえてきてはくれません。
「掘り出すぞ!」
「おうよ!」
誰かの掛け声で男衆たちは一斉に土砂を取り除きにかかります。
やがて四人の亡骸が掘り出されました。生き埋めになったのは三人のはずなのに、なぜか四人。
「変だな。」
男衆たちは首を傾げましたが、どう数えても泥だらけの亡骸は四人。
「柴吉んとこは四人家族だったかな?」
「いや三人だ。四人目は聞いたことがねえ。」
「もう一度数えてみよう。」
「これが柴吉。これがお花。そしてこれが松坊と。あともう一人、この爺さんが余計なんだ。おいみんな。この爺さんに心当たりのある者はあるか?」
住職の与一が皆に呼びかけると、入れ替わり立ち替わり男衆たちがご遺体の顔を覗き込みます。が、誰の目にもこのやせ細った裸のおじいさんに心当たりはなく、みな不思議そうに首を傾げるばかり。当然です。心当たりなどあるわけがありません。才遍和尚が即身仏となるため穴に入ったのは百年も前のこと。以来田平子村の住人で和尚の顔を見た者はなく、住人もすっかり入れ替わっておりました。
ともかく、亡骸をいつまでも雨風にさらしておくわけにもいきません。あたりも日が落ちてきたのでしょう。ますます暗くなってきました。男衆たちはとりあえず四人の仏さんを近くの掘立て小屋まで運び入れ、翌朝まで仮安置することにしました。
「どうして俺一人が番をしねえといけねえ?」
抗議したのは山猟師の茂平、このお話にもたびたび登場した茂平の子孫で、田平子村伝説の山猟師だった祖先の名前を継いでいる若者です。
「お前、柴吉とは仲がよかっただろ?」と住職の与一。
「ああ仲がよかったな。幼馴染だからな。」
「お前暇だろ?」
「ああ暇だ。この嵐じゃしばらく山には入れねえからな。」
「じゃあ頼む。仏さんたちを朝まで見ていてくれ。俺は葬式の手配を整えて明日朝一番で戻ってくる。それまでの間だ。」
「頼むぜ。すぐ戻ってきてくれよ。」
その晩遅く、嵐もすっかり収まり、夜空には明るい月も戻ってまいりました。
茂平が四人の亡骸の横で、小屋の薄い壁板にもたれ掛かり、うつらうつらしていると、ふとどこからともなくブーンという細い蚊の羽音のような音が聞こえた気がしました。
「こんな寒い夜に飛ぶたあ、トンマな蚊もいるもんだ。」
さすがの茂平も今日は疲れました。たかだか蚊一匹のために心地よいうたた寝をやめるつもりはありません。目を閉じたまま、夢うつつの中で蚊を引っ叩こうと、ブーンという音に耳を澄ませ、蚊の位置を定めようとします。すると、そのブーンという音はどうやら何かしゃべっているように聞こえます。
「なんだろう?近頃は蚊も人間の言葉を喋るようになったのか?」
好奇心にかられ、さらによくよく耳を澄ませてみると、蚊の羽音はどうやらお経のような文句を低く呟いております。
「なるほど。与一の野郎、戻ってきてお経を唱えてやがるな。元々いい奴だとは思っていたが、なかなか感心な坊主だ。俺が疲れていると思って、起こさねえように静かに経を唸ってやがる。まったく気を使いやがって。ありがてえ坊主だ。ありがとよ。心配しなくたって俺は起きやしねえよ。」
茂平がもう一度寝ようと尻の位置を直したところで、ふと、おかしなことに気が付きます。
「はて?与一の声はこんなんだったかな?こんなジジ臭い声をしていたかな?だいたい坊主ってのはお経を読む時には腹から声を出す。すると普段とは違う声の出るもんだが、これはどうにも与一の声じゃねえ気がするな。それに、このお経はなんだ?こんな複雑なお経を、俺はこの村じゃあ聞いたことがねえ。何を言ってるのかさっぱりわからねえ。俺たちの村のお経は『ナムサイペンブツ』って与太様の昔から相場が決まってるんだ。村じゃいつだって『ナムサイペンブツ』。与一だって唱えるのは『ナムサイペンブツ』。だとすると、こいつは与一じゃねえな。」
そおっと目を開けると、小屋の中は青白い月明かりにぼんやりと照らされています。板の間には、こもを被された四体の亡骸がこれまた青白い月明かりにぼんやりと照らし出されておりました。他に人はいません。
「一つ、二つ、三つ、四つ。それに五と。この小屋にゃあ人間が五人いて、生きている人間は俺一人。残る四つは仏様だ。なのにお経は聞こえるぜ。俺がお経を唱えてねえとなると、他にもう一人生きた人間様がいるってことになる。誰だ!返事はないね。誰もいやしねえ。見たまんまだ。だけどよ、まだお経は聞こえやがる。こいつは気味の悪いことになってきたぜ。ああそうか、わかったぞ。俺は夢を見てるんだ。ああそうに違いねえ。起きているように見えて、どっこい俺は寝ているんだよ。ああよかった。ぐっすり夢の中ってやつだ。痛え!頬っぺたを引っ叩いたら、やっぱり痛えじゃねえか。するってえとこれは夢じゃねえな。どうやら俺は起きていやがる。どれ?うん。やっぱり聞こえる。誰かが訳のわからねえお経を唱えてやがる。さあこうなると茂平よ。ここは偉大なご先祖様の名にかけて、勇気の出しどころだぜ。だてに伝説の山猟師の名を継いでるわけじゃねえってとこを見せねえといけねえ。ここが俺様の意地の見せ所よ。」
呟きながら、茂平は四つん這いになり、ゆっくりと慎重に前へ進み出しました。
「おーい、柴吉さんよー、お経を唱えてるのはおめえかーい?」
茂平は、恐る恐る柴吉の青白いこもに耳を近づけました。
「ナムサイペンブツ。ぐっすりと死んでやがる。お経どころか息もしちゃいねえ。鉄砲で撃たれた猪みてえに死んでるね。するとこっちかな?おーい、お花―、おめえがお経を唱えているのかい?」
今度は隣に安置されているお花のこもに耳を持っていきました。
「何も聞こえないね。すっかり死んでいる。ナムサイペンブツ。お邪魔しました。するってえと、まさかな、まだ言葉だってろくに話せねえ松坊に、お経なんて読めるはずはねえからな。うん。やっぱりそうだ。かわいそうに。まだ小せえのによ。こんなことになっちまってさ。ナムサイペンブツ。おや?おやおやおや?やっぱりそうだ。そうだよ。お経ってのはジジイが唱えるものって昔から相場が決まってるんだ。聞こえるのは、うん、ジジイの方からだ。」
茂平は仰向けに安置されている老人のこもに耳を当てました。
「なるほど。このジジイ、死んでるくせに偉そうにお経なんて唱えてやがる。驚いたね。お経ってのは一度覚えちまうと、死んでからも口から出てくるもんなんだな。ありがたい、ありがたい。いや、ちょっと待てよ。このジジイ、もしや生きてるってことはねえかな?」
茂平は老人にかかっているこもを取り除き、その耳元に声をかけました。
「もしもし。お爺さん。生きてなさるか?生きているなら返事をしてくれ。だめだ。まだお経を唱えてやがる。こうなったら奥の手だ。」
茂平はお清めのために置いてあった御神酒徳利を持ってきて、傾けると、老人の唇に一滴、酒を垂らしました。効果はテキメン。一滴の酒は瞬時に、老人の乾いた全身を稲妻の如く駆け巡り、眠っていた細胞一つ一つに狂った雷鳴を轟かせました。百年の眠りは、ついに一滴の酒という巨大な鐘撞き棒で完膚なきまでに叩き壊されたのです。無理もありません。才遍和尚は即身仏の行に入るそのずっと以前、髪を剃り仏門に入った瞬間から完全に酒を絶っておりました。断酒は百年どころの騒ぎではなかったのです。
「ホー!」
両の目をカッと見開き、頭のてっぺんから奇声を上げると、ついに才遍和尚、ここに大復活を遂げたのであります。
「爺さん、生きていたな!」
茂平はすぐさま背負いかごに才遍和尚を詰め込むと、村の中心部へ向けて走り出しました。
「爺さん、待ってろよ。今すぐ医者に診せてやるからな。」
月明かりを頼りに、嵐でぬかるんだ道を走っていると、背中のかごから再びお経が聞こえ始めました。
「またブツブツ始めやがったな。死んでねえって証拠だ。好きなだけやりやがれってんだ。おーい!みんな!起きろ!ジジイが生きてやがったぞー!医者だあ!医者を呼べ!」
お経を唱える才遍を背負い、走りながら、茂平は大声を上げて村のみんなを起こしました。もちろん、美濃国のこんな山奥に医者なんていません。茂平が医者と言ったのは住職の与一のことで、田平子村では僧侶が医者を兼ねるのが与太以来の伝統です。大声で叩き起こされた村人たちを従えて、茂平は与一の待つ寺の本堂に才遍を連れて行くと、慌てて敷かれた布団の上に寝かせました。生きているといっても、百年飲まず食わずで土の中にいたのです。才遍はまだ無意識の世界にいて、胸の前で両手を合わせながらブツブツとお経を唱えております。
「確かに生きているな。」
与一が、本堂に集まり好奇心をいっぱいにして才遍を覗き込んでいる村人を代表して茂平につぶやきました。
「ああ生きてる。死人は経を読まねえからな。だから連れてきた。」
「見たところ、怪我はないようだ。」
「ないね。どこからも血は出てねえ。」
「お経を読んでいるな。」
「坊主のおめえがこれをお経だってんなら、お経だな。」
「立派なお経だ。どこか由緒正しいお寺さんのお経に違いねえ。だとすると、この方は立派なお坊さんかもしれねえな。」
「おめえがそう言うならそうだろう。」
「どうする?」
「どうするってどうするよ?俺は医者じゃねえし坊主でもねえ。この村で一番医者に近いのはおめえだ、与一。」
「そうだな。まず目を覚ましてもらったほうがいいな。もしもし、お爺さん、起きてください。お爺さん。」
「むにゃむにゃむにゃ。」
与一が肩をゆすっても、才遍はまだ両手を合わせお経を唱えています。ただお経の声が少しだけ大きくなりました。
「気付け薬を使ったらいいんじゃねえか?」
集まっていた村人の誰かが提案しました。
「そうだな。気付け薬を使ってみよう。」と与一。
「誰か、気付け薬を持ってないか?なんでもいい、気付け薬を持ってきてくれ。」
「与一よ。みんな気付け薬を持ってきてやりたいのは山々だがよ。俺たちはみんな医者じゃねえ。この中で誰が医者かって言えば、やっぱりおめえしかいねえんだ。おめえがその気付け薬ってやつが何なのかまず言ってくれねえと、俺たちが気付け薬を持ってきてやりたくても持ってこれねえぜ。」と茂平。
与一は顔をしかめて、
「茂平、お前は気付け薬も知らねえのか?他のみんなもか?ええ?ここには気付け薬を知っている垢抜けた人間は一人もいねえんだな。まったく気付け薬も知らねえたあ、どいつもこいつも困った田舎者だ。いいか、気付け薬といえば、あれだ。そうだよ。あれに決まってるじゃねえか。本にも書いてある。」
「だからそれを言ってくれ、与一。」
「困ったな。ここには気付け薬がないときた。気付け薬がないとすると仕方がない。乱暴なことはやりたくねえが、ないんじゃあしょうがない。お爺さん、あなたはもしかしたら偉いお坊さんかもしれませんが、どうかお許しください。今からあなたの横っ面を引っ叩きます。いいですか。覚悟してくださいよ。そーれ!」
「待て待て待て。」
慌てて与一の手を押さえたのは茂平です。
「与一よ、そんなことをしてみろ、爺さん本当に死んじまうぜ。見てみろ。骨と皮しかねえんだ。おめえのこのぶっとい腕でぶん殴ってみろ、折角助かった命だってえのに、あの世へまっしぐらだ。」
「だったらどうすればいい?」
「俺にも気付け薬が何なのかは知らねえ。だけどよ、ここには気付け薬の代わりになるものがあるぜ。」
「そんなものがあるのか?あるならさっさと言えばいいじゃねえか。もったいぶってねえで出せ。」
「ちょっとごめんよ。」
茂平は立ち上がり、仏壇のお供え物の中から徳利を一つ取ってまた戻ってきました。
「おいおい茂平、その御神酒をどうするつもりだ。」
「与一よ、決まってるじゃねえか。さっきもこの手を使ったんだ。爺さんに飲ませるのよ。」
「ダメだダメだダメだ。」
「どうして?」
「どうしてって、バカだなお前は。このお方は立派なお坊さんなんだぞ。いいか、立派なお坊さんは酒を飲まねえんだ。飲んじゃいけねえんだよ。俺だって飲まねえ。」
「おめえは元から下戸じゃねえか。じゃあどうする?」
「それが酒じゃなくて、気付け薬ってことにすれば、問題はない。」
誰かが言いました。
「いやこれは酒だ。」
与一は言い張ります。
「酒でもあり気付け薬でもある。」と他の誰か。
「何だかめんどくせえな。じゃあ俺はやらねえぞ。与一、おめえが決めろ。」
「わかった。茂平、こうしよう。これは酒ではなくて気付け薬ということにする。今夜だけ、これは酒ではない、薬だ。これでいい。これならこの偉いお坊さんも満足してくれるはずだ。よし、茂平、この老人に気付け薬を飲ませてやってくれ。」
「坊主ってやつはまったくめんどくせえ。」
茂平が再び才遍の唇に酒を一滴、今度はさらにもう一滴余計に垂らすと、
「ほー!」
才遍は頭のてっぺんから蒸気を噴き出すように布団から飛び起きました。
「ついに目を覚ましましたか!」
与一が才遍を抱き止めて体を支えます。
「私を抱いてくださるのは阿弥陀如来様。実にありがたきこと。ついにわしの長い行も満行を迎えました。どうか、阿弥陀如来様、そのご尊顔を拝ましていただきたい。ん?なんだお前は?阿弥陀様ではないな!」
蘇った才遍は与一の顔を見て眉間に皺を寄せました。
「あなた様が、どちらか由緒あるお寺さんの高僧だと、私にはわかっております。私は名を与一と申す者、この寺の住職で、」
「なんということだ!周りにおるのも皆菩薩たちではない!皆薄汚い人間ではないか!ここは涅槃ではないのか!なんということだ!また俗世界に戻ってきてしまったぞ。弟子たち!わしの弟子たちはどこだ!わしを箱に戻せ!即身仏の行はまだ終わっていない!」
「お坊様、お坊様、どうか落ち着いてください。あなたは山の崩落に巻き込まれたのです。命が助かっただけでも奇跡というもの。まさに御仏のありがたい御慈悲によるものです。」
「なに山が崩落したと?北の山が崩落したのか?」
「はい。ひどい嵐のせいです。」
「そうか、そうであったか。で、弟子たちは無事か?」
「山崩れから掘り出されたのは、お坊様の他は麓に暮らしていた三人の家族だけでございます。」
「なるほど。では弟子たちは無事なのだな。すまんが、ご住職、ええと、」
「与一と申します。」
「与一殿、すまんがわしの弟子たちを呼んできてはもらえぬか?わしはすぐにまた即身仏の行を再開せねばならぬ。」
「お坊様、お弟子さん方はどこにおられます?」
「何を申しておる?蛙鳴寺が無事なら蛙鳴寺におるのだろう。目の前で山が崩れて震えているやもしれぬ。みなまだ子供で、気の小さい奴らだでな。」
ケイメイジと聞いて、与一をはじめ集まっていた村人の数人がハッと息を飲みました。その寺の名を知っている村人も、その頃にはもうほとんどおりません。田平子村が野武士たちによって襲われ焼き払われてから、何しろもう百年の月日が経っています。時代もすっかり変わり、時はすでに天下泰平の江戸時代。それでもまだその名が微かであっても人々の記憶の端っこに引っかかっていてくれたのは、かつての村の大恩人、偉大な与太様が子供の頃に修行した寺だったからです。おかげで歴史好きで信心深い与一と他の数人の老人はなんとか蛙鳴寺を記憶していました。
「あなたは、今ケイメイジとおっしゃられましたか?蛙が鳴く寺と書いてケイメイジ?」
「さよう。お主は蛙鳴寺を知らぬのか?見たところ僧侶の様子だが。わしは随分と村から離れたところに連れてこられたようだ。弟子たちが無事ならそれでよい。お手数をかけるが人をやって、彼らをここに呼んでもらいたい。わしは行を続けねばならぬ。戦乱の世を終わらすため、わしは即身仏となるのだ。弟子たちに箱を作らせ、また穴に埋めてもらわねばならぬ。」
「はあ?」
「墨念、木念、即念、鎮念の四人が寺におるはずだ。どなたか人をやって呼んで来てはくれまいか。いや、待てよ、四人だったかな?わしには、五人、弟子がいたはずだ。墨念、木念、即念、鎮念とあと、確かにもう一人いたな。ええと、そうだ。そうそう、忘れていた。与太だ。あいつは与太といった。うむ。与太も入れてわしの弟子は五人だ。」
与太という名を聞き、そこにいた村人たちが今度は全員ざわつきました。蛙鳴寺の名を聞いた時とは大違いです。誰もが与太の名を耳にした途端、ハッと息を飲み、正座をし、身仕舞いを正しました。
「あのうお坊様。」
与一がおずおずと口を開きます。
「他の四人は知りませんが、蛙鳴寺の与太様ならこちらにおいでになります。」
「何?与太がおると?」
「はい。どうぞご覧ください。こちらでございます。」
与一が恭しく掌で指し示した方向には、立派な仏壇があり、才遍が目を凝らして見ると、中央には堂々と一人の僧侶が胡座をかいて座っております。ただその僧侶は微動だにせず、また表情も柔和な笑みを浮かべたまま固まっているので、やがて才遍にもそれが見事に彩色された等身大の僧侶の坐像だということがわかりました。ただ、才遍がこの木彫りのお坊さんを生きている人間と勘違いしたのも無理からぬことで、この像は、才遍のように百年も土の中にいたモグラ人間の目ではなく、二十歳の健康な人の目で見たとしてもやはり生きているように見えました。と言いますのも、この像は、戦国から江戸にかけて大活躍し、天才と謳われたかの有名な彫刻師、左巻甚五郎の作だったからです。左巻甚五郎は戦禍を逃れ一時期、田平子村の与太の庇護の元にありました。甚五郎はその恩を死ぬまで忘れることはなく、与太の恩に報いるため、彼は十年の長い年月と全身と全霊をその手とノミに込めて、この『与太聖人坐像』を彫り上げたのであります。
「はて?このお方、どこかでお会いしたことがあるな。」
才遍は仏壇に鎮座している与太聖人坐像を見上げ、じっと目を凝らしました。
「やや!これは!いや、そんなはずはない。あいつがここにいるはずはない。あいつはどうしようもないバカなんだから。それにしても、うーん、実によく似ている。これはどこからどう見てもやはり奴だ。歳を取ってはいるが、間違いない。どう見ても奴に生き写しだ。これはいったいどういうことだ?うむ。これは与太だ!間違いない与太の坐像だ。」
「お坊様、この村で与太様を呼び捨てにする者は、誰でも平手打ちにしてよいことになっております。お気をつけください。」
与一が言いにくそうに言いました。
「なんだと?」
「こちらに鎮座しておられますのは我らが御本尊、与太様にございます。そしてここは田平子村で唯一の寺、与太寺でございます。」
「田平子村?」
「はい。」
「ここは田平子村なのか?」
「はい。」
「間違いないか?」
「はい。」
「それで?それでここはなんという寺だと?」
「与太寺にございます。」
「与太?」
「はい。」
「デラ?」
「はい。」
才遍は再び意識を失いました。
「大変だ。茂平!酒だ。違う。気付け薬を持ってきてくれ!」
茂平は与一に酒の入った御神酒徳利を渡すと、老人が再び意識を取り戻すのを見ることもなく、さっさと三人の亡骸の待つ掘立て小屋へと戻っていきました。他の村人たちも同様です。皆、それぞれに挨拶を交わし本堂を後にしました。あとは住職の与一と与太寺の僧たちに任せておけば大丈夫だ。夜も遅い。俺たちの手はもう必要ない。何しろ明日は村の片付けや葬式の準備や何やらで忙しいのだ。帰って少し寝ることにしよう。というわけです。
村人の結論はすでに出ていました。この老人は、たまたま北の山が崩れた時に、運悪く、下の道を歩いていた旅の僧侶で、その時強かに頭を打ったため一時的に頭がおかしくなり、自分を、旅の途中どこかで耳にした大昔のお坊さんだと思い込んでしまったのだ。そう村の人々は考え、いつまでもそんな頭のおかしいジジイにかまってはいられないとそれぞれの家の寝床へと戻っていきました。
「あの爺さんいつになったら正気に戻るかね?」
「さあな、一生戻らねえんじゃねえかな。」
与一の耳には、みんなが帰りしな、そんな会話を交わしているのが聞こえてきました。
「むにゃむにゃむにゃむにゃ」
与一が唇に落とした気付け薬ならぬ酒により、再び意識を取り戻した才遍和尚は、すぐさま身じまいを正し、正座をして手を合わせ、すべての邪念を振り払うかのように再びお経を読み始めました。
「あのうお坊様。」
与一が話しかけます。
「むにゃむにゃむにゃ」
才遍は構わずお経を上げ続けます。
「お坊様、もしよかったらお経を中断していただいて、お名前などを伺ってもよろしいでしょうか?」
「むにゃむにゃむにゃむにゃ」
「あのう、」
「才遍だ。わしの名は才遍和尚。」
「サイペン?蛙鳴寺の才遍和尚ですか?」
「その通り。」
「あの蛙鳴寺のあの才遍和尚ですか?」
「だからそう申しておる。」
「本当に才遍和尚ですか?」
「しつこいぞ!」
「困りました。お坊様はご存じないようですので申し上げます。ケイメイジという寺は確かに田平子村のお寺でございます。ただ残念ながら今はもうありません。また物の本によりますと、そこの住職に才遍和尚という人がいたという話も確かに書いてはあります。ただ同様に今はいないはずです。と申しますのも、蛙鳴寺が焼け落ち、ご住職の才遍和尚が弟子を連れてどこかへ行方をくらましたのは、何しろ今から百年も前のことですので。」
「百年?」
「はい。確かに百年です。おい金兵衛、巻物を持ってきてくれ。そうだあの巻物だ。」
与一は、本堂を出たり入ったりしている僧たちの一人に声を掛けると、再び才遍と向き直りました。
「まあ、お坊様、実のところ巻物を読むまでもありません。私たち与太寺の僧侶は皆、数え切れないほど与太様のご生涯が書かれたあの巻物を読んでいますから。与太様が若い頃に修行された蛙鳴寺が野武士どもに襲われ、焼け落ちたのは間違いなく今から百年も前です。そうなると与太様の師匠の才遍和尚が村を捨てて逃げたのも百年前ってことになります。」
「わしは逃げてなどおらぬ。」
「そうでしょう。だからあなたは百年前の才遍和尚ではない。」
「わしは才遍だ。即身仏となるため、ずっと蛙鳴寺の境内の土の中にいたのだ。」
「まあ確かにあなたは随分とお年寄りに見えます。百年くらいは生きたようにも見えます。どうやらあなたは崖崩れに巻き込まれて混乱しておられるようです。百年前、寺が失われた当時すでにいい大人だった才遍和尚が今も生きているわけがございません。それにもしも、万が一にですよ、才遍和尚が今日生きておられたとしても、おそらく恥ずかしくて村には戻ってはこられますまい。何しろ与太様を一人残して逃げたんですから。」
「いったいお主は何を言っておるのだ?このわしが逃げただと?わしは逃げなどせぬ。それどころか、村を戦乱から救うため、ずっと寺にいて即身仏の行に励んでおったのだ。」
「いったいそんな話をどこでお聞きになったんです?誰だか知りませんが、とんでもないホラ話を吹き込まれましたね。この村にはどんなに歴史を遡っても即身仏は一人もおりません。おお金兵衛、ありがとう。この巻物には与太様が生前行われたことや、おっしゃられたことが逐一全部書いてあります。どれどれ、いいですか?与太様が生前に才遍和尚について語られた部分は二か所あります。」
「二か所?たったの二か所か?わしのことを奴は二度しか言っておらぬのか?薄情な男よ。」
「いいですか、一つは、才遍和尚が与太様に僧籍を与えたときの会話です。『よいか。お前はこの先ずっと困った人を助け続けるのだ』と才遍和尚は言い、与太様は生涯その言葉を忘れることはありませんでした。」
「わしはそんなことを言ったかな?覚えておらん。」
「もう一つは、ある晩、与太様が熱病で苦しんでいる娘を前にして、とっさに『南無才遍仏』と唱え、娘の命を救ったくだりです。以来この村ではお経といえば『南無才遍仏』となりました。」
「ナムサイペンブツ?なんだそれは?」
「うちのお経です。」
「田平子村の経は古来より『南無阿弥陀仏』だ。ここが本当に田平子村ならの話だがな。ナムサイペンブツだと、サイペン?なんでわしの名が経になる?バカバカしい。代々田平子村の寺の御本尊は阿弥陀如来様だ。その書が与太の言行録なら阿弥陀様のことが記してあるはずじゃ。どうだ?」
「与太様は阿弥陀様のことを一言もおっしゃったことがありません。」
「罰当たりめが!ではわしの即身仏の行はどうだ?その巻物が本当に与太の生涯を記してあるのなら書いてあるはずだぞ。わしが即身仏の行に入ったことを与太が忘れるはずはない。何しろ与太自らが、他の弟子たちと共にわしを入れる箱を作り、蛙鳴寺の境内に穴を掘ったのだからな。あれは与太にとって忘れようもない大事な経験だったはずだ。自分の師匠が生きながら仏となるところを見たのだ。」
「ありません。その蛙鳴寺だって出てくるのは二回だけです。怪我をした与太様が、野武士に焼き払われた蛙鳴寺の様子を見てきてくれと世話役の銀蔵に頼み、銀蔵が茂平と茂吉の双子の偉大な猟師をやるくだりと、与太様がお亡くなりになる直線、蛙鳴寺のあった北の山へみんなでお連れするくだりだけです。」
「それで?」
「それで?」
「そのくだりにわしが出てくるだろう?」
「ええ出てきますよ。寺の様子を見て村に戻ってきた双子から与太様は『才遍和尚と四人の小僧はさっさと村を捨てて逃げた』と伝えられます。師と仲間に裏切られたことを知り、与太様はさぞかし悲しみ、怒り狂うだろうとみんなは思いますが、とんでもない。高貴な心をお持ちの与太様は『ではみんな無事なんだね。よかった』といたくご安心なされました。」
「高貴な心。何?与太が高貴だと?あのバカがか?だいたいわしは逃げてなどいない。ずっと土の中にいたのだ。」
「まあ似たようなものです。」
「なんだと。まあいい。わしが言っているのは次のくだりだ。どうだ?よく読め。与太はおそらく死の間際、土の中にいる即身仏のわしと会いにきたのだ。」
「違いますね。自らの死期を悟った与太様は、村を一望のもとに見渡せる北の山まで自分を連れて行くように命じ、そこまで辿り着くと、正座をし、村と村人たちのとこしえの平安を祈りながらその生涯を閉じられたのです。」
「どこに蛙鳴寺が出てくる?」
「『蛙鳴寺へ連れて行け』。与太様はそうおっしゃられました。ああそうそう。あなたも出てきましたよ。大事なところを忘れていました。」
「そうであろう。」
「『南無才遍仏』。与太様が最期におっしゃられた御言葉です。大地に頭を垂れながら、与太様は何度も南無才遍仏と唱えられました。」
「即身仏は?」
「そんなものはありません。いいですか、お坊様。与太様は生涯ただひたすらに困っている人を助けて亡くなられた方です。この巻物には、与太様がそのご生涯で行われた数え切れない善行の数々が書かれています。どうです?こんなに太い巻物を見たことないでしょう?この太さを見ただけでも与太様がどれほどたくさんの善行を積まれたかがわかるってもんですよ。私たち与太寺の僧侶は皆、その一つ一つを全部暗記して、自分もまた与太様のように人々のお役に立ちたいと日々念仏を唱え、困っている人の手助けをして暮らしています。百年前の才遍和尚って人を与太様が師匠として尊敬していたことは、確かにその通りでしょう。ここにもそう書いてあります。何しろ与太様は師匠の名を入れた経を作り、師匠の言いつけを生涯守り、人々のために最後の最後まで尽くされたんですから。ただお坊様、だからといって我々がその師匠まで尊敬していると思ったら大間違いです。我々が尊敬しているのはあくまでも与太様であって師匠の才遍和尚ではない。なんといったって村を見捨てて逃げたお坊さんを、いったい誰が尊敬できま、おや?」
「むにゃむにゃむにゃむにゃ、」
「人がまだ話をしているのに、お爺さん、またお経を読み始めたよ。それにしても立派なお経だな。山崩れに巻き込まれる前はよっぽど偉いお坊さんだったに違いない。まあいいや。俺だっていつまでもこんなことに付き合ってはいられないんだ。明日は忙しくなる。」
「穴を掘ってくれ。」
「なんですって?」
「早くわしの入る箱を作り、穴を掘ってくれ。即身仏の行がまだ完成していないのだ。」
「いいですかお坊様。あなたは運よく命が助かった。だけど、僧侶として大事なことを忘れてやしませんか?」
「わしは即身仏の行を続けねばならぬ。」
「そんなことじゃない。あなたと一緒に三人の人が亡くなっているんです。まだ若い夫婦と赤ん坊でした。みんな嘆き悲しんでいます。俺はこの村の坊主として、みんなを慰めなきゃいけない。あなたがどこかで耳にした昔話に付き合っている暇はないんですよ。」
「むにゃむにゃむにゃ。」
「またお経が始まった。自分が困るとお経を始めるのかな。お坊様、箱と穴はもう少し待ってください。考えます。」
「むにゃむにゃむにゃ。」
「それにしてもこれはいったいどうしたことだ?わしはいったいどうなっている?」
奇跡の復活から一週間、百年という長く深い瞑想の深淵から現世に蘇った才遍和尚は、与太寺の本堂に座り、与太様の像を前にして、ただただ一心不乱にお経を唱え、同時に考え続けていました。才遍和尚は熱心にお経を唱えながらも、頭の中は混乱し、疑問符ばかりが浮かんできていました。
「ここが田平子村だと?馬鹿なことを言うな。村の者など一人もおらぬではないか。だが似たような顔の者はおる。それも一人ではない。たくさんおる。ここの住職の与一なども銀蔵に瓜二つだ。だとすると、百年が経ったというのも本当なのか?まさか。飲まず食わずで、どうしてわしが百年も生きていられる?生きていたら、わしは百四十歳だ。生きてるはずがない。だがわしはこうして生きておる。本当に生きているのか?わしが生きているのなら、今は戦国時代なはずだぞ。江戸だと?なんだそれは?ああわからぬ。ともかく弟子たちを探してもらわねば。いったいあいつらはどこへ行ってしまったのだ?むにゃむにゃむにゃ。」
お経を唱えながらも、和尚の頭は大混乱。ただそれでも正面を見ると、そこには確かに一人、見間違いようのない自分の弟子が座っています。
「確かにこいつは与太だ。」
すべてがわからないことだらけの中で、それだけは才遍和尚にとってもはっきりしておりました。与太の木像は今にも動き出しそうに生き生きと威厳すら漂わせ、生前の姿そのままの柔和な笑みを浮かべながら、立派に仏壇の中心で鎮座しています。名工、左巻甚五郎の腕は実に見事なものでした。
「バカの与太は立派な僧に成長した。」
与太の像を目の前にすると、これだけは紛れもない事実だとはっきりわかります。
「与太はバカなのに皆から尊敬されていたのだ。わしが人知れず穴の中にいる間に。」
木像を見れば、誰だってそれだけははっきりとわかりました。だとすると、あれから百年も経ってしまったことや、恐ろしいことに自分がまだ生きていることが、紛れもない事実であると才遍にも思えてきます。
「だがわからん。わからんのだ。わしは何一つ覚えておらん。この百年間、わしが土の中におったときに起こったことを、わしは一つとして覚えてはおらぬ。寺が焼き討ちにあっただと?わからん。弟子たちが村を捨てて逃げた?わからん。与太が死ぬ前にわしを訪ねてきた?ああ!そんなことまったく覚えがない。わしは即身仏になるため、ただただ真剣に経を唱えていたのだ!」
せっかく土の中から出てきたというのに一週間、この調子でごちゃごちゃと考え事をしながら、才遍和尚はお経ばかりを唱えておりました。不思議なもので、百年間飲まず食わずでいても、一度地上の空気を吸ってしまうと食欲も出て、便通も復活してしまいます。おかげで和尚は寺で出された食事を残さず平らげていました。そのために、どれほど長く自分が土の中にいて厳しい修行をしていたのかを必死になって与一や寺の僧侶たち、他の村の人々に力説しても、誰も信じてはくれません。このやせ細った老人は、おそらくどこかの偉いお坊さんが頭を打ち正気を失っているのだと誰もが信じて疑いませんでした。そこで仕方なく、和尚は食事と厠以外の時間を、ずっとお経を唱えることにしておりました。何しろお経だけは百年も続けていたことです。本堂の真ん中に座り、ひたすらに唱え続けていても、ちっとも辛くはありません。それより才遍和尚が辛いのは、今、自分が置かれている状況がまったくわからないことでした。いや、それ以上に苦しいのは、大事な修行が中断されてしまったことでした。
「一日も早く土の中へ戻り、修行を完成させねばならぬ。即身仏にならねばならぬ。」
焦って与太寺の住職の与一に伝えても、
「今は収穫時期でとても忙しいので、もうしばらく考えさせてください。」
の一点張り。一向に箱も作ってくれませんし、穴も掘ってはくれません。
「坊主が収穫となんの関係がある?」
才遍は抗議しましたが、こうして本堂に座り、お経を読みながら周囲を観察しておりますと、ここの寺の僧侶たちは皆、日中外へ出て村の人々の仕事を手伝っていることがわかりました。
「この寺の者たちは畑仕事に大工仕事、おまけに医者のふりまでやっておる。が、肝心の仏教については何一つ知らん。誰一人としてお経の一つも読めやしないではないか。どいつもこいつも僧侶の本分を忘れておる。わしがもう一度穴に入る前、時間があったらお経を教えてやらねばならんな。」
こうして才遍和尚は日がな一日お経を唱えながら、頭の奥から次から次へと湧き上がってくる考え事を、次から次へと考えては、忙しく頭を動かしておりました。すると夕方、体格のよい僧侶が泥だらけで本堂に入ってきて、才遍和尚の隣に座り、
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ。」
与太の作ったお経を三回唱え、すぐに立ち上がるとまた出て行きました。立ち上がり際、僧侶が「ふんっ」と自分のことを鼻で笑ったのを、才遍はお経を唱えながらも見逃しません。
「『ふんっ』だと。これがお前たちの朝晩のお勤めだというのか。バカバカしい。いかにも与太の考え付きそうなお勤めだ。簡単でどんなバカにでもできる。今出て行ったあいつはこれで自分が一人前の僧になったつもりだ。実におめでたい。」
本堂には入れ替わり立ち替わり、一日の仕事を終えた僧侶たちが帰ってきては各々、
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ。」
と与太の作ったお経を唱えてはまたすぐに出て行きます。皆汗まみれの泥だらけ、一日の重労働で全身はボロボロです。ところがその顔は皆与太様の教えを実践している喜びで輝いていました。
「これはいったいどうしたことだ?」
才遍が再び自問します。
「阿弥陀様はいったいわしに何を見せ、何を教えようとされているのだ?与太寺だと?与太様だと?どうもわしが土の中に入り、百年が経ったのは本当のようだ。百年も経たないと、バカが聖人などになれるわけがない。どうしたことだ?何もかもが違ってしまっておる。与太だと?よりによって与太が、わしが土の中にいる間にこの村の寺の住職となっただと?あの頭の弱い子が皆に慕われる僧となった?信じられん。弟子たちはどうした?みんなどこへ行った?みんな与太よりも優れた子たちだったではないか。与太以外はみんな逃げただと?バカな。わしと一緒に逃げた?わしは逃げてはおらぬ。村のため、世の安寧のために命を捨てて飲まず食わずで経を読んでいたのだ。」
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
また別の若い僧侶が外から帰ってきて、才遍の隣に座りお経を唱えると、すぐにまた出て行くかと思いきや、出て行きません。才遍の隣でひたすらにお経を繰り返しています。
「ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、ナムサイペンブツ、」
この若い僧は、隣に才遍などいないかのように一直線に与太坐像を見つめ、手を合わせ、一心不乱に経を唱えております。才遍には、この僧が他の僧侶たちよりも一際疲れていることがわかりました。それどころか、与太坐像を見つめる目が潤んでいることも、才遍にはわかりました。
「この子は今日一日何をしてきたのだ?何をしていたにせよ、誰かの苦しみや悲しみと共にあったことは間違いあるまい。」
「むにゃむにゃむにゃ。」
才遍も心を込めて自分のお経を読みました。
「それにしても阿弥陀様はいったいどこへ行ってしまわれたか?」
才遍がその行方を求めたのは、天のどこかにおられる本物の阿弥陀様ではありません。この時才遍が求めたのは、かつて蛙鳴寺の仏壇に御本尊として祀られていた小さな阿弥陀如来の木像のことです。
「せめて阿弥陀様に向かってお経を唱えたいものだ。与太に向かってでは、いくら経を読んでも読んだ気がせぬ。これが百年ということか。まったく変われば変わるものよ。世も末を越えると、バカが阿弥陀様の代わりになってしまうのか。これが太平の世だと?バカバカしい。阿弥陀様のおられぬ村に平穏などあるわけがない。与太はいったい何をして阿弥陀様の座についたのだ?ええ?『生涯困っている人を助けなさい』。わしは与太にそんなことを言ったのか?覚えておらん。阿弥陀如来よ。どうぞお答えください。わしはなぜ仏になれぬ?いつまで経を読み続けねばならぬのですか?百年では足りぬとおっしゃるか?そんな短い時では生やさしいとおっしゃるか?よいでしょう。わかりました。この才遍、どこまでも続けますぞ。あなたが私を即身仏とさせてくださるまで、この先百年、いや千年、万年かかろうとも経を読み続けます。どうぞ私の経をお聞きくだされ!むにゃむにゃむにゃ!」
「和尚様、和尚様、」
すると、才遍の耳にどこからともなく自分を呼ぶ声が聞こえてきました。そのどこか懐かしい声に、才遍はついにお経を止め、耳を澄ませます。
「和尚様、和尚様、与太でございます。弟子の与太でございます」
「与太か?」
恐る恐る聞くと、突然、才遍の脳裏にはっきりとした記憶が蘇ってきました。それは与太が北の山で亡くなったあの日の出来事です。
「ああ和尚様!生きててくださったか!」
暗い箱の中の才遍の頭の上に、与太の朗らかな声が一筋の光と共に降りそそいできました。
その日も、寺へ一番遅く帰ってきたのは住職の与一でした。一日中忙しく困っている人々を助け、疲れ果てた体を引きずってようやく山門まで辿り着くと、そこに身なりのよい旅姿の見知らぬ男が与一を出迎えました。
「こんばんは。先ほど若いお坊さんが住職は一番最後に帰ってくると教えてくださいましてな。こちらのご住職の与一殿ですかな?」
「ええ。私が与一です。何かお困りごとですか?」
「困っているというほどのことではございません。ご住職に興味のありそうなお品を持参し、はるばる京より参りました。」
寺の客間へ通すと、男は京で骨董を商っている仁兵衛という者だと名乗り、挨拶もそこそこに風呂敷から一体の古い小さな仏像を取り出しました。
「この仏像ははるか昔、越前国で行き倒れた貧しい僧が大事に持っていたものです。流れ流れてこの度、当方の手に渡りました。」
「はあ。見事な阿弥陀如来像ですな。こちらがどうなさいました?」
与一をはじめ与太寺の人間は、すでに立派な御本尊様があるので、仏像に興味はありません。
「こちらのお寺が仏像の収集にご興味がないのはよく聞いております。まったく世間には檀家さんから集めた浄財で骨董道楽しているお寺のなんと多いことか。私も骨董業をやりながら嘆いているところでございます。もちろんこちらのお寺は違います。ただ、この仏様はだけは特別でございましてな。おそらく、いえ、間違いなくご住職も喉から手が出るほどご所望になるはずでございます。」
「いえ、私はどうもそのような、」
「まあそう言わず、どうぞ仏像の背中をご覧なさい。」
すすめられ、渋々仏像の背中に書いてある裏書を見て、与一はハッと息を飲みました。
「これは?」
「だいぶ薄くなってはおりますが、確かに『田平子村蛙鳴寺』とあります。おそらくこちらの村と関係のある仏様かと思い、本日ご持参いたした次第です。」
「なるほど。これは驚いた。いやつい最近、ある人から村の御本尊は与太様ではなく阿弥陀様だと聞いたばかりでしたので、つい驚いてしまいました。」
与一は男に仏像を返そうとしますが、男はまだ受け取りません。
「どうぞ仏様の足裏もご覧ください。」
与一は仏像を裏返してみましたが、今度は特に何も書いてありません。
「この仏様は仕掛け箱になっておるのです。お貸しください。」
男は与一から仏像を受け取ると、乱暴にひっくり返し底の部分を親指でぐっと押し込みます。すると、カチリ。中で錠の外れる音とともに阿弥陀様の両足首から先の土台部分が外れ、中から幾重にも折り畳んだ古い和紙が落ちてきました。男はその和紙を拾い上げると、与一へ渡します。
「どうぞお読みください。この仏像を所持していたお坊様の遺書です。」
「はあ。」
与一が丁寧に紙を開くと、中にはびっしりと細かい字で何か書いてあります。
「なになに、『愚僧、名乗るほどの価値なき者ゆえ名を名乗ることさえ憚られるが、名、なければ我を葬りくださる方のご不便にもなる故、ただそれのみを恐れ、ここにその名を記すこととす。愚僧、師からは即念と呼ばれし者にて候、』。」
「面倒なお坊さんですな。自分の名前一つ書くのにもその長い前置きです。ご心配召されるな、与一殿。中身を全て読む必要はありません。この仏像を村から盗み出した即念というお坊さんがご自分を恥じ、一日も早く仏様の元へ召されたいと念仏を唱え諸国を渡り歩き、ついに極寒の越前でまもなく人生を終えることができそうだと長々と書いてあるだけです。さあどうです?こちらの阿弥陀如来像、お買い求めいただけますかな?」
「はあ。そうですな。当寺といたしましては、」
と言いながら、何気なく手元の紙を眺めると、即念の書いた細かく長い文字の行列から、つい最近与一が耳にした文字が浮かび上がってきて、目に飛び込んでまいりました。それは『才遍』という文字。ハッとしてよく見ると『才遍和尚』とあります。夢中で前後を読むと、即念は自分が恥ずかしながら名僧、才遍和尚の弟子だったとあります。
「ご住職?与一殿?」
男が声をかけても、与一の耳にはもう何も聞こえません。食い入るように即念の書いた細かい文字を読み進めていきました。
「なんてえこった。」
「与一殿、どうなさいました。」
「本当だったんだ。即身仏は本当だったんだ。与太様は師匠が即身仏の行をしていたことをすっかり忘れていたんだ。いや、そうじゃない。与太様は最後の最後に思い出したんだ。だから北の山へ連れて行けとおっしゃった。」
そこへ、若い僧侶が息を切らせて客間に飛び込んできました。先ほど才遍和尚の隣に座り、涙目になりながら熱心にお経を唱えていた若い僧侶です。
「ご住職!大変です!」
「どうした?」
「才遍様が、才遍様がお亡くなりになられました!」
「亡くなった?どうして?」
「わかりません。ただ突然お経を唱えるのをお止めになったと思いましたら、いきなりお立ちになり、『若いの、明日はわしもお前たちと共に働くことにした』とおっしゃった途端、そのまま成仏されてしまいました。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
