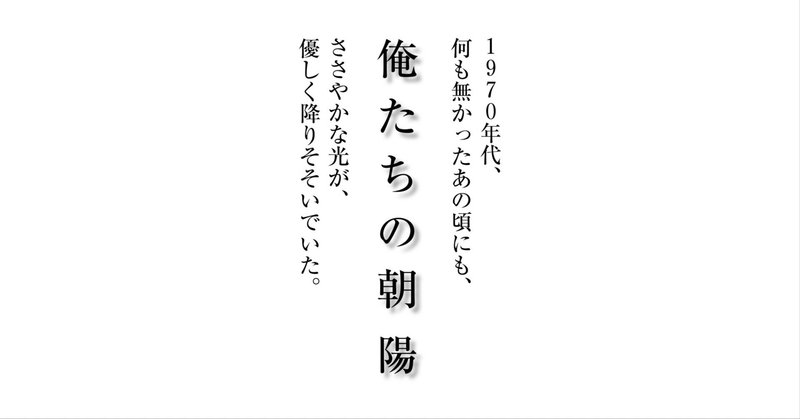
【連載小説】俺たちの朝陽[第7章]みんなが出るから全員野球だろ
【みんなが出るから全員野球だろ】
スナック『愛』のママのマー姐ぇも、ホステスの桃ちゃんと一緒に『27時』の応援団を結成すると張り切っていた。なんでも桃ちゃんの元旦那というのが、関西の大学野球でならしたスラッガーだったという。大阪のプロ球団に入り、そこそこの成績をあげていたが、監督と折り合いがつかず、東京の球団へ放り出され、桃ちゃんもついてきたが、元旦那は怪我をきっかけに解雇され、お決まりの喧嘩から離婚の道を歩んできたという。
「だからさ、野球っていうと、辛いんだけれど、ふと気がつくと、なぜかお店のテレビで野球を見ている自分がいるんだよね」と、幸せだったらしい頃を思い出すように言う。
マー姐ぇは、
「私は文学青年好みだったから、そんな物語はなかったけれど父さんが野球命の人で、よく球場へ連れていってくれたから、並の娘よりは知っているわよ」と、ルールはあまり知らないがホットドッグの味なら再現できると自慢する。
「あのホットドッグ食べたくて、父さんのご機嫌とってさ」
ここに応援メニューとして『愛の27時ドッグ』が誕生したのだった。
春は案外早く訪れるものだと、北国生まれの地金は、最近になって初めて気がついた。 練習試合はおろか、身内で行う紅白試合さえもせずに早朝野球リーグの開会式を迎えてしまったのだ。試合をしなかったというよりは、行える状態ではなかったといった方が正しい。
5人の自称エースのうち、3人はまともにキャッチボールもできなかったし、4人の自称四番候補のうちのひとり、電気工事屋のナベちゃんなどは、思いっきり引っ張った打球は、その思いとは裏腹にバットの先端をかすり90度反対方向に行ってしまうため、「だまし打ち」打法と命名される始末。とても試合どころの話ではなかったのだ。それでも懲りない面々は、今か、今かと公式初試合を待ち望んでいた。彼らの意気込みは、『ヒゲ』の餃子がいつもの月の倍の売り上げがあったことでもそれは解るというものである。
「この連中が餃子を食べるとは」と、洋助が驚いたほどである。しかし、「何人様も現金にてお願いします」という貼り紙があるにも拘らず、3割ほどの〈ツケ率〉ではあったが。
開会式の前日、洋助は店が終わってから22人分の例の真新しいユニフォームを、白菜の入っていた段ボールに詰め込む準備をしていた。そこへ哲彌が入ってきた。
「もう終わり、明日早いからな」
「そう言わないで、一杯だけ飲ませてよ。酔わないと寝れそうにないからさ」
哲彌は、新聞社の編集整理部の契約社員として働いていて、遅番だと帰りは真夜中を過ぎてしまうのだ。インクで爪の中まで真っ黒にした手で、コップを突き出しながら頼み込むと、
「しょうがないな、一杯だけだよ」
一合升に酒をなみなみと注ぎ、受け皿にも溢れさせて出し、洋助は酒はあまり飲めないのだが、自分のコップにも少し注いだ。
「明日の『27時』のために」と、ふたりで乾杯した。
「地金と綾ベーがいままで明後日の先発メンバーで揉めてさ」
「それでどうなった」
「どうなったって、決まるわきゃないよ」
哲彌は少しホッとした。先発投手は俺しかいないはず、とは思っていたが地金がはっきりとは言わないので気になっていたのだ。コバが入ってからは、受けられるキャッチャーができたので、今や空き地になっている浄水場の跡地の四号地で数回のピッチング練習をした。濡れ手拭いを使ったシャドウピッチングのお陰もあってか、高校時代とまではいかないが、かなりのスピードが戻ってきたように思えた。
しかし、監督の地金には、まだ見せてはいない。ほかにはいないのだから、開幕投手はは自分だと勝手に決めていたのだった。コバから地金に報告も入っていることだろうし、なにしろ投手というものをやったことのある人間は、俺を除いて誰ひとりいないのだから。
しかし、地金と綾べーは何を揉めていたのだろう。
「まあ、俺とコバ以外は何も決まってはいないも同然だから、仕方ないだろうなあ」と、哲彌は監督、副監督である地金と綾べーに同情していた。
洋助は洋助で、朝は早いから全員の連絡をどうするか頭を悩ませていた。なにせ人数が人数だ。どこかで酔い潰れていない限り、ほとんど全員が顔を出すはず。雨が降ったりして中止にでもなったら、どう連絡をつけていいか解らなかったからだ。朝っぱらから、20人を超えるむさ苦しい男たちが店の前をたむろしていたら、俺だってうっとおしいからな。周りにだってうるさがれるだろうし、近所のお得意様あっての飲食店商売だと洋助は日頃から思っている。が、自分が板塀を打ち壊したことなどすっかり忘れているが。
「マスター、もう一杯」
「一杯だけって言ったんじゃなかったのか」
「しょうがねなぁ」と、言いながら哲彌になみなみと酒を注いでいた。
開会式に参加するだけなのに、気分が昂揚するのを洋助も押さえられず、自分にも少し注ぎ足した。明後日の初戦を迎えたらもっと興奮するのかなと、久しぶりの胸の高鳴りに戸惑いながらも、そんな自分を嬉しく思っていた。それは、全員が同じ気持だろうと思っていると、こんなことそうそうあるもんじゃないからという哲彌に丸め込まれ、おしんこも一緒につけて、三杯目を注いでいた。開会式は6時だったが、これから一年間のことを考えて集合時間は、4時半にしていた。
「お、あと2時間しかないぞ、少し寝よう」
洋助は、戸締まりといっても、釘一本あれば簡単に誰でも開けることができそうな鍵をかけて奥へと引っ込んだ。哲彌は間借りというより、一畳分を借り間しているというべき亀ちゃんの三畳の下宿へ帰っていった。
2時間後、案の定、まだ真っ暗なうちから男たちは集まってきて、あっという間に全員が揃っていた。店の中に納まりきらず道に溢れていた。開会式だからグローブはいらないのだが、みんな嬉しそうにそれを手にはめながら片手をポンポンと当てていた。中には待ち切れないといった感じで、道端でバットを振りまわす奴もいて、朝帰りの酔っぱらいたちを怖がらせていた。
「前が『27時』のマークで、後ろが自分の背番号だ」と、洋助がひとりひとりに例のユニフォームを全員に手渡していた。Gパンをはいた者、上下のジャージで揃えた者、一応野球着を着てきた者、各自バラバラではあったが、その上に例の真新しいユニフォームを上からかぶり、両脇のところで紐を結ぶ。そんな各々の身支度の上にそれを纏うと、『27時』のそれなりのユニフォーム姿が完成した。自分たちで作ろうと言ったはいいが、内心どうなるものやらと少々心配だった洋助は、全員の姿を見て、いかにも手作りといった仕上がりに「案外いいじゃないか」と、誇らしくさえ思っていた。
「さあ、行こうか」と、地金が監督としての第一声を放った。
もちろん、車などあるはずもないので、球場まで30分、22名が隊列を組んでの行進だ。近道をくねくねと進みながら行くと、すでに出勤の支度が整ったサラリーマンたちが、一団を見て一様にギョッとした顔をするので、
「こちらのほうがびっくりしてしまうなあ。でも、奴らもう会社に行くんだな」などと妙に感心しながらも、そのことはすぐに忘れ、明日のポジションと打順についてお互い熱心に誰彼となくアピールしていた。
やはりといういべきか、当然というべきか、球場には一番乗りだった。それから徐々に集まってきたが、第一回にしてはまずまずのメンバー12チームが一同に会すると圧巻だった。周囲に対する配慮から車での球場付近の駐車は許されなかったため、少し離れたところに車を置いてきたらしく、外車のキーをチャラチャラさせている奴や、開会式だからといって、監督と代表者しか来ないチーム、何人かしかユニフォームを着ていないチームなどもあり、「こいつらには負けられない」と、地金は思った。
そんななかで、『27時』の大所帯は目をひいた。なにせ圧倒的な人数だ。面々は他のチームの洗練されたユニフォームとリラックスした様子に少しの気後れと戸惑いを感じてはいたが、それはそれ、彼らのことである。かえって闘志に火がついたようだった。
企画をした区の役人たちは、その参加チーム数に満足していたが、それ以上に喜んだのは、どんなところにも顔を出す区議会議員たちだった。12チーム×最低でも9人=108人(票)は我にあり、と思っているのだろう。そして、『27時』ときたら最低票から13票も多いのだ。自然と顔がほころんできている。区役所の役人の挨拶に始まって、会長、副会長の挨拶と続き、来賓の区議会議員たちの祝辞が延々に行われていった時、鮨屋の信介が聞こえよがしに、
「学校の体育祭じゃあるまいし」と言うと、区議のひとりが睨んだ。それを見て『27時』のメンバー全員が一斉に睨み返した。チームワークは良さそうだ。その区議はしまったという顔をしたが遅かった。
その瞬間、彼は22票を失ったのである。少なくとも対抗するもうひとりの区議はそう思ったはずだ。しかしながら、ふたりとも認識が甘かった。もちろん、22人がそっぽを向いたのは事実だが、票読みは違っていたのである。面々は、数人を除き、彼らの地盤にはいないのだ。住民票もそこにはなかったし、あったとしても、ハナから彼らに入れるはずもないからだった。
選手宣誓までやっと辿り着き、解散になった時は、すでに1時間半が過ぎていた。
「こんなことなら、一試合できるじゃないか」参加者全員が思った。
「役人や議員のセレモニー好きを何とかしなきゃ」と、哲彌。
「なにが、この佳き日にだよ、もっと気のきいたこと言えよ」
選手宣誓をする機会があったら、
「来賓の皆様もチームを作って参加していただきたく」と、嫌みのひとつでも言ってやるのにと哲彌は悔しがった。それでも、
「店に帰って乾杯しよう」と、洋助がかけ声をかけると哲彌はみんなと、朝来た道を嬉しそうに戻っていった。
『ヒゲ』に戻り、仕事のある者を除き酒盛りが始まった。哲彌は今日も遅番で午後出社のため、軽く一杯やり仮眠を取ってから行くつもりだ。地金は出勤に間に合うかと心配して帰ってしまったので、副監督なのだが本人は正監督のつもりの綾べーが口火を切った。
「四番は、コバで決まりだ」
それには、誰も異論はなかったが、信介が、
「置物にはいいかもね」と、まぜっ返した。構えは一応どっしりとしていたから、打順のまん中に置物としておけば、相手チームが畏縮するかもしれない。フォームも固まらない面々にしてみれば、納まりがよいといった程の意味だ。
「じゃ、一番は誰さ」
一番を打ちたい駅前の老舗バーに勤めるバーテンの守田が聞いた。
「勘太かな」
「じゃ、二番は」と、二番を打ちたい信介が聞く。
「三輪田かな」と哲彌の高校の後輩の名前を挙げた。現役といっても野球部には所属せずフラフラしている現代っ子だ。
「確かに若くてフレッシュだけれど、その割に俺より足遅いけどな」と、伊勢のお父。
「三番は」と哲彌がせっつく。
「う~ん、そりゃ、監督だろう」
「じゃ、五番は」
「じゃ、六番は」
「じゃ、七番は」
「じゃ、八番は」
「じゃ、九番は」
名前を呼ばれない者たちは「誰か、お忘れじゃありませんか」と、全員が広沢虎造の浪曲『森の石松』になっていた。
「でも、今のは全部綾べーが考えた先発メンバーだろう」
「監督はなんて言ってるんだ」
「それがさ、地金も頑固でさ、俺に言わせるだけ言わせて、結局言わないんだ。試合開始のみんなの状態を見て決めるんだとさ。でも、地金のことだからもう決めてるかも知れないけどね」
試合に出たい者ばかりではなかった。能一は、できれば逃げたかった。2度目の東大受験に失敗し、いよいよ後がなくなってきたのだ。弟が追ってきている。弟が先に東大に受かってしまったら……。なんとしても来年こそは合格せよ、と厳父のきついお達しがあったのだ。
しかし、いまはそんなことを言い出せる雰囲気ではない。洋助のトスバッティングの相手からは解放されたものの、今度は伊勢のお父の深夜のランニングパートナーに強制連行されていた。近くの公園を一周するだけのことだし、お父の体重から見て楽なペースと思い、運動不足解消にと引き受けた。
それが大きな失敗だった。1周2、3キロだから軽く汗を流す程度だと考えていた。しかし、お父は真剣だった。一周回り終え帰ろうとするのかなと思っていると、お父は突然公園の中に入り込んだ。そして広場に来るとダッシュをしようと言い出した。
「30メートルダッシュ10本」と、勢いよく宣言した。
「え、10本も」
能一は、自分の体力も危なっかしいが、お父の心臓も心配になっていた。
「あまり飛ばさない方がいいんじゃないですか」
息を切らせながら言って見たが、
「最初からそんな気持でどうする」と、ハッパをかけられてしまう。
お父はその日が初めてではなかったのだ。聞いてみるともう2週間ほど続けているという。どおりで思ってたよりも軽快なランニングだったし、幾分顔も締まっているように見えた。
能一は息も絶え絶えになりながら10本のダッシュをこなしたが、それからが能一は未知の世界に入っていった。彼に下った命令は、腕立て伏せと腹筋だ。能一は運動らしきことは、いままでほとんどしたことがないため、自分がどのくらいできるかさえ知らなかったが、今宵、己の体力の基礎数値を思い知らされることとなった。
腕立て伏せ2回、腹筋4回でダウン。
なんと虚弱な奴だとお父は思った。こんな体力のない奴が、東大に入って官僚か何かになったら、日本の将来は真っ暗だ。よし、鍛えてやると自分をそっちのけで深夜特訓のスケジュールを考え始めていた。それから足元も覚束なくなった能一を、後ろから急き立てるように階段の昇り降りを駆け足で何回も繰り返すのだった。
そんなふたりのにわか仕立てのトレーニングは、一週間も続かなかった。能一が階段で足を滑らせ、両足首を捻挫してしまったのだ。捻挫はおろか擦り傷さえも負った経験がなかった能一は、足首が腫れ妙にユラユラとする足首の感触を知り、初めて肉体という存在を感じた。お父がバケツに氷水を入れきてくれた。
「そこに足を突っ込んでおけ」と言われた能一は、
「これで、体温計を口に入れていれば、昔映画で見たピーターパンに出ていた風邪をひいた海賊みたいだ」と、情けなく思った。〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
