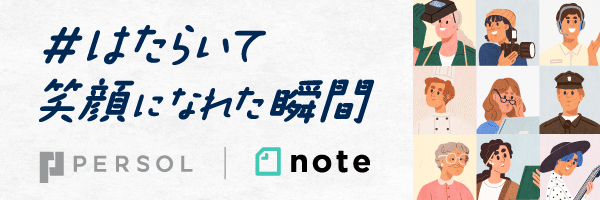アパレル店員の「アドレナ売リン」の正体
アパレル店員が苦手だ。
人と喋るのは得意な方なのに、場所がアパレルショップ、相手がアパレル店員になると、途端にうまく話せなくなる。飲み屋のカウンターで初対面の人と酒を酌み交わしながら無駄話に興じる私と同一人物だとは、自分でも信じ難い。
お店に行く際は、極力気配を消す。常に店員の位置を把握し、店員から死角になるよう陳列棚やマネキンで自分の存在を隠し、こそこそと商品を物色する。ただ、私がいくら必死に隠れようとも店員は目を光らせている、というか、そんな不審者はむしろ見張られて当然なわけであるが、よさそうな服を見つけて、ちょっと手に取ろうものなら最後。遠くで服を畳み直していたはずの店員が一瞬にして隣に現れ、「そちら色違いもございます」と黒いブラウスを探している私の目の前にアイボリーが差し出される。いや、わかっている。「黒を探してまして」と言えばいい、ただそれだけのことなのだが、アパレル店員のことを西遊記に出てくる返事をしたら吸い込まれるひょうたん持った妖怪みたいに思っている節があるので、まともに返事をするのが恐ろしく、ほとんど吐息みたいな声量で「はいぃ……」と発しながら不気味な笑みを浮かべて俯き加減でススーッと後退するのがやっとである。妖怪はどっちだ。
試着したあと買うかどうか迷っているときの、店員からの「押し」も苦手だ。やれ最後の一点だの、やれ私も着てますだのと、あの手この手のセールストークを張り手の如く繰り出し、迷っている私の背中をどすこいどすこい突っ張って、土俵際まで押しやる。あの果敢な精神はどこからくるのか。江戸から代々続く商人の家系なのかと疑う程、「売る」ことに気合が入っている。ああいうとき、アパレル店員の体内ではアドレナリンならぬアドレナ売リンが大量分泌されているに違いない。
さて、この流れでどうかしていると思われるかもしれないが、実は私、先月からアパレルショップで働いている。
どうしてアパレルショップで働くことにしたのかというと、立ち仕事、そして多少なりとも美意識が必要な仕事に就くことで、結婚式が終わって以降滑り台を下から駆け上がるが如く増加している体重に何とか歯止めをかけられるのではないかと考えた為である。賃金を得ながら痩せられるなら一石二鳥というわけだ。
それに、自分がやりそうもないことをあえてやってみるのも面白いのでは、という冒険心もあった。いつも無難な選択をしがちな私にしては珍しいチャレンジ精神である。しばらく無職だった反動かもしれない。indeedの応募ボタンを押したあと一瞬、「血迷ったな」とも思ったが、すぐに連絡が来て面接に行くと即採用。あとには引けぬこととなった。不安はもちろんあったが、前述のように人と話すこと自体は好きだし、コツを掴んで売って売って売りまくれば、アドレナ売リンがドバドバ分泌され、今まで知らなかった新たな快感の扉が開かれるかもしれない。そう思うとなかなか楽しみでもあった。
で、働き始めてまず衝撃を受けたのが、大抵のお客さんは優しくて感じがいいということである。私がたどたどしく「お探しのものあればお声がけください」なんて言うと、「はーい、ありがとうございまーす!」とか普通に答えてくれる。自分が長らく妖怪・座敷わらしならぬ阿派零流わらしだった故に感覚が狂っていただけで、世界は私が思うよりずっとずっと明るかったのだ。そして店員の立場になってみると、そういう優しいお客さんの反応はとにかく有難いものである。
まだスキルや知識が乏しいので、教わった接客の流れを必死でこなしている状況ではあるのだが、それでも季節柄もあってか思いのほか売れていく。次から次へと売れることもある。しかし、アドレナ売リンらしきものは感じられない。売れたら売れただけ高揚感を得られるはず、それがこの仕事への原動力になるはずと思っていたのだが、そこまでの気持ちには到達できていない自分がいる。
それに、もう一歩踏み込んでおすすめすれば買ってくれるかもしれない、というようなときも、余計なことを言って嫌がられたらどうしようという恐れが勝る。売るという目的のためにそんな危険は冒したくないと思ってしまう。
やはり私には向いていないのだろう、私はアドレナ売リンを分泌できない体質なのだろうと、やんわり思い始めていた。
そんなある日、一組のお客さんが来店した。制服を着た女の子と、そのお母さんだ。スニーカーを熱心に見ている。季節は春、新学期に向けて新しい靴を買いたいのだろうと想像した。
サイズを聞き取り、女の子が選んだ二種類のスニーカーを試着してもらった。明るい子で、私の拙い接客にも笑顔で「お願いします!」「ちょうどいいです!」などとハキハキと答えてくれた。若いのになんて感じのいい子なんだ、それに引き換えいい歳して妖怪・阿派零流わらしだった私……と忸怩たる思いでいっぱいになりながら接客する。
「うわあ、どっちも可愛い。どっちにしよう。悩む~!」
女の子は二種類を何度も履き比べて迷っている。どちらも白いスニーカーで、一方は側面の柄が鮮やかなピンク色、もう一方はは少しくすんだピンク色だった。
本当はそれぞれの特徴や履き心地の違いを詳しく説明できたらよかったのだが、まだそこまでの知識はない。とは言え、ただ突っ立っているだけでは能がない。買う前提でどちらにしようか迷っているわけだから押し売りにはならないだろうし、この状況なら私も何か言える気がする。そろそろ店員らしく、お客さんの役に立ってみたい。そんな思いが芽生えたとき、女の子が着ている制服のスカートが目に入った。えんじ色のチェック柄のスカート。
「こちらのくすんだピンクの方が、スカートの色には合っているような気がします。」
思い切ってそう伝えてみると、と女の子は、「あ、確かに!」と目を見開き、お母さんに「こっちの方がスカートに合うね!」と投げかけた。お母さんも「うんうん、そっちが合ってるわ!」と頷く。
「こっちにします!」
そう言って笑いかけてくれた女の子から、後光が射した。その光に照らされて、私の内側から熱を帯びた何かが溢れ出す。あ、これだ。アドレナ売リンだ。
お客さんに「いい買い物をした」と思ってもらえること。それこそが、アパレル店員のアドレナ売リンの正体に違いない。私の接客によって、「スニーカーを買った」が「制服にぴったりのスニーカーを買った」になった。買い物の価値が上がった。そう思えたことが嬉しかった。
ショップの紙袋を下げて去って行く女の子の後ろ姿を見送っていると、これからあの子が新しいスニーカーを履いて歩むであろう輝かしい青春の日々が浮かんできた。学校が始まったら、あの子の友達は新しい靴を褒めてくれるに違いないし、あの靴を履いてみんなでTikTokの曲とか踊ってみるに違いないし、「え、なんか音すると思ったら画びょう刺さってたんだけど!」と靴の裏を見せて笑い合うに違いないのである。おこがましいかもしれないが、私もその青春に、人生に、一枚噛ませてもらえた気がした。
もうしばらく、この仕事を続けてみようと思う。立ち仕事というのを免罪符にごはんをおかわりしまくっているので、体重は一向に減らないが。
いいなと思ったら応援しよう!