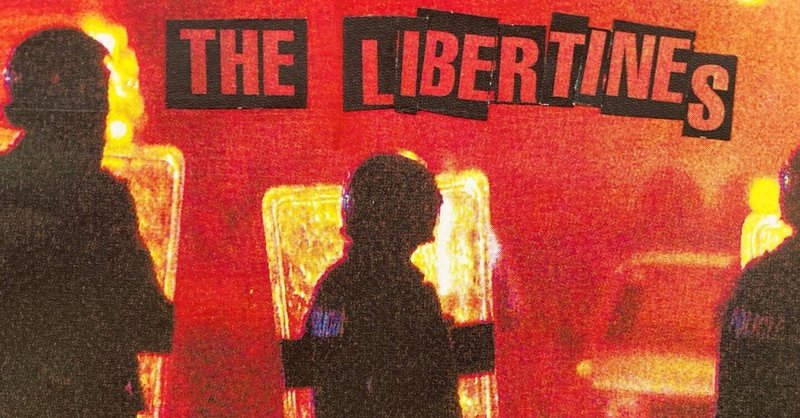
('02) The Libertines / Up the Bracket
2000年代の英国音楽シーンに、ギター・ロックと文学と衝動を復活させたザ・リバティーンズの鮮烈なデビュー・アルバム。
’00年代の吟遊詩人、ピーター・ドハーティがカール・バラーと出逢い、ロンドンのリアルな日常を、生活感や叙情やロマンティシズムとともに歌い、切羽詰まったように、激情的で不安定に演奏する。そんな彼らの楽曲からは、抗いがたいほどに美しい、感傷的で繊細なメロディが零れ落ちる。
ピストルズやクラッシュらに代表されるロンドン・パンクや、さらに前のパブ・ロック、さらにはスモール・フェイセズ、ザ・フー、ジャムらのモッズ、キンクス~スミス~ブラーといった”ブリティッシュ・ロック”からの影響はもちろん、ロックンロール以前のダンスホール・ミュージック風の曲調もあり、そのすべてにおいて彼らの”歌心”がストレートにダイレクトに心を掴む。
’00年代以降のUKにおけるインディ・ギター・ロックの原点であり、前年のUSのストロークスとUKのリバティーンズこそが、21世紀のロックンロールの旗手であった。本作のプロデューサーは元クラッシュのミック・ジョーンズ、デビュー・シングルでは元スウェードのバーナード・バトラーが務めるなど、まさにUKロックの申し子として彼らはスタートしている。
ストロークスがロックンロールを演奏することの楽しさとクール&スタイリッシュな佇まいを世に広めたのだとしたら、リバティーンズは音楽に乗せて自分を語る(叫ぶというべきか)ことの意義を鮮烈に伝えた、21世紀のUKロック・シーンにおける最重要な存在(の一つ)といえる。
迸るエモーションを、転びそうに疾走する演奏と吐き出すように捲し立てる歌に乗せて、発散させている。”アルビオン”という、あるかわからない理想郷を追い求めながら。
歴代屈指のろくでなし男、ピート・ドハーティが書く珠玉のメロディはたまらない。ズルい。カール・バラーとの”バディもの”映画的なコンビもドラマティックでロマンティックで、リバティーンズの歴史は本当に映画のようだ。どこで切るかにもよるけれど…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
