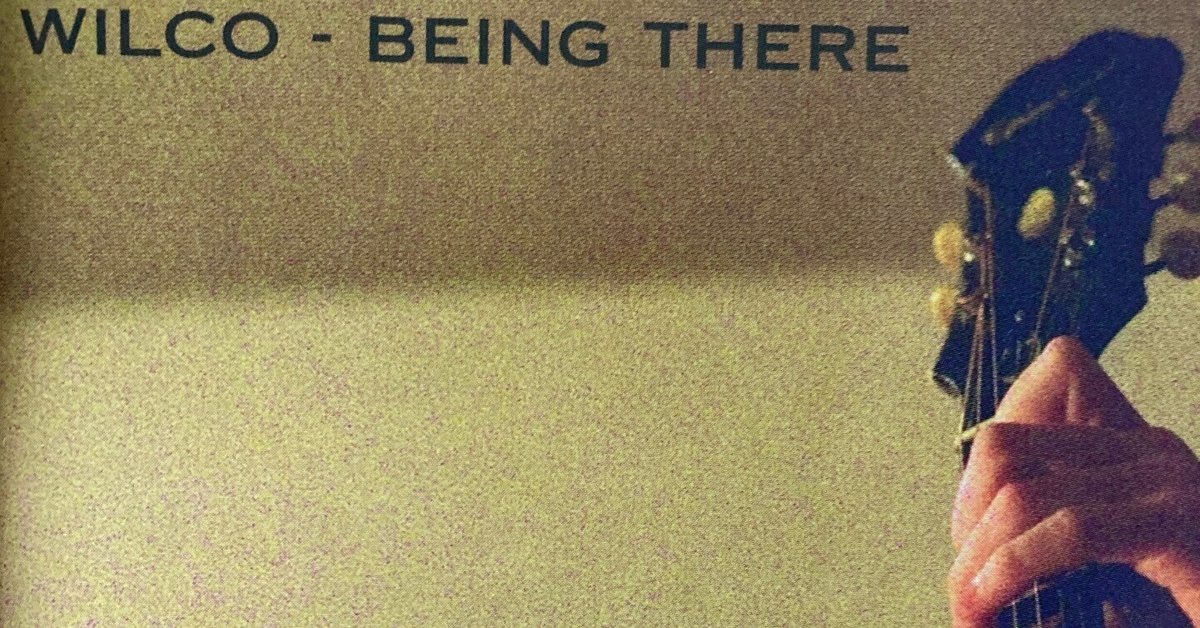
Wilco / Being There (1996)
ウィルコのセカンド・アルバムは、「オルタナ・カントリー」期の集大成と、その枠からの脱却を図った2枚組の力作となった。
前作のレイドバック感はやや薄まり、ポップ・ソングとしての輪郭がよりはっきりとしたシングル曲も収めている。
70年代のストーンズを彷彿させるタッチやビートルズ風の”黄金比”のメロディ、カントリーに根差したソングライティングに加え、歪むギター・サウンドなどの音響面には、のちのウィルコのアヴァンギャルドな側面も感じさせる。
ジェフ・トゥイーディは本作では全曲を書き上げ、ソングライターとして、そして滋味のあるシンガーとして、さらなる成長を見せている。
僕にとって、アメリカのバンドとしてはR.E.M.と並んで”心のバンド”になっているウィルコ。ジェフ・トゥイーディの書くメロディと声は、僕の心の真ん中を捉えて離さない。
「ヤンキー・ホテル・フォックストロット」は史上最高のロック・アルバムのひとつだし、「AM」は田舎道のドライヴにぴったりだし、「スカイ・ブルー・スカイ」は毎朝聴きたいぐらいだし、「Kicking Television」は歴代屈指のライヴ・アルバムだと思う。
それ以外にも素晴らしいアルバム揃いのウィルコの2作目がこれ。
ダブル・アルバムの両面どちらも内省的な空気すら感じさせるトラック(途中からウィルコらしい音響やノイズが入ってくると毎回期待感が高まる)から始まるけど、そこに重苦しさはなく、メロディの爽やかさと美しさ、音の厚みと深みがちょうどいい按排で響き、広がっていく。
前身のアンクル・テュペロ時代からの”オルタナ・カントリー期”の締め括りといえる作品。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
