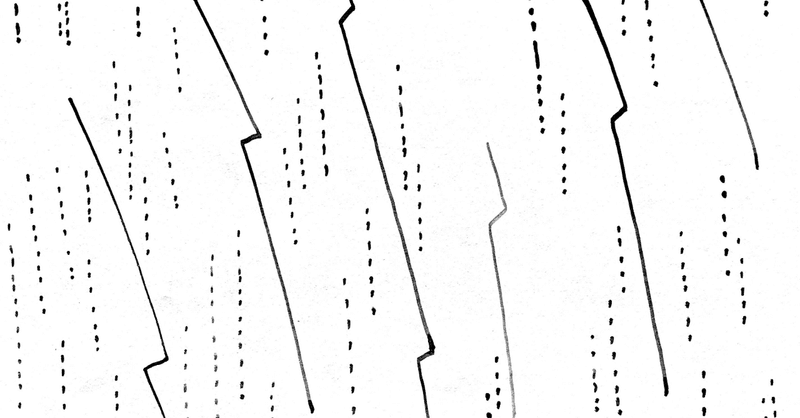
杉本真維子詩集『袖口の動物』について
この詩集を初めて読んだのがいつのことだったのか、手に取ったきっかけが何だったのか、そういったことをまったく思い出せません。気づいたらそばにあって、何度も何度もくりかえし開いてきました。いちばん好きな詩集は何かと問われれば迷わずに『袖口の動物』と答えてきました、その答えは今後もおそらく変わらないでしょう。人に贈ったことも、貸したまま返ってこなかったこともあります。苦しい職場にいた頃におまもりとしてかばんの中に入れて出勤していたことや、かなしすぎる夜に抱きしめてねむったこともあります。明日のこともよく分からないような日々をずっと過ごしていますが、この詩集についてだけは、いつまでもそばにいたいと願っています。
このような一冊に出会えたから私はずっと詩を書いているのだと思います。私にとっての『袖口の動物』のような存在になってみたい、誰かの中で。そういう憧れがずっとずっとあります。
*
発行日を確かめると「二〇〇七年十月二十五日第一刷、二〇〇八年四月二十五日第二刷」と記されていました。つまり『袖口の動物』はおよそ十年前に刊行された詩集で、第58回H氏賞を受賞しています。収録されている詩の数は全部で二十一篇です。
表題作であり、私が本当に好きな詩のひとつでもある「袖口の動物」について書きます。まず、第一連と第二連を引用します。
手暗がりの
よわよわしい視野の中にしか棲まない
動物を、連れてかえり
水をのませる
食事を与え
数日後とうとう、名前をつけた
母になるのに覚悟などいらぬと
耳打ちする
きもちのわるい愛情だけで育ったが
動物を手放すと家が消えた
(泣いてもおそいと耳が割れる
ここには「動物」と、動物を連れてかえった「母」が現れているように読めます。しかし何度読んでも私には、ここにいるのが「動物」だけであるようにしか感じられないのです。なぜなら〈母になるのに覚悟などいらぬと/耳打ちする/きもちのわるい愛情だけで育ったが/動物を手放すと家が消えた〉この四行の向こうからどうしても声が聞こえてくるからです。それはこんな声です。
(母になるのに覚悟などいらぬと思っていたのでしょう/あなたが愛情だと思っていたものは、私にとっての愛情ではなかった)
つまり「母」に「手放」された「動物」はみずからの「母」を疑っていて、「母」はきっとこんなふうに私を捨てたのだ、という「動物」の想像として第一連と第二連は書かれている。そのようにしか私には読めないのです。そして、最終連である第三連を読むことでこの声はさらに大きく、確かなものとして私に響いてくるのです。
春になれば
瓦礫の土をわける
ほつれた袖口に運ばれて
「勝手に、
勝手に、あいされたから
もう土しか舐めるものがないんだ。」
ときに文字を真似
あなたが誤読するように
それだけのために生きている
動物になる
〈「勝手に、/勝手に、あいされたから/もう土しか舐めるものがないんだ。」〉これはまちがいなく「手放」された、つまり捨てられた「動物」の声です。この声は〈きもちのわるい愛情〉を指して、責めている。
さらにこの声が言っていることは、この詩を初めて読んだ当時の私自身が強くつよく叫んでいたことそのものでもありました。直接的に描かれてはいないけれど、この詩を読むと私は家族というものと、それが内包する暴力について考えずにはいられません。世の中には、家族の内側にある暴力を知らない人や、その存在自体を信じない人もたくさんいるのでしょう。私だってそういう人だったらよかったけれど、そうではない。だからこそ暴力(=「動物」を「手放」すという行為)の存在を直視して「母」をちゃんと疑っているこの詩を読めたことが私は嬉しくてしかたありませんでした。
こんなふうにひとのこころを刺してくる詩が存在することにおどろき、深く刺されて、私は今でもこの詩に打ちのめされたままでいます。
他にも「ある冬」「あかるいうなじ」「いのち」などの詩を読むと、爪を切られる・洗濯物を干す・飴を舐めるといった日常行為の底から不穏さをひきずり出して詩として成立させているその観察力と手腕に見惚れます。それから、たとえば「笑う」という詩の〈白蛇のように流れた/くらやみの包帯について/かち鳴らす銀色の箆(へら)のような/うすく、清潔な悪いこころ〉このような、美しくて巧みな比喩表現に詩集の中で何度も出会うことができます。そして「やさしいか」のいちばん最後の二行、さらにその直後に置かれた「世界」が残していく余韻。
本当に大好きで、大切な詩集です。
(初出:『詩の練習』vol.1(発行所:詩の練習 発行日:2018年6月1日))
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
