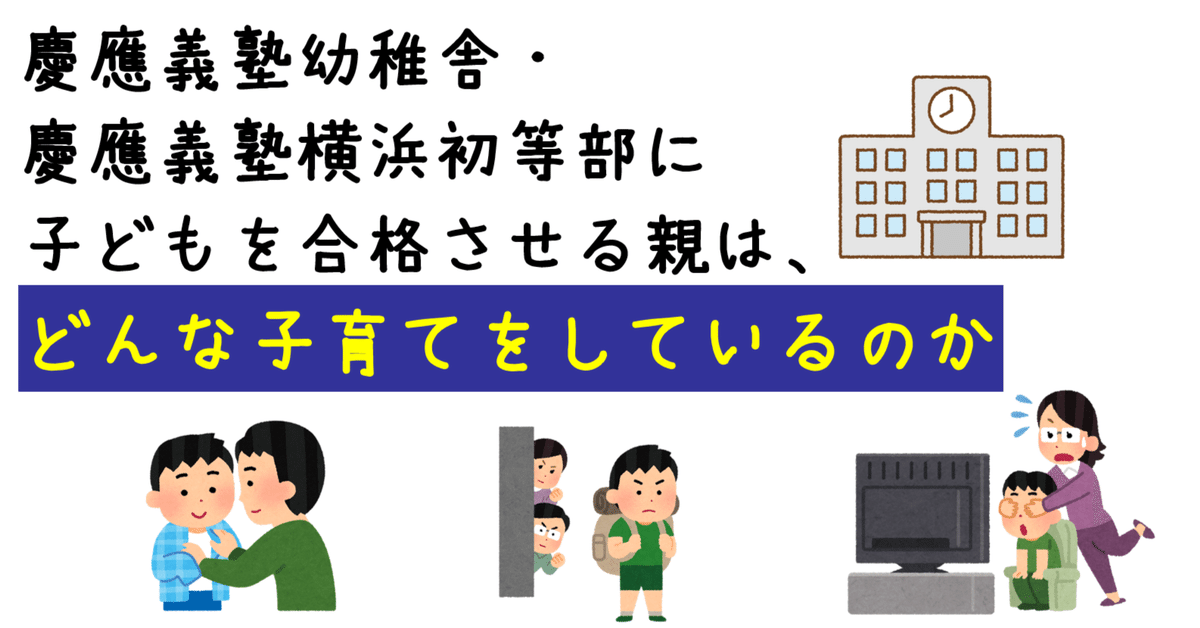
慶應義塾幼稚舎・慶應義塾横浜初等部に子どもを合格させる親は、どんな子育てをしているのか
どんなタイプの子が慶應義塾幼稚舎や慶應義塾横浜初等部に合格するのかの記事で、子どもには、「自立している」「言葉が達者」「運動神経がいい」「活発で負けん気が強い」「細身で見た目がいい」の5つの特徴をあげました。
一方で、親はどのような特徴があるでしょうか。
慶應義塾幼稚舎・慶應義塾横浜初等部に子どもを合格させた親の家庭での子育ての特徴をあげていきます。
人との関りをつくる
慶應義塾幼稚舎、慶應義塾横浜初等部に通われるご家庭は裕福な方が多いです。
他の私立小学校に比べて、慶應系列2校は、授業料、寄付金が高く、更に大学までの一貫校ですので、小学校から大学まで高額の学費を払い続けられる金銭面での体力が必要です。
そのため、通われている方の中には、バイオリンやピアノ、バレエ、プログラミングなど、多様な習い事に通われている方も多いのは事実です。
それを参考に、願書に「映える」習い事を安易に選択するのでしたら、「人との関りを増やすお出かけや習い事」を選択した方が良いと考えます。
慶應系列2校で出題される「行動観察」は「人との関り合い」を見る試験です。
複数人のグループに課される取り組みのルールを理解しているか、取り組みの全体像を正確に把握し、チームが勝つためにはどうしたらよいかを即座に考える必要があります。
自分勝手に行動したり、周りの気持ちを考えずに、一方的に話を進めることはNGです。
お友だちの表情や行動から、優しくお願いしたり、困っている人にアドバイスしたり、更には周りを引っ張る力も必要となります。
ご兄弟がいらっしゃるご家庭は、日常の中で、兄弟同士の関わり方を学べますが、そうでない方は、通われている幼稚園・保育園・塾などのお友だちと遊ぶ機会を頻度高く設けることがよいでしょう。
沢山の体験をさせる
小学校お受験全般に言えることですが、「体験の多さ」は「受験の強さ」に関わります。
季節に合わせた行事をご家庭で行った、夏には潮干狩りや花火をして、秋には紅葉を見に行き、タケノコ狩りやキノコ狩りに行ったなど。
多くの刺激を与え、視点を沢山増やしていると、言葉や表現が豊かになります。
慶應系列2校で出題される「絵画」では、その体験の多さ、感受性の豊かさがものをいいます。
これまで感じたことを目いっぱい絵画として表現し、更にそれを、お声がけで伝えることが求められます。
誰にでも明るく優しく接する
親がいつも明るくニコニコしていると、子どもも同じように明るくニコニコします。
子どもは、親の鏡のような存在です。
そして、子どもは親をよく見ています。
お友だち家族との接し方など、親のふるまいを本当によく見ており、言葉のかけ方、表情などから、子ども自身が他人との振る舞い方を学びます。
お母さん同士が仲良く会話しているか、お父さん同士が楽しそうに遊んでいるかなどが大切です。
皆に優しい親の子は、同じように人と争ったりせず、他の人の気持ちを理解して行動できます。
先ほどの、行動観察にも関わることですし、数時間かけて行う試験時間の中で、そのお子さんの性格は試験官に伝わるものです。
リーダシップを発揮する
親の行動を子どもは見ているとお伝えしましたが、親のリーダシップも実は大事だったりします。
慶應系列2校に通われるお母様・お父様と会話すると、親がリーダシップがあるご家庭が多いことに気づきます。
親が何人か集まったときに、ここに行こうとか、これを選ぼうなど、小さなことでも結構です。
色々な価値観を持つ人の意見をまとめて、その場を楽しませたり、解決策を率先して見つける力を持っている親が多いと思います。
行動観察の中で、子どものリーダーシップ力は、採点項目に入っています。
初めて会った子ども同士で解決策を見つけ、お互い声をかけながらチームを勝利に導く際に、「〇〇をやろうよ!」「△△に気を付けてね!」など、率先して周りを引っ張るリーダーシップ力が見られています。
親が受け身の場合、子どもも受け身になります。
自ら考えて行動できる子どもを、慶應義塾幼稚舎、慶應義塾横浜初等部は好むため、親のリーダーシップの能力も実は子育てに大事なんです。
慶應義塾幼稚舎、慶應義塾横浜初等部を目指すにあたって
慶應義塾幼稚舎、慶應義塾横浜初等部に合格するためのテクニックを学ぶことも大事ですが、そればかりが先行するのは危険です。
何故なら、慶應義塾幼稚舎、慶應義塾横浜初等部は、倍率10倍を超えるモンスター小学校ですので、合格すること自体が、ある意味「奇跡」なのです。
とっても優秀で、絶対に合格できると期待された子が、慶應系列2校に落ちることはよくあります。
この2校に特化した教育も大事ではありますが、まずは、それらを支える「人間としての土台づくり」が大事でしょう。
子どもは親をよく見ています。
こんな子に育って欲しいと思える人物像を、親が体現し、子どもが真似をする形で、素敵な人格形成を進めてほしいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
