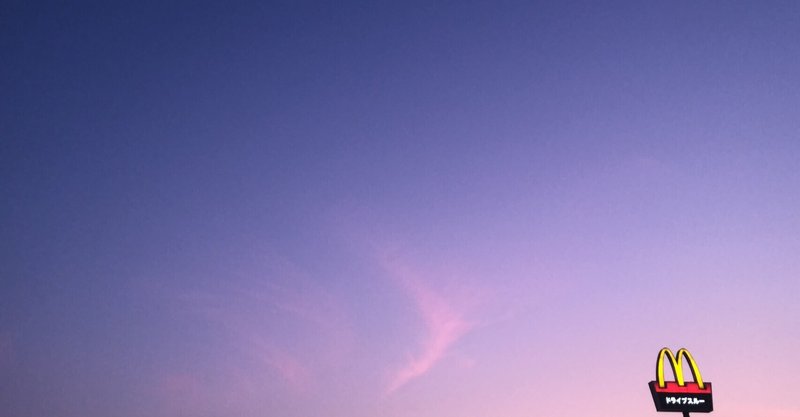
『千歳くんはラムネ瓶のなか』6を読んだ話
ご無沙汰しております。矢五八寝倉(やごはち ねくら)と申します。
平たく自己紹介をさせて頂くと、小説家を志している者です。
最近ようやく予測変換が私のペンネームの名字を一発で変換してくれるようになりました。大分時間が掛かったな。
今回もおおよそタイトルの通りです。
『千歳くんはラムネ瓶のなか』という、ガガガ文庫から刊行されているライトノベルシリーズの最新刊、第6巻が発売されました。
買いました。
読みました。
読んだら書かずにはいられなかった。そういう話です。
もしお暇があれば、お付き合いいただけると幸いです。
因みに、千歳くんはラムネ瓶のなか、通称「チラムネ」と呼称される本シリーズそのものについては、前巻の際に書かせていただいたNoteで紹介しています。
もしも「読んだことないんだけどそのシリーズ」って人がいらっしゃいましたら、下の記事の前半部分を読んでいただければと思います。
あわよくば買ってください、読んでください。
絶対に後悔はしないはずです。
さて、と言うわけで早速本題に入っていきましょう。
例によってネタバレ全開です。
まだ読んでいないと言う人はここでブラウザバック推奨です。
そして、正直今回は自分でもまだ物語を咀嚼しきれていません。
ある程度はまとめているつもりですが、全体的にとっちらかった文章になってしまっていると思うのでその辺はご了承ください。
去る8月19日、数日に渡って空を覆い続けた雨雲が通り過ぎ、ようやく夏の雲が顔を見せ始めた日。
チラムネの6巻が発売され、勿論その日のうちに本屋へと走りました。

前巻よりは早めに行ったつもりでしたが、やはり本棚に並んでいたのは最後の一冊。やはり争奪戦は今後続いていくらしいことがはっきりしました。相変わらず危なかった。
今回の第6巻は発売前からその「厚さ」が話題になっていましたが、実際に手に取ってみるとその存在感と重さたるや。
試しに並べてみましたが、第5巻の特装版と比べるとこうです。

……いやもう差がほぼ無ぇな。
5巻の本編+SS冊子に堂々と立ち並ぶ6巻本編の厚さ。
それほど、今巻の存在と内容には〝重み〟があるということ。
その期待に胸を膨らませながら、「あの第5巻」から続く物語の展開に胃を痛めながら。
意を決して、私は表紙をめくりました。
まず目に入るのが口絵と目次。
中でも今巻の目次は何やらヤバいらしい、というのは前情報で触れていたので、どれどれとページに指を掛けました。
最早おなじみとなったプロローグの先にあったのは、「五章」の二文字。
そうきたか、と。
この一冊が間違いなく5巻に対する回答であることを指し示すのに、あまりにも確実すぎる二文字。
……ならば。
Ⅵ:宵闇に消える吐息
普通とは、何なのでしょう。
人の人生、人の生き方の数だけ、それぞれの人間にそれぞれの理想があり、それぞれの事情があり、そしてそれぞれの普通がある。
だからこそ、その定義はきっとこの世で最も難しい。
それは多分、「特別」以上に。
人生には多くの始まりがあり、そして多くの終わりがあります。
それは例えば、学校だったり、習い事だったり、趣味、仕事、勉強、生活――あとはそう、恋とか、友情とか。
築き上げてきた友情がガラスのようなものだったなら、まだその破片をかき集めることは容易です。
しかし生憎、人間関係というのはそこまで汚れなく透き通ったものじゃない。
千歳朔が教室を去り、それを内田優空が追いかけていった後。
柊夕湖が教室を飛び出し、浅野海人が駆けだしていった後。
各々がバラバラについた帰路は、そんな彼らの、綺麗で、青くて、けれど歪に濁った関係を象徴していたように感じました。
流れる涙も、滴る汗も、弧を描いて宙を舞うバスケットボールも、ふつふつとコーラに浮かぶ炭酸も。
その全てが、場所を違えど等しく宵闇に吸い込まれていく。
浅野海人は、決して間違っていない。
第5巻にて、夕湖に対する想いを明らかにし――そして何より、彼女を振った朔を殴った、決定的な行動を取ってしまった、男。
けれど、彼を責めることは出来ない。
なぜなら、そうしなければならなかったから。
勉強合宿、二日目の夜。彼は千歳朔と「男の約束」を交わしました。
誓約書も血判も存在しない、ただの口約束。
しかし、それは他の何よりも堅く、そして大切な約束だったのだと思います。
それを千歳朔が破ってしまったのは、それに浅野海人が激昂してしまったのは――やはり、遠いいつの日にか来るものだと思っていたその時が、想像の何十倍も早く、呆気なく訪れてしまったからに他ならない。
……それでも。
夕湖の後をただ一人追いかけていった彼が放った、ある一言。
「それに、いまの夕湖をひとりにしたら、今度は俺が朔にぶん殴られちまうよ」
その言葉は、決して浅野海人と千歳朔の関係が切れたわけではないことを証明していました。
誰か夕湖の隣にいてくれ。そう願った朔。
そして誰よりも愚直に夕湖を追いかけ、寄り添っていた海人。
離れていても。仮に手を上げ、罵ってしまったとしても。
そんなものでやすやすと壊れてしまえるほど、彼らの友情は薄くは無いのです。
……やがて、彼は彼自身の心にも踏ん切りを付けようと決意します。
それはケジメだったのか、贖罪だったのか、それともその両方だったのか。
いずれにせよ、全てを精算した彼の表情に曇りはありませんでした。
だからきっと、浅野海人は間違っていない。
……正しくもなかったかも知れないけど。
七瀬悠月は、決して間違っていない。
堅実に、丁寧に、されど情熱的に、誰よりも重く。
千歳朔という存在に向かって、積み木を組み上げていた少女。
組み上げられた積み木にはほんの少しの欠けもなく、確かに彼へと近づいていたことでしょう。
だからこそ、恐れていた。
誰かがそれにぶつかって、崩れて、全てが水の泡になってしまうことを。
だからこそ、許せなかった。
崩した先に他の誰かがいるかも知れないことを忘れていた、自分が。
チーム千歳(或いは「それは悠なる月のように」)の女性陣の中で、おそらく最も頭が切れると言っていいであろう悠月。
そんな彼女でさえ、いくつもの後追いの後悔をしてしまうのだから、恋は盲目とはよく言ったものです。
たとえ、彼女の組み立てていたものが感情論に過ぎなくとも、そこには明確な目標があり、標的があり、そして未来があった。
誰が彼女の感情を、激情を、愛情を、否定することができるでしょうか。
彼女がはりぼての美しさの裏に隠した恋心に、綻びは無いというのに。
だからきっと、七瀬悠月は間違っていない。
そしてそれは、隣にいる彼女も。
Ⅶ:底抜けた洞
内田優空は、かつて間違っていたかも知れない。
今巻の大部分を占めていたのは、千歳朔と内田優空の関係。
その始まり、過程、そして、今でした。
「普通」というものに縛られるように固執し、その道に無いもの全てを排して生きてきた少女。それが、高校に入ってすぐの内田優空という人間でした。
これまでの巻でも細々と、少しずつ少しずつ小出しに語られていた彼女の過去ですが、表紙を飾った今巻にてようやくその全貌が明らかとなりました。
普通を愛していた母。
両親の離婚。
そして自己犠牲とも呪いとも言うべき、彼女自身の昏い決意。
彼女が作っていた壁は、きっと向こう側も見通せなくなるほどに厚い壁だったに違いありません。
しかし、そんな彼女を救ったのも、やはり千歳朔という男でした。
彼の操る言葉、態度、表情、果てには自身の境遇、信念に至るまで。
飄々と、風に吹かれるカーテンのように薄い外面の内側には、どこまでもまっすぐで力強い、出来過ぎた正しさがありました。
誰も彼もみんな、千歳朔という生き方に救われている。
その事実が当たり前のようであり、けれどどこかに違和感があるような。
人間とは、ここまで完璧でいられるものだろうか?
そんな疑問がふと、私の頭によぎってしまうような。
でもやっぱり、千歳朔という生き方はどこまでも眩しく、尊いものであることに変わりは無くて。
そんな彼に当てられ、自分の殻を破った優空は、決して間違ってなどいないのだと思います。
きっと、今の内田優空に間違いなど無い。
だからこそ誰よりも、その心の中には炎を燻らせていたのでしょう。
こんなのはきっと、間違っている、と。
青海陽は、間違いを知らなかった。
彼女が恋に落ちるまでの過程を描いた、第4巻。
上村亜十夢の株が爆上がりした巻でもあります(二度目)。
彼女はそれまで、おおよそ恋というものを知らなかった。
だから、恋というものが何を生み、何を失うことになるのか。
恋において何が正解で、何が間違いなのか。
何をすると満足できて、何をすると後悔するのか。
何も、知らなかった。
けれど、そんな彼女は少なくとも、夕湖の告白を切っ掛けに後悔と恨みと、そして痛みを知りました。
どこまでも突き抜けていく性分だった彼女は、きっと初めて選択という壁にぶち当たったのでしょう。
彼女が朔を元気付ける為に選んだのは、やはり「彼女らしい」選択でした。
そんな「らしさ」に縛られるのが、果たして彼女にとっての「正解」なのかは、言うまでもなく――
ほら、やっぱりだ。
こんなやり方でしか、あんたの隣にいられない。
きっと、青海陽は間違いを知らなかった。
だから、正解も知らなかった。
上村亜十夢。
お前はマジで何も間違ってない。
そのままのお前でいてくれ。
Ⅷ:その糸を手に取って
縁。
この世のありとあらゆる関係を表す言葉、そのもの。
「――どっちか片っぽだけでも、結ばれたご縁の端っこを握りしめていたらいい。それだけで繋がりは途切れんもんやよ」
人と人、男と女、親友とライバル。
ありとあらゆる関わり合いの形を描いてきたこのシリーズですが、今巻は特にそのつながりが大きな意味を持つ話でした。
それ故に、このエピソードは今巻の物語の中核を担っていたのだと思います。
西野明日風は、正しく「先輩」だった。
お盆のある日。
8月の中心を永遠に分かつその日に、朔と明日風は朔の祖母へと会いに行きました。
蚊取り線香の匂い、畳の香り、蝉の鳴く声、風鈴の音。
それらを経験したことが無い人も、きっと不思議と懐かしさを覚えてしまうであろう、日本の夏の原風景。
ノスタルジックな雰囲気が、めくるページから蜃気楼のようにゆらゆらと立ちこめてくるような、そんな感覚。
それは「不思議な先輩」でありながら「幼馴染」でもあった彼女にしか醸し出せない、独特の世界観。
そんな世界に酔いしれている暇も無く、一日はあっと言う間に過ぎていき、やがて彼女は千歳朔に言葉を説きます。
「君は、愛されることに慣れすぎて愛し方を知らないんじゃないかな?」
おそらくは、かつての関係としてではなく先輩として。
確かな的を射た助言を、千歳朔に投げかけました。
彼が夕湖の告白を断った日、掛ける言葉を見つけられなかった明日風は、どうしてこの時、彼の心を刺すことが出来たのでしょう。
それもやっぱり、かつて彼のまっすぐさに救われたからだったのではないでしょうか。
誰よりも千歳朔という人間を追い続けたからこそ、弱さを分かち合ったからこそ、彼の違和感に気付くことが出来たのではないでしょうか。
物語の序盤、朔は、明日風との通話の後ろで、ある曲を流していました。
BUMP OF CHICKENの「Embrace」です。
その歌詞、始めの方には、こんな言葉があります。
震えているのはきっと 寒さのせいじゃないな
どんな台詞もきっと 役にも立たないな
通話の中で、明日風はこう呟きました。
『いまの君に届けられる言葉があればいいんだけど』
『駄目だね、なにを口にしても薄っぺらく上滑りしちゃいそうだ』
Embraceの歌詞、終盤にはこんな言葉があります。
腕の中へおいで 隠した痛みのその傷口に触れてみるよ
時間の無い部屋で理由も忘れて 確かなものを探しただけ
見つけただけ
彼女が朔の傷口に触れて見つけた、彼の完璧な生き方にあった綻び。
君は、と明日姉が言った。
『――ラムネの瓶に沈んだビー玉の月だったから』
完璧だったからこそ、まっすぐでいたかったから、誠実でありたかったからこそ、遠ざけて、見て見ぬ振りをしていた綻び。
それを貫いて、砕いて、揺らがせた。
西野明日風だったから、「明日姉」だったからこそ、その言葉は朔の胸に強く響いたのでしょう。
「先輩」、だったからこそ。
水篠和希、そして山崎健太。
彼らはずっと、信じていた。
誰も悪くないのだと、誰も間違っていないのだと、誰もが正しいのだと。
そう信じて、海人の元を訪れ、朔の元にも訪れた。
水篠和希。彼もまた、朔を想う少女を好きになった少年でした。
そして、誰よりも早く諦めた男でした。
彼には彼なりに思うところがたくさんあったでしょう。
でも、少なくとも「あのとき」、彼は部外者であり、傍観者にすぎなかった。
「その資格も、ないよ」
「寂しげな笑み」を浮かべた彼もまた、後悔していたのでしょう。
自分自身で決着を付けてしまったことを。
そうでもしなければ負けてしまう戦場に墜ちてしまったことを。
彼が動いたのは、その後悔を無駄にしないためだったのか、それとも……。
山崎健太。彼もまた、千歳朔という生き方に救われた少年でした。
そして、誰よりも憧れた男でした。
今巻において彼は、1巻から続いていたその大きな成長の成果を見事に証明して見せたと言っても良いでしょう。
「間違っている」憧れの存在に対して、その間違いを突きつけられるほどに、彼は成長を果たしました。
千歳朔が復活を果たしたのは、誰かのおかげではありません。
彼と繋がっていた皆が、少しずつ少しずつ、勇気とか、元気とか希望とか情熱とか、そんなものを分け与えていったからこそ、今巻の最終章へと千歳朔が進んで行けたのだと、そう思います。
そう、それはまさしく。
「それぞれのひとに、かけがえのないものをたくさんもらっていて」
Ⅸ:一欠片の想いを
千歳朔は、いつだって正しかった。
彼の生き方にはいつだって真っ当な信念があって、
彼の言葉にはいつだって確かな暖かさがあって、
だから、彼の周りには人が集まっていた。
けれどそれが、ただこなしているだけ、躱しているだけだったとしたら。
彼自身も無自覚だったのであろうその行為は、これまで長くに渡ってこのシリーズの中心となってきた「完璧な男」「身近なヒーロー」というイメージの崩壊とも言えるでしょう。
慣れすぎたから、
ずっとそうだったから、
それが普通だったから。
だから、千歳朔はいつだって間違っていた。
柊夕湖は、いつだって正しかった。
彼女の胸の内にはいつだって確かな恋心があって、
彼女の笑顔にはいつだって嘘偽りが無くて、
だからこそ、彼女は心を痛めてしまった。
心に刻んでいった傷からじわじわとあふれ出した膿が、だんだんと焦りに変わっていって。
焦りを生んだのは自分で、
傷を付けたのも自分で、
恋に落ちてしまったのも自分で。
だから、彼女はいつだって正しくない。
――そう、彼女は思っていた。
チラムネの前半、そのクライマックスを彩る最後の章となった、第八章。
それは、これまですれ違いを続けてきた二人と、誰よりも奮闘した一人の少女が想いをぶつけ合う、まさにクライマックスと表現するにふさわしいものでした。
以前の記事で私が「蛮勇」と表現した、最後の告白。
柊夕湖が抱え続けていた、その真意。
明日風に射止められた、千歳朔の抱えていた心の内。
そこにいた、少女達のこと。
そして――大切な二人の間で想いを隠し続けていた、内田優空の恋心。
我慢し続けていた、涙。
言い合って、叫び合って、泣き合って。
チラムネのお家芸でもあった地の文すらほとんど鳴りを潜めた夕湖と優空の感情的なシーンは、煌びやかな祭りのお囃子を遙か遠くに押し込んでしまうほどの迫力があって、臨場感があって。
何より、確かな感情が、或いは魂が、一文字一文字に重くのし掛かっているような、そんな感覚を覚えました。
いったい、この一冊でどれだけの涙を見たでしょう。
そのうちのどこにも、無駄な涙は一粒たりとしてありませんでした。
全てを吐き出し合って、また祭りへと戻っていった千歳達。
そこで合流した、いつもの仲間達。
わだかまりも後腐れも無く、また不可逆な日常の新しい1ページが始まって。
最後に落ちた線香花火の種に至るまで、たったの一粒も。
無駄な雫は、ありませんでした。
Ⅹ:備忘録としての回顧録
……また要約みたいになってしまった。
今巻は、地の文の語り口がめまぐるしく変化する構成が大きな特徴であったと思います。
青春ラブコメという分野はなんとなく、主人公の一人称に徹しているからこそ生まれる違和感やすれ違いを描く作品が多かったように思います。
だから、こうして登場人物ほぼ全員に役割を当て、全員の思いを描きつつ、しっかりとまとめ上げていく展開は本当に度肝を抜かれました。
そんな特徴にあやかって、今回の感想は時系列よりも人物にフォーカスを当てて書いてみました。読みづらかったら申し訳ない。というか読みづらいと思うので先にメチャクチャ謝っておきます。ごめんな。
帯にも書かれていた、「私を見つけてくれて、ありがとう」という言葉。
よもや意味が二つあるとは思いませんでした。
相変わらず、このシリーズは何処までも王道に私たちを楽しませてくれるな、と。
改めてそう実感した巻でした。
……一方で、読んでいて何度吐きそうになったか分かりません。
勿論良い意味で、なのですが。
登場人物全員の思いが、感情が、どれもあまりにも青くて、眩しくて。
読み終わった後、ふと自分自身に立ち返ってみたとき。
こんなにも、「何かを成さなければならない」と思わされたのは久しぶりでした。
……あ、ここから先は私という一個人、単なる男子大学生の独り言です。
興味ねぇ!って人は全然読み飛ばして頂いてかまわないんですけれども。
最初にもちらっと申し上げたとおり、私は細々と小説家を目指しています。
作品を作ろうと思い始めたのは小学校高学年の時に読んだ「カゲロウデイズ」が切っ掛けで、本格的に小説家を志したくなったのは中学生になってから読んだ「俺ガイル」とか、その辺だったでしょうか。
それ以来長らく、小説家という夢は、ぼんやりと「こんな物語が書いてみたい」なんていう程度のものでしかなかったのですが。
最近になって、色んな作品を読むにつれて、思い至ったことがあります。
自分はきっと、今の自分ではない何者かになりたいのだと。
例えば、この本を読み終わって、本を閉じて、ふと目の前のデスクに目を向けたとき。
バイト帰りに夜食として買ってきた、スープまで飲み干したカップ麺の食べ殻が横倒しになっていたり。
どっちが美味いのかなんてことが気になってまとめて買ってきた抹茶ラテの空のペットボトルがならんでいたり。
洗い損ねたマグカップがほったらかしになっていたり。
――付けっぱなしにしていたパソコンの画面に、書きかけの小説があったり。
そういったものを目にしたときに、強く感じることが増えました。
今の自分じゃ、きっと何者にもなれない、と。
この作品の中には、こんなにも自分を向き合って、自分を変えようと頑張って、ぶつかり合って、認め合って――そんな人生が詰まっているのに。
この606ページにすら詰まっているのに。
自分の18年間には、一体何が詰まっているのだろう。
そう思うと、何かを生み出して、残さなければならないような。
自分が生きた証を、形として残したくなってしまうような。
そんな気分になってしまって。
その瞬間、小説を書きたいと、強く思いました。
なので、私は裕夢先生に一方的に感謝の言葉を贈りたいと思います。
この『物語』を世に出してくださって、本当にありがとうございます、と。
きっと、私以外にも、この物語に触れて同じようなことを感じている人は少なくないと思います。
それほどの力が、人生観が変わってしまうような力が、この作品にはあると思っています。
私たちが結末を見届けたとき、一体どれほどの人の心にこの作品が残ることになるのか。
そう思うと、今後の展開に期待が止まりません。
改めまして、裕夢先生。
ありがとうございました。
そしてこれからも、宜しくお願いします。
まずは短編集、6,5巻。楽しみにしています。
……さて、まずはキネティックノベル大賞に応募する用の作品を書き上げよう。
それが書き終わったら……
今度は、ガガガ文庫の公募に挑戦してみようかな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
