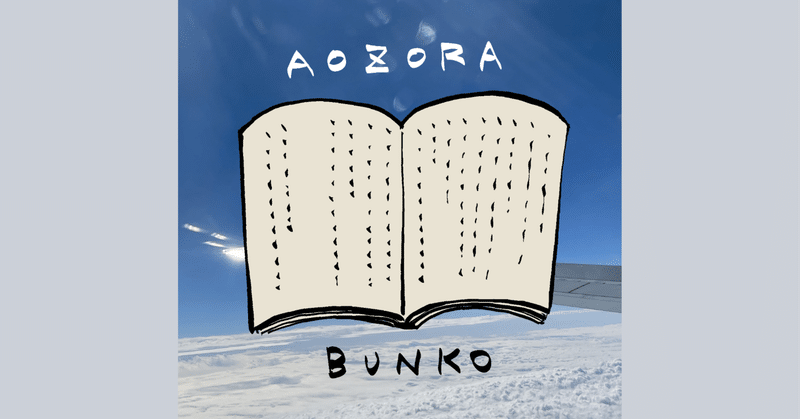
朗読を始めた理由
趣味で朗読を始めたが、人前で話すのは気後れするたちである。頭の中にあることを自由に話してみなさいと言われると、大変まごつく。思い浮かぶあれこれをこうして文章に綴ることはできる。それを口に出せとなると、途端に尻込みしてしまう。
だから朗読はやっても、フリートークはやらない。たいして面白くもない話をごにょごにょ喋るだけになるのは目に見えている。面白くない上に、話があちこち飛び火し、結局何を言いたいのだか、わからないまま終わるのだ。それでは聞いてくれる人に申し訳ない。
朗読も本当は、ただやりさえすれば満足だ。下手な朗読をわざわざ録音し、インターネットに公開する必要などまったくない。たくさんの人に聞いてほしいとは露ほども思わない。しかし自分の満足のためだけに文章を読む行為は何だか虚しく、張り合いがない。自分の朗読がただいま録音されており、このあと公開されるのだと思うと気持ちが引き締まり、普段よりはよい声が出そうに思われるのだ。
私は自分の声をこどもの頃から好きではなかった。もっと低く、できればハスキーな声がよかった。まさにその理想の声を持った人が高校の同級生にいた。国語の授業で彼女に朗読の順がまわってくる瞬間を、どれほど待ち望んだことか。先生に指名され、すっと起立した彼女が、手に持った教科書をやや遠くに構えて、丸い唇から第一声を放つ。静かな教室の床の上を這うような、低く甘く掠れた声。私は必ず目を閉じて、彼女の声に聞き入った。数十年が経ったいまでも、あの声を忘れずにいる。
私が朗読を好むのはなぜか。理由を考えてみて、ふと思いついたことがある。作中の登場人物になりきる行為が好きなのではないか。「私」、「僕」、「おっ母」、「小次郎」。さまざまな人物が発する言葉を、あたかもその人のごとく読む。その人のごとく驚き、あるいは悲しむ。
私は自分でもよく、架空の物語をこしらえる。それを漫画や小説で表現するのが、ことのほか好きなのだ。朗読もその延長線上にあるのかもしれない。漱石や太宰になりきって、世を憂いたり酒を飲んだりする。私にとって、なかなか愉快な遊びであることは間違いない。
最後まで読んでくださってありがとうございます。あなたにいいことありますように。
