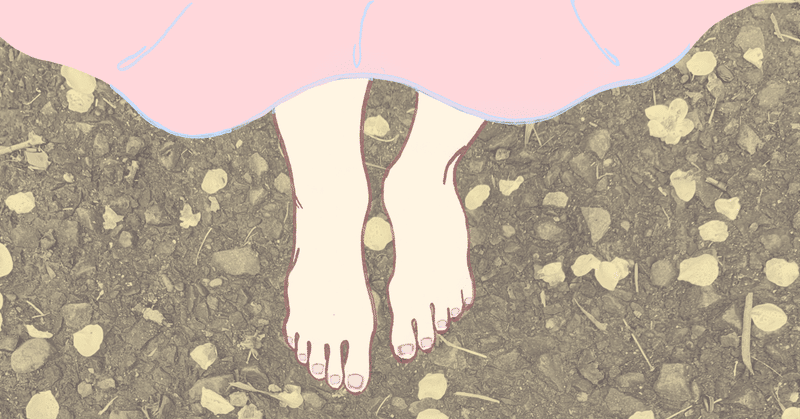
『彼女が欲しいもの』
01-小さな本屋
本が欲しいと彼女は言った。
「どんな本?」と尋ねてみても、ふふと笑うばかりだ。
日曜日の昼下がり、彼女は僕を本屋へ誘った。古くからやっていそうな、ごく小さな本屋さん。
「わたしの欲しい本はここにあるの」
店の前でそう言うと、彼女は僕に手を振って、風のように去っていった。
僕は店の中へ入った。いらっしゃい、とエプロンをつけたおじさんが、僕に気のいい笑顔を向けた。僕は軽く会釈して、さてどうしようかと思案した。
雑誌コーナーを覗いてみる。ファッション誌がたくさん並んでいる。手を伸ばしかけて、ふと思った。そんなもの、彼女は読まないかもしれない。なぜなら彼女は何というか、いつも個性的な格好をしているから。こないだ会ったときは、つばの広い真っ赤な帽子をかぶっていた。今日は襟元に大きな黄色いリボン。彼女には彼女の確たる美学がありそうだ。
そういえば猫が好きだと言っていなかったか。いつか一緒に暮らしてみたいと。いくつかあるペット雑誌を、僕はぱらぱらめくってみた。あまりピンと来なかった。"鳴き声でわかる猫の気持ち"なんて、彼女が知りたがるだろうか。猫以上に気ままな彼女が、猫の気持ちに頓着するとは思えない。
隣の棚へ移動した。恋愛小説。時代小説。サイエンスフィクションと続き、ミステリーコーナーの前で、僕はふと足を止めた。謎解きなんていかにも彼女が好みそうではないか。現に彼女は、僕にただ本が欲しいとだけ言って、自分はどこかへ消えたのだ。
なんとなく、あまり聞き馴染みのない作家のほうが喜ばれるような気がして、全然知らないロシアの作家の推理小説を一冊抜き取り、手に持った。
もうほとんどその本に決めかけていたのだが、不意にある詩集が僕の目にとまった。夜空のように深い青の分厚いカバーの背に、タイトルが金文字で埋め込まれてある。La Nuit.フランス語で、夜。僕は戸棚からそっとその詩集を引き抜いた。革のような手触りといい、両手に収まるサイズといい、中に綴られた詩のリズムといい、何もかもがしっくりくる。
二冊買うにはお金が足りなかった。僕は悩みに悩んだ末、推理小説を元の棚へ戻した。
店を出ると、意外にも彼女が僕を待っていた。僕は彼女に詩集の入った袋を渡した。
表紙を見るなり彼女が言った。
「欲しかった本よ」
ページを繰ると中の詩を一編、くちに出して読み上げた。甘い声音に僕はうっとり目を閉じた。
パタンと本の閉じる音がした。目を開けた僕に、彼女は詩集を差し出した。
「いまの詩が欲しかったの。この本はあなたが持っていて」
紺色の小さな詩集は、僕の部屋に迎えられた。鍵のついた引き出しの中で、いまもひっそりと眠っている。
02-くまとおもちゃの万年筆
通りを並んで歩いていると、彼女が突然足を止めた。百貨店の大きなショーウィンドウに飾られた、マネキンの女の子をじっと見ている。女の子は大きなくまのぬいぐるみを両腕に抱えて笑っていた。
「欲しいの?」と僕は彼女に尋ねた。尋ねたからと言って、買ってあげられるかどうかはわからない。百貨店のおもちゃ売り場に売られているぬいぐるみなんて、きっと何万円もするはずだ。
「欲しいわ」と彼女は言った。「でもこれじゃない」
僕は内心ほっとして、「でもくまのぬいぐるみは欲しいんだね?」と彼女に訊いた。彼女はそれには答えずに、ウィンドウからすっと離れた。首に巻いた桃色の長いスカーフが、風になびいて僕の頬を撫でた。
次に彼女に会ったとき、彼女は隣町に用があると言った。電車を二本乗り継いで、降りた駅から十五分ほど南へ歩く。右手に小さな雑貨屋の丸い看板が見えてきた。
「あの店よ」
指を差してそれだけ言うと、彼女は路地を左へ曲がってどこかへ行ってしまった。
僕は仕方なく雑貨屋に入った。どうやらアンティークショップらしい。キーの丸い旧式のタイプライターや、くすんだ緑色のグラス、バレリーナの踊るオルゴールなどが、テーブルの上へ雑多に置いてある。
小さなくまのぬいぐるみを僕は見つけた。正確には、くまが両手に持っている濃紺の万年筆。取り上げるとくまも一緒についてきた。万年筆はおもちゃのようだが、精巧に作られている。僕は値札を見た。ぎりぎり払える額だった。
「お買い上げですか」
後ろから突然声をかけられ、驚いた僕は慌てて振り向いた。まるで昔の洋館に住んでいそうな、古めかしいメイド服を着た小柄なおばあさんが、僕の顔をじっと見上げていた。僕は商品をおばあさんに見せて、代金を支払った。おばあさんはにこりともしなかった。
店を出ると彼女がいた。買ったものを手渡すと、彼女は小さなくまの手から、おもちゃの万年筆を離そうとした。「それは外れないんだよ」と僕が言う前に、彼女は右の指でつまんだ万年筆を僕の目の前へ差し出した。
「あげるわ」
僕は不思議な気持ちで万年筆を受け取ると、部屋に帰って鍵つきの引き出しの中へ、そっとそれをしまった。
03-揺れるイヤリング
僕は机の前で悪戦苦闘していた。
「詩を書いて。私のために」と彼女が僕に言ったからだ。いつまでに、と期限を決められたわけではない。とはいえ明日会う約束をしているのだから、明日渡すべきだろう。
時計は夜の二時をまわっている。彼女に捧げたい言葉は山ほどあった。それがいざ紙の上へ書こうとすると、文章がまるで浮かばない。そもそも僕は詩の書き方すら知らないのだ。
机の引き出しの中に、一冊の詩集が入っている。いつか彼女にプレゼントしようとして、受け取られなかった詩集。あの深い夜色のカバーを、ひとたび開けたなら。小さな宝石のような言葉が、無限にあふれ出すだろう。引き出しにかかった鍵を開け、彼女が喜びそうなとびきりのフレーズを盗み出す誘惑と、僕は何度も闘った。闘いは明け方まで続いた。
午後三時きっかりに、喫茶ロンドで彼女と会った。菫色の丸い大きなイヤリングが、彼女の耳の下で揺れていた。コーヒーを待つ間、彼女は濡れた目で僕を見つめた。僕はジャケットの内ポケットから、おずおずと白い封筒を差し出した。
二枚重なった四つ折りの紙を彼女は開き、中の詩を読み始めた。コーヒーが運ばれてきても、まだ熱心に読んでいた。僕はコーヒーを一気に飲んだが、喉の渇きは少しも癒えなかった。
やがて彼女は紙を畳み、元の通り封筒の中へしまった。それから少し首を傾けて、イヤリングに手をやった。
「なんだか混沌としてるわね」と彼女は言った。僕には言葉の意味がすぐに理解できなかった。
「コントン?」
「混沌。カオス。狼狽。無秩序」
「それはつまり——ぐちゃぐちゃってこと?」
ふふ、と彼女は笑った。
「ぐちゃぐちゃ。そうね、つまり——あなたは私を愛していながら、同時に憎んでもいるし、離したくないと思いながらも、一緒にいるのが怖いんだわ」
「そんなこと」
「ないと言い切れる?」
僕は開きかけたくちを閉じ、また開いた。
「でも好きなんだよ」
「そうね。いいのよ。私はただあなたの正直な気持ちが知りたかったの。おしえてくれてありがとう」
彼女は封筒を小さなハンドバッグの中にしまうと、最近見た映画の話をし始めた。彼女の耳の下で菫色の大きな丸いイヤリングが揺れるのを、ぼんやりと僕は眺めていた。
04-白いスニーカー
喫茶ロンドで彼女と別れ、僕はすっかり途方に暮れた。
日は傾きかけている。彼女はどこかへ出かけてしまい、街へ放り出された僕はやることが何も思い浮かばなかった。
映画を観る気にもなれず、読みたい本を探す気にもなれない。夕飯のための買い物をするか、どこかで一人前の食事をとるか。
彼女にあの詩を渡したことを、僕はひどく後悔していた。彼女が『混沌としている』と言った詩——。
『あなたは私を愛していながら、同時に憎んでもいるし、離したくないと思いながらも、一緒にいるのが怖いんだわ』
『でも好きなんだよ』と慌てて言うのが精一杯だった。僕が彼女を憎んだり怖がったりしているはずがない。それなのにはっきり否定することができなかった。なぜ。
どこへともなく僕は歩いた。雨が少し降ってやんだ。街を外れ、河川敷にたどり着いた。おろしたての白いスニーカーが泥を跳ねるのも構わず、僕は黙ってただ歩いた。
空は群青色に染まり、小さな星が瞬いた。自転車のライトが正面から近づいてきて、すれ違いざま僕の耳に軽快なハミングを聞かせた。夜の河川敷には、思いのほか多くの人が行き交っていた。犬を連れた人、手を繋いでいるカップル、勤め帰りの人。僕の隣に彼女はいない。
どん、と僕の背中に何かがぶつかった。それほどの衝撃ではなかったが、不意だったので僕はよろけた。
「すみません!」とすぐに声がして、僕の右腕が後ろからつかまれた。倒れ込むと思われたらしい。僕は体勢を立て直すと、振り向いて声の主を振り返った。
「ごめんなさい。ふざけていて」
学生みたいな男性が、背負っていた大きなデイバッグを僕に示した。
「後ろ向きに歩いていたんです。そしたらあなたにぶつかってしまって」
「後ろ向きに?」
僕は彼に連れがいることを確かめようとしたが、彼はどうやらひとりで歩いていたらしかった。
「時々やりたくなるんです。ごめんなさい」
「大丈夫」と僕が言うと、彼は軽く頭を下げて、小走りに去っていった。
ふっと小さな笑いが僕のくちから漏れた。途端に空腹を感じた。ある店のボンゴレが、潮の香りを伴って僕の頭に浮かんだ。身がたっぷり詰まったあさり。いつか彼女に教わった味。僕は地面を蹴り出すと、足早にその店を目指した。
05-青いガーベラ
僕は花屋に向かっていた。彼女に花を贈るために。
彼女が何かを欲しがるとき、それを正しく用意するのに僕は大抵苦労する。たとえばただ本が欲しいと言われる。あるいは詩を書いてくれとせがまれる。どちらも答えは無数にある。それで僕は、本屋の中をあてもなくウロウロしたり、徹夜で詩を書いたりするはめになる。
けれども今回のリクエストは、いつになく明快だった。
「ガーベラが欲しいの。一輪でいいわ」
それなら造作もないことだ。
僕は一時間ほど早く家を出て、ある小さな花屋に立ち寄ることにした。何度か利用したことのあるその店には、花屋にあまり似つかわしくない、筋肉質な店主がいる。彼はとても親切なのだ。
店の入り口へ足を踏み入れるなり、店主は「いらっしゃいませ」と僕に笑いかけた。僕も彼に微笑み返し、まっすぐガーベラのある場所へ向かった。赤、黄、ピンク、オレンジ、同じピンクでも薄いのや濃いの、たくさんの色で咲き誇っている。
近づいてきた店主に向かって、僕はにこやかに言った。
「青いガーベラをください」
店主の笑顔が戸惑いに変わった。
「青はちょっと……」
「品切れですか?」
「いえ、その……青いガーベラそのものがこの世に存在しないんです」
彼の言葉に僕は唖然とした。青いガーベラが欲しいと、彼女が僕に言ったのだ。
「この世にない?」
「すみません。造花ならありますけど」
彼は僕を店の隅に案内し、一本の造花を抜き取った。
「これです」
確かに青いガーベラだった。いかにも作りものといった感じの。仕方がないのでそれを買い、花屋を出た僕は考えた。彼女は本当にこんなものを欲しがっているのだろうか。プラスチックでできた花など、彼女が喜ぶだろうか。
しばらく思案したあと、僕は画材店に入った。画用紙を一枚と、青と黄緑のクレヨン二本。喫茶ロンドのテーブルの上で、造花を見ながら一生懸命青いガーベラを僕は描いた。
ちょうど描き終わった頃、彼女が僕の前に現れた。目の覚めるような緑色のワンピースに身を包んだ彼女は、真っ白な帽子をかぶっており、まるで開いたばかりのチューリップのように瑞々しかった。
僕は造花のガーベラと、へたくそな絵を彼女に示した。
「貰ってくれる?」
彼女は絵を覗き込むと、ガーベラの花びらを一枚一枚指でなぞった。
「真っ青で綺麗」
青く色移りした指を、ふふっと笑って僕に見せた。それを見て僕も笑った。
春の日差しが暖かい、土曜の昼下がりだった。
06-半月
ふと思い立って髪を切りに行った。さっぱりして帰ってきたら、玄関でスニーカーを脱いだ途端に具合が悪くなった。
胸がむかつく。冷や汗が出る。頭が痛む。
立っていられないほどの疲労感に襲われ、僕は這うように部屋へ入った。すぐベッドに倒れ込み、布団を鼻まで引き上げた。寒気に震える体を縮め、この不具合の正体を探ろうと今日これまでを振り返る。
朝、牛乳を床へこぼした。
お気に入りの靴下が片方見つからなかった。
落ちていた細い紐を掃除機で吸い込んでしまい、ローラーから取り除くのに三十分かかった。
観るつもりだった映画の公開が、終わっていることに気がついた。
出かけようとしてスマホを見たら、バッテリーが残り五パーセントだった。
こうして振り返ってみると、ろくなことのない一日だ。実を言うと、髪も希望より短く切られた。もうあの美容師は指名しない。
体が温まってくると、途端に僕は眠気に襲われた。何か大事な用があったような気がするが、瞼が重くて頭が働かない。
目が覚めると真っ暗だった。布団の中から手を伸ばし、枕元にあるライトスタンドのスイッチを探った。
頭の中はクリアになっていた。それに空腹だった。僕は起き上がって部屋の電気をつけた。
キッチンでベーコンを刻みながら僕は再び思い返した。
牛乳、靴下、掃除機、映画、スマホ、髪型、それに原因不明の体の不調。
数えてみたら七つもある。ラッキーセブンならぬ、アンラッキーセブン。
手早く作ったパスタと缶ビールをテーブルへ運んだ。ビールをひとくち飲んで、スマホを見る。カレンダーのポップアップが表示されていた。
〈19:30 ボンゴレ〉
僕の全身から血の気が引いた。すぐに時刻を確認する。19時38分。僕は上着とバッグをつかみ取ると、部屋を飛び出した。なんという一日だ。
引いた血液が一気に顔へ戻ってきて、僕は額に汗が滲むのを感じながら、店の番号を探した。彼女が待っているに違いない。彼女の連絡先を僕は知らないのだ。
大通りまでの細い坂を急ぎ足で下りながら、僕がやっと店の番号を見つけたと同時にスマホが鳴った。驚いた僕は反射的に緑のボタンに触れた。耳に聞こえたのは彼女の声だった。
「ごめんなさい」と彼女は言った。
「なんだか風邪を引いたみたい。お店には行けないわ」
僕は足を止めた。「それは……」と言ったあと、言葉が続かない。「お大事に」となんとか言って、電話を切った。
これはラッキーと呼ぶのか、それとも。
空を見上げると、大きな半月が僕を無言で照らしていた。
07-僕が欲しいもの
彼女から連絡が来ない。
最後の約束は、ボンゴレの美味しいレストランでの夕食だった。僕のスマホに、風邪を引いたから店には行けないと電話があって、それからふっつり音信が途絶えたのだ。
着信履歴にあるのは、「非通知番号」の五文字だけ。彼女は僕に連絡先を教えてはくれなかった。いつも次に会う約束をして別れていたから、それで何の問題もなかった。
彼女のバラのような笑顔を、僕は何度も思い出した。つばの広い赤い帽子も、菫色の丸いイヤリングも、鮮やかなグリーンのワンピースも、本当によく似合っていた。もう一度彼女に会いたい。せめて元気でいるのか知りたい。
よく待ち合わせた喫茶ロンドへ、毎日のように僕は通った。出勤前、仕事帰り、週末は何時間も本を読んで過ごした。彼女は現れなかった。似た人すら来なかった。
ある日僕は思い切って、マスターに尋ねてみた。僕の連れ合いだった女性を、最近見ませんでしたかと。そんなことを訊くのは妙だし、変に思われるのもわかっていたが、それでも僕は勇気を出した。ほかに手がかりが見当たらないのだ。
マスターはコーヒーカップを磨く手を止め、僕を見て少し眉を上げた。
「女性ですか」
「はい。僕の向かいに座っていた」
マスターは首をひねり、戸惑いながらこう言った。
「あなたの姿はよく見ましたが、いつもおひとりでしたよ」
どう帰ったのか覚えていない。気がつくと僕は部屋にいた。カーテンを開け放した窓の外は群青色に染まり、ぽつぽつとオレンジの明かりが揺れている。
詩集のことが頭に浮かんだ。夜色の革表紙。預かっておいて、と彼女に言われたもの。
僕は机の引き出しの鍵を開けた。中を見て息を呑んだ。
詩集。おもちゃの万年筆と、小さなくまのぬいぐるみ。僕が彼女に書いた詩。青いガーベラの造花と、それを描いたクレヨン画。彼女にあげたはずのものまで、ごちゃごちゃに詰め込んである。
黄色いリボンの端が見えた。引っ張り出して、それを眺めた。彼女がいつか襟元に結んでいたもの。
そんな。
まさか。
何かの間違いだといういいわけが頭の中に渦巻く一方で、僕の心ははっきりと思い出していた。
こどもの頃になりたかった、もうひとりの僕。
もうひとりの、わたし。
僕はリボンを首に結び、鏡の前に立ってみた。
不安げな目をした彼女が、僕をじっと見返していた。
「カクヨム」のある企画に参加するために書いたものです。3日置きに1つのお題が出て、それが7回続く。お題はこれでした。
01-本屋 02-ぬいぐるみ 03-ぐちゃぐちゃ 04-深夜の散歩で起きた出来事 05-筋肉 06-アンラッキー7 07-いいわけ
それぞれのお題ごとにまったく別の話で参加してもよかったんだけど、うっかり連作で書き始めてしまい、「ぐちゃぐちゃ」でくじけそうになり、「筋肉」でもうやめようかと思いました。とりあえずゴールできてよかったです。楽しかった。
最後まで読んでくださってありがとうございます。あなたにいいことありますように。
