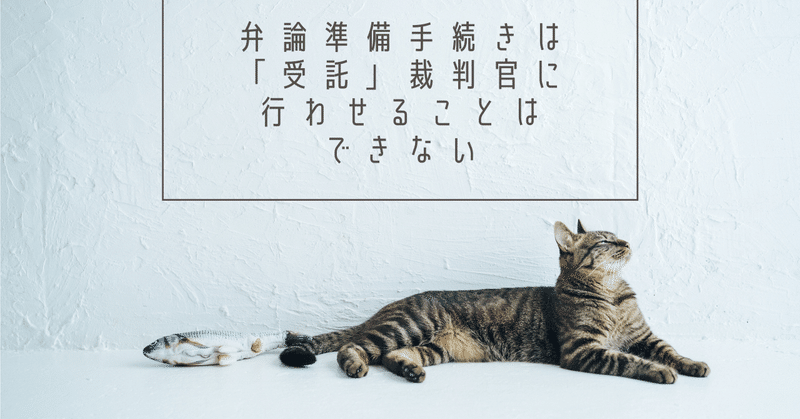
今日の民事訴訟法8
○弁論準備手続き当事者の意見を聞いてする
・期日前に弁論準備手続きをするには当事者の意義がない必要がある
弁論準備手続きは「受託」裁判官に行わせることはできない
弁論準備手続、当事者双方から申し立てがあれば取り消さなければならない、
一方の申し立てもしくは職権で取り消しできる
(弁論準備手続きは制限のある手続きだから)
弁論準備手続きにおいて、証拠の申し出に対する裁判、訴訟引受、訴訟救済、補助参加、訴えの変更、審理計画が定められた場合の主張証拠の申し出の却下は受命裁判官に主宰させることはできない
受訴裁判所が行う
○文書送付嘱託は受命裁判官が主宰できる
文書提出命令はできない
例外として外国の法律や地方の慣習は当事者が取り寄せる
先行自白は相手の援用があるまでは撤回できる
証拠調べ却下の裁判に抗告できない
調査嘱託は職権でおこなう、申し立て権はない
未成年者を承認とする場合に法定代理人の同意不要
16歳未満のもの、宣誓の趣旨が理解できないものには宣誓させることはできない
公務員または公務員であったものに職務上の秘密を尋問する場合は監督官庁の承認が必要であり、公益を害し若しくは公務の遂行を著しい支障が生ずる場合には承認を拒絶できる
証言拒絶の裁判には即時抗告できる
共同訴訟のうち1人が判決確定した場合他方の控訴審でのはその1人は証人尋問
鑑定人質問は原則裁判長から質問する
当事者引用文書、引渡閲覧請求可能文書、挙証者の利益のために作成している文書に当たるかどうかのインカメラ手続きはできない
当事者が文書を提出しない場合に
文書内容を具体的に主張し かつ
文書の他の証拠での証明が著しく困難な場合には、主要事実まで認めることが「できる」
証拠保全で証人審問した場合には、口頭弁論で当事者が審問の申し出をした場合は再度審問をしなければならない(証拠保全を行った裁判所と受訴裁判所は異なることがあるから、証人尋問は直接主義の要請が強いから)
訴え提起前の証拠保全の管轄は
証拠方法所在地の地裁or簡裁(申立人が選択できる)
訴え提起後の証拠保全の管轄は口頭弁論開始までは証拠を使用すべき審級の裁判所
(名古屋地裁など広義)
口頭弁論開始後は受訴裁判所
(実際の審理をする裁判体 狭義の裁判所)
○訴え提起前の証拠保全
予告通知不要
(証拠保全の必要性の疎明必要)
申し立て却下には抗告できる
罰則付きで証拠調べできる
費用は訴訟費用になる(敗訴者負担)
訴え提起前の証拠収集処分
予告通知必要
相手方の意見を聞く必要あり
文書提出命令はできない
地裁へ必ず申し立て
相手方の普通裁判籍もしくは文書や調査物等の所在する地裁
費用申立人
罰則付き証拠調べなし
不服申し立てできない
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
