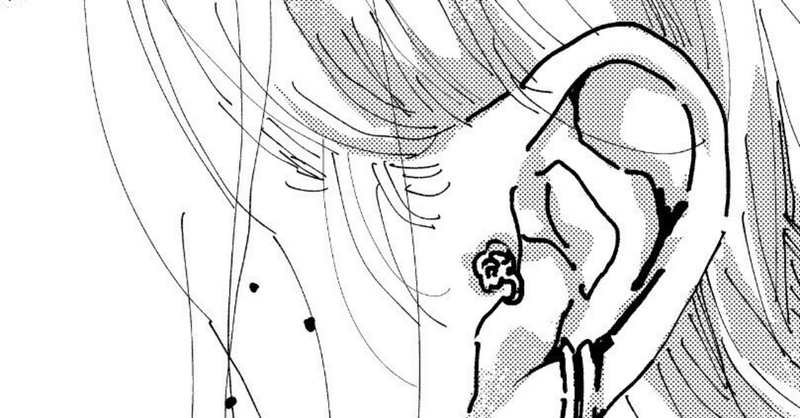
姉妹の設定で
19歳のころ、専門学生をしていた。
クラスでのグループづくりにあぶれ、授業で
「二人組つくってー」
「適当に班つくれー」
のときは、わたしと同じように浮いていたMちゃんとあぶれもの同士組んでいた。
わたしたちは特に仲が良いわけではなかった。
わたしは彼女に興味がなかったし、彼女ももちろんわたしに興味がなかった。ちがう点、というとMちゃんは一人でも平氣そうだったし、授業で積極的に挙手して発言する子だったけれど、わたしはただの陰キャだったことだ。
学校はデザイン系ではないものの映画監督をはじめとするクリエイターを輩出しており、「ご近所物語かよ」的な個性的なファッションの生徒で溢れていた。
毎日がさながらファッションショーのようで、
地味すぎるわたしは若干、浮いていた。
クラスでも近寄りがたい存在とされていたわたしは、学校全体で見てもやはり異質だった。
「孤高」「クールな一匹狼」「話しかけんなオーラえぐい」と囁く者もいた。
Mちゃんが「不思議ちゃん」と陰で揶揄われているのを聞いていたので、ただの人見知りで卑屈なあぶれ者が「孤高」ととってもらえるのは、それでもいくらかマシに思えた。
「人見知りで…」とかわいく言えるようなタイプでもないわたしは、ただただ、強がっていた。
そんな陰キャなわたしにもなんとなく話しかけてくれる子はいた。わたしを入れると奇数になるからだろう、グループには招かれないものの、相手がひとりのとき、話しかけられることはあった。
ギャルのアラキ(仮名)もその一人だ。
ある日、同じクラスのアラキとランチして梅田の街をぶらぶらしているとき
ギャル男っぽい、チャラい男に囲まれた。
アラキは声を掛けられることに慣れているのか
適当にあしらいながらも会話に応じていて、満更でもなさそうだった。
わたしはというと街で知らない人と話すことも、同世代の明るいウェーイなノリもどうも苦手だった。どちらかというと親世代、もっというとお年寄りと話すほうが安心できた。
どうしてギャルのアラキと遊ぶことになったのかその経緯は覚えていない。
別のグループで楽しくやっていたはずのアラキはわたしと歩きながら「学校クソづまんねー」というようなことを言っていて、その頃は学校で姿を見かけることもほとんどなかった。
「ギャルも色々あるんやな」とわたしも深く追及しなかった。
「学校クソつまんねー」
本当のところわたしもそう思っていたが、口にはしなかった。30人ほどのクラスだったけれど、
5月を過ぎると朝の授業にはじめから来る人は
4〜5人という出席率だった。何かのせいにするわけではないけれど学科選びしくじったな、と思っていた。
何しろ、退屈だったのだ。
それを同じ学科のアラキに言ってもただの愚痴になるし、「『クソ』なんて言葉は品がないから口にすべきではない」と、かたい頭でいたく真面目にそう思っていた。他人が言う分にはいいけれど、自分が言ってはならない、と。
本当に、「クソつまんねーヤツ」だったと思う。
アラキは低身長で胸が大きかった。
ただのTシャツを着ていてもエロく見える。
が、人の体型をいじるスキルもノリも自虐ネタも持ち合わせていなかったわたしは、ただただ目のやり場に困っていた。
自分に「無い」ものだからか、アラキと話すときはどうしたって胸に目がいった。
同性には興味のないわたしですらそうなのだから、ぎらぎらした裏若き男どもが、アラキを放っておくはずがなかった。
アラキ狙いのギャル男は、わたしとアラキのあいだに入り壁をつくるようにこちらに背を向けアラキと話している。ワックスで固めたツンツンの髪、整髪剤と安い香水の匂いが鼻をついた。
妙なバックプリント入りのだぼだぼのジーンズは腰パンのしすぎでパンツがしっかり見えており、こちらはこちらで、目のやり場に困った。
わたしにさして興味もないであろうもう一人の男は、わたしが「彼ら」の邪魔をしないようしきりに「お姉ちゃん美人やな〜」と同じセリフを繰り返していて、もうちょっとボキャブラリーないんか、と自分のことは棚にあげ、ため息をつきそうになるのをぐっと堪えた。
とりあえずはアラキと離れないようにしながら、アラキがナンパについていくなら、わたしは頃合いを見計らって帰ろうと思った。
「妹ちゃんは高校生?お姉ちゃん彼氏いんの?」
わたしに張りついた男はでれでれとアラキのほうを見やる。「お姉ちゃん」は「わたし」のことではなく、アラキのことを指していた。
どうやらわたしは「妹」らしい。
アラキは金髪巻き髪、バリバリのギャル。
対してわたしは少年のようなスタイル、ひょろひょろした体型を隠すような古着を纏っていた。
「しっかりものの姉」を生きてきた第一子長女としては、同い年の子と並んで歩いているのに「姉」ではなく「妹」と思われたこと、高校生と思われたことに若干氣分を害したけれど、もう二度と会うこともないであろう相手に正確な情報を説明するのもためらわれ、わたしはギャル男たちのその設定にのることにした。
アラキのことを初めて「おねーちゃん」と呼ぶ。
「おねーちゃん、彼氏いますよー」
「マジかーそうやんなー」
違和感は拭えないが、一度そう呼んでみると、
おもしろさが勝った。
アラキに彼氏がいるかいないかは知らなかった。
何しろわたしたちは、お互いそんなに興味がなかったのだ。興味がないからこそ、一緒にいられたのかもしれない。
Mちゃんにしろ、アラキにしろ、
その時間をただ一緒に過ごす、という関係に過ぎなかった。それはお互いに干渉しないということでもあった。アラキがギャルでも、ヲタクでも、ロリータでも、要するになんでもよかったのだ。
姉と妹、の設定にのってみたものの
そもそもアラキは青森の出身で言葉が訛っているし、わたしは関西弁に近い言葉を話す。
「姉妹」の設定には少々無理があったが、
ギャル男たちはそのことには氣づいていないようだった。というか、そんなことはどうでもよかったのだろうけど。
わたしは「おねーちゃん」と離されないよう、アラキとの距離を詰めた。
「てか二人、姉妹のわりには全然似てへんな」
そら他人やからな、とつっこみが出そうになるのを堪え、失礼なことを平然と言う男にわたしは伏し目がちに答える。
「父親が違うんで……」
わたしのほうについていたギャル男が少し怯んだ。わたしは二つ折りの携帯電話を開いた。
嘘を言うとき、わたしは標準語をつかう。
「あ、おねーちゃん!おかーさんから連絡きてるよ〜『まだ?どこにいるの?』だって。
どうする〜??」
しらこい、と思われるセリフだったが、アラキには通じたらしい。
「あ〜もうそんな時間?行ぐべか」
わたしたちはあっさりとギャル男らから離れられた。
「さすねぇ〜しつこかった〜」と口悪く一蹴するギャルのアラキ。
ああ、青森弁で蹴散らすところも見たかった氣もする。
いつのまにかギャル男らに囲まれたときに感じていたビクビクはわたしのなかから消えていた。
「てーか、母親も違うがらさ」
「ぶはっ。がっつり他人やんな」
「なじょして姉妹の設定?」
「いや、さっきの人らがそう言うてはったから」
「いもうどー!」
「おねいちゃん……!!」
わたしたちはケラケラと笑った。
HEPの観覧車の赤と夏の日差しが、いつまでも眩しかった。
その後、アラキが学校を卒業したんだかしてないんだか、わたしははっきりとは覚えていない。
何しろ彼女は学校に来ないことも多かったし、
わたしはというとアラキと過ごした学科を一年で辞めて、別の学科に編入したからだ。
その後の彼女の消息は知らない。
東京に行くだとか、そんなことを言っていたような氣もする。
翌年、アラキと歩いた街で星の数ほどある美容室から選択をしくじったわたしは、森ガール風のAラインのゆるふわパーマを所望して、なぜかコテコテの巻き髪にされてしまった。名古屋嬢のようだった。
そのときに写した学生証の写真を編入先のやはり「ご近所物語かよ」的なクラスのお洒落な人たちからからは散々いじられ、
「髪型だけギャル」のあだ名をつけられた。
わたしは「孤高の人」ではなくなっていた。
アラキと歩いた梅田の街をその後、二年間通学のために通ったけれど「髪型だけギャル」のまま、日によって古着やら森ガールなどちぐはぐな姿をしていたわたしが、ギャル男たちから声をかけられることは、二度となかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
