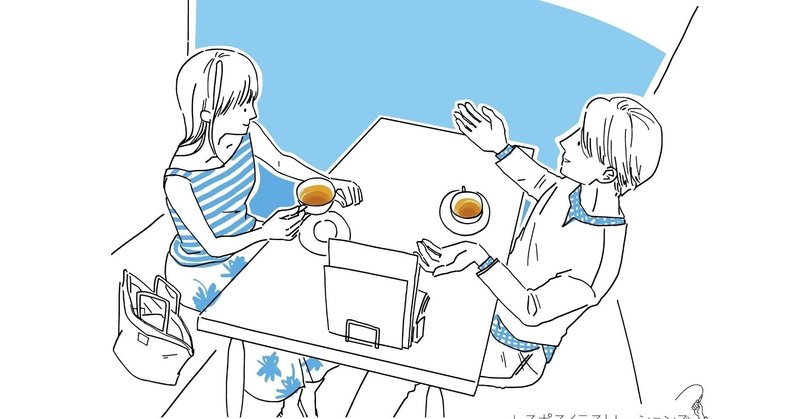
農学部の人・経済学部の人・文学部の人
農学部の学生と経済学部の学生が、コロナについて激しく議論していた。一方は、ウィルスの脅威を語り活動を少なくすることで感染者を減らしていくべきと主張し、また一方は、経済停滞により死者が生まれる方が重大だと意見を述べる。当然のことながら、話は平行線のまま、時間切れになった。お開きになると、二人で普通に帰っていった姿を見て、久しぶりに大学生を見たなと嬉しくなった。
この議論には全く入らず、少し離れたところで聞いていただけだが、では、私ならどういう視点で話に入っていただろうかと帰り道ぼんやり考えた。
私なら…「文学部の人」は何を主張するだろう。
お互いがお互いの主張の意味を、価値をついつい軽んじてしまわないように見守り、もし批判的になることがあれば、それを修正していく、という役割を発揮するかな…
つまり、多様な価値観の存在を主張する。
今だに文学部は就職の時に不利だ、とか、学んだことを社会に活かせない、などという人に出会う。そういう人は少数派だと信じたいが、いるのは確かだ。
私が文学や芸術を学んだことで後の社会人人生で活かせていることは多々あるが、一番良かったなと思うことは、世の中にはいろんな人がいることを当たり前なこととして知っている、ということかもしれない。
それは作家や芸術家自身と彼らが生み出した作品から学んだことだ。
フィクションや今とは異なる秩序の中で生きていた芸術家には、良くも悪くも、現実には出会わない、出会えないような人が沢山いる。しかも、物語の役割上、悪者であったとしても、よくよく考察すると、その悪者にも人間的な面があり、行為には理由があったりするから面白い。
オスカー・ワイルドという人の『サロメ』という作品がある。
王女サロメは、妖艶な舞の褒美として自分の恋心を拒否した預言者ヨカナーンの首を所望する。所望されるのは義父である王ヘロデだ。
このヘロデはいわゆる娘に欲情する俗物で小人物として理解されていることが多い。そういった面はもちろん否定できない。しかし、この『サロメ』を自分なりに読み解きに読み解くと、ヘロデには預言者を恐れる心根がある。この点はあまり注目されていないけれど、残虐で俗物なヘロデにはそれ以外の幅も物語から感じることが出来る。
一人の人間は多面的で自分がその人の全てを知っているわけではないことを知っているということは、世の中を穏やかに住みやすくしていくには大事なことではないだろうか。
文学や芸術を学んだ人はそういうことを世の中に伝える力があるはずで、社会に活かすことなんて学んでないと思う人が減るようにまずは先輩が頑張んなきゃ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
