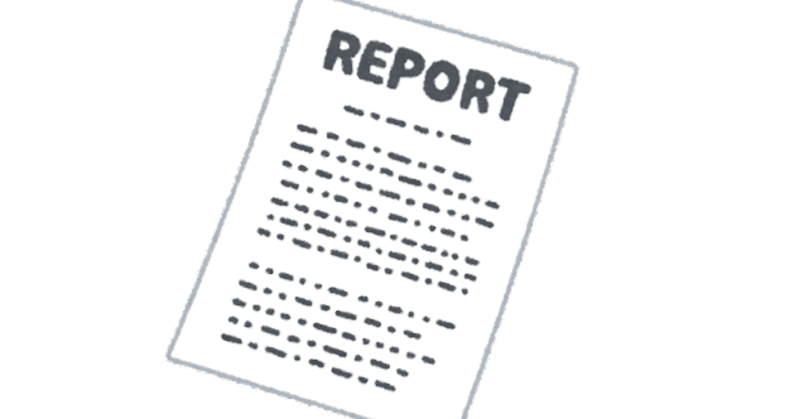
政治資金収支報告書上の住所のネット転載とプライバシー
事情は上掲記事参照。
概要は、政治資金収支報告書上の住所のTwitterへの転載がプライバシー侵害だとして発信者情報開示請求を予告したというもの。
本エントリは政治資金規正法の目的等を確認し、諸外国の政治資金の公表等についても参照して本件が違法とされるべきかを具体的に論じ、望ましい在り方を探るものです。
前提として政治資金収支報告書がざっくりどんなものなのか、関係法令はどうなってるのかを先に提示します。
政治資金収支報告書の記載内容

これが対象となる政治資金収支報告書の記載内容。個人住所は伏せているが、総務省がWEB公開していることは適法。
総務省HPの政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書で過去3年分を見る事ができる。この公表は政治資金規正法20条により定められています。
総務省での掲載期間が過ぎたものは国立国会図書館インターネット資料保存事業「WARP」で見る事が可能です。
似たようなものに公職選挙法に基づく「選挙運動費用収支報告書」と自治体での「政務活動収支報告書」がありますが、具体例のレベルではここでは扱いません。
政治資金収支報告書は1年間(1~12月)の収支、保有資産などを記載し、1年ごとに提出しなければならないもので家計簿のようなもの。その記載内容や制度の背景についてはJ-castニュースの記事が簡潔なので読んでおくとよいでしょう。
政治資金規正法の目的と基本理念
政治資金規正法
(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
基本理念まで書かれている法律は珍しい(大抵は2条は言葉の定義規定)。
【逐条解説政治資金規正法改訂版 政治資金制度研究会編集 行政】においてその趣旨を多少明確にした表現がある部分を抜粋すると…
本法1条の解説では
「政治活動の公明の確保とは、政治活動の実態を国民の前に公開し、いわばガラス張りの中において国民の不断の監視と批判の下におくことを意味し」
とされています。
他方、2条1項の後半部分についての解説では
「また、本法は、政治活動の公正を確保するため、政治資金の授受についての量的、質的な制限についても規定しているが、これは、政治献金に節度を持たせようとするものであって、政治資金の拠出についての国民の自発的意思を抑制しようとするものと解されてはならない。」
とあります。
こうした法律の趣旨も含めて考えていきます。
なお、「寄附」についての規制については以下の状況です。

https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/3001kifuseigen.pdf
政治資金収支報告書上の住所の扱いの問題構造
現行法をそのまま是認する態度ではなく、本件での理論上の課題を考えると以下の3つに分けられる。
1:個人住所を政治資金収支報告書に掲載することの是非
2:1を是認した場合に国や自治体のHP上で住所を掲載することの是非
3:2まで是認した場合に他のWEB媒体に住所を転載することの是非
本件は3番の問題であるが、前提として1,2番について考えてみる。
個人住所のWEB公開と個人献金の委縮可能性?
総務省HPで住所掲載することすら、個人献金の委縮を招くとして懸念する声がある。曰く、個人住所は原本で記載されれば良く、HPで公開される写しには住所記載をしない運用をするべき、と。
たとえば立憲民主党の森山浩行議員が国会質疑でその認識を披歴している。⇒第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号 令和2年6月1日
諸外国の政治資金報告書における個人の情報の扱い
この点について、イギリスでは2000年政党、選挙及びレファレンダム法(Political Parties, Elections and Referendums Act 2000)(c.41))により政党の政治資金に関する規制や政治資金監督機関の設立等が定められる前までは、政治資金に関する報告書の作成・公表についての法的義務は無く、各政党によって公表するかしないか・書式などもまちまちでした。
公表を頑なに拒んでいた保守党は、政党等への寄附は慈善団体への寄附と同じく基本的権利であり、氏名を明らかにすることは寄附者のプライバシーに対する権利の侵害である、とする見解だったと紹介されている。
参考:政治資金と法制度 明治大学政治資金研究会 日本評論社
その後、報告書の公表はParty and Election Finance (PEF) Online というWEBデータベースで行われるが、寄付、貸付及び選挙運動費用支出については、個人の寄付者の住所等の非公表情報は取り除かれている。
アメリカでは、政治委員会が連邦選挙委員会(Federal Election Commission: FEC)に寄附者や支出先の住所氏名等を記した収支報告書を提出し、WEB公開されている⇒https://www.fec.gov/data/committees/pac-party/?cycle=2022
ドイツでは政党が受けた寄付等で、年間1万ユーロ(約140万円)を超える寄付をした者については、その名前、住所及び金額等を会計報告書に記載し、1件につき5万ユーロ(約680万円)超の寄付については、直ちに連邦議会議長に報告する必要がある。提出された報告書は、連邦議会の刊行物として公表され、ウェブサイトにも掲載される。
フランスは政党・政治団体を除く法人による寄附の禁止をしている点に特色があり、個人献金がベースとなっている。そのためか、報告書の内容は簡略化された形式により官報で公表され、CNCCFPのウェブサイトにも掲載されるものの、寄附者の氏名等の個人情報は公表されない。
参考:国立国会図書館 米英独仏の政治資金制度 調査と情報―ISSUE BRIEF―
NUMBER 878(2015. 9.29.)
参考:『レファレンス』No.731 英国の政治資金制度(資料)英国の政治資金制度政治議会課 木村 志穂
したがって、政治資金収支報告書上の個人住所のWEB公開と個人のプライバシー、ひいては個人献金の委縮可能性というのは、諸外国でも懸念が存在しており、荒唐無稽な話ではないということ。
人物の特定と監視の便宜に適う住所の公開
諸外国の政治資金に関する制度全体をここで書くことはできないので詳細は省くが、わが国ではどうするべきか。
たしかに住所が公開されることで個人献金が心理的に抑制される面もあるのかもしれない。もっとも、少額の個人献金は総額だけ公表される。法律上も個人との関係で記載義務が発生するのは年間5万円を超す寄附と1万円を超す支出。
この金額を大きくするべき、という方向もあろうが、同時に政治資金規正法は政治に使われる金が巨額になってきたことからルールが緻密化されていったという経緯を忘れてはならないだろう(経済成長による物価上昇で相対的なボリュームはそんなに変わっていないという事情があれば別だが)。
しかし、記載すればよくて記載漏れした取引だけ(或いは重点的に)問題視するという考え方ではなく、資金の流れの適切性を記載内容からもより多く・精密に審査するには、相手が「どこの誰か」がわからないと意味が無いだろう。
これは①人物の特定と②監視の便宜の側面がある。
①について、同じ名前の人間が居た場合には、住所で判別するしかないのは自明だろう。
②について、たとえば100億円が個人によって寄附された。住所が載っていない。しかし、ネット上で名前から誰であるかや所在が分かるという人が居り、訝しんで住居に行ったら、安っすいアパート暮らしだった…のようなケースがあるかもしれない。
明らかにおかしいので、どこか別の組織がその個人の名前を使って迂回献金している可能性を疑うだろう。外国からの資金提供かもしれない。
これは極端だが、住所から判明する所有或いは占有する不動産の価値からその資力を推定することで、怪しい献金なのか実体のある献金なのかという点を一定程度判別できる。不動産に詳しい者であれば人については知らずとも、その住所地域の土地の時価などから異常性を検知するだろう。
住所がネット公開されていないと、このような怪しげな寄附がしれっと混ざり込んだ場合に検知されない可能性がある。対して、公開されているとなると抑止力になる。
だから住所も含めたネット公開をする意義はあるだろうし、それが政治活動を「国民の不断の監視と批判の下に」置くという法の目的に適うだろう。
さらに言えば総務省がHPで公開してるのは、それをすることでより多くの眼による監視が可能になるからだろう。実際、政治資金収支報告書のページを見れば分かるが、膨大なページ数に昇る。これを政治の世界の関係者らや捜査機関だけでチェックし、問題点を全て洗い出せるとは到底思えない。
そして、事務処理の問題としてWEB公開時にいちいちマスキング処理する判断に無理が生じるし、膨大な手間がかかる。寄附の場合もそうだが、特に支出の場合、いったい誰が記載住所が事務所のもので個人の住居なのかを判別できるのだろうか?いちいちGoogleで地図検索して「ビルのテナントだから事務所だな…」とするのだろうか?政治家の側で寄附や支出時に「その住所は自宅ですか?事務所ですか?」などと確認する手間をかけさせるのだろうか?
違法な献金の推知に住所の記載が役に立つ場合
匿名・偽名による寄附の禁止が定められている(政治資金規正法22条の6)ことからは、チェック時に人格の同一性が偽られていないかを推知するには住所が必須。
さらに外国人による寄附が禁止されていることからは(政治資金規正法22条の5)戸籍上、日本人らしき名だが外国籍である、という場合には外国人等からの寄附の受領禁止に該当するか否かも、どこの誰が寄附したかわかることが前提。
具体例として、大阪府のイムボンブ=林範夫という韓国籍の弁護士が辻元清美議員に寄附して報告書を提出したが、この件は夕刊フジの独自取材によって発見され、辻元事務所に事実確認をした後に訂正が為された報告書が存在している。
本件は「林範夫」が弁護士なので公開情報から特定が可能であり国籍が辿れたが、実は「林範夫」という表記の弁護士は2名が登録されていた(それぞれ別人の「いむぼんぶ」と「はやしのりお」)。住所がなければ特定に労力がかかっただろう。
仮に弁護士でない場合に住所も無かったら、果たして名前だけで特定ができただろうか?住所も併せて記載して初めて特定できるだろう。さらに言えば、これはネット公開されてなければ気づかなかった事案だろう。
なお、イムボンブ弁護士の件は1万円の寄附であり、記載義務の無い額であったという点は指摘しておく。
少し別角度からの話として、個人献金にかかる税制上の優遇措置を受けるためには住所の記載は必須。この場合に住所記載をしないという選択肢はあり得ない。
したがって、個人の住所の記載とそれを政府HPでネット公開することは是認されるべきだろう。問題は、掲載されている場所とは別のネット上に転載する行為。
別のWEB媒体に個人の住所を転載する行為:判決文や登記簿等の場合
従前の原告と被告との訴訟の判決文をインターネット上のブログに掲載した際に原告の住所が公開された(3ヶ月後に削除)ことがプライバシー侵害とされ6万円の損害賠償が認定された事案【東京地裁 平成22(ワ)47931号 平成23年8月29日判決】において以下判示されました。
登記簿や電話帳への自宅住所の記載は、いずれも一定の目的の下に限定された媒体ないし方法で公開されるもので、同目的に照らし限定的に利用され、同目的と関係ない目的のために利用される危険は少ないものと考えられ、公開する者もそのように期待して公開に係る自宅住所情報の伝搬を上記範囲に制限しているというべきであるから、原告X1が自宅住所情報につきプライバシーの利益として保護されることまで放棄していると評価することはできない
次にインターネット上で閲覧可能な登記簿上の住所のうち、法人代表者の個人住所は記載しないこととするという運用変更があったという経緯があります。
法務省:法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第19回会議(平成31年1月16日)開催
また、以下の内容の附帯決議がされた。
省略
2 省略
(2) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)」 では、電気通信回線(インターネット)での登記簿上の住所閲覧制限については法改正での対応はありませんので要綱案には記載されませんでしたが、運用の変更として行われることが決定されました。
これは法人の代表者の個人の住所がネット上で閲覧できてしまうことでみだりに利用される事案が発生したことから制限の必要性があり、実際上も法人の住所だけがあれば良い場合がほとんどであることから、ネット上での閲覧のみ規制がかけられた経緯があります。
法務局に直接足を運べば代表者の個人住所も見ることができます。そういう人が悪用するケースはほとんど無いと判断されたからです。
この点が問題になったのが、立憲民主党の森ゆうこ議員が登記簿上の法人代表者の個人住所をWEB媒体に転載した行為が原英史 氏のプライバシー侵害だとして訴訟が行われている事案です。
似たような話として、神戸地裁平成11年6月23日判決ではNTTの電話帳記載の氏名・住所・電話番号等をネット上の掲示板にUPした行為がプライバシー侵害の不法行為となるとしました。
他、「破産者マップ」がWEB公開された件も個人情報保護委員会によって違法だとして閉鎖に追い込まれました。
いずれも【「既にWEB上で公開されているものだからインターネット上で拡散しても違法ではない」というわけではない事案】です。
なお、小林貴虎議員が同性カップルからの公開質問状が事務所に届いたことを知らせるために、公開質問状が入っていた封筒に記載の氏名住所が映っている画像をブログで公開したところ、同性カップルらが個人情報・プライバシー侵害だと騒いだため、話合いにより当該画像が削除された件では、掲載された住所は実は既に同性カップルらが商売のためのブログに掲載されていたものでした。⇒https://www.jijitsu.net/entry/kobayashitakatora-koukaishitsumonjou
政治資金収支報告書上の記載住所の転載は許されないのか?
このように、既にWEB上で公開されている情報でも、それを別のWEB媒体に転載する行為は別個に検討される事柄と言えます。
事例判断ですが裁判所は違法方向の判決を出す傾向があると言えます。政治資金収支報告書についても同様の判断が為され得る。
政治資金規正法の目的と基本理念との関係で言えば、「ガラス張りの中において国民の不断の監視と批判の下におくこと」という政治資金の監視目的を重視するのか、「政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように」という理念を重視してプライバシー保護を図るのか、という調整問題と言えます。
東小雪氏の場合
では東小雪氏の政治資金収支報告書上の住所をTwitterに転載した行為は、どう判断されるべきか。
政治資金規正法の目的が「国民の不断の監視」であるならば、総務省HPで掲載しているだけでなく、他のネット媒体に転載してもそれは「ガラス張りの中において監視の目を増やす行為」であり、法の目的に合致した行為でしょう。
この点が登記簿や判決文、NHK電話帳上の住所の記載とは異なる事情と言えます。これらは「インターネット上に拡散された場合のレベルでの不特定多数の人間」が住所を知る意義が無いか乏しいもの。
それに、領収書記載の住所は金銭の受取人が何らかの方法で指定するはず。
東氏はTwitter上に事務所住所を公開していて、報告書上のものとは異なっていますが⇒https://archive.is/km8jV、なぜ事務所住所ではなく自宅住所にしたのか、やむを得ない事情があったのかもしれません。もっとも、それを選択した時点で東氏の責任。
たとえば早稲田リーガルコモンズ法律事務所所属の弁護士の複数人が立憲民主党から弁護士報酬や書籍代として支払を受けていますが、全て住所は早稲田リーガルコモンズ法律事務所のものが記載されていました。このように、支出欄の住所は、通常は事務所・事業所の住所が掲載される欄だと認識されるものでしょう。判決文や森ゆうこ議員の場合は、明らかに個人の住所だということが分かる事案であったという違いがあります。
したがって、「政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように」という理念に抵触したとまで言えるかというと疑問。
なお、政治資金収支報告書上の【支出欄】にある名目「Twitterアドバイザー」という記述からすると、基本的に業務の対価として支払っているという外観がある。たとえば「タクシー代」「航空機代」「会合代」と比べるとその印象は強い。そのため、これが事務所・事業所とは異なる専ら個人の住居として利用している住所であると判別できるかは難しく、過失を認めて良いかどうか。
個人的な結論
このように、個人的には東氏の事案の場合は、政治資金収支報告書上の個人住所を別のWEBに掲載しても、違法とすることは避けるべきではないかと思います。
繰り返しますが、裁判所はWEBへの転載に厳しい傾向なので、この結論が採用されない可能性は十分にあります。
また、仮に違法ではないにしても、個人の自宅住所であり掲載しないでほしいとお願いされた後にも継続して掲載することは、少し可哀想な気がする(「お願い」の仕方による)。法人登記簿上の代表者の住所へのいたずらがあったためにネット公開をしない運用に変化したということもあるので、そうした懸念を覚えること自体は仕方がないだろう。
ここから先は
¥ 500
サポート頂いた分は主に資料収集に使用致します。
