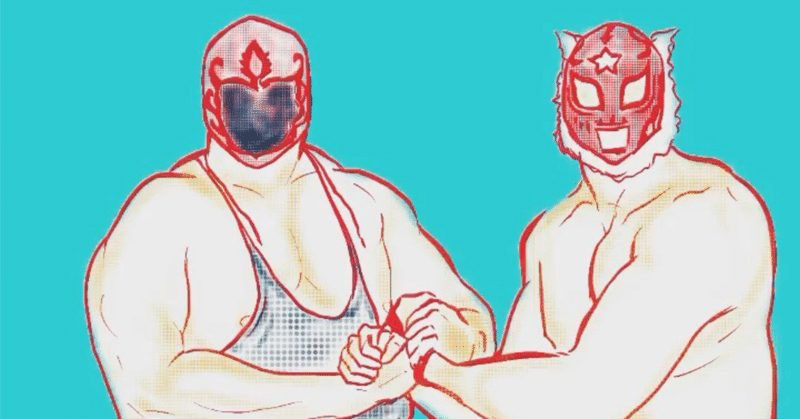
【町民代表の折衷案、議会議員と審議会委員の融合/議員の成り手不足解消への試論その4】
その3の続きです。そろそろ収束させたいところですが……どうなることやら。
前回「議会とは別な民意の反映手段である、各種審議会(例:総合計画審議会)のあり方も変わってくるような気がする」と書きました。
議会の例と同じく DX(デジタルトランスフォーメーション)によって、各種審議会の情報公開と参画の機会の提供は、進めようと思えば今までとは別次元で、それこそ乗り物がロボットに変身しちゃうぐらいのトランスフォーメーションできちゃいますよね。
そんなこんなも踏まえて「議会と各種審議会の融合を進めてはどうか」というのが今回の試案です。
具体論に入る前に、私が議員だった頃に感じた議会と各種審議会との関係性についての違和感について述べておきます。
総合計画を始めとする重要な計画・事業については、各種審議会などでの議論を経て議案として議会に提出され、議会で認められてから実行されます。
議会では、その議案の可否を本会議あるいは委員会審査で見極めます。私は基本的にクリティカルシンギングで臨みますので、議案に対し批判的な視点から質問をすることも多々ありました(批判と非難は区別しています)。
すると「審議会などで町民代表の意見を聞き、反映し、理解を得ている」というような答えが返ってくることがあります。
暗に「町民代表の意見を反映した議案なので異論を挟む余地はない」と言われているような気がして「もや」っとしてました。
「じゃ、議会も議員もいらなくない?」
町長側で人選を行える審議会の委員と、選挙をくぐった(ただし出馬のハードルが高い)議員と、どちらが真の「町民代表」なのか……難しい問題です。
議会がただの追認機関になっていると批判されて久しく、私もそうした批判精神を持って議員になったわけですが、なるほど、こういうことかと。
他の自治体のことは分かりませんが、少なくとも下川町では、重要な計画・事業について議論する審議会の委員に議員は入らないことがほとんどで、それはつまり、政策の形成過程に議員が直接関わることはしない、ということになります。
なので議会は、ほぼ仕上がった(そして「行政の無謬性」というベールを身に纏った)議案に対し、最終的に賛否二択の決断をする準備としてチェック機能を果たすのみで、そうなると粗探しで重箱の隅を突くような質疑になりがちなのは、当然の帰結ではないでしょうか。
そこで、チェック機能だけではなく政策提言機能も果たす仕組みを作ろうと、私が2期目の時に議会運営委員長として↓こんなことに取り組みました(顔写真アップが恥ずい……)。
これはこれで意義ある取り組みだったと思いますが、こうやって議会が頑張れば頑張るほど担い手のハードルが上がってしまったような気もしています。
そこで思いついたのが、町民代表の折衷案、議会議員と審議会委員の融合です。
ケツから言って(参照:『七つの大罪』デリエリ)
最新の下川町総合計画審議会委員が18人であることを参考に、議員定数を8人から19人に【増】
議員報酬は矢祭町を参考に【日当3万円】とし、実質【減】?
議会の常任委員会を、総務産業常任委員会だけの1委員会から、総合計画審議会の3部会制を参考に3委員会(福祉・教育、快適環境・ 地域づくり、産業経済)に【増】、各委員会に議員6人が重複なしで所属
総合計画審議会には、3部会に3委員会所属の議員が委員として就任
その他の審議会などは3委員会の所管で分担して議員が委員として就任(例:農業振興審議会なら産業経済常任委員会所属の議員が委員として就任)
議員以外の委員は必要に応じて委嘱
各種審議会などの会議は、意見の取りまとめまでに十分な時間を取り、原則公開、オンライン・録画オンデマンドなどで町民ならいつでも・どこからでも参画して意見が出せる。開催日時は昼夜を問わず、委員間で調整
各種審議会などの会議は、議員・町民の意見を聴いた上で素案を改善していく場で、案に対し承認を得る場ではない。最終的には町長が議会に議案を提出し、議会で議決
という感じ。粗々のラフスケッチです。
要するに、今、総合計画審議会の委員など公的な会議に出て発言する労を引き受けている方々が、議員にスライドするようなイメージです。
ちなみに総合計画審議会の委員を議員が務めている例は検索したら出てきます。
その3の冒頭で私はこう書きました。
結論から言うと、ざっくりとした方向性としては、議員報酬は減らし、議員定数は増やした方がいい(ただし定数は奇数に)のではないかと考えています。
ただし、自治体DXなどいくつかの前提を満たした上で、というのが条件になります。
ここで、ただし書のDX以外の前提について補足しようと思ったのですが、またもや長くなってしまったので次回へ持ち越します……続きが気になる方は「スキ」をポチッとしてぜひ追い風を。
バーカウンターで「あちらのお客様からです」ってあこがれます。
