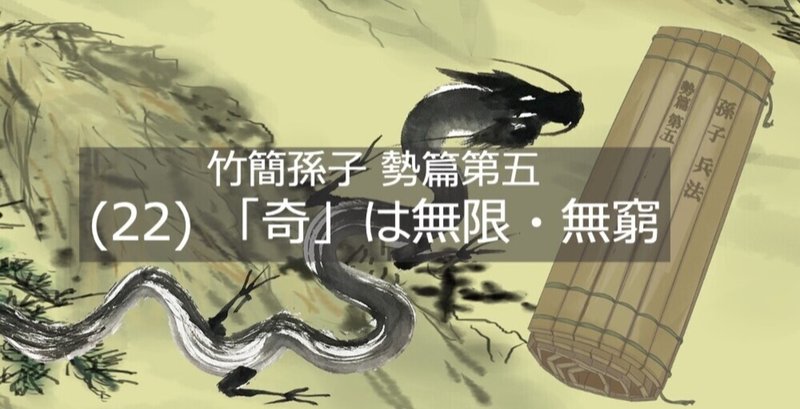
(22)「奇」は無限・無窮-竹簡孫子 勢篇第五
兵法において「奇」の存在によって、兵法は無限の広がりを見せると言いました。
ではそもそも「奇」とは何なのでしょうか?

「正」とは、戦力を集中させる「形」を為す戦法、「強」「実」「佚」などの状態の総和とも言えます。「正」の特色は、相手からよく見えるということです。多方面から戦力が集まってきますので、相手からも察知されやすいです。
それでは「奇」は何かというと、様々な形態に変化するものだと言います。
【書き下し文】
故に善く奇を出だす者は、窮(きわ)まり無きこと天地の如く、竭(つ)くる无(な)きこと河海(かかい)の如し。終わりて復(ま)た始まるは、日月(じつげつ)是なり。死して復た生じるは四時(しいじ)是なり。声は五に過ぎざるも五声の変は勝(あ)げて聴く可(べ)からざるなり。色は五に過ぎざるも五色の変は勝げて観るく可からざるなり。味は五に過ぎざるも五味の変は勝げて嘗(な)む可からざるなり。
【現代訳】
上手に「奇」を繰り出す者は、天地の働きのように行き詰まる事がなく、大河や大海のように知恵が尽き果てる事もありません。「奇」を例えると、太陽の昇り降りや月の満ち欠けのように、終わってはまた始まり、季節の移り変わりのように死滅と誕生を繰り返します。音楽を構成する音階、は五種類に過ぎませんが、それらを組み合わせてつくる音楽は、無限の組み合わせがあって、そのすべてを聴き尽くすことはできません。絵を構成する原色も、五種類に過ぎませんが、それらを組み合わせてつくる色合いは無限であって、そのすべて観ることはできません。料理を構成する味覚も、五種類に過ぎませんが、それらを組み合わせてつくる料理の味は無限であって、そのすべて味わうことはできません。
月の満ち欠けや季節、動植物の誕生と死滅など自然界の巡りのように、変化し、さらに味や色や音のように各要素が組み合わさって、同じものが存在しません。このように「奇」は、どこまでも変化するというのです。
では陰陽理論からも考えてみましょう。
「奇」は「陰陽」に当てはめると、「陰」の性質を持ちます。
「陰」は、女性性の如く、万物を受けてものを産み出します。内側に向かい、物事を統合させます。柔軟で、そして全体性を帯びます。「陽」は、男性性の如く、物事を推し進める外に向かうエネルギーで、物事を分化させ、発展させていきます。剛直で、個体性です。
「陽」は竹を割ったような真っ直ぐさで、力を込めて押し進めっるイメージです。このようなイメージが「正」です。
「陰」は複雑で神秘的です。単純でなく、矛盾を違和感なく包み込みます。柔軟に変化してつかみどころがありません。男性からみた女性のイメージでしょうか。そういう特性があります。
私の新解釈では、「奇」の兵法の本質として「詭道」があります。目に見えない不思議な要素が絡み、目では把握できなくなります。

そういった相反する特性を持つ、「陰」と「陽」が組み合わさって、兵法は様々な形に変化し、その形態は無窮・無限になるのです。
「正」だけでは、特性は強いが変化できず、勢いを維持できません。相手の方が強ければ策もなく負けてしまいます。また「奇」だけでは、意表をついて変化を作り出すことで、相手の目をくらますことができるが、強さがないので敵からの攻撃に弱く、決定打を打つことができません。
手を握れば硬い拳になるが、手を広げれば自由に指を動かして色々な働きをすることができる。ある時は拳を握り、ある時は手のひらを広げる。その変化が兵法と言えるでしょう。
この「正」と「奇」の組み合わせることで無限の変化を作り出すことができます。
そして「孫子」では、「凡そ戦いは正で以て合し、奇を以て勝つ」という法則をあげています。
はじめは「正」、つまり負けない態勢で戦いをはじめ、戦いが進行する中で様々な形に変化し彼我の関係に強弱、虚実を作って勝利を収めるとしています。
戦い(奇)においては、「正」→「奇」の順番ですが、政治(正)においては、「陰(奇)」→「陽(正)になると先述しました。この順番は、論語などの他の中国古典を一緒に学ぶ時に、気をつける項目です。「孫子」は「奇」について書いており、論語は「正」について書いているので、順番が違うだけで、陰陽相待原理、自然摂理の視点では矛盾はありません。
最後に捕捉をさせて頂くと、「正」と「奇」の概念は、孫子の中だけでは説明されていません。
孫子の著者の孫武の子孫が著した「孫臏(そんびん)兵法」、武経七書の中で最も新しい「李衛公問対」に、「奇」の別視点からの理論、それが何なのかを究明しようとする議論があります。実際は、あまりよくわからないのが
本当のところですね。
その中の一つの考え方を紹介すると、相手の出方(正と奇)に対する方法として「正」と「奇」があるといったものがあります。「正」で攻めてきた相手に対して、正攻法で対応するのが「正」である。イレギュラーな方法で対応するのが「奇」であるといった考え方です。
私の見解では、この考えは複雑に考えすぎていると感じています。敵との相対的な関係で「正」と「奇」が決まるのであれば、「陰陽相待原理」との整合性も取れない部分も出てくると思います。今後の研究につなげていきたい分野です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
