
【マガジン】手は外に出た脳〜自我の制御法の成り立ち〜
僕らは意思を具現化するときに字を書いたり、絵を描いたり、何かを作ったりしますが、それは全て手を介して行われます。
私たちは直立二足歩行をする動物として進化し、手をフリーにしたからここまで複雑な社会や文化を形作ることができたといえます。
そして手が自由だから文字が発達し、世界の概念化が進み、記録の保持が可能となり凄まじい進歩が起こっているのです。
さて、ペンフィールドのホモンクルスはご存知でしょう。
脳の中の小人ですが、手と唇がとてつもなく大きいですね。
つまり私たちの大脳新皮質は人間の特徴である手の器用さと言語によって肥大してきたということが分かります。
【エゴと手】
これは同時に、「意思」が大きくなったことを表します。意思の座である前頭葉は、大脳新皮質の30%を占めます。
一般的にはアイディンティティであり、自我を形成している場所でしょう。
しかし現実社会では、この自我によって自分自身を苦しめることも多々あります。
進化で獲得した高次機能である概念化や言語化、そして創造性を具現化する巧緻的な手。
でもその高次な機能が故に、概念に囚われ、自我と理想との間で悩み苦しみます。
この矛盾は全ての人に共通する矛盾でしょう。これを上手く制御して、苦しみよりも幸せを実感できる社会システムとして、宗教ができ、ヨガや座禅のような実践法が出来たのでしょう。
座禅では「上虚下実」という概念が重要とされています。肚を安定させて手や肩は脱力せよということですね。
このようなことに注意しつつ実践を行うと、不思議とエゴが小さくなります。
手は先ほど述べたように意識を具現化する効果器です。肩肘に力が入るというのは緊張した人の特徴ですが、それはエゴが強い状態ともいえます。
「失敗したらどうしよう。」
「負けるわけにはいかない。」
「間違えないように、間違えないように、、、!」
緊張した思考は、緊張した体と適合し、緊張した手や肩肘を作ります。
逆に、緊張した手や肘肩を弛緩させると、体が弛緩し、思考も弛緩してきます。
このように、瞑想のための座禅などの形では、手を印で結び、肘肩をリラックスさせて、思考もリラックスさせ、結果的にエゴを抑えて苦しみを消し去る方法なのだろうと思います。
ここから先は
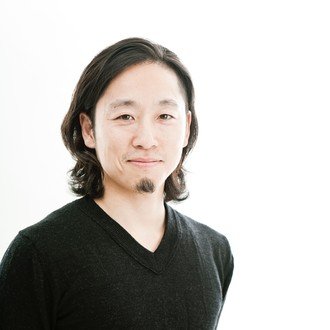
ヨガインストラクターのための指導ポイント
ヨガ指導におけるヒントや有益な知識情報をお伝えします。特にヨガの解剖学や安全安心な指導への情報を中心にお送りします。
よろしければサポートをお願いします。私自身ではまだまだ微力です。当たり前の選択や情報を得ることができていない方々に、予防医学の視点で、知らなかったことで損した方を少しでも減らすよう、有益な情報を発信していきます。皆様の応援を励みに、より精進して行きます。応援ありがとうございます。
