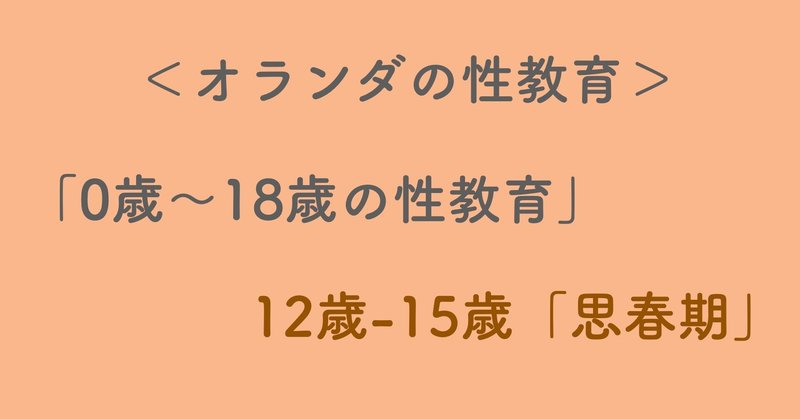
12歳-15歳 思春期 / 0歳-18歳の性教育
このマガジンでは「世界一」と称されるオランダの性教育において、この国で紹介されている性教育の資料を日本語にすることで、多くの方々に性教育の大切さをお伝えしています。
シリーズ最初は、Rutgersというオランダの性教育のシンクタンクとされる団体が提供している「0歳-18歳の性教育」というパンフレットの「12歳-15歳」のページについてご紹介します。
自立心の芽生え
子どもたちが思春期に差し掛かると、自分で自分の思う通りに物事を進めたいという気持ちがどんどん強くなります。自分のことは自分で出来るという風に考え始めることで、両親や保護者の言うことに耳を傾けなくなってきます。よって、思春期の子どもと保護者が口論になったり、言い合いをするようなことも多くなります。しかし、忘れてはいけないのは、そういった状況が頻発するようになったとしても、保護者というのは思春期を迎えた子どもたちにとってとても重要な存在である。ということです。
年齢に応じて様々な仕組みが理解できるようになるこの年齢では、やってみたら1人で出来た経験や、周囲の友達の行動などを見ることで、自分1人で出来ることを証明したいというような欲求が生まれるかもしれません。
まだまだ子どもを未熟だと感じる保護者と、責任と自由を与えて欲しいと望む親子の間では口論になることもあるでしょう。ただ、その状況というのは決して絶望的なものではなく、発達の過程であることを冷静に捉えられるか、そして、困った時に真っ先に相談できる相手が保護者であると判断されるためにどのような親子関係を築けるかを保護者側が考える必要があるかもしれません。
友だちや、人間関係がもっと大切になる
思春期の子どもたちにとって、友達関係やある特定のグループに属しているというような帰属意識は、より重要になってきます。同時に、重要であるからこそ、人間関係から生まれる拒絶や批判に対してはとても敏感になります。そして、そういった人からの拒絶や批判を気にしていまうといった感情が、友人による圧力やプレッシャーに対して彼ら自身を傷つきやすい状態にさせるのです。
SNSが当たり前の時代に生まれた子どもたちの中には、人からのポジティブな意見やネガティブな意見を自分の価値だと感じてしまう者もいます。それは、自分自身がどこに属していて、誰だと認識されているかということが、この年齢にとってとても重要だからかもしれません。これもまた発達の過程だと理解して、その価値を完全に否定したりすることがないように気をつけてあげられると良いかもしれません。
SNS(ソーシャルメディア)
この年齢に達した子どもたちは、より多くの時間をオンライン上で過ごすことになります。連絡はスマホで取り合ったり、行為を抱いた相手とオンライン上でイチャつくような行為も起こります。また、セックスに関する情報をオンライン上で探すような行動も見られるようになります。
自分の手で情報を集められるツールを手に入れることが当たり前となってしまったこの時代の子どもたちのコミュニケーションは、スマホが現れる前とは全く別のものとして存在しているということを理解する必要があります。もちろんその危険性については、家庭でもよく話合われるべきでしょう。
性的な魅力
この年齢に達した多くの子どもたちは、恋に落ちたり、誰かに対して性的に魅力を感じるようになってきます。その相手は異性であったり、同性であったりするものです。同性に対して恋愛感情や性的な魅力を感じることは、時に子どもたち自身に混乱を招くことがあります。また、この年齢に達するあたりから、キスの経験をすることが多いことも事実です。
日本の感覚だと少し早いと感じる人も多いかもしれませんが、この冊子ではこれくらいの年齢から「付き合う」といったような行為が見られるようになることについて言及されています。多少なりとも文化の違いがあるかもしれませんが、発達段階としては適切とも言えるのかもしれません。
質問:息子が14歳になり、どんどん自立して自分の身の回りのことを自分1人でするようになってきました。保護者として、彼の中にどういった変化が生まれているのかが知りたいです。
保護者が思春期の子どもの在り方について興味を示す方法はいくらでもあります。例えば、夕食時に今日1日はどんな日だったかを尋ねたり、どんな友だちと遊んでいるのかについて聞いてみたり、彼自身、最近はどんな日々を過ごしているのか。オンラインでどんなことが楽しいと思っているのか。息子さんがどんどん自立していったとしても、保護者として子どもの在り方や生き方に興味を見せることはできます。そして、保護者が子どもの生活について興味を示して話を聞くことは、困ったことがあればいつでも頼って良いんだよというサインを知らせることにも繋がります。
ここでは、自立する子どもに対して「関心を示し続ける保護者の役目」について言及しています。子どもがどんどん大きくなり、成長することは、必ずしも保護者としての役目を手放すことではありません。保護者が子どもの生活に対して「興味」を持つことは、子どもたちにとって「自分を放置しないでいてくれる」という安心感に繋がります。「興味」が「批判」ではなく、「あなたのことが知りたい」という純粋な気持ちに基づくことで、保護者に受け入れられていると感じながら、安心して自立の道を歩むことができるのかもしれません。
次は15歳-18歳の「成人間近の時期」について
次の記事では「15歳-18歳の成人間近の時期」についてご紹介します!
私たちの活動内容に賛同いただける方々からのサポートをお待ちしています。ご協力いただいたサポートは、インタビューさせていただいた方々へのお礼や、交通費等として使わせていただきます。よろしくお願いいたします!
