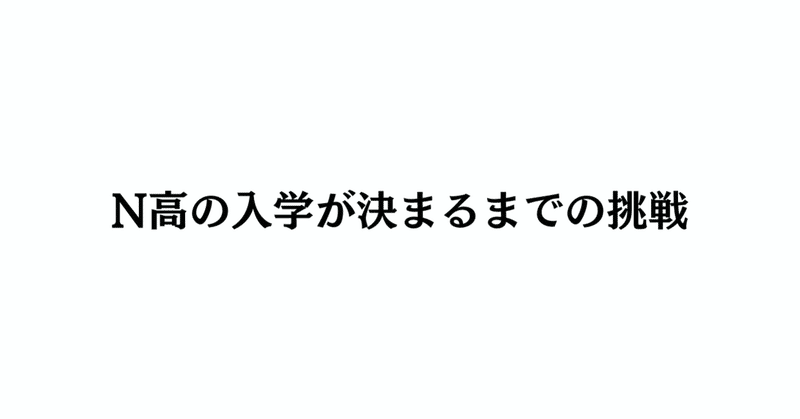
N高の入学が決まるまでの挑戦
あまり、Noteには書かなかったけどN高に僕は在学している。
需要がないかなと思ったのが本音だからだ。
それにN高のことを書く記事や動画はたくさんあるのも一つの理由。
でも、チャレンジした記録や挑戦のコツとして記事を書きたいと思ったのがキッカケだ。
今回のNOTEでしないこと
・学校であったことや入学したぶっちゃけな感想は書かない。
・N高の通学コースの試験内容や面接内容は記載しない(禁止されているため)。
どうやって「不可能だと思える状態から目標を達成できたのか?」に焦点をあてたい。
なぜそもそもN高に入学しようと思ったんだろうか?
それは今までの学校教育と関係していると思う。もともと僕は、小中学校までアナログな学校教育を受けてきた。
学校の教育は、いつも黒板にチョークだ。2000年代に入っても、2010年代に入っても、変わらない教育スタイル。実は、小学6年生のころにパソコンを自作し、パソコンを持つようになった。
当然パソコンを持ってからアナログに我慢できなくなったのも大きな理由だった。
僕が不満を感じていた理由はいくつかある。
1,インターネットを使って勉強できない
2,ホワイトボードで授業を受けれない
3,場所と時間が拘束される
4,パソコンを使ってメモを取れない
やっぱりインターネットを使えないというのは大きかったと思う。ネットを使ったほうが理解がスムーズに進むからだ。実際、僕は進研ゼミを使って勉強していたし、パソコンの知識を習得したのもネットからだった。
(全て説明すると、文章が3000字を超えてしまうので、ホワイトボードについて語ったら次に移る。)
それにホワイトボードで授業を受けたいという熱意があったから。
正直、チョークは苦手だ。黒板を消す時に嫌な臭いが発生するし、黒板の下に溜まったチョークの粉も掃除が大変。
その点、ホワイトボードは変な粉も発生しないし、何よりもカッコいい。書くときの特有のあの音も好きなのと、白という色が美しさを感じさせてくれるから。
大体そんな理由だったと思う。
だからN高に入学しようと思った理由は、「新しいモノ好き」で「時代の先を行く学校」というのが僕にマッチしていたからだ。
厳しかったN高への入学
すぐに行きたいと思って入れたらそれは良いと思う。けれど、現実はなかなかうまく行かない。
親にも反対されるし、学費の用意もしてない。いくら「パソコンで授業が受けれる」「会社を設立できる部活がある」「投資について学べる部活がある」「E-SPORTS部がある」ということを説明しても、親が理解できるとは思わなかった。
そもそも「学校は黒板のある場所で、ノートとペンで勉強する」という常識がある限り厳しい。こんなときは、N高で出来ることじゃなくて①情熱を伝えるといい。
「自分はこうしたいんだ!」「こんな人生を歩みたいんだ!」ということを言う。
僕はこれでも中々親を動かすことができなかった。まだ他の方法もある。それは、②相手の常識や価値観の矛盾点を突くこと。
人は誰しも価値観や常識を持っている。だからその常識の矛盾点を探して突くのが大切だ。
これは相手を日頃から観察する必要がある。特に価値観や常識は、「相手の好きなもの」や「好きな番組や人」に現れやすい(相手の反論にも常識が混ざっている)。相手の信念や価値観に訴える言動や行動が良いと思う。
僕は「子供の夢を応援するのが親の役目でしょ?」と言ってみた。
相手の信念や価値観に訴えたり、核心をつくといい。
ちなみにこの戦術は、相手にレッテルを貼り、価値観の矛盾を見せるというやり方。ただ核心をつくと、相手は機嫌が悪くなったり、余計意地を張って行動しなくなる場合もある。
そんな時は、③強制的に環境を動かすこと。無理やり環境を変えたら相手も流石に逆らえない。僕は、この方法を使って中学の先生や親を動かしてきた(もちろん相手を尊重するのも大切)。
③について僕は、学校の先生に相談し気持ち的にN高に行かないといけないという状態に持っていった(できなければ恥をかくから)。
それと教科書を捨てて、後戻りできなくした。
※最終的には、母親の理解も得られたが父親の理解は得られなかった。
ただ入学したあとに父親の理解も得ることができた(N高の異質さが理解できたみたい)。だから①〜③を匠に使う必要がある。あとは、あなたなりの方法を編み出してほしい。
僕は、③と②を①を実行した。
自分の中で意志を固め→親に相談し(失敗)→教師に相談し(成功)→教科書を捨て→資料請求し→N高の入学試験に応募する。
あなたの人生なのだから誰かに「あーだこーだ」「これはこうあるべき!」
と言われる必要はないと思う。決めるのはあなただし、相手にその権利と責任は一切ないはずだ。
※もしかすると、この記事の続編を書くかもしれません。
*
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
