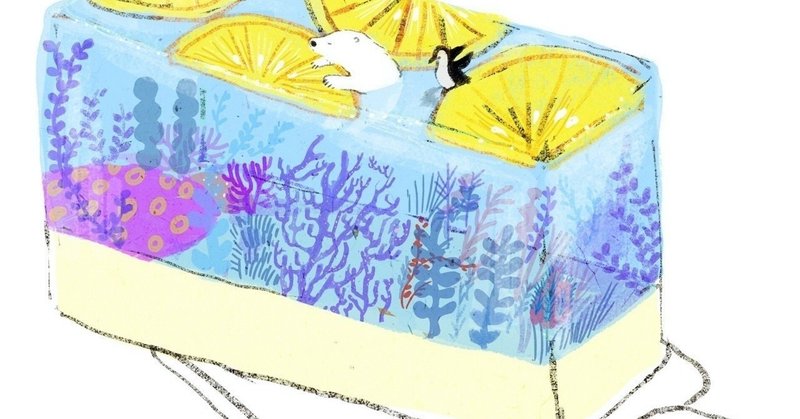
Beaさんから学び東京で実践する生活 2
Bea JohnsonさんのTED×Talks "Two adults, two kids, zero waste"。3つに分け、どういう内容だったかをまず書いてみたいと思います。
1. ゼロウェイストをはじめるきっかけと5Rに行き着くまで ( - 2:13)
2. 長期に持続して行えるゴミ0生活のルール 5Rとは (2:13 -9:44)
3. 実践して起こったこと (9:45 - 14:00)
先に2の、ゼロ・ウェイスト生活を長期に持続する方法である"5R"について講演をみてみたいとおもいます。
まず、5Rとは、Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot(compost)のことで、最初の2つは”ゴミの発生を防ぐ”、3つ目は”配慮ある消費、最後の2つは”出してしまったゴミの適切な処理”になります。
その最初のR、Refuseについてはこうおっしゃっています。
----------
・定義は、必要ないものに対してシンプルに”No”ということ
・シンプルに”No”ということを、家族で学んだとも言っています
・挙げられていた具体例としては次のとおり。
迷惑メールはNo、試供品やノベルティにNo.
single -useのプラスチック(ペットボトルやビニルの買い物袋)にNo
・(Noをいう理由として)現在、私たちは大量の対コンシューマー向けの商品サービスの”ターゲット”になっている。毎回ターゲットとして受け止めていたらそれは新たな需要を生むことなんだと、と言っています。
・例えば、カンファレンスに参加するたびに、無料のプラスチック製のペンを持って帰ることは、彼女に言わせたら「replacment/替えのためにもっと地下からオイルを掘ってくれ、そしたらまた替えを生み出すことができるから」と言っているのと同じだと言っています。
----------
この中の3点に、私はすごく思うところがありました。
1点目は、「シンプルにNoということ」と言う言葉。
2点目は、「家族もNoということを学んだ」という点。
3点目は、何気に持って帰るペンなどが提供側には必要だというメッセージになるという点。
1ですが、私たちがNoという主な対象は、店舗のレジの方や企業の方、もしかしたらお友達かもしれません。
その方々にNoという際に、せっかく出してくれるのに申し訳ないとか、私なりの理由があるのけどでも初対面の人に長々話しても..という気持ちになったりすると、No=必要ないです、が口から出にくくなると思います。
ですからまず最初に、「Yesと同じくらいNoも言う権利、アクションを起こす権利を私たちも持っているのですから」ということを知って欲しい。
そうも言われているのかなと捉えました。
ですが、「権利は行使しましょう」というと、少し語気の強めな印象を持ちます。2番目の家族もNoということを”学んだ”の学ぶという言葉に、相手のあることですから色々とあったのではないかと想像しました。
私も、まさに私の生活で、Noをいうことを学んでいるのかもしれません。
レジ袋Noはサービスとして浸透しつつ且つ明示しているところも多いため、Noをいうのは何の問題もないのですが。
先日のように、初めて自分の箸を持っていき、そこにそのサービスなどが書かれていなかった時。Noの言い方はどうしようか。あ、すんなり受け止めてくれたので今の言葉でいいんだななど。
先日の大好きな店でのマイ箸利用はまさにそれでした。
自分の生活圏で自分が心地よい言葉と態度で発するることを探るのは、学ぶという表現がまさにぴったりです。
そして最後の、試供品などの作り手に需要としてそれ必要だというメッセージです。
コンベンション等で大量のペンなどを頂き、本来必要でないかららと私たちはそれを返すでしょうか?私は、それどころか、これいらないのにって言いながら持って帰る回数の方が多かったです。
そのなかの全てが無駄になったとは言いませんが、私の「これむしろいらないのにー。不必要」の声が「xx個減ったから補充しなきゃ。必要だね」というメッセージになっているというその不健全さを痛感させてくれた一言でした。
まずは、不必要なものは手に入れない。
次は二番目のR、Reduceについてです。
